
ホーム > インタビュー&レポート > 「今が一番音楽をやっていて楽しい」 自分の“好き”=価値観は、自分が決める シーンに進攻するここにしかない声と音楽『NOBODY KNOWS』! 中田裕二撮り下ろしインタビュー&動画コメント

「今が一番音楽をやっていて楽しい」
自分の“好き”=価値観は、自分が決める
シーンに進攻するここにしかない声と音楽『NOBODY KNOWS』!
中田裕二撮り下ろしインタビュー&動画コメント
我々はいつになったら中田裕二の“正体”を掴めるのだろう――? そんな心地よい裏切りを幾度も繰り返す彼が提示した、新しくも、ここにしかない音楽。ソロ7作目のオリジナルアルバムとなった『NOBODY KNOWS』は、日本のポップスの最前線で活躍するTOMI YO、松岡モトキらをアレンジに招聘。ソウル・フラワー・ユニオンの奥野真哉(key)、GREAT3の白根賢一(ds)、初恋の嵐の隅倉弘至(b)ら気心知れたツアーメンバーに加え、KIRINJIの楠均(ds)、千ヶ崎学(b)、King Gnuの新井和輝(b)らも参加し、持ち前の音楽的探究心が導くまま自由に、そして大胆に、心から音楽を楽しむ彼の姿が伝わってくるようだ。椿屋四重奏という自ら築いた牙城への、ソロとしてのキャリアを重ねた自分への、SNSによって翻弄される時代へのカウンターを打ち続けてきた中田裕二が、己の音楽を世に知らしめるために、ついにその歩みを進めた『NOBODY KNOWS』。今作のリリースに伴い東京・渋谷の街を、“18禁の歌声”をテーマにセンセーショナルなコピーでポスタージャックするなど、その戦略にも新たな展開が見えた彼が、久々のライブハウスツアーとなる『TOUR 18 “Nobody Knows”』開幕前に、その真意を語るインタビュー。自分の“好き”=価値観は、自分が決める。時に見失いがちなそんな当たり前のことを、ありきたりじゃない音楽に乗せて。



「自分の味を変えるというよりは、そこにお客さんを引きずり込まなきゃいけないからね(笑)。『正体』とかはまさに狙い通りで、今の俺が武器としている“ネオソウル的なビート歌謡”みたいな。ずっとコード進行も一緒だし、今回は全体的にコードをかなり減らして研ぎ澄ませました。『thickness』と比べても、結構シンプルですね」




「毎年ライブDVDを出していたから、ちょっと変化が欲しいのはあって。その先駆けとして、まずはライブアルバム(『tour 17 thickness final live at 人見記念講堂』(‘17))を作って。今はもうYouTube時代だから映像がないことを不自然に思うかもしれないですけど、レコードを聴くようになってから、ライブアルバムのよさを再確認したというか…ジャズなんてほとんどがライブアルバムだし、やっぱり瞬間瞬間にしか生まれない音があるんですよ。ちょっとハラハラする感じとか、演奏者の息遣いとか、そういう生々しさがたまらなくて。それを耳だけで想像しながら聴くと、自然と絵が目の前に現れてくるじゃないですか。そういう体験をしてみてほしいのもあったんですよね。あとは、ソロになってからドキュメンタリー的なものをちゃんと作っていないなと。『ボブ・ディラン/我が道は変る ~1961-1965 フォークの時代~』(‘15)を観たときに、その人の生きてきた人生のスナップというか…何となくロードムービーみたいなものがいいなと思って、追いかけてもらいました」


(2018年5月 8日更新)
Tweet
Movie Commnet
ありがたきお言葉と真意とメッセージ
中田裕二の雰囲気伝わる動画コメント
Release
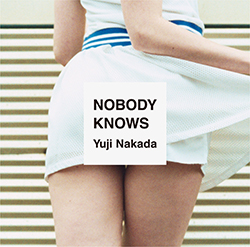
歌謡もフォークも洋楽も全て飲み込み
磨き上げた至高の7thアルバムが完成!
Album
『NOBODY KNOWS』
発売中 3000円(税別)
Imperial Records
TECI-1585
<収録曲>
01. Nobody Knows
02. 正体
03. ロータス
04. BLACK SUGAR
05. 傘はいらない
06. 静かな朝
07. マレダロ
08. CITY SLIDE
09. むせかえる夜
10. オールウェイズ
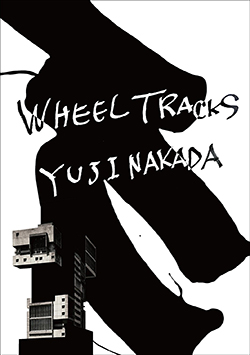
この1年を追いかけた濃厚な80分!
初のドキュメンタリー映像作品を発表
DVD
『WHEEL TRACKS』
発売中 4500円(税別)
Imperial Records
TEBI-48513
<収録内容>
・ドキュメンタリー映像(オフショット/
ライブ・ダイジェスト/インタビュー他)
・椿屋四重奏時代の代表曲『幻惑』のセルフ
カバーを含む3曲の最新スタジオライブ映像
Tour Book

中田裕二を掘り下げまくり毎回好評の
ツアーパンフが各ライブ会場で販売!
Book
『誰も知らない中田裕二のこと』
5月10日(木)発売
2800円
B5サイズ/48P
<掲載内容>
・巻頭グラビア 純喫茶裕二
・NOBODY KNOWS
SPECIAL TALK SESSION YU TO YO
・NOBODY KNOWSを構成する11の正体
・NOBODY KNOWS全曲解説
-誰も知らない裏エピソード付-
・不惑カウントダウンインタビュー・前編
中田裕二の“回り道の10代”
・WHEEL TRACKS誌上副音声解説
etc...
詳細はコチラから!
Profile

なかだ・ゆうじ…’81年生まれ、熊本県出身。’00年、仙台にて椿屋四重奏を結成。フロントマン及びソングライターとしてキャリアをスタート、’07年のメジャーデビューを経て、『紫陽花』『恋わずらい』『いばらのみち』に代表される、ロックバンドの枠に捉われないスケール感と個性溢れる楽曲で人気を集めるも、’11 年に突然の解散。3.11東日本大震災の被災地/被災者に向け作られた『ひかりのまち』を震災直後に配信(収益は全て義援金として寄付)したのを機にソロへ。同年11月に1stアルバム『école de romantisme』をリリース以降、『MY LITTLE IMPERIAL』(’12)『アンビヴァレンスの功罪』(’13)『BACK TO MELLOW』(’14)『LIBERTY』(’15)『thickness』(’17)とコンスタントにリリースを重ねる。’14年には、カバー曲をレパートリーの中心としたアコースティック・ライブプロジェクト『SONG COMPOSITE』から派生したカバーアルバム『SONG COMPOSITE』も発表。他にも、期間/テーマを限定しない弾き語りライブツアー『中田裕二の謡うロマン街道』や、アコースティックトリオ“中田裕二 trio saloon”としてもライブを行うなど、精力的に活動している。確かな歌唱力に裏打ちされた艶のある歌声と、幼少時に強く影響を受けた70~80年代の歌謡曲/ニューミュージックのエッセンスを色濃く反映したメロディを核に、あらゆるジャンルを貪欲に吸収した一筋縄ではいかないサウンドメイクと、様々な情景描写や人生の機微をテーマとした詞作によるソングライティングへの評価は高い。’18年3月21日に、最新アルバム『NOBODY KNOWS』をリリースした。
中田裕二 オフィシャルサイト
http://yujinakada.com/
Live
リリースツアーがいよいよ開幕へ
関西圏は京都・大阪にてライブ!
『TOUR 18 “Nobody Knows”』
【埼玉公演】
Thank you, Sold Out!!
▼5月10日(木)HEAVEN'S ROCK
さいたま新都心 VJ-3
【福岡公演】
▼5月12日(土)イムズホール
【熊本公演】
▼5月13日(日)熊本B.9 V1
Pick Up!!
【京都公演】
チケット発売中 Pコード107-265
▼5月18日(金)19:00
KYOTO MUSE
オールスタンディング5000円
[メンバー]奥野真哉(key)/
白根賢一(ds)/平泉光司(g)/
隅倉弘至(b)/カトウタロウ(back.vo)
夢番地■06(6341)3525
※3歳未満は入場不可。3歳以上は有料。
【静岡公演】
▼5月19日(土)SOUND SHOWER ark
【宮城公演】
▼5月26日(土)仙台Rensa
【東京公演】
▼6月2日(土)マイナビBLITZ赤坂
【北海道公演】
▼6月9日(土)帯広メガストーン
▼6月10日(日)ペニーレーン24
Pick Up!!
【大阪公演】
チケット発売中 Pコード107-267
▼6月15日(金)19:00
BIGCAT
オールスタンディング5000円
[メンバー]奥野真哉(key)/
白根賢一(ds)/平泉光司(g)/
隅倉弘至(b)/カトウタロウ(back.vo)
夢番地■06(6341)3525
※3歳未満は入場不可。3歳以上は有料。
【愛知公演】
▼6月16日(土)エレクトリック・レディ・ランド
【広島公演】
▼6月28日(木)広島クラブクアトロ
【鹿児島公演】
▼6月30日(土)鹿児島CAPARVO HALL
【福岡公演】
▼7月1日(日)イムズホール
【神奈川追加公演】
▼7月18日(水)大さん橋ホール
Interview & Report History

「自信を持って、これは
“誰にも作れないはずだ”って言える」
宿命に逆らわず、時代に従わず、
己の音楽を高らかに鳴らす
これが中田裕二の戦い方=『thickness』!
撮り下ろしインタビュー('17年)
特設ページはコチラ!

「何かすごく大きな変化が
自分の中で生まれつつある」
業も使命もプライドも
ソロ5周年に自らをブレイクスルーする
『THE OPERATION/IT'S SO EASY』
撮り下ろしインタビュー('16年)
特設ページはコチラ!

「椿屋四重奏で出来なかったことが
ようやく出来ました」
孤高のソングライティングで
AOR/歌謡曲をアップデートする中田裕二の
輝ける第二幕『BACK TO MELLOW』!
撮り下ろしインタビュー('15年)
特設ページはコチラ!

歌手・中田裕二から
素晴らしき名曲たちに愛と敬意を込めて
解放と挑戦の絶品カバー盤
『SONG COMPOSITE』
撮り下ろしインタビュー('14年)
特設ページはコチラ!
YesもNoも、時代も歌謡もロックもロマンも
背負い込んで。中田裕二の会心の
3rdアルバム『アンビヴァレンスの功罪』
撮り下ろしインタビュー('13年)
特設ページはコチラ!
中田裕二がシーンに築いた絶対領土
『MY LITTLE IMPERIAL』!
やりたい放題の2ndアルバムを異端児にして
偉才が語る撮り下ろしインタビュー('12年)
特設ページはコチラ!
椿屋四重奏解散、3.11、そして
初のソロアルバム『école de romantisme』
を語る撮り下ろしインタビュー!('12年)
特設ページはコチラ!
Comment!!
ライター奥“ボウイ”昌史さんからの
オススメコメントはコチラ!
「いや~TOMI YOさんの仕事、素晴らしいな~TOMIさん路線で1枚聴いてみたいな~なんて思うほどスパイスが効いている。そういったアレンジ、人選、宣伝に至るまで、最新作『NOBODY KNOWS』には新しい血が加わっています。まさに、中田裕二の音楽が世に正当に評価されるべく動き出したプロジェクトの第一歩と言えるでしょう。それにしてもホント独特。こんな音楽、他にない。そして、今年も担当させていただきました! 『TOUR 18 “Nobody Knows”』のツアーパンフ、その名も『誰も知らない中田裕二のこと』!! 今回も大阪の某聖地で撮影した魅惑の巻頭グラビアから、弾丸東京取材したここだけの貴重な対談に、中田裕二の若かりし頃の写真と紆余曲折の人生に話を聞いているこっちが感動した必読のインタビューシリーズetc…徹底的に凝り倒した充実の内容なので、ぜひ各ツアー会場にて観賞用、保存用、お土産用とお買い求めのうえ、SNSでステマしてください(笑)。毎年、“かれこれ何時間、中田裕二と話したんだろ?”って考えるんですけど、今年は昨年からさらに増量の約7時間って…後から作るの大変なのに何で自分にそんな重荷を…Mなのか…いやホントはSなのに…それもこれもみんな読者のため、ファンのため。その売れ行きに、あなたの反応に、中田裕二のこれからも、僕のこれからも握られているのです! よろしくお願いします~!」




























