
ホーム > インタビュー&レポート > 「ルーツ受け継ぎつつ、自分なりの答えを出していく」 中田裕二の逆襲たる最新作『LIBERTY』解剖計画【後編】 時代を超えて生まれる歌、世代を超えて生きる歌―― 初ホールツアー開幕に捧ぐ撮り下ろしインタビュー&動画コメント

「ルーツ受け継ぎつつ、自分なりの答えを出していく」
中田裕二の逆襲たる最新作『LIBERTY』解剖計画【後編】
時代を超えて生まれる歌、世代を超えて生きる歌――
初ホールツアー開幕に捧ぐ撮り下ろしインタビュー&動画コメント
理想を追い求めるのは、この世を生きる上で綺麗事なのか? 自分を信じ続けるのは、叶うことのない絵空事なのか? そして人はいつか、ゆるやかな時の流れを理由に、その確かな想いからそっと目を逸らす――。だが、この男はどうだろう? 最新アルバム『LIBERTY』を再生するや飛び込んでくる、ロック、ニューウェイブ、ヴィンテージ・ソウル、ファンク、レゲエ、ラテン、ボサノヴァ…海外の機運を敏感に嗅ぎ取りながら、80sオマージュ溢れる自らのルーツとキャリアとのジャストな関係を築き上げた、徹底的にハイブリッドでハイクオリティな楽曲群は、前作『BACK TO MELLOW』(‘14)がもたらした予感を礎に、歌手・中田裕二の消えない情熱と妥協なき理想郷を描いている。そこで、今作のリリースに伴い前後編フルボリュームで贈るスペシャルな撮り下ろしインタビュー【前編】は、先行配信されたEP『STONEFLOWER』を軸に、中田裕二のシーンとの独自の距離感とスタンスを語ってもらった一方、思い信じ続ける、まるで音楽少年のようなきらめきに思わず笑みがこぼれるインタビューとなったが、今回の【後編】では、彼が『LIBERTY』に込めた意思と意図、椿屋四重奏~ソロの15年を経たからこその決意と、初のホールツアーについて語ってもらった。リリースツアー開幕を前に、中田裕二の現在地を紐解くインタビュー。






撮影協力:Shangri-La

(2016年2月24日更新)
Tweet Check
Movie Comment
『LIBERTY』&ツアー話を某楽屋から
中田裕二からの動画コメント!
Release
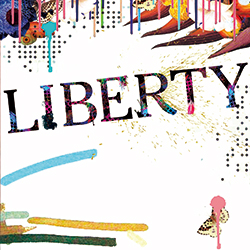
80sオマージュに留まらない己の表現
を徹底的に磨き上げた5thアルバム!
Album
『LIBERTY』
発売中 3000円
Imperial Records
TECI-1472
<収録曲>
01. WOMAN
02. KILL YOUR SMILE
03. en nui
04. SO SO GOOD
05. リボルバー
06. とまどい
07. MUSK
08. ヴィーナス
09. 朝焼けの彼方に
10. 月の恋人たち
11. STONEFLOWER
Tour Book

今回も濃厚、特盛りの内容!(笑)
『TOUR 16 “LIBERTY”』にて発売へ
Book
『歌謡サスペンス劇場』
2月25日(木)発売
3000円 A5全64P
※特製ミニバッグ付
<掲載内容>
・巻頭グラビア『追う男』
・ナカダ・ベストテン
・中田裕二とその周辺、タレコミノート
・『LIBERTY』全曲解説
・中田裕二解体新書 其のニ“愛用品編”
etc...
詳細はコチラから!
Profile

なかだ・ゆうじ…’81年生まれ、熊本県出身。 ’00年、仙台にて椿屋四重奏を結成。フロントマン及びソングライターとしてキャリアをスタート、’07年のメジャーデビューを経て、『紫陽花』『恋わずらい』『いばらのみち』に代表される、ロックバンドの枠に捉われないスケール感と個性溢れる楽曲で人気を集めるも、’11 年に突然の解散。3.11東日本大震災の被災地/被災者に向け作られた『ひかりのまち』を震災直後に配信(収益は全て義援金として寄付)したのを機にソロへ。同年11月に1stアルバム『école de romantisme』をリリース以降は、’12年に2ndアルバム『MY LITTLE IMPERIAL』、’13年には3rdアルバム『アンビヴァレンスの功罪』を発表。’14年6月には、カバー曲をレパートリーの中心に歌に特化したアコースティック・ライブプロジェクト『SONG COMPOSITE』を音源化したカバーアルバム『SONG COMPOSITE』を発表、配信限定EP『薄紅』を経て、11月には4thアルバム『BACK TO MELLOW』をリリース。そして、’15年6月には4th DVD『TOUR 15 BITTER SWEET 赤坂、春の宵』を、8月には配信EP『STONEFLOWER』を、11月25日には5thアルバム『LIBERTY』をリリースした。確かな歌唱力に裏打ちされた艶のある歌声と、幼少時に強く影響を受けた70~80年代の歌謡曲/ニューミュージックのエッセンスを色濃く反映したメロディを核に、あらゆるジャンルを貪欲に吸収した一筋縄ではいかないサウンドメイクと、様々な情景描写や人生の機微をテーマとした詞作によるソングライティングへの評価は高く、Superflyの最新作『WHITE』への楽曲提供も話題に。
中田裕二 オフィシャルサイト
http://yujinakada.com/
Live
キャリア初のホールツアーが遂に開幕
大阪公演はサンケイホールブリーゼ!
『中田裕二 TOUR 16 “LIBERTY”』
【愛知公演】
チケット発売中 Pコード282-167
▼2月25日(木)19:00
名古屋市青少年文化センター
アートピアホール
全席指定6300円
サンデーフォークプロモーション■052(320)9100
※中学生以下は、コンサート当日入場時に窓口にて身分証提示で2000円キャッシュバック。対象の方は必ず中田裕二オフィシャルサイトにて年齢制限・注意事項をご確認ください。
3歳以上有料。3歳未満は入場不可。
Pick Up!!
【大阪公演】
チケット発売中 Pコード280-069
▼2月27日(土)18:00
サンケイホールブリーゼ
全席指定6300円
夢番地■06(6341)3525
※3歳未満は入場不可。3歳以上は有料。
公演当日開場時間1時間前より、中学生以下の方は年齢のわかる身分証明書提示で2000円返金。
【神奈川公演】
チケット発売中 Pコード282-096
▼2月28日(日)17:30
関内ホール 大ホール
全席指定6300円
KMミュージック■045(201)9999
※3歳未満は入場不可。3歳以上はチケット
必要。中学生以下は当日会場にて2000円返金。
要身分証明書。
【宮城公演】
チケット発売中 Pコード280-599
▼3月3日(木)19:00
イズミティ21 小ホール
全席指定5800円
G・I・P■022(222)9999
※3歳未満は入場不可。3歳以上はチケット
必要。中学生以下は当日会場にて2000円返金。
要身分証明書。
【北海道公演】
チケット発売中 Pコード280-038
▼3月5日(土)18:00
道新ホール
全席指定5800円
マウントアライブ■011(623)5555
※中学生以下は当日会場にて2000円返金。
要身分証明書。※3歳未満は入場不可。
3歳以上はチケット必要。
【福岡公演】
チケット発売中 Pコード280-207
▼3月12日(土)17:30
都久志会館
全席指定5800円
注釈付指定席5800円
BEA■092(712)4221
※注釈付指定席はステージの全体および一部演出が見えにくい場合がございます。予めご了承ください。※中学生以下の方は、公演当日入場時に窓口にて身分証提示(コピー不可)で2000円キャッシュバックいたします。入場後の受付不可。中学生は学生証、小学生以下は
身分証をご持参ください。※3歳未満入場不可・3歳以上チケット必要。
【東京公演】
チケット発売中 Pコード281-227
▼4月17日(日)17:00
中野サンプラザ
全席指定6300円
ソーゴー東京■03(3405)9999
※3歳未満は入場不可。3歳以上はチケット
必要。中学生以下は当日会場にて2000円返金。
要身分証明書。
Interview & Report History


「椿屋四重奏で出来なかったことが
ようやく出来ました」
孤高のソングライティングで
AOR/歌謡曲をアップデートする中田裕二の
輝ける第二幕『BACK TO MELLOW』!
撮り下ろしインタビュー('15年)
特設ページはコチラ!
Comment!!
FM802『Superfine Sunday』
ディレクター小寺章加さんオススメ
「どこからお話すれば…と、思うのですが、出会いだけ端的に言うと、一目惚れです。間違えた。一耳惚れです。’11年。ソロアルバム1枚目の『école de romantisme』を初めて聴いて、ちょっとけだるいけれど、静かなカフェやバーで流れていそうな大人な音楽。さらに、歌詞を聴いていると、しっかりとした画が浮かぶ。この世代には、他に見当たらない…と思ったのが、気になり始めたきっかけです(大人な雰囲気…と思っていたら、年下でした)。椿屋四重奏が解散して、本格的にソロ活動を始めて、5年を迎えるこれまでの活動をざざっと振り返って、中田裕二とは、何者ぞ。と、考えると、こだわり屋だというコト。その“こだわり”がふんだんに盛り込まれているのが、『LIBERTY』なのじゃないかと。歌詞に物語があって、とても美しい。歌詞に使われる言葉選びと、メロディのバランスで、その世界が色っぽく感じられたり、純真無垢な印象を残したり…。ちなみに、今回は、朝を迎えたり、朝に始まる歌詞も多い。ぐっと、拓けた印象です。音やアレンジへのこだわりに関しては、プロじゃないと分かんないよ~、と思われるかもしれないけれど、過去のライブDVD『SERENADE OF”IMPERIAL SUITE”』の中で、そのときのツアーメンバーが語っている“めんどくさっぷり”(笑)が証明しているみたいです。とんでもない角度からの新しいアレンジ、注文が飛んでくる。でも、それが楽しい。その発想がすごい、と。そして、今回の『LIBERTY』に関していうと、収録曲11曲にドラマーは4人です。どんな音色や音の違いが出ているのか、CDで演奏しているメンバーを比較してみるのも楽しいと思います(私だけでしょうか?)。音遊びのこだわりは、CDでもしっかり楽しめるけど、間もなく行われる関西初のホールツアーで、今の中田裕二をどんな風に聴かせてくれるのか…にやにやして待っています」






























