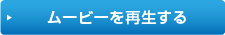生みの苦しみの先にある絶景こそが、この『REVOLT』!
バンドの分岐点となる重要作を引っ提げ全国ツアー中の
Nothing’s Carved In Stoneのフロントマン村松拓(vo&g)が
その予感と確信を語るインタビュー&動画コメント
村松拓(vo&g)もインタビューで語っているが、思えばこのバンドの成り立ちはそのスタート地点から羨望と嫉妬の眼差し入り混じるものだった。そりゃそうだ、ELLEGARDENの生形真一(g)、ストレイテナーの日向秀和(b)、FULLARMOR / killing Boyの大喜多崇規(ds)、腕もキャリアもあるロックシーンのスタープレイヤーが一堂に集った胸高鳴るプロジェクトは、このメンツが集まり音を出すだけで、化学反応は約束されていたようなものだった。その期待と真っ向勝負で立ち向かい、音で、ライブで全てを納得させてきたNothing’s Carved In Stone(以下、NCIS)が、メジャー2作目となる5thアルバム『REVOLT』をリリースした。だが、彼らとて“バンド”である。結成から5年の歳月を経て、バンドという1つの船を動かしていくのには、もはや今まで以上に踏み込んだぶつかり合いを避けては通れない時期を迎えていたという。その生みの苦しみの先にある絶景こそが、この『REVOLT』なのだ。NCISについては既発の全アルバムについてインタビューしてきたが、今回は初めての村松単独のインタビュー。だからこその言葉、フロントマンとしての自覚、4分の1であることへのフラットな目線。今作の制作にあたってバンドに訪れた変化の季節を、1つ1つ確かめるように語ってくれた。
何だか頼もしいぜ、村松(vo&g)からの動画コメント!
――メジャー2作目のアルバム『REVOLT』は意識改革もあって、音を聴いたときにもその変化が如実に分かるものですけど、メジャーデビュー以降このアルバムにたどり着くまでを振り返ってみてどう?
「手応えがまずあったということと、それがあった故にもっと先に進みたいと思ったので、ツアーにもそれを求めていった結果、バンドがオープンになっていったというか。生身を見せることに対しても少しずつ抵抗がなくなっていったのはあると思いますね。あとは、4人それぞれがこのバンドを続けてきたことで、やりたいことが少しずつ見えてきた。元々あったというよりは、やることで見えてきた部分があったというか。俗に言うバンドのリーダーは(生形)真一(g)なんですけど、いわゆる誰がバンドのコンセンサスを取るかみたいなパワーバランスは、以前よりもフラットになっているのを感じますね」
――やっぱり特殊な成り立ちのバンドじゃないですか。同時にそれぞれに所属する場所があっても、それだけじゃないものを感じさせてきたバンドでもあるし。もう結構なキャリアの大人たちが集まってバンドをやっていく中で、人が音に出るとすればその大人であることが距離感だったり関係性になるところが、大の大人が言い合えるようになったのが大きな変化というか。
「インタビューで話すと、解散しそうになったとかどうしても大ごとになっちゃうんですけど(笑)、5年もやってると、暗黙の了解でお互いに理解しているような気持ちになっていて。この前のツアーも結局うまくいったじゃないですか? そういう実感があったからこそ、“俺たち、もっともっと先があるんじゃないか? もっとこういう風になっていった方がいいんじゃないか?”っていう思惑が生まれて、それが暗黙の了解とは若干違った。みんな同じ方向は向いているんですけど、ほんの少しだけボタンをかけ違っている。だから一度それを外して、もう一回みんなで穴に通していく、そういう作業が必要だったんですよね。今まではそれを敢えて口に出さずに音でやってきたところが、そのフレーズに納得がいかないとか、その方向性はどうなんだとか、それぞれが口を出すようになって。そういう瞬間に険悪になることが結構あったけど(笑)、それって今までのNCISにはなかったことで。やっぱり楽曲制作における感情の乗せ方とか、入り込み方が変わってきてる。音で納得させたい気持ちはあったと思うので、それぞれに生みの苦しみがあってキツかったと思うんですよ。結果、スゴい振り幅のある曲たちになってるし。もうプリプロの最終段階ぐらいでRECまで何日も残ってない頃に、もう一度今どこを向いているのかをちゃんと言葉にして話してね。それがなかったら、その後の制作もレコーディングも、気持ちが入り過ぎちゃってて出来ないくらいだったんで」
――今までのやり方じゃ乗り越えられないというか、膝を突き合わせて言うことを言わないとダメな時期というか。
「でもそう出来たことで、楽曲の中に本当に今まで見せられなかった表情が、信じられないくらいいっぱい生まれたんで。終わってしまえば、自分たちでは想像していなかったところに踏み出せたかなって」
――それぞれプレイヤーとしてのキャリアがある中で、ちゃんとまだ“変われる”っていうのは素晴らしいというか。
「=それは4人じゃないと出来ないことがある実感にもなるんですよね。もうそれぞれがキツかったんだと思うんですよね、黙っていることが」
――NCISに限らず、各パートにフレーズは委ねるところはどのバンドにもあると思うけど、“何だか分からないけど何かが違う”みたいな感覚もあるじゃないですか。“じゃあお前なんだよそれ”みたいな話には絶対になるけど(笑)、それを言うか、言わないかみたいな。
「あるあるある!(笑) そうなんですよ。感覚で違うってことはやっぱりあったし。作ってる段階で全貌が分かるわけがないので二転三転するしかないんですけど、やっぱりそれぞれの想いが強かった気がしますね、今回は特に」
間違いなくこのバンドは一歩進んだんですよ
――前作くらいから自覚はあったと思うけど、ボーカリストとしての自分自身の覚悟と変化という意味ではどう?
「実を言うと、ちょっと前まですごく自分自分で。元々そういうタイプじゃなかったんですけど、それやらなきゃと思ってやってたんですよ。特に前作の『Silver Sun』(‘12)からガラッと変えて。フロントマンってそうであるべきだし、そうするためにもインタビューでは俺のことだけ話そうみたいな」
――ちょいビッグマウス乗せるみたいな。
「そうそう。その方がカッコいいと思ってやってたんですけど、最近はもっとフラットでいいかなって。4人で1つのもので、ちゃんとメンバーのことを代弁出来るだけの器を持って、受け入れていきたい。だから今はすごく難しいですね。やっぱり俺のことをフィーチャーして欲しいし、勝手にみんなのこともフィーチャーしといてくれたらありがたいんですけど(笑)。バンドがどこを向いているのかも、ちゃんと伝えていけるだけの人間になりたいなって」
――それこそ先行シングル『Out Of Control』(M-5)の時期くらいはまだまだガンガン行くモードみたいな印象があったけど、アルバムまでの間だけでも結構温度差があるね。
「今回のアルバムは、4人で作っているものなのに、これは俺だなって思うし、俺が作っているものだけど、これは4人だなって思うんですよ。無条件で1つの生き物みたいに思っているので、あまり自分だけフィーチャーしたくない気持ちが今はある。ある意味以前よりは自分に自信があるからだろうし」
――そもそもなんやけど、みんなの中でちゃんと話さなきゃいけない時期が来たのは何なんやろうね。何か大きなきっかけがあって?
「3枚目の『echo』(‘11)を作って、サウンド的な面で一周した感じがあったんですよ。で、4枚目の『Silver Sun』で言わば1stみたいな衝動と手応えを感じて、じゃあこれから先どうするんだ?って正直なってて。次のアルバムまでの短いスパンで、まだ何も補充出来てない状態で、俺たちまた同じことやんの?って」
――リリースのペース的にはアウトプットばっかりやもんね。
「そうなんです。ただ俺たちの宿命って、そこと闘っていかなきゃいけなくて。絶対に1年にアルバム1枚は出したいし、俺たちを見てくれている人たちの想像通りにはなりたくないし、いい意味で裏切りたい。でも、このアルバムを作るときも曲のネタを持ってくるのが精一杯で、それに対しては不安もあったし。そうなってくると自分たちで自分たちを更新していくのって、気持ちでしかないじゃないですか? 内面をどんどん削っていくしかない。だから、ボタンの掛け違いみたいなものがあったまんまで、不安な気持ちのまんまじゃいられないんですよ。“本当にみんなの向いている方向は一緒?”っていう答え合わせが必要だった。これは絶対に運命だと思ってますよ。それがやっと出来るようになったのも、4人それぞれが成長したからで、4人でちゃんとバンドになってる。何日も徹夜してヘトヘトになってでも描くことは1人なら出来るけど、4人がそういうことを一緒になってやると、どこかで歪みは生じるわけで。それをちゃんと健全に乗り越えていかないと、絶対にバンドって強くならないんですよ。健全っていうのは、結局はどんな形でも“続ける”ことだと思うんですけど。間違いなくこのバンドは一歩進んだんですよ。だから自信を持って先があると言えるし、オーディエンスにも“ついてこいよ”って言える」
――そう考えたら、今回の『REVOLT』は本当に重要な作品やね。
「あんまり見たくないところですよね、感情がそこに全部収まっちゃってるんで。多分他のメンバーも一緒で、ライブとかキツそうですよね(笑)」
――バンドってやっぱり面白いなって思うんですよ。ライブを2階席とかから客観的に観てるときに特に思うけど、何で大の大人が4人も集まってって(笑)。
「すごい分かる(笑)」
――一生懸命何してるんだろうって(笑)。でも、それが美しいなと思うし、年数を重ねたバンドであればあるほどそう思う。結成当初はやっぱり出来ると思うんですよ。でも5年、10年、15年とやってるバンドが今でもこうやってステージに立って、それを観に来るお客さんがいるって、もう最高の景色だなと思うんで。ソロにはソロの良さもあるけど、4人で何かする方が難しいじゃないですか。それが面白いし、美しいですよね。
「何なんですかね。バンドってどこか馬鹿正直なところを持っていないと、ピュアなところでつながってないと出来ないんだろうなって。ピュアって=ものすごくキレイで、ものすごく汚い。ちょっと歪な形をしてるものが集まってるから、バンドって美しく感じるんじゃないかな。うちのバンドも早くそうなりたかったと思うんですよね」
延長線上にあって、同時にカウンターだった
――それこそ前作はソリッドなロックを極める、シンプルなロックンロールという命題があったけど、今回は音色的にも明らかに違って。どの時点でこのムードはあったんですか?
「ダンスミュージックとかエレクトロとか…もしかしたら『echo』の頃からあったのかも」
――ちょっとずつはフレーバーとしてはあったけど。
「そうなんですよ。それを少しずつ強めてきた感覚があって。それはロックからのカウンターでもあったんですけど。『echo』だと『Spiralbreak』、『Silver Sun』だと『PUPA』とか『Inside Out』…音は複雑に絡んでるけどダンサブルというか。それを『Out Of Control』とか『Bog』(M-8)『Predestined Lovers』(M-9)の制作時期にちょうど感じてたんじゃないですかね。あとは単純に前回は音を抜いたから、今回は詰め込もうという話もあって。だから延長線上にあって、同時にカウンターだったと思うんです」
――この試みはめちゃくちゃ成功してるというか、NCISが新しい地点に行けた感じがする。あと、今は“踊る”って言ってもダンスミュージックでダンスするんじゃなくて、ロックミュージックでいかにダンスするかっていうところも、シーンのムードとしてどこかに感じるから。NCISがやるとこうなるっていう意味では、すごく鮮烈な表現が出てきたというかね。『村雨の中で』(M-4)なんかのアレンジは、途中でゴソッと音がなくなってまた動きだす感じがめちゃカッコいいな~。
「ドラマティックですよね。サビはエモーショナルなコード進行に持っていく。このアレンジは結構考えましたね」
――ただ全編通して踊らせるとかじゃなくて、今までやってきたこととの親和性もちゃんとあって。こんなにヒリヒリしてるのに、ちゃんとトライもしてる。『Predestined Lovers』なんかも、音色も含めて面白いよね。
「新しいですよね、NCISぽくないというか。これは出来たときに“俺たち天才だ”って思いました(笑)。メロディありきなんですけど、全体のアレンジも普通の歌モノではないというか。こういうことが出来たことで、のびしろがまだまだある感じがしたし。『Assassin』(M-2)は最後に出来たんですけど、Bメロが一番カッコいいっていう(笑)」
――いや、Bメロがカッコいい曲=名曲なんですよ(笑)。でも、実際『Assassin』が出来たときには腸炎で倒れ…。
「俺いない、みたいな(笑)。そんなこともありましたねぇ」
“こんなに全部乗っけていかないと、いいアルバムって出来ないんだな”って
――今までの話を聞いてても、今回のRECは結構壮絶な感じが。
「みんなそれぞれにあったみたいですよ。それをなかなか表に出さないけど。『村雨の中で』とかサビの歌詞ハメをしたとき、ヘロヘロの声で歌ってたのに、ひなっち(=日向、b)とかちょっと泣きそうになっちゃってたし(笑)。だからすごい思い入れがあったんだろうなって。オニィ(=大喜多、ds)はPVを撮ったときに久しぶりに会って、ポロっと“やっとアルバム聴けたんだけどさ、いいアルバムだね”って言うんですよ(笑)。それは、本当にやれてるのかという不安とか、今までにいろいろあり過ぎて聴けなかったんだと思うんですよ。みんなそれぞれに、いろいろキツかったんじゃないですか」
――生形さんの時間がある限り練り続ける癖は?(笑)
「今回は結構抑え目ですよ(笑)。ただ自分のフレーズには相当のめりこんでましたね」
――緻密なフレーズを構築していく精度にかけては本当に日本有数やもんね。フレーズとして美しく、しかも幾何学的というか。弾ける人だから弾いちゃうよね(笑)。
「そうなんですよ。俺、弾けないですからね(笑)」
――みんながちゃんと自分を出してぶつけ合って。しかし本当に始まっちゃったというか、これからの作品を生み出すのにはパワーいるぞ~っていう。
「ひなっちも言ってましたよ。“こんなに全部乗っけていかないと、いいアルバムって出来ないんだな”って」
――今までは出来ちゃってたんだろうね、才能あるプレイヤーだから。それだけ自分を出さないと太刀打ち出来ないものになったのかもね、このバンドが。
「いいっすね。うちはバンドの成り立ちのことがよく話題に上がってしまうんですけど、周りにいてくれる人たち、面白がってくれる人たち、味方でいてくれる人たち、逆に言うと“はぁ?”って言う人たちも含めて、すごく反応があるバンドだったじゃないですか。ただ、バンドとして順当な経験が積めないように見られてるというか、そりゃそのメンツなら最初からスゲェだろみたいな(笑)。だから俺たちはいい加減には出来ないし、それを言い訳にしたくないので。バンドとして少しずつ積み上げていこうという気持ちがいつでもあった。それが少しずつ出来てきて、ようやくスタートラインに立てたところもあると思うんで。いいアルバムだと思いますよ」
――とりあえずオニィはすぐには聴けないくらい自分を詰め込んだということやね(笑)。
「そういうことですよね(笑)」
――どうですか、そのときの自分は?
「俺は毎日聴きましたよ。でも、やっぱり歌詞も歌録りも正直時間がかかってしまったんで。みんなが本当に気持ちを込めてたんですよ。だから俺はそれ以上にエモーショナルでいたくて、ガンガン感情を込めて歌ったんです。そうしたら『朱い群青』(M-7)なんか、最初は演歌みたいになっちゃって(笑)。気持ちが入り過ぎちゃって、自分の想像とは全然違うものになって。だから、そのときは最大限気持ちを込めてやるだけやって、真一が大丈夫って言ってくれるジャッジを信用して。今までだったら絶対に嫌だったけど、そういう風に頼れることも出来るようになったし」
――感情を込めまくったらいいってもんじゃないんやね。
「こぶしが効き過ぎちゃって(笑)。何せ小学4年生くらいで初めて歌ったカラオケが、島倉千代子の『人生いろいろ』なんで(笑)」
――アハハハハ!(笑)
「あと小学校1年生くらいの合唱でも、歌が好きだったし自信もあったので、思いっきり演歌調で歌ってた(笑)。そしたらさすがに怒られて(笑)」
――そのときに褒められてたら、案外そっちの方向に行ってたかもね(笑)。
俺たちでルールを決めて、自分たちの国を作る
今回やったことって、俺たちの中のルールとかそういうものに対しての
いわば革命じゃないですか
――あと、タイトルの『REVOLT』はREVOLUTIONからきてるということですよね。
「REVOLUTIONの元になる言葉なんですけど、暴動とか反乱とか、抵抗とか革命の意味も含めて。政治的な意味合いの強い言葉ではあるんですけど、思ったのはバンドって4人しかいない国みたいなものなんですよ。俺たちでルールを決めて、自分たちの国を作る。今回やったことって、俺たちの中のルールとかそういうものに対しての、いわば革命じゃないですか。今までのアルバムでも新しいことをやろうと毎回いろいろ変えてきたけど、それ以上に今回はメンタル面の革命がそれぞれに何度も何度も起きてて。今回は誰かのためのアルバムじゃなくて、自分たちのやったことをタイトルにしようって、『REVOLT』にしたんですけど」
――前作ではオーディエンスと目線が対等になっていく感覚が1つの距離感としてあって。今回はバンド間での距離感の変化という感じですね。対オーディエンスというところに意識が働いた後は、もうそこにいくしかないという。
「なるほどね。そうだったのかもしれないな。確かにオーディエンスとの関係性を考えるのに必死だったところもあったので。ただの自己満足じゃいけないと思ったし、聴いてくれる人たちに何が出来るかをずっと考えてたんですけど、それだけが=バンドをやる目的じゃない。俺たちは好きだからやってるっていうのが根本なので。あの頃はそれに必死でしたよね(笑)。そこにばかり目がいってて」
――そして、『REVOLT』に伴うツアーもあります。
「ただ、さっきも言ったんですけど、ライブするのはキツいんじゃないかなというのもある(笑)。気付いたら隣でちょっと涙ぐんでるとか、前回のアルバムから結構そういう傾向があったんで(笑)。泣くだけじゃなくて、音にのめりこんで溺れる、トリップするみたいな感覚になることが増えるんじゃないかな。そういう音楽を使って、どこまでオーディエンスと共有出来るか。多分みんなのめり込んでいくし、もっともっと深化していくと思うんですよ。俺はみんなよりはフラットな位置で、感情込めて歌を歌うことに徹して。オーディエンスを受け入れていくだけの、手を広げた状態でライブをして、今までのようにつながっていたい。より深いところでみんなの感情を呼び起こすような、そういうライブが出来たらいいなと思ってます!」
Text by 奥“ボウイ”昌史
(2013年9月 5日更新)
Check
Release

よりアグレッシヴに深化するメジャー
2作目となる転機の5thアルバム!
Album
『REVOLT』
発売中 2800円
エピックレコード
ESCL-4066
<収録曲>
01. Song for an Assassin
02. Assassin
03. You’re in Motion
04. 村雨の中で
05. Out of Control
06. Sick
07. 朱い群青
08. Bog
09. Predestined Lovers
10. きらめきの花
11. The Fool
Profile
ナッシングス・カーブド・イン・ストーン…写真左より日向秀和(b)、村松拓(vo&g)、生形真一(g)、大喜多崇規(ds)。’08年に現在活動休止中のELLEGARDENの生形、ストレイテナー / killing Boyの日向を中心に、村松(ABSTRACT MASH ※現在は活動休止中)、大喜多(FULLARMOR / killing Boy)が集まり始動。’09年には1st アルバム『PARALLEL LIVES』、‘10年には2ndアルバム『Sands of Time』、’11年に3rdアルバム『echo』と、コンスタントにリリース。高い演奏力とキャリアに裏付けられたハイボルテージなライブで、各地のイベントや大型フェスで圧倒的な存在感を見せ付けている。'12年7月にシングル『Pride』をリリース、8月に4thアルバム『Silver Sun』にてメジャーデビュー。そして、今年6月26日には5thアルバム『REVOLT』を発表、現在は同作に伴う全国ツアー中である。バンド名はモーゼの『十戒』に出てくる十の規律が刻まれた石に、何も書かれていない=規律、タブーがないという逆説的な意味。
Nothing's Carved In Stone
オフィシャルサイト
http://www.ncis.jp/
Live
絶対いいに決まってる壮絶なツアー
大阪公演が間もなく開催!
Pick Up!!
【大阪公演】
チケット発売中 Pコード199-351
▼9月6日(金)19:00
なんばHatch
1Fスタンディング3300円
2F指定席3300円
ソーゴー大阪■06(6344)3326
※3歳以上は有料。
【福岡公演】
チケット発売中 Pコード199-283
▼9月7日(土)18:30
DRUM LOGOS
オールスタンディング3300円
BEA■092(712)4221
※3歳以上要チケット。
チケットの購入はコチラ!

【名古屋公演】Thank you, Sold Out!!▼9月13日(金)19:00
クラブダイアモンドホール
前売3300円
ジェイルハウス■052(936)6041
※3歳以上有料。
【札幌公演】Thank you, Sold Out!!▼9月15日(日)18:30
ペニーレーン24
オールスタンディング3300円
WESS■011(614)9999
※3歳以上はチケット必要。
【東京公演】Thank you, Sold Out!!▼9月20日(金)19:00
Zepp Tokyo
スタンディング3300円
2F指定席3300円
ディスクガレージ■050(5533)0888
※3歳以上はチケット必要。
Column1
4thアルバム『Silver Sun』で
メジャーシーンへいざ出航!
ロック無敵艦隊NCISが
バンドの現在を語るインタビュー
Column2
バンドの成長過程と覚悟を語った
3rdアルバム『echo』インタビュー