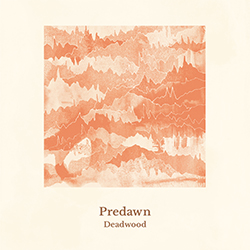「音楽は日常に潜む神様のようなもの」
活動10周年を迎えたPredawnインタビュー&動画コメント
2008年に自主制作盤『10 minutes with Predawn』をリリースし、清水美和子のソロプロジェクトとして始まったPredawn。今年活動10周年のアニバーサリーイヤーを迎えた。2月にはデジタル配信シングル『Deadwood』をリリースし、同月、Billboard Live TOKYOで10周年記念公演、8月には上野恩賜公園 野外ステージで自主企画『Predawn 10th Anniversary “Dusk” Party』を開催。そして11月22日(木)大阪・ユニバース、12月6日(木)東京・キネマ倶楽部で開催の『Predawn 10th Anniversary Grand Finale “Nectarian Night #06”』を以て10周年アニバーサリーイヤーは締めくくりとなる。やわらかく、聴く者の心にそっと染み入る天性の歌声。ふんわりとした空気を纏う彼女の中に潜むのは、音楽への飽くなき探究心と確固たる愛情だった。これからも続いていくPredawnの物語。今回は清水美和子に、ゆるく10年間を振り返ってもらった。
良いものを出さないと意味がない
――10周年おめでとうございます。今実感としてはどんな感じですか?
「実感……ないんです(笑)。あんまり音源も出てないっていうのもあるかもしれないですけど(笑)」
――10年間でリリースされたのは、自主制作盤1枚、ミニアルバム1枚、フルアルバム2枚、シングル1枚、 DVD1枚ということで、確かにだいぶじっくり制作してこられてはいますね。
「中身の薄い10年みたいな(笑)。でも、“あ、続けてきたんだな”っていう感じがしますね」
――作品は少ないながらも、続けておられるということが素晴らしいと思います。過去のインタビューなど拝見していると、美和子さんは本能で生きてらっしゃるというか、音楽活動に関してもすごく芯がある方という印象です。
「頑固だって言われます(笑)」
――音楽は生活に根ざしたもので、良い音楽を作りたいという気持ちで作られているんですよね。
「まあそうですね」
――Predawnとしての活動を始めた時のことを思い返すと、どんな自分だったと思いますか?
「大学3年か4年かだったんですけど、その頃は自信もないから周りの人に“やりなよ”って勇気づけられてなんとかステージに立てたという感じでしたね。マイクからの位置がすごく遠くて“聴こえねえよ”って(笑)」
――自信がなかったんですか?
「今でもないんですけど、もっと全然自信がない。いつも“どうしよう”っていう感じで。でもPredawnっていう名前をつけたことで、プロジェクトとしてやっていこうという気持ちになったのかなって、今では思います」
――自分で歌を歌いたいという気持ちは、ずっと持っていたんですか?
「そうですね。自分で曲書いて歌ってる時は楽しかったし、充実してたんだろうなと。あんまり覚えてないんですけど(笑)」
――(笑)。22歳から32歳という、1人の女性としての人生の10年間とも言えますね。
「大人になったなあと、思いますね」
――思われます?
「体にガタがきたなあとか、お酒が弱くなったなあとか(笑)」
――そこですか(笑)。デビューの頃、線が細くて可愛らしくて、少女みたいなイメージだったんですよ。作品も絵本のような世界観で。ただ、作品を経るにつれて、内容も大人びてきていると感じていました。ざっくりと作品のことをお聞きしていきたいと思うのですが、『10 minutes with Predawn』を作った時のことは覚えてますか?
「おぼろげに(笑)」
――全部宅録だったんですよね。
「そうです。宅録と打ち込み。私はだいたい東京で育って、長野の大学に通っていて。高校の友達とバンドを組んでたんですけど、夏休みとか、機会がある時だけちょっと集まってやったりしてて。 『10 minutes with Predawn』は、そういう時メンバーにうまく“こうしたい!”って伝えづらいから、デモを作りたいと思って機材を揃えたりしたのが始まりなんですね。若いバンドとかライブする時にデモ盤を配ったりするじゃないですか。そういうのを私も作りたいなって」
――名刺代わりの盤を。
「で、ミックスをどんどんしているうちに“これは売れるぞ”って耳打ちが(笑)」
――え、どこから?(笑)。
「周りからこそっと(笑)。私は打ち込みだしな~とか、自信がなくて、あんまり売る気はなかったんですけど(笑)」
――打ち込みはお好きではないんですか?
「その時の私はバンドサウンドが好きだったし、打ち込みはエレクトロやヒップホップの文化だと自分の中で分けていたので。ほんとは生バンドを入れて作りたかったんです」
――なるほど。でも『10 minutes with Predawn』は1年間で2000枚が売れましたね。
「最初、東京のモナレコードさんでライブさせてもらった時に、うちでも売りたいからとりあえず5枚預かりますって言われて、そうこうしてるうちに10枚とか20枚とか、注文の数が増えてって。そしたら今度は大阪のFLAKE RECORDSさんが売りたいと言ってくださって。ちょいちょい50枚くらいを宅急便で送ってました」
――ご自分で梱包作業を?
「はい。注文入った時とか大変でした。CD焼いて、プリンターで印刷して、自分でジャケット切って。マネージャーさんが当時勤めてた流通会社で捨てられてしまうCDケースを横流ししてもらって(笑)」
――今だから言える話ですね(笑)。自分の音楽がじわじわ広がっている感じはどうでしたか?
「嬉しいですけど、なんか、すごい騙してるんじゃないかって(笑)」
――え!? 打ち込みだし?
「こんなのが売れるのかって(笑)。自分ではミックスも上手くできるようになってきたし、気に入ってはいるんですけど、このクオリティで、っていうのはあって」
――なるほど。最初はひとまず活動するための名刺代わりがあれば、という感じだったんですか?
「うん、そうですね」
――その名刺が広がっていき、 2010年に1stミニアルバム『手のなかの鳥』ができるわけですね。『10 minutes with Predawn』から2年が経っていますが、それまでは曲作りをされていたんですか?
「そうですね。各方面からプロデュースしたいっていうお話をいろいろいただいたんですけど、自分で作りたくて。今でこそいろんな女性シンガーソングライターの方がいらっしゃるけれど、当時は結構ステレオタイプというか、はめられてしまうのかもしれないという恐れを抱いてて(笑)」
――個性を消されてしまうんじゃないかと。
「そういうのに乗っかるなら、一旦ミックスまでやって自分が好きな音楽を出してからかなと思って、『手のなかの鳥』を作りました。多分ずっと自分でいじくりまわしてたから、すごい時間がかかったんですよね」
――演奏、録音、歌、作詞、作曲、レコーディングを全て1人でされていたんですよね。少しずつ進めて完成したのが2010年ということだったんですか?
「おそらく(笑)。ライブもやりながら、バイトもしながらだったので、そんなに時間かかったんだろうなって。ちょっとグダグダしてたのかも(笑)」
――2009年にはフジロックやap bankフェスに出られてお忙しかったんじゃないですか?
「そうかもしれないです」
――あんまり覚えてないですか?
「すいません……結構ゴロゴロしてたんだと思います(笑)」
――ゴロゴロ(笑)。2013年の1stフルアルバム『A Golden Wheel』まではセルフレコーディングでされていますが、そうしようと決めていたんですか?
「特に決めてはないんですけど、“今ある曲たちを出さなくちゃ”という使命感に駆られて。あと引きこもっていろいろ作業をするのが単純に楽しいですし、“この感じ良いな”って、味をしめたんだと思います(笑)」
――好きな音楽にひたすら集中できるのが嬉しい?
「そうですね。あと周りのバンドとか見てて、バンドって大変そうだなって(笑)」
――1人で良かったなと?(笑)。
「はい。なんでも思い通りにできるので(笑)」
――『手のなかの鳥』から『A Golden Wheel』は3年越しのリリースで、かなりスローペースだと思いますが、やはり自分のやり方でいきたいという気持ちが大きかった?
「結局、良いものを出さないと意味がないなというのはずっとあったので、別に焦らなくてもいいのかなって。適当なものを出したくない。ちょっとそういうところがあるのかなと思います」
――なるほど、納得のいくものを作りたい。ずっとブレずにいるのはすごいと思います。
「ブレないところはブレずに、その中で考えさせられるところは考えたりしつつ。でもすごい頑固だってよく言われますね(笑)」
いつも作品が完成した後に、2週間ぐらい寝込むんですよ
――『A Golden Wheel』に関しては、楽器の種類が増えたり、ギターをバイオリンの弓で弾いたり、伊豆まで音を録りに行かれたりと、実験的な試みも取り入れておられますね。
「ああ、懐かしいです」
――ドラムにも挑戦されていて。
「ドラムに挑戦したというより、打ち込みするための材料を録ったという感じですね。スタジオに行っていろいろマイクを借りて、何曲かほんとに簡単なフレーズだけ叩いたりしてるんです。それを家に持ち帰って作業して。“パズルを組み立てたい、然るべきタイミングで音を入れたい”っていう欲がすごくて(笑)」
――パズルを組み立てていく感じなんですね。
「そうなんですよ。だからドラマーの方からしたら全然整合性がないと感じると思うんですけど、自分の中では“この辺からこういう音を鳴らしたい” とか、こだわりがあったんだと思います」
――理想の音を追い求める。先ほどのお話にも通じますね。
「結構思い切ってた気がします。しっちゃかめっちゃかというか」
――しっちゃかめっちゃかというのは。
「何だろう、『手のなかの鳥』と『A Golden Wheel』は割と冒険しているというか。聴く音楽も偏っていて、そういうものへの愛を感じるというか、やってるうちにどんどん迷路にハマっていくような感じもあって。でもそれはそれでおもしろかったと今では思っています」
――当時は苦しかった?
「“やっとできた!”って、いつも完成した後に知恵熱なのか、2週間ぐらい寝込むんですよ」
――全身全霊で出し切った感じなんですかね。
「そんなこともないんですけど、なんかいっつも体調を崩してましたね」
――1枚目の時も、2枚目の時も?
「確かそんな記憶があります」
――曲を作るのはパワーを使うものですか?
「曲を作るというか、音源を作るということがですね。時間とか結構いろいろ忘れてやってしまってたので」
――寝食忘れて?
「お腹空いたら食べますけど(笑)。でも一旦入り込むと、ずっとやってるところがあります」
――だいたいどれぐらいの間、集中する期間になるんですか?
「細かく1ヶ月ずつくらい、いろんなフェーズでやってた気がします。あと時間がかかるのは、特にレコーディングがちょっと億劫になってしまうというか」
――それはなぜですか?
「当時白いibookを使ってたんですけど、今のに比べたらだいぶちゃちくて、Protoolsとか入れるとほんとにすぐ止まっちゃって。だから結構億劫になってしまって。“ダメだ今日は!”って(笑)」
――乗り気になったら早いんですか?
「そうなると何時間でもやっちゃうんですけど、気が乗らないと何もできないタイプですね」
――2016年の2ndフルアルバム『Absence』では初めてゲストミュージシャンとして、ライブメンバーでもある神谷洵平さん(ds)、ガリバー鈴木さん(b)、武嶋聡さん(fit)が参加されています。ゲストミュージシャンと一緒にやってみようと思われたキッカケはあったんですか?
「『手のなかの鳥』を出して、自分のイベントをやりだした辺りから、ライブでは神谷くんとガリバーさんを迎えてバンド編成で割と何年もライブしていて、だいぶ打ち解けてきたというか(笑)。この感じを音源にしたいなというのもあるし、単純にバンドサウンドでもガンガンやってみたいというのもあって、頼むことにしました。世界に対して作っていた殻をちょっと開けてみたというところもそうですね(笑)。私蟹座なんで、すごい殻があるって言われるんですけど(笑)」
――蟹座の人は家族や友達、身近な人をすごく大事にするイメージがあります。
「お家が大事なんです。そこはすごい当たってる気がします」
――殻で自分を守っていた部分がずっとあったんですか?
「小さい頃から自然とそうしちゃうんだと思います。それが時々チラッと開いたりするんです(笑)」
――歌詞の内容で言うと、『手のなかの鳥』と『A Golden Wheel』は自身のことを歌いながらも少し俯瞰していますし、物語の1つというイメージがありましたが、『Absence』からは“絶望”という単語が出てきたり、『Hope& Peace』(M-9)で、“求めていたものではなかったけれど 人生は思い込みだらけの 信じられないほど素晴らしい物語”だったりと、生身の人間らしさが出てきて印象が変わったと思います。やはり30歳という年齢からも深みが加わったような。
「まあまあ、その前にいろいろあったんで(笑)」
――言えないやつですか(笑)。
「言えないです(笑)。まあわかりづらい表現になるんですけど、最初は歌詞を書く時に、言葉の響きと意味を同じように見てたんですよね」
――響きと意味。
「響きが直接空気を揺らして意味になっていくみたいな感覚があって、今まではそういう感覚を中心に歌詞を作っていったんです。『Absence』を作った時は、大学卒業したあとに哲学の本をゆっくり読んだりしていて。割と詩的な表現をする哲学者も時々いるんですよね。それで、“詞とはなんだろう”ということをいろいろ考えてました」
――答えは出ましたか?
「答えは全然出ないですけど、そういうのを考えながら作っていった気がします。前みたいに“言葉は響きだ。響きは言葉だ”みたいな感覚もあるんですけど、“詞”というものを捉え直したというか。1回バラして組み立てるということをしてる時期でもあるのかなと思います」
――美和子さんの場合、歌詞は曲とともに出てくるんですよね。
「前はそんな感じだったと思うんですけど、今は全体を通してどういう詞にするかを悩んだりしていて、『Absence』はそういう努力がみてとれるアルバムになったと思います(笑)」
――では歌詞はすんなりとはいかなかったんですか?
「そうですね、結構悩んだり、後から書き直したり、修正も多くなったと思います」
――『霞草』(M-6)は『A Golden Wheel』のボーナストラック『虹色の風』を除くと初めての日本語詞の曲ですが、日本語で詞を書いたというのには何か理由がありますか?
「……特に(笑)」
――(笑)。
「でも『霞草』は、このアルバムの中にいてもいいなと思えたので。地つづきで聴けるなっていう気がしたし、アルバムのテーマもちゃんと含んでるというか」
――振りかえってみて、ターニングポイントとなった曲や作品はありますか?
「アルバムとしてはやっぱり『Absence』がターニングポイントだと思います。さっき言ったみたいに、詞を捉え直したところが大きいですね」
音楽や音を通して世界を認識してるみたいな感覚がある
――今年2月に配信で出たシングル『Deadwood』はどんな気持ちで作った曲なんですか?『TOYOTA T-Connect「クルマとワタシ」編』のテレビCMソングになっていますよね。
「この曲は、“許せないぞ!”と追っ払ったものに対して、許すことがどういうことなんだろうと考えてる時に書いた曲ですね」
――許すということ。
「癒されるのも1つなのかもしれないですけど、傷が癒えるとか、割とそういう詞になってるのかなと思います」
――許す、癒されるがキーワード。
「そうですね。『Deadwood』を録った時はCMの話がきてて、今できてる曲の中でこれが1番合うし、録ってやろうじゃないかという気になったので、パッと録ったんですけど、良い感じにできてすごい満足してます」
――大きな質問になっちゃいますが、音楽って美和子さんにとってどういう存在ですか?
「どう、なんですかね。あまりに身近だし神々しすぎて、これというのは言えないですけど、でもそういう感じですかね。日常に潜む神様、みたいな」
――神様。
「神の力みたいな。日本で歩いてると、ちょいちょいお地蔵さんがあったり、お寺さんがあったり、お家に入ると仏壇や神棚があったり。自分はそんなに宗教的ではないですけど、なんかそういう感じで存在するものというか」
――日本は八百万の神と言いますしね。
「昔の人はすごいカッコ良い木があったりすると、そこに神社を建てたりするんだろうなって。その場所が神々しかったから神社を作って、今も残ってて、ありがたがってるんですけど、そういうのと近いかもしれないです」
――具体的にはどういうことですか?
「いろんな人がそうだと思うんですけど、満員電車で殺伐としてても、イヤホンで好きな音楽聴いてるとホッとするとか、そういうところはほんとに神様みたいだと思います。救われてる」
――Predawnの音楽がそういうふうにあってほしいという気持ちは?
「そうだったら嬉しいですね。時々“寝る前に聴いてます”とか言われるとすごく嬉しいなって思いますし」
――美和子さんご自身も、音楽を作ることで自分が救われている部分が大きいですか?
「作るのは大変ですけどね(笑)。でもこれしかないなというのはずっと感じてるところではありますね。音楽や音を通して世界を認識してるみたいな感覚もあるし。ほんとにちっちゃい頃からそこは変わってないと思います」
――アーティスト活動10年ですけど、今楽しいですか?
「楽しいです。落ち込むこともありますけど。最近、神谷くんとガリバーさんとレコーディングをした後、こういうふうにサポートしてもらえたり、自分の好きな音楽を好きなようにやらせてもらえてるって、ほんとありがてえなあって思いながら帰りました(笑)。続けるにつれてやっぱり感謝の気持ちは大きくなってきましたね」
――10周年のアー写がギリースーツなので、10年間は戦いだったのかなと勝手に解釈したんですけど。
「あれは悪ふざけですけどねえ(笑)。10年だからアー写の衣装代が出るぞっていうのを聞いて“ギリースーツが着たい”って(笑)」
――なぜ?
「擬態したかったんです。ほんとはどこに私がいるのかわかんないアー写にしたかったんですけど(笑)。いろいろ後付けで理由が生まれましたね。はじめは大人の悪ふざけです(笑)」
――ちょっとかわいらしいギリースーツですね。
「犬を飼ってる人からモフりたいと言われました(笑)」
――やわらかいんですか?
「結構やわらかいです。でも最初届いた時、葉っぱとかをつけやすいようにワックスがついててペトーってなってたらしくて、モフモフをほぐすのが大変だったって(笑)。だからあれ買いたい人はそこに注意してください。多分買ってすぐ着れないです(笑)」
――ひと手間必要なんですね(笑)。11月の大阪・ユニバースと12月の東京キネマ倶楽部で開催される『Predawn 10th Anniversary Grand Finale “Nectarian Night #06”』で10周年アニバーサリーイヤーが締めくくりですが、どんなライブになりそうですか?
「まだ何も考えてないです(笑)」
――意気込みは?
「そうですねー、まあやりたいようにやる感じです(笑)。椅子もあるので、お客さんにもそれぞれ好きなスタイルで、いい感じで楽しんでもらえたらいいなって、それだけは決まってます(笑)」
――ちなみに2月にはBillboard Live TOKYOでストリングスも含めた編成でライブをされていましたが、いかがでしたか?
「6人編成で何年かぶりにライブができて、めっちゃ楽しかったです。やっぱり管弦楽器がすごい好きなので。疲れたんですけど、もうちょっとやっていたかったなと思えるライブでした」
――6人編成はもうされないんですか?
「今んとこ予定がないですけど、『Nectarian Night #6』は一応バンドセットで、大きい人と小さい人をつれていきます(笑)」
――改めて、2018年の10周年イヤーはどうでした?
「10周年というだけでいろいろやらせてもらえてありがたい限りだったんですけど、おだてられるのに耐性がないので(笑)。“今年10周年なのでこれやります、あれやります”と告知すると、皆さんがすごい拍手してくださって。まだ音源出してないのにこんなに祝ってもらって、ほんとかたじけねえと思って(笑)。でもほんとにやってきて良かったなと改めて思いました」
――これからもアーティスト活動は続いていくと思いますが、この先のビジョンなど、今考えていることはありますか?
「いろいろあるんですけど、開けてみてのお楽しみってことでいいですかね(笑)」
text by ERI KUBOTA
(2018年11月15日更新)
Check