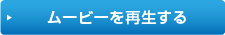『選ばれてここに来たんじゃなく、選んでここに来たんだ』
メジャー1stアルバムを引っ提げた全国ツアーもクライマックス!
'10年代のロックシーンを刺激するThe Mirraz畠山承平(vo&g)の
“ものづくり”のプライドとスタンスに迫る
シニカルでユーモアに富んだ言葉の弾丸をマシンガンビートに乗せてぶっ放すロックンロール・スナイパーにして、インディーズシーンでその名を知らしめた’10年代のロックシーンをリードする異端児The Mirrazが、昨年10月遂にメジャーシーンへ進出! 1st シングル『僕らは/気持ち悪りぃ』がいきなりオリコンデイリーチャートで最高 8 位を記録、あの桑田佳祐が選ぶ2012年の20曲にも『気持ち悪りぃ』が選ばれるなど、デビュー早々旋風巻き起こした彼らは、今年2月に満を持してリリースしたメジャー1stアルバム『選ばれてここに来たんじゃなく、選んでここに来たんだ』に伴う全国ツアーの真っ只中にいる。そこで、2013年代を飾るロックアルバムを手に、今まさにバンドの充実期を迎えているThe Mirrazの頭脳・畠山承平(vo&g)にインタビューを敢行。ツアーも東阪を残すのみとクライマックス、夏に向けたミニアルバム『夏を好きになるための6の法則』のリリースもアナウンスされるなど攻撃の手を緩めない彼らの、バンドのヒストリーから現在進行形のマインドに至るまでを探る。
畠山(vo&g)がアルバムとライブを語る動画コメント!
——今日に至るまで、去年のメジャーデビューからまずさかのぼって聞かせて頂きたいのですが、今はインディーズでもセールス的にメジャーに引けをとらないアーテイストも多くいる中で、The Mirrazはその代表的なところでもあったと思うんですけど、このまま自分たちでやろうというのはなかったんですか?
「The Mirrazを始めたとき、100万枚CD売りたいとかトップアーティストになりたいと思っていたので、メジャーに行くのが普通かなと思っていたんですよね。本当は3rdアルバム『TOP OF THE FUCK'N WORLD』(‘10)の前ぐらいからメジャーに行こうと思っていたんですけど、いざ契約の話をすると何を決め手にしていいのか分からなくてなかなかまとまらず。でも、よりステップアップしたいと思っていたし、そこに可能性を感じていたので。1回メジャーに行ってみないと分からないというのもあるんで、ようやく良い話が出来たから今、という感じなんですよね」
——The Mirrazってインディーズの頃からヒール役を買って出るじゃないですけど、話題にはなるけど痛みも伴うようなこともガンガンやって、消耗しながらようやく音楽的なところだけできちんと支持されるところまで登ってきたというか。振り返ってみて結構壮絶なストーリーだと思ったんですけど。
「The Mirrazっていうバンドのイメージがあると思うんですけど、実は自分でもそこまで狙ってやってきたわけではなくて。2ndアルバム『NECESSARY EVIL』(‘09)でも、音楽的な面で敢えて洋楽をパクって日本で出すってことは、音楽として最先端であると同時に必要悪だと思ってたんです。でもそういうバンドの活動的なところをフィーチャーされて情報とかイメージが先行しちゃって、仰る通り意図せず消耗することが多かったのはありますね。それを逆に利用する瞬間も当然あったし、それぐらいしなきゃ損しちゃう部分もあった。だからこそ今回は音楽で勝負したいというのもありました。フレッシュなイメージでやりたかったし、音楽一本でちゃんと聴いてもらえたら嬉しいです」
——いろんなインタビューを読んでいても、畠山さんは日本の音楽シーンにないもの、新しいことをやることに対して、すごく意識がありますよね。
「“ものづくり”ってそうじゃないと意味がないと思っていて。例えば、“今はこれが流行ってるから”っていうのは売り物を作る発想で、だったら俺は音楽をやる意味が全くないと思う。音楽をやる以上、今にないものを作ってそれを日本というマーケットに置くことで、日本の文化が変わっていくのが好きなので。そこは常に意識していないと、“ものづくり”する人としてのプライドとか立場を維持出来ないんじゃないかと思うんですよね」
——後追いしたものって、時代には合うかもしれないけどカルチャーを作れないというか、“初めて”を作らないと流れは出来ないですよね。畠山さんは今回のパッケージのデザインもそうですし、ミュージックビデオも作る。“ものづくり”としてはいろんなアウトプットが選択肢としてあったと思いますけど、何で音楽を選んだんですか?
「一番表現として難しいしやり甲斐があるなと思ったんですよ。映像も好きなんで今でも自分でPVを作ったりしてるんですけど、分かりやすいものを提示するっていう意味では、視覚の表現ってすごくストレートに届けられるけど、聴覚に届けるのってちょっと難しいんですよね。形がないからいろんな形に出来るというか、人それぞれの形になる。それがまた面白いなぁって。俺自身単純に音楽が好きなのもあって、音楽が一番世界が変わる感じがして。例えば、音楽を聴きながら街を歩いていても、その曲によって街の風景が全然違って見えたり、悲しいときにそういう曲を聴いたらより悲しくなるとか、逆に楽しい曲を聴いたら楽しくなれちゃうっていう、心に直接届くようなものの気がするんですよね。人の心を変えることで世界が変わるのがすごく気持ちいいし、単純に音楽を聴いてて楽しいな、テンション上がるよなって感覚があるので、音楽を選んだ気がします」
——あと、音楽は行為と共存出来るのも面白いですよね。
「ありますね。例えば、昔ドラクエでレベル上げするとき、音を消してずっとTahiti 80を聴きながらやってたんですよ。だからTahiti 80聴くとドラクエを思い出しちゃう(笑)。もっといいエピソードであれば、“あのときの思い出が蘇る”とかですけど、俺の場合はドラクエ(笑)。でも、逆もあるんです。ドラクエをやってるとTahiti 80を聴きたくなるっていう(笑)。やっぱりそういう不思議な力があると思いますね」
——そういう意味ではメジャーに来て、今までのThe Mirrazを知らなかった人に知ってもらって、“あのとき俺The Mirraz聴いててさ”っていう話もね、起こり得る。面白いことが始まった気がしますよね。
「そうなんですよね。若い子にとっては青春の1枚みたいになるかもしれないんで」
音楽で新しい時代感を感じるには、リズムが一番大事だと思う
——The Mirrazの存在ってシーンに対するカウンターみたいなところもあったと思うんですよね。でも今回のアルバムを聴いて思ったのは、“勝負する”とか“引き受ける”という意思というか、人と違うことを、新しいことをやるのはもちろん、同じ土俵に立って勝つんだという意識があるなと。
「そうですね。そのカウンターカルチャーみたいなところとはまた別で、俺たちの武器がこれだけあるから、その中から選んで単純にカッコいい音楽を作ろうよって。メジャーでの1stアルバムなんだから、知らない人が聴いたときに“The Mirrazってこういうバンドなんだ”って分かるような作品にしたいとは思ってたので」
——今ある武器というのは?
「例えば言葉数が多いとか、イギリス直系の攻撃的なサウンド。歌詞の内容もただ言葉数が多いのではなくて、そこにメッセージ性だけではなくユーモアと余裕があるというか。そこに最近聴いているダブステップだったりUSインディーの要素もあって、でも、『ハッピーアイスクリーム』(『TOP OF THE FUCK'N WORLD』(‘10)収録)とか『シスター』(『OUI! OUI! OUI!』(’08)収録)みたいな曲が持つ優しい世界観もあるし」
——すごく自己分析出来ていますね。
「今回は特に、みんなで振り返って自己分析したのはありますね。メジャー1stアルバムだから今まで以上に考えて」
——作っていく中で得た、新しい自分たちの武器はありました?
「今回はダブステップとか新しい音楽を取り入れたくて、ギターのリフにリバーブなりディレイをかけていくことで世界観が広がって、さらに高い音域に敢えて行ってみたら全体的に宇宙っぽいサウンドが出来あがって。あと、『S.T.A.Y.』(M-11)『きっと、きっとね』(M-12)とかは敢えて言葉を減らしたんですけど、全然成立してるじゃんって感じもあったし」
——音が良いと同時に独特の音ですよね。言葉数の多さとかリフがありながら、めちゃくちゃ隙間もあるという。どうやって録ったんだろう?って。
「ヴィンテージのアンプとかエフェクターを使ったりもしたんで、そこは結構デカいと思いますね。ギターをあんまり歪ませ過ぎないとか。あと、音楽で新しさを出すには、新しい時代感を感じるにはリズムが一番大事だと思っていて。そこはThe Mirrazって独特だと思うんですね。クラブミュージックを意識もしてるし、打ち込みっぽいところをわざと生で演奏するとか。最近のダブステップ、レゲエ、ヒップホップとかそういうリズムの影響からロックをやっているので、そこが隙間と言われるのにつながっているとも思いますね」
——模倣から始まって、異物だった物が王道になったというか、そこを極めたら新しい音楽になったと、このアルバムを聴いて感じました。今まで時間をかけて培ってきた“らしさ”を、ようやく自分たちのものに出来たというか。時間はかかったじゃないですか。最初はスキャンダラスな感じで騒がれて、かと言ってそこで一気にハネるわけでもなかった。やっぱり諦めずに真摯にここまでやってきたことが音に出るんだなと。
「今回は特にそれを思いましたね。やっぱり精神状況みたいなものがハッキリ出たなと。メンバーみんなが前向きにいい作品を作りたい気持ちだったので。当たり前なんですけど、それは今までと全然違う種類のものだったと僕は感じていて。それがハッキリ音に出た」
——どうしてもミュージシャンって自分の精神状態が音に出ちゃう。だから、音に出てもいいように普段の精神状態を良くしなきゃいけないと。
「それ、すごい分かりますね。今まで活動してきたからこそ思うんですけど、やっぱりそのときその人の何かが結局音楽に出ちゃうんだなって。それは最近自分でもすごく感じるところですね」
——それが映像だとかデザインよりも如実に出るところが、音楽の面白さかもしれないですね。そういう意味では、音楽における作品集を“アルバム”って最初に名付けた人はすごいなと思うんですけど、ホントに写真みたいなもので、そのときのその人の記録という機能もあるなぁと。
「うまいですね。なるほどね」
——そんな中での“ものづくり”は、充実してたんじゃないですか?
「楽しかったですね。音作りにこんなにこだわって時間をかけられたのも初めてだったし、可能性がいくつかあるときに、その可能性をちゃんと1つずつジャッジして、これが一番カッコいいと決められる。それって時間がないとなかなか出来ないことなんで。あと、自分がイメージしているものが割とすぐに形に出来たというか。もちろん今までの経験もあるとは思うんですけど」
——今回のアルバムはメンタル面もそうだし、サウンドを作るフィジカル面でも、充実の状態にバンドがあることを証明したと思うんですよね。
音楽を続けていると、プレゼントみたいなものがあるんだなって
――そして、『選ばれてここに来たんじゃなく、選んでここに来たんだ』というタイトルは最高だなと。これはどうやって名付けたんですか?
「メジャーに来たからこういうタイトルっていうのもあるんですが、違う深い意味もあるというか、俺にも分かっていない何かがこれにはありそうだなって。今までは、自分で“こういうものを作ろう”ってネタを見付けて曲を作る発想だったんですけど、今回は逆に音楽が俺の方に来てくれて、自然と曲が出来あがっていった感覚があったんですよ。それって今までになかった感覚だし、音楽が『選ばれてここに来たんじゃなく、選んでここに来たんだ』っていうタイトルにもつながっていて。あと、単純にThe Mirrazのお客さんって10代の子がすごい多いんですけど、子は親を選べないじゃないけど、何でこんな家に生まれちゃったんだろうとか、金持ちの息子になりたかったとか、逆に金持ちの息子だったら何でこんなつまらない家に生まれちゃったのかとか、いろいろ思う人がいると思うんですよね。でもそうじゃなくて、選ばれてここに生まれたんじゃなくて、選んでここに生まれてきたんだって考えられたら、人生観は変わるよなって。そういう気持ちを持ってもらえたらっていうメッセージというか願いも、このタイトルには含まれているなと」
——よくこういう言葉がふと出てきましたね。
「何でかは覚えてないんですよね。僕は思い付いたタイトルとか歌詞とかってだいたいメモしておくんですけど、思い付いた瞬間のことは全然覚えてなかったりするんで」
——The Mirrazの詞の世界はずっと焦点が当てられていた部分だと思うんですけど、特にタイトルがいつもめちゃくちゃ残る=キャッチーじゃないですか。その瞬間をパッと捕まえる能力がすごいなと。
「僕が小学~中学の頃って、J-POPのシングルがトリプルミリオン売れるとかそういう世代で。だからシングル曲のタイトルもキャッチーさが全てみたいな感じが好きなんですよね。当然良い名前を付けてあげたいし、もちろん聴いて欲しいから聴いてもらえるタイトルを付けたい。そういう風にみんなが何かしら興味を持つようにはしたいといつも思ってるんで」
——いかに曲をキャッチーにするかだけではなく、そこからいかに再生ボタンを押させるか。子供の頃に培ってきたそういう感覚とか、インディーズの頃に消耗したこととかその全てが、良い作品が生まれると報われるんだなと感じますね。
「本当にそう思います。一昨年ぐらいは音楽をやってるとき以外はダメだなぁって。音楽だけが救いになってる時期があったんですけど、逆にメジャーに来てからは音楽って本当に楽しいなと思えるようになって。デビューシングルの『僕らは』(M-4)が出来たときも、何でこんな歌詞が生まれたのか、自分でも最初はよく分かっていなかったんですよ。けど、後々ライブで歌っていて、これは単純に俺が音楽をやれる喜び、聴ける喜びみたいなものが書いてあるんだなって。だからお客さんも喜んで盛り上がってくれる。今までの『CANのジャケットのモンスターみたいのが現れて世界壊しちゃえばいい』(『OUI! OUI! OUI!』(’08)収録)とか『check it out! check it out! check it out! check it out!』(『NECESSARY EVIL』(‘09)収録)とかは暴れるような盛り上がりだったんですけど、『僕らは』に関しては、みんなが同じ何かを共有して盛り上がってる、喜んでる感じがして。最初はそれがすごい不思議だったんですよ、何だろこの感じって。やっていくに連れて、こういうことかぁって」
——そこに気付けたのはよかったですよね。
「音楽続けててよかったなって。ヘンな言い方ですけど、音楽を続けていると、プレゼントみたいなものがあるんだなって感じはしましたね。諦めずに、って全く諦める気はないんですけど(笑)、そうやって続けていくと何かプレゼントみたいなものが必ず落ちてくる。僕にとってはそれが曲だったりするんですけど。苦労しただけいい曲が出来るわけでもないんだけど、苦労しただけプレゼントがある感じはします」
——出来あがったときに、達成感というか手応えはあったんですか?
「すごいありましたよ。スタッフもメンバーもみんなそうだけど、とにかく迷いもないし、今までやりたかったものが1つ実現出来た感触はありましたね」
——全13曲、というか14曲(笑)。最後のあのラーメンの歌は何だったのっていうね(笑)。
「あれは『HELL’S DRIVE』(M-5)を最初遊びで鼻歌で歌ってたのがギャグバージョンみたいで面白かったんで、敢えて塁(ds)にレコーディング当日ドッキリで録らせて。“え? 俺が歌うんすか?”みたいな(笑)。いきなりそう聞かされていきなりやるわけだから、まぁ歌えないじゃないですか(笑)。録ってみたら面白かったから、最後に入れてみようかって」
——あれをメジャー1stアルバムの最後に入れちゃえる遊び心が面白いなと思って聴いてましたよ。バンドが今を楽しめてるし、ライブも絶対にいいものになると感じますね。
「今は特にライブでやりたい曲、この曲をやってるバンドってカッコいいってイメージ出来る曲がすごくあるんですよ。その感覚って不思議なんですけど、バンドじゃなくて曲が先にあるというか。すごくライブをやりたいし、今のライブを観て欲しい。去年のツアーではストイックに音楽と向き合ってライブしてたんですけど、今年はそういう部分も当たり前に出来るから、より余裕が生まれて楽しいライブになると思うんでね」
Text by 奥“ボウイ”昌史
(2013年6月 5日更新)