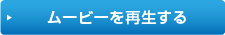ホーム > インタビュー&レポート > 山下達郎の血統を受け継ぐ新世代のシンガーソングライター ジャンクフジヤマが自らの音楽人生を辿るインタビュー

山下達郎の血統を受け継ぐ新世代のシンガーソングライター
ジャンクフジヤマが自らの音楽人生を辿るインタビュー
山下達郎を彷彿とさせる、ソウルフルで艶やかなボーカルと熱いライブパフォーマンス、そしてAOR、ジャズ、ファンクetcなどあらゆるジャンルの旨味を濃縮還元したハイクオリティなポップソングで、ジワジワと人気上昇中のシンガーソングライター・ジャンクフジヤマ。最新作『JUNKWAVE』に伴い、豪華バンドセットで廻る初の全国ツアーが6/25(土)心斎橋JANUSにて控える彼は、日本が世界に誇るドラマー・村上“PONTA”秀一ら凄腕のミュージシャンたちも惚れ込んだ歌声と実力、そしてバイタリティを持った熱い男だ。今回は、昨年より続いたアルバム3作連続リリースで俄然注目を集める新世代の熱き歌い手に、音楽人生を劇的に変えた怒涛の1年を振り返ってもらった。それは自ずとアーティストとして歩んできた道のりとこの先の未来を照らす、ジャンクフジヤマの音楽家としての軸に迫るインタビューとなった。
――昨年11月に『JUNKSPICE』というアルバムを全国リリースして、こうやって各地を廻ってみて、自分の周りの状況が変わっていく感覚はありましたか?
「『JUNKSPICE』にも入ってるんですけど、『Morning Kiss』(M-1)っていう曲がラジオですごくかかり出したりしたときに、やっぱり何か変わってきたかなと思いましたね。友達が仕事中にそれを聴いて、最初は“(山下)達郎さんかな?”みたいな感じで聴いてたら“おいおいアイツだよ!”みたいな(笑)。突然電話がかかってきて、“今かかってたぞ!”っていう(笑)」
――ジャンクフジヤマがちょっとずつ認知されてきて、『Morning Kiss』がひとつ、自分の名前を広めるのを手伝ってくれたってことですね。かつては音源を出さずにライブを積み重ねていく時期があったと思うんですけど、現在に至るまでの流れをちょっと聞いていきたいんですが、そもそも音楽を始めたきっかけは何になるんですか?
「本気で音楽でやっていこうって思った瞬間っていうのは、Blue Note Tokyoで観たライブなんですけど、黒人系のファンクミュージックのライブがあって、初めて生で体感したときに、“音楽でいうグルーヴっていうのは、こういうことなのか!”と感じたんです。常々みんながグルーヴ、グルーヴって言ってるけど、譜面にも書けないし、要は感覚で掴まないことには始まらない。後から思えば、それまではどういうものがグルーヴなのかが、まったく分かってなかったですね。そのライブで初めてそれを体感して、なんか違うスイッチがバチッと入ったんです。何だか“お前がやれよ”って言われたような気がして…(笑)」
――それはちなみに幾つくらいのときなんですか?
「20歳くらいですかね」
――それまでは普通に音楽が好きで生きてきたけど、自分が職業として音楽をプレイする側、人前に立つ側になろうという気持ちはなかったと。でも、プロフィールを見ると、高校時代には音楽団体を結成してライブを主催・出演すると書いてましたけど、それでも音楽でどうにかするぞっていうのはなかったんですね。
「思ってなかったですね~。あと、当時は達郎さんの曲しかライブでしなかったんです(笑)」
――マジで!?(笑)
「もうホントに達郎さんにどっぷりはまってて、達郎さんしか聴きたくなかった。音楽が好きなんじゃなくて、達郎さんが好きだった(笑)」
――(爆笑)。じゃあ達郎さんに辿り付くまでは、どういう道を辿っていった感じなんですか? みんなと同じように流行っている音楽を聴いていたのか、それとも…。
「結局90年代に同世代の人たちが聴いていたような音楽には、まったく興味が沸かなかったんですよね。全然スイッチが入らないというか。みんなはいいと思って聴いてるんだろうけど。そこで達郎さんの音楽を聴き始めて、時代に流されないでこういう音楽をやっている人がいるんだーって初めて気が付いて」
――周りに溢れてる音楽が、自分にとって刺激的でないものばかりの中でも、達郎さんの音楽には出会えたわけじゃないですか? なぜそんな中でも音楽を探そうと思えたのか、どうやって達郎さんの音楽に出会ったんですか?
「探して辿り着いたわけではないんですよね。そのときは音楽が趣味としてもそれほど好きなものでもなくなってたんで。でも、テレビを普通に流し見してるときに達郎さんの曲がかかってたんですよ。そこで、景色と融合してこんなに美しい曲を書ける人がいるんだ!と思って。俺はそれまでは(井上)陽水さんくらいだと思ってたんですけど、その陽水さんとはまた違った世界を描ける人がいるのを初めてそこで知って。だから音楽が好きとかそういうことだけではなくて、達郎さんそのものに興味があって買い漁って全部聴いてたんです。そうすると、ホントに面白いなと。のめりこんでいきましたね~。達郎さんの音楽はルーツミュージックがハッキリしてるんで、そこから派生していく音楽も聴くようになるわけですね」
――自分の音楽の筋肉となるものを吸収していって、本気の決意をしたのがBlue Noteのライブだったと。
「そうですね。達郎さんの音楽を聴いて、達郎さんを目指して音楽を始めたと思われるんですけど、そうじゃないんですよね。達郎さんは達郎さんでカッコいいけれども、僕のアイドルなわけです(笑)。それとは全然違うところでスイッチが入ってるんですよ」
――Blue Noteのライブを観て、俺は音楽でいくぞとスイッチが入ったものの、当時活動していたバンドは結果解散してしまったと…。僕は今回の取材の前にジャンクさんのブログを’04年までさかのぼって見てたんです。毎日のように更新してなかったから最後まで読めたんですよ(笑)。そのブログを読んで思ったのは、この5年間の心境の変化、状況の変化がめちゃくちゃ分かるというか。バンドを解散するときに、やっぱり自分の責任で解散というか…まぁ悔しかったという想いが書いてあって、その辺はいったい何があったのか、どう悔しかったのかを聞きたいなと思っていたんですけど。
「そのバンドが解散するときに、結果僕だけ抜けた形になったというか…要は後ろの4人がですね、他のボーカルを連れて来たんです」
――マジで!?
「それでまたやり出したわけですよ! そういう意味でも1人でやり始めたときには、絶対にこいつらブッ潰してやる!と思ってました(笑)」
――確かに(笑)。
「結局はそのバンドも解散して、そこからそれぞれプレイヤーとして派生していったんですけどね。今では割とみんな活躍し出してるので、お互い負けてられないなみたいな」
――それは刺激になりますね。ブログを読んでいたら、やっぱり最初はお客さんがいない時代がずっとあって。今の言葉で分かったんですけど、みんな巣立っていくというか。まぁ巣立つというのは社会に出るために音楽を辞めてサラリーマンになるのも1つの巣立ちですし、バンドを辞めてプレイヤーとしてやっていくのもある種の巣立ちだと思うんですけど、そんな中で、悶々としながらもあきらめずに音楽を続けてきた原動力は何だったんですか?
「やっぱり音楽が好きっていうのもありましたし、あと、こういうスタンスで音楽をやっている同世代の若者がね…ホントに全然いなかったんです」
――確かに。
「今は幸運にもポンタさんとかと一緒に音楽がやれてますけど、なんて言うんですかね…一時代どころか本当に生まれる前から先輩たちが伝えてきた音楽のスタイルを、自分の年齢でも表現したかったんですよね。だから、この感じっていうのは同世代だけだと絶対にかたちにならないんですよ。やっぱりその時々にちゃんとした経験を積んできた、言ってしまえば一流と呼ばれるような人たちとやらないと、そういう音にならないんです。あと、まぁ本当に希望的観測なんですけど、こういう出来事が俺には絶対起こるはずだと勝手に思ってたんです(笑)」
――言ったら、ポンタさんとどっかで出会い…?
「そうそうそう! そういう大御所になぜか認められ(笑)、一緒にやらないかと言われるであろうって勝手に思ってたんです(笑)」
――でも普通、実際はそんなこと起きないじゃないですか。
「そう。普通は、普通は起きないんです」
――それこそ日本最高峰のミュージシャンである村上“PONTA”秀一(ds)さんとどうやって出会ったのかと。特にここ2~3年のジャンクフジヤマのストーリーを見ていたら、やっぱりポンタさんがフックアップしてくれたのはすごく大きなポイントで。周りのプレイヤーたちが“ジャンクフジヤマ? 誰だコイツ?”って思っても、ポンタさんが“こいつすごくいいんだよ。だからやってくんないか?”って言ったら、もうそれはすごい説得力だと思うし。その出会いはいったいどうやって生まれたんですか?
「一番初めにインディーズのアルバムを出したときに、ポンタさんが聴いてくれたんですよ」
――それはたまたま?
「いや、お渡しを…(笑)」
――あ、なるほど。ルートが(笑)。
「でもまぁ、僕自身もポンタさんが聴いてくれると思ってなかったんで。そしたらある日。直接電話がかかってきたんですよ。“ライブ観に行くぞ。用意しとけ”と(笑)。実はその前の日にですね、しこたま酒を飲んでしまって声がガラガラだったんで(苦笑)、これで会ったらやばいな…と思ってたんですけど、ポンタさんが仕事の都合で来れなくなって、回避されてですね(笑)。それもある意味運だったと思うんです。その後にちゃんとしたセッティングがされて会う機会があって。そしたら“ホントにお前みたいな音楽は絶対に一流のメンツでやんなきゃ意味がないから。俺が全員揃えるからその中で自由にやれ”と言われて。そういう出会いでした」
――さっきも山下達郎の曲をライブでやっていたという話がありましたけど、あれをただ再現することでも相当な技術も音楽的な引き出しも必要なのに、それをさらに自分のものにすることを考えたら、ハードルとしては高すぎる目標ないわけじゃないですか(笑)。例え山下達郎のフォロワーと呼ばれたとしても、そのフォロワーたるクオリティを獲得することがまず難しいことで、そのラインに到達してないと、ただの物マネになっちゃう。声質的なところも含めて引き合いに出されるとは思いますけど、要は勝てるわけがないというところから戦いがスタートするわけですから。それでも背中を追いかけて追いかけて…。
「でも、ある意味面白がってもらえてるわけですよね、その時代の一流と言われてる人たちに。リハーサルとかでも、“こういう風にしたほうがいいよ”とか一切言われないんですよ。要はそういう風に受け入れられたのが奇跡なんです。自分の中に絶対にそうなるはずだと信じてきたアレです(笑)。無駄に自信があるんですよね。誰に何を言われても、“いや、絶対にやれるはずだから”って。あの人の背中を追いかけている最中でも、まぁ勝てるわけがないんでしょうけども、その追いかけてる人間の中で最も先頭を走ってるはずだと、そう思ってます(笑)」
――そういう日本のトップにいるプレイヤーたちが、ジャンクさんをいいなと思って引き上げてくれる。その行為が音楽の世界を活性化させてくれているような気がしていて。今回のストーリーを聞いていて、こういう人がいてくれるから、埋もれかけた才能がちゃんと世に出て行くんだなってすごく思いますね。
「完全に才能だけでどうにかなるっていう世界でもないですし、その後押しをしてくれる“やれ”というひと言が必要なんですよね(笑)。でも、それにビビッちゃうと駄目なんです。言われたことに変に構え過ぎちゃうのは駄目。自由にやれというひと言をやり切れるかどうかを、リハーサルのときに試されてるわけですから」
――現在に至るまで、曲も書き溜めライブをやってっていう感じだと思うんですけど、今みたいな状況になるまでは、どういった活動の流れだったんですか?
「ライブをやりながら曲は書いていて、その頃からデモみたいなものはあったんですよ。それをどこかに持ち込めば?て周りには言われてたんですけど、全然そういう気にならなかったんですよ。なんかまだまだな気がして。要は1回聴いてもらって、そこで駄目だと思われればもう2度とチャンスは来ない。だったらあたためておいたほうがいいんじゃないかって、全然何の根拠もないんですけど(笑)。だから全然音源も作らないし、渡さないし、送るわけでもないという…。ここ4年間は本当に腐ってる時期もあったんですけど、でも絶対にやめる気にはならなかったですね。本当に変な自信があった(笑)」
――曲自体はどうやって普段作ってるんですか?
「ギターで作ることが多いんですけど、楽器を触って作るのはやめたほうがいいなっていうのはどこかにあって。まぁでもまぁどんな曲を聴いてもそうですけど、魂が伝わるような作り方をしていかないと、やっぱり流れていっちゃう。だからこそ流れていかない音楽を作ればいいっていう、すごく単純なことなんです。自分が思っていることをちゃんと書いていく。ごく単純な作業を続けてるだけです」
――現代の音楽が溢れいとも簡単に手に入る時代に、その人にとって大事な音楽になるのってすごく難しい。音楽を取り巻く状況としてはすごく困難な時代の中で、何か突き動かされるものはあるんですか?
「今の僕ら世代の人たちって、70~80年代の音楽をほとんど聴いてないんですね。でも、その時代こそ本当に音楽にパワーがあった時代なんで、その音楽に突き動かされるものがすごく多いんですよ。かと言って、みんながその時代の音を聴いても、何がいいのか、どこがすごいのか分からないみたいなんですよね。もう完全に感性がかけ離れちゃってる。どっちが良い悪いは別として、僕が消化したそういう音楽を、現代に伝えることによって若い世代も分かって欲しいと。どれだけその年代の音楽を知らないで生活してることが損なことかを知らしめるがための僕の活動なんです(笑)」
――70~80年代の音楽をジャンクのフィルターを通して現代にアップデートして聴かせるっていうのは、そういう世代のつなぎ役じゃないですけど、課題は大きいですけどやりがいもありますね。
「あの時代の音楽を聴かないと、ミュージシャンとしては育たないと僕は思ってるんです。50年代ないしは60年代までの音楽っていうのは、やっぱり芸能的な部分が多かったし、グループでも誰か作家が書いてそれで歌っている。そういうスタイルの音楽もあっていいんだけど、70年代になってくると、そこから派生して自分で作って歌う、そういう理念がある人たちがだんだん出てくるわけですよね。その人たちの音楽を聴かないのはやっぱり損だし、そういう世代の音楽を知らずにミュージシャンになっていく人たちも多いんですよね。そうなるともう本当に無感情というか」
――まぁでもこれから世直しが始まると(笑)。
「早くどけやーって(笑)。僕らの世代の人たちって、結局何の予備知識もなくライブを観に行って、そのライブでスイッチが入る=感動するっていう感覚があんまりないですよね。基本的に前から知っていて、好きだからライブを観て楽しんでるだけであって。それは本当に哀しい話で、全然分からないものも観に行って、感動させることができるのが音楽だし、それをさせなきゃいけないのが僕らの仕事なんで。本来は自分のことを全然知らない人が来ても、泣かせてやろうじゃないのっていう気合でやらなきゃいけないわけですよ。本当に自分のファンだけに向けて音楽をやってるスタンスの人が多いので」
――それで言うと、ジャンクさんにとってライブっていうのはどういう場所になるんですか? ブログにも書いてありましたけど、やっぱりライブを観に行くってその音楽だけじゃなくて、“人”を観に行くっていうのはすごく共感できるなと思いましたね。生で伝わってくる情報が音だけじゃないですからね。どう動くのか、どういうことを喋るのかっていうのも含めてライブだと思うんで。
「僕、ライブ大好きなんですよ。要はこういう仕事ってやっぱり自分1人だけじゃ出来ないわけですよね。ポンタさんも含め、それこそ音をいっしょに奏でるバンドマンもそうですし、ジャケットを作ったりする人もそうだし、この1枚を作るにあたって、関わってくれる人間がいっぱいいるわけなんです。で、その全部を僕が背負うわけですよ。そしたらナヨナヨしてる場合じゃないわけですよね。腹くくって、かかってこいや!っていう感覚でやらないと、誰も動いてはくれません(笑)。フワフワしながら“やめよかうな…”とか言ってる奴に、誰が魂預けるんですかと。もう死んでもいいからやってるようなもんです(笑)」
――でもなかなかそこまで思えない人が多いですよね…。
「僕からしたらきっとそういう人は天才肌で、なんでも自分で出来ちゃうんだろうなって。やっぱり自分だけで磨くよりもいろんな人の手が関わってると、作品がもっとキラキラ光りますから。自分が寝てる間にも誰かが磨いてるわけですよ(笑)」
――そう考えたらジャンクの名前をより知ってもらうことになった、『JUNKSPICE』なんかはすごく、その力を感じられた作品だったんじゃないんですか?
「もう如実に出るというか。ライブあり、スタジオで生録音したのもあり、純然たるスタジオレコーディングもありますし。いろんなコンディションの中で録りましたけど、もうすべていいほうに転ぶと(笑)」
――ポジティブ(笑)。
「これちょっと駄目かなと思ってても、世の中信じてやっているいい方に転ぶんです」
――『JUNKSPICE』は作るときにコンセプトはあったんですか? 『JUNKSPICE』はライブが間に入ってたりまたスタジオテイクに戻ったりと、なかなか珍しい造りですね。
「ライブだろうがスタジオだろうが、作品の価値は変わらないはずなんです。やっぱりスタジオテイクはいろんなお化粧が出来る。でも、ライブはお化粧出来ませんから。人間がそのまま映ります。だからなるべくライブを大切にしたいんですよ。僕なんかはまだ知名度が低いわけで、スタジオ版だけを聴いても、そのソウルがそこまでは伝わりづらい。だったらそのライブの生の姿をぶち込んでしまえば、分かってもらえるかなと」
――そして、今年の5月には早くもアルバム『JUNKWAVE』がリリースされましたが、そもそも1年に3枚もフルアルバムを出す奴なんていないと思います(笑)。ハードですけどステップアップを感じられた1年だったとも思いますけど、振り返ってみてどうですか?
「僕の場合は作る以前にやっぱり歌いたい、まずはそれが大きな仕事だと思ってるんで、作り上げたものがあれば世に出したいというのは当然で。その想いが結果的にそのスパンになったのかなと。去年の11月に『JUNKSPICE』がまず出来て、次にどういう流れかと思ったときに、やっぱり自分でムーブメントを起こしたいなって。僕がこのアルバムを出したことによって、まぁ大きなことを言うようですけど、音楽業界の中でちょっと旋風を巻き起こしたいなっていうのもあって。それが『JUNKWAVE』だったんですね」
――そういう強い意志、ちょっとかき回してやるぞっていう想いがあったっていうことですね。コンセプトをひとつ掲げて、このアルバムでムーブメントを起こそうとなったら、今までの作り方とはちょっと違いますよね?
「違いますね。やっぱり演奏を全部生で録りたかったんですよ。それがこのアルバムで初めて実現したんですけど、もう素晴らしいです、本当に。こんなに素晴らしいメンバーでスタジオで録音するっていうことが。全員がスタジオの中に集まって、演奏を始めるわけですよ。その始まった演奏に合わせて僕が歌って…これが本当のプロの仕事だなって強く思いました」
――みんなが同じ気持ちでいることをプレイで感じるっていう感じですね。あと『JUNKWAVE』は今までで最も間口が広い感じがしたんですが、その辺は意識してましたか?
「すごくノンジャンルなアルバムになってますけど、それは本当に自分の中にそういう要素があるからなんです。ロックだったりフォークだったり、ポップス、ファンク、ソウル…全部自分のルーツにはあるから、それを見せたかったのもありますね。一辺倒じゃなく自分の好きなことはいろいろあるっていうことをアピールしたくて」
――前作の『JUNKSPICE』はやっぱりある種の濃厚さがあって、またそれがひとつの味になってるんですけど、今回はそれを多角的に見せるというか。
「濃密なものも好きなんですけど、それを聴く人っていうのは耳がある程度肥えてると言いますか、慣れてないと反応出来ないわけですよね。だからそういうときにストレートにバッと入ってくれる、イントロで“誰だろうコレ?”って思うようなアルバムを作ってみたかったんですよね」
――ここ半年の間でも、ジャンクさんの顔つきや発言も含めて、すごく力強くなった感じがしますね。だから本当に怒涛の半年間だったんだろうなって。
「僕の場合、目標があって曲を作っていた方が、より明確に意志を見せることが出来るっていうことが自分では分かりましたね。漠然と曲を作っていても、それを自分の中では消化出来ていても、割と伝わりづらかったりするんでね。当時はこういう風に音源を出したくても出せなかった時代があったんで、その時代に出来てまだ焦げ付いてない曲もたまに出てくるし」
――それまでに溜まったマグマのように煮えたぎるものがあって、“コノヤロー、分からせてやるぞ”と(笑)。
「それで一気に3枚出たわけですよ(笑)。プロデューサーに言わせると、“このペースは尋常じゃないから、一度クールダウンする時間がないとあんた枯れちゃうよ”って(笑)。ただ僕の場合はまだ、いろんなものを見聞き出来ていないわけで。まだ経験出来ることはいくらでもありますよって」
――ムーブメントを起こしたいという気持ちで制作に向かって、凄腕のミュージシャンが集まってレコーディングして完成を迎えた『JUNKWAVE』ですが、今作を引っ提げてようやくバンドセットで初のツアーを廻れるっていうね。ライブに向けては如何です? あのメンバーのスケジュールをどうやって合わしたんですか?(笑)。
「いざツアーが決まったら、“お前のためだったら空けるよ”って言ってくれて」
――俺がその立場だったら緊張しますね~リハとかで吐きそうです(笑)。
「自分のやりたいことをそのまま表現しろ、自由にやれっていうのがこのバンドの方針なんで。最初はリハでも“お前今日本番じゃないんだよ!?”って言われたりしましたけど(笑)。もう本当にガツガツやってたわけですよ。リハでもこのくらいやらないと全然まだ追いつけてないし、横並びで演奏出来る立場にない。燃え尽きるくらいやらないと追いつきませんから、僕はマックスでやります(笑)」
――時代もそうなのかもしれないけど、特に先輩方は本気でアホなことが出来る奴を探してると思うんですよね。コイツ仕方ねえな、バカだなって言えるくらいの破天荒さというかエネルギーというか。
「ポンタさんからも“こんな奴いねぇよ、久々に見つけたよ”って笑われて。尾崎豊さん、清志郎さんと並べられました(笑)」
――それはすごい(笑)。
「リハーサルであれだけガーってやって、ライブでもガンガン歌って。汗ビショビショになりながら、顔もクシャクシャになって大暴れするっていう(笑)。そういうスタンスでやってるの、俺の知ってる中でこの3人だけだって」
――光栄ですね、本当に。まだまだ振り返るのには早いですけど、ソロとしてももう5年以上やってきて、多分またここから始まると思うんですけど、振り返ってみてどういう音楽人生だったと思いますか?
「まぁモグラですかね、一言で言うと。土の中にいましたから、ずっと(笑)。光を求めているというよりは、初めの内はみんなに潜ってきて欲しかったんですよね。そしたら本当に潜ってきてくれたわけですよね、大物が。それで、“じゃあ一緒に出りゃいいじゃん”って、一気に地上にボーン!と出てきたんです。だから、まだ目がちゃんと開いてない状態なんですけど、その目が開き出したときにどんなことが起こるのかを楽しみにしててください(笑)」
――目が慣れたときに何が起きるのか(笑)。
「その怖さを知らないんですもん(笑)。だから“お前よくあの人にそんなこと言えるね”って言われるんですけど、ビビッてる時間がもったいないわけですよ。恐れおののいて、リハのときにかしこまって考えてる時間がもったいないんです。お客さんはそうやってビクビクしてる人間を観に高いお金を払って来てるわけじゃないですからね。そのキャリアであの人たちをバックに歌って怖くないのか?って言われても、何を怖がる必要があるんだと。向こうが演奏をすべて担保してくれてるなら、好き勝手にやるだけですから」
――まだ僕もライブをね、映像でしか観ていないので。まぁそれでも十分にほとばしる暑苦しさは伝わってきたんで(笑)。
「アハハハハ!(笑)」
――今後アーティストとして目指すところがあれば聞かせていただきたいなと。
「突き放した立場にはなりたくないんですよね。だってその辺にいる兄ちゃんとたいして変わらないわけで。だから変人とかもしくは天才とかみたいな、見られ方はされたくなくて。もう本当に単純にその辺の兄ちゃんが魂込めて本気で歌ったらこうなったっていう、本当に身近な存在でいたいですね。そういうミュージシャンになりたい」
――うんうん。
「ポンタさんみたいなタイプもカッコいいですけど、やっぱり近寄りがたいというか怖いんじゃないか?みたいな(笑)。そういうカリスマ性のある方もいいですけど、僕はむしろ庶民的な立場でありたいなっていう感じです」
――それでみんなに上質な音楽を知らない間に食べさせて、みんな舌が肥えてしまって、ジャンクじゃないと物足りなくなると(笑)。それでは最後にライブに向けて、読者の方々にメッセージをください。
「『JUNKWAVE』は本当に熱い作品ですし、熱い人たちが作ってますから、それを生で体感して欲しいってのがまずあって。クールな音楽もいいんですけど、それ以上の人間臭さが、もうプンプンしてますから。やっぱり作り手側が満足して送り出せるアルバムが出来たっていうのは、本当に珍しいと思うんですよね。予算、時間、人数、曲数とか、いろいろ制限がある中でこれだけのものが出来たのは、本当に自信になりました。だから皆さんも自信を持って3枚4枚買って広めてください(笑)。広報担当は皆さんですから」
――で、ライブには1人あたり3人4人連れてきてね(笑)。
「そうですね。手をつなげばみんな輪になりますから(笑)。お願いします!」
――本日はありがとうございました!
Text by 奥“ボウイ”昌史
(2011年6月24日更新)
Tweet
Release

Album『JUNKSPICE』
発売中 2100円
Mil Music
MICL-70002
<収録曲>
01. Morning Kiss
02. SUMMER BREEZE
03. Undercover Angel (Live)
04. 雨上がりの向こうに
05. 曖昧な二人
06. Night Walker(Live)(Full Version)
07. Morning Kiss(Live)
08. ノスタルジア
[Bonus Track]
09. Morning Kiss(Back Track)
10. SUMMER BREEZE(Back Track)

Album『JUNKWAVE』
発売中 2940円
Mil Music
MICL-70003
<収録曲>
01. 僕の女神
02. この街~meet again~
03. 束縛
04. 遠い日の手紙
05. はじまりはクリスマス
06. コーヒーソング
07. 優しい名前
08. I Feel The Earth Move(Live)
09. 秘密
(灼熱のnew Arrange Live Version)
10. 曖昧な二人(Fantasista Version)
[Bonus Track]
11. さよなら通り3番地
Profile
ジャンクフジヤマ……’83年生まれ。大学時代に自らのバンド、ハヤオキ×を結成。路上ライブを皮切りにライブハウスでの活動を行うものの、バンドは解散。その後ソロとして活動を開始。’09年に初のミニアルバム『A color』をリリースし、シティポップのホープとして早耳のリスナーより注目を集める。その音源を聴いた世界的ドラマー・村上“PONTA”秀一はその歌声に惚れ込み、以来ジャンクを厚くサポートすることに。’10年4月にはアルバム『JUNKTIME』を発売。ジャズランキングで1ヵ月間トップをキープし、新人ながら記録的なセールスを更新。夏には『Morning Kiss』『SUMMER BREEZE』が全国のFM局で頻繁にオンエアされ、その名前を広げるきっかけとなる。続いて、同曲を収録したアルバム『JUNKSPICE』を同年10月に、今年の春には『遠い日の手紙』『僕の女神』を配信で連続リリース。今、その一挙一動を見逃せないアーティストのひとりである。モットーは人に優しく、趣味は旅行、格闘技。
ジャンクフジヤマ オフィシャルサイト
http://junkfujiyama.com/
Live
日本最高峰のプレイヤーを引き連れたバンドセットで初の全国ツアーへ!
『村上“ポンタ”秀一プレゼンツ
ジャンク フジヤマ with ファンタジスタ
TOUR 2011“JUNKWAVE”』
▼6月24日(金) 19:00
エレクトリック・レディ・ランド
自由5500円
[共]村上“PONTA”秀一(ds)/天野清継(g)/
知野芳彦(g)/バカボン鈴木(b)/
本間将人(sax、key)/柴田敏孝(key)/
岡嶋かな多(cho)
※当日券その他のお問い合わせは…
サンデーフォークプロモーション
■052(320)9100
▼6月25日(土) 17:30
心斎橋JANUS
自由空間5500円
[共]村上“PONTA”秀一(ds)/天野清継(g)/
知野芳彦(g)/バカボン鈴木(b)/
本間将人(sax、key)/柴田敏孝(key)/
岡嶋かな多(cho)
※当日券その他のお問い合わせは…
ソーゴー大阪■06(6344)3326
▼7月1日(金) 19:00
Mt.RAINIER HALL SHIBUYA
PLEASURE PLEASURE
指定5500円
[共]村上“PONTA”秀一(ds)/天野清継(g)/
知野芳彦(g)/バカボン鈴木(b)/
本間将人(sax、key)/柴田敏孝(key)/
岡嶋かな多(cho)
ソーゴー東京■03(3405)9999
※ドリンク代別途必要。出演者は予定のため変更の可能性あり。