
ホーム > インタビュー&レポート > 「素敵な恋愛なんて本当にあるのかよ、という疑いがある」 『映画 夜空はいつでも最高密度の青色だ』 石井裕也監督インタビュー
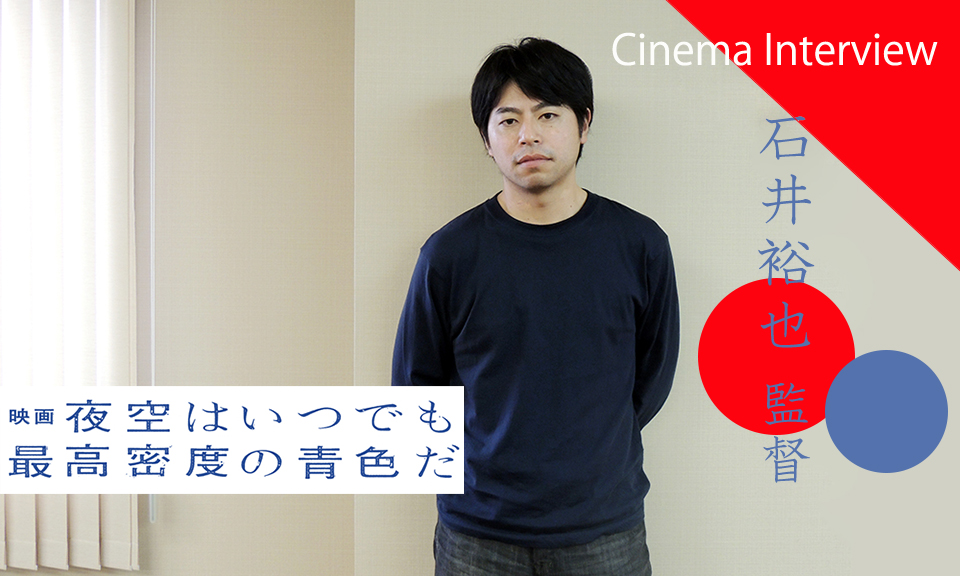
「素敵な恋愛なんて本当にあるのかよ、という疑いがある」
『映画 夜空はいつでも最高密度の青色だ』
石井裕也監督インタビュー
最果タヒの詩集を、ここまで見事に映画化できるのはこの先、もうないんじゃないんだろうか。石井裕也監督が、石橋静河、池松壮亮を主演に迎えて生みだした恋愛映画『映画 夜空はいつでも最高密度の青色だ』が5月27日(土)よりテアトル梅田ほか関西でも公開される。東京を舞台に、社会に適応できず、生きづらさを抱えて過ごす若者、美香と慎二。ふたりは、奇跡に近いような偶然の出会いを何度か重ね、次第に関係を縮めていく。『舟を編む』『バンクーバーの朝日』といった大作も手がけてきた、石井監督。33歳にして撮りも撮ったり、これが長編12本目となる。それでも本作には、すさまじい瑞々しさがみなぎっている。終始、感情をかきまわされる傑作だ。
――この映画は、言葉が印象的でした。まずは「死」という言葉。最果さんの詩にはこのワードがモチーフとして度々出てきますが、ポップに聞こえることがあります。2016年には流行語で「日本死ね」もありましたし、若者の間では日常的な会話でごく当たり前に「死」が使われるようになりました。劇中でも、気持ちに負担をおった美香が、慎二に「何か俺にできることはあるか」と尋ねられて、「死ねばいいのに」と返しますが。
生きている実感がないからこそ、死という言葉を弄びたくなるんだと思います。重い意味ではない、むしろ軽い。時代とともに「愛」や「希望」が違う意味として捉えられているように、死という言葉もずれてきてはいるのではないでしょうか。
――時間が経つことで受け取り方が変わるという部分でいくと、この映画で象徴的なのが音楽面の使い方ですよね。秀逸でした。まず、AKB48が2013年にリリースした『恋するフォーチュンクッキー』。美香が勤務するガールズバーの同僚がカラオケで唄っていますけど、「未来はそんなに悪くない」と言った後に、「ヘイヘイヘイ」で済ませちゃう、あの楽観さ。物語とかなりリンクします。
『恋するフォーチュンクッキー』を聴いたとき、あの楽観的且つまるで根拠のない希望の見せ方に驚いたんです。もちろん楽曲への批判的な気持ちは一切ありません。あの場面は、そういう楽観性に付き合えない美香との対比の面白さですね。あと僕自身、この曲が個人的に好きなんです。この曲には、さしこ(指原莉乃)の感情が入っていく、まさにさしこの歌。基本的にAKBの歌の主人公は、ファンですから。だから『恋するフォーチュンクッキー』は、他の曲とは違った魅力がある。
――あともうひとつが、2007年にリリースされたYUIさんの『CHE.R.RY』。美香と慎二がデートでカラオケにいく。美香のことが気になっている慎二は、勝負曲として『CHE.R.RY』を唄う。でも美香に話しかけられたせいで、肝心なところが唄えなくなりますよね。
『CHE.R.RY』はどうしても使いたかったんです。あんなに素敵な歌はなかなかない。あの純粋な楽曲を、男性である慎二がまっすぐに歌う。そして、サビの歌詞は、歌声としてではなくモニターの文字で見せるという。
――あの展開がすごく良かったんですよ! 喋くりの慎二が、さえぎられてしまう。その唄えなくなる歌詞というのが、「好き」というところ。彼の言葉の中で一番の見せ場なのに、唄えなくなる。で、その後は美香と慎二のケータイに、それぞれあるメッセージが入る。これも、『CHE.R.RY』の唄い出しが「手のひらで震える」というケータイのことを意味した歌詞に引っ掛けていますし。とにかくロマンチック。そもそもこの映画はそういうロマンチックさを決して大衆に強要せず、「自分だけのものでいいんだ」と思わせてくれる。
ロマンチックの大量生産・工場生産みたいなものって、もういらなくないですか? 個人のもの、固有のもの、自分なりのものをもっと大事にした方がいい。ムカつき、違和感とか何でもいい。気に入らないなら気に入らないって思った方がいいし、言った方がいい。そうじゃないからこそ、今のように、いろんな意味で明らかに間違った方に進んでいる時代になっている。もう少し個人の感覚を大事にしたいですよね。
――ちなみに、主題歌のThe Mirraz『NEW WORLD』は、『恋するフォーチュンクッキー』と同様に2013年リリース。4年前の楽曲。それを今のムードに重ねて、エンディングで流れます。この曲の言葉量の多さは、物語の言葉量と近い物があるのでぴったりなんですけど、ただ曲中「2013年」とはっきり唄われますし、そのあたりのはっきりしたズレは気になりませんでしたか?
『NEW WORLD』はいつか使いたいとずっと思っていたんです。確かに、2013年という歌詞が気にはなりましたが、それ以上に今の時代の気分を歌っていると感じることができた。そこに関しては、良い意味で無視できましたね。
――そしてもっとも重要な歌が、野嵜好美さん扮するストリートミュージシャンの“頑張れ”の歌。『舟を編む』で石井監督にインタビューをさせていただいた際、「強い言葉に違和感がある」おっしゃっていたんですよね。それこそ震災の後で、当時は「頑張れ」が溢れていた。強い言葉の代表例ですよね。でもあれから時間が経過して、僕自身は「頑張れ」という言葉を今は好意的に受け取れるようになった。この映画でも終盤で「頑張れ」が生きてくる。
例えば「この映画は観客に対しての応援歌なんです」と作り手が自ら言っちゃったら、興ざめじゃないですか(笑)。でも、表現者としてやらなきゃいけないことって、結局「頑張れ」ということなんだと思う。誰かに向けてそういう気持ちを乗せることが大切。でも、頭ごなしにいろんな人が出てきて、「頑張れ」と言い出しても絶対に伝わらないし、疑いの疑念を抱きがちな「頑張れ」という言葉を何とか変容させ、最後に額面通り、その言葉を届ける。これは表現者としてやるべきことであり、トライする価値がある。そういう意味合いで「頑張れ」という言葉を使いました。
――ストリートミュージシャンが「頑張れ」と唄うけど、道行く人は誰も振り向かない、立ち止まらない人。その流れがSNSのタイムラインのように見えました。
僕自身、SNSのことはよく分からないのですが、でもそういうことですね。至極真っ当なことを一生懸命主張しているのに、誰の耳にも届かないのは、全世界的に同じだと思います。何を言っても届かないという諦めや無力感がある。それをモチーフにしました。

――慎二たちが集まる、マンションの一室を使ったトランスパーティーが象徴的ですよね。パーティーをやっている横の部屋は、普通の人が暮らしていて、あまりにもうるさいから壁ドンをするけど全然それが届かない。
そうです。世の中は無駄な言葉、無駄な音、不必要な音の方が届いたりするんですよね。本当に必要なことって何ひとつ届かないのに。
――でも、この映画で描かれているそういうムードを「東京」という街に限定して語るのは大間違いですよね。舞台は東京だけど、田舎町もちゃんと出てきてそれらの表現を成している。現代の生きづらさは何も東京に限っていませんよね。
おっしゃる通り。東京限定の表現をしたつもりはないんです。生きづらさ、言葉への疑念、信用できない感覚はあらゆる都市にあてはまる。東京はあくまで、先頭を切って破滅に向かってひた走っている、「暫定一位」みたいな感覚。それを多くの街が追随している。
――でもそれが東京の最高のおもしろさですよね。破滅に向かっている感が。
もちろんその通り。こんなにおもしろくて、ばかげた街はないと思うんです。何でもありだし。
――生きづらくて、息もつまるような社会、街、時代にあっても、愛があれば何とか生きていけるという着地点を持って来たところが、石井裕也監督の作品としては異質ですよね。だって、かつての石井裕也監督の社会映画はそこには絶対に立ち寄らなかったじゃないですか(笑)。
「人を好きになる感情は素敵なものだ」という思いと、「恋愛なんて本当にあるのかよ、そんなもの」という疑いが自分にはあるんです。みんなもその両方の気持ちを抱いていると思うけど、もしかすると先ほど話題に挙がっていた、AKB48の楽観的な楽曲には、そういった疑いはないのかもしれない。これは僕自身の意見ですが、少なくともモーニング娘。の安倍なつみさんの在籍時代には、その疑いは確実になかったと思っています。『ふるさと』(1999)という曲なんですが、男にフラれて故郷へ帰ってきた女の子が、お母さんに慰めてもらう歌。「また恋するけれどいいでしょ」という歌詞を聴いたときに、「え!?」となったんです。母親にそんなことを言うなんて、恋愛に対する疑いがまるでないじゃないですか。びっくりして、この曲にすごく興味を持ったんです。コントロールできなくなるくらい人を好きになるのは素敵だけど、でも恋愛を疑って掛かり、それを乗り越えた先にしか本当の愛はないはず。そんな事実を、この映画は突きつけている。そもそも、本当の愛なんて分からないものですからね。
取材・文/田辺ユウキ
(2017年5月26日更新)
Tweet
Movie Data

©2017「映画 夜空はいつでも最高密度の青色だ」製作委員会
『映画 夜空はいつでも最高密度の青色だ』
▼5月27日(土)より、テアトル梅田ほかにて公開
出演:石橋静河/池松壮亮/松田龍平/市川実日子/田中哲司/佐藤玲/三浦貴大/ポール・マグサリン/大西力/野嵜好美
監督:石井裕也
原作:最果タヒ
「夜空はいつでも最高密度の青色だ」
【公式サイト】
http://www.yozora-movie.com/
【ぴあ映画生活サイト】
http://cinema.pia.co.jp/title/172311/
























