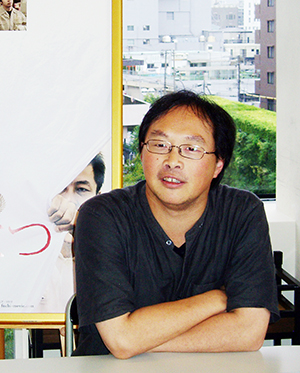「ぼくは『淵に立つ』を、“黒い『歓待』”と呼んでいます(笑)」
カンヌ映画祭「ある視点」部門で審査員賞を受賞した、
浅野忠信主演の日仏合作映画『淵に立つ』深田晃司監督インタビュー
『歓待』(2010)で東京国際映画祭「ある視点」作品賞、『ほとりの朔子』(2013)でナント三大陸映画祭グランプリを獲得するなど、新作ごとに注目を増してきた深田晃司監督。長篇第5作となる『淵に立つ』(10月8日よりシネ・リーブル梅田、京都みなみ会館、OSシネマズ神戸ハーバーランドほかにて公開)では、初参加となるカンヌ国際映画祭で、「ある視点」部門審査員賞に輝いた。殺人罪で服役していた男が、ある平凡そうな家庭にもたらす波紋を通し、コミュニケーション不全に陥った人間の心の闇や孤独の深淵を見つめる、挑戦的な受賞作について、そして、映画制作に懸ける想いを、語っていただいた。
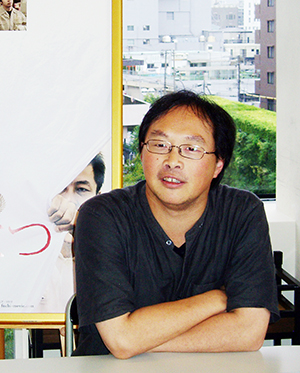
――まずは、おめでとうございます。受賞後の手応えは、いかがですか?
ぼく自身、経済的には何も変わっていないのですが(笑)。受賞したことで、世界中に情報が伝わるので、海外と取り組もうとしていた企画などが、作りやすくなった部分はあります。
――元々、カンヌに出品することを、目標に掲げていらっしゃったのでしょうか。
プロデューサーは、最初から言い続けてはいましたね。自分は、そんな大それたことは、口が裂けても言えなかったですけれど(笑)。ただ、カンヌを視野に入れていたことで、脚本の段階から、フランスと合作でという話は決まっていました。
――ポストプロダクションの大半は、フランスで行われたとのことですが。
編集や色の調整など、フランス人スタッフに入ってもらっています。傾向として、日本のスタッフは、技術力はものすごく高いのですが、自分を押し殺して、監督がやりたいことを実現しようとする方が多い。それはそれで、良い結果を生んだりもするのですが、フランスの人たちは、技術者である前に、ひとりの表現者として、この映画がどうすれば良くなるのか、自分の感性に沿って、意見を言ってくれる。すごく言葉を尽くして説明してくれるので、こちらも、それに応えなくちゃいけない。キャッチボールのようなやり取りの中で、作品が変化していくのが面白かったです。
――『淵に立つ』という意味深なタイトルは、どこから?
ぼくは、2005年に〈青年団〉の演出部に入り、未だ演劇を作らずに映画を撮り続けている、変な立場なのですが、最初の研修の時に、主宰者の平田オリザさんから聞いた言葉が、基になっています。芸術や表現に携わる人間は、ひとの心の闇を覗き込むために、崖の淵に立ちつつも、そのギリギリの際(きわ)で、踏み留まらなければならないと。お客さんと一緒に、人間が本質的にもつ闇を覗き込むような作品にしたいと思い、タイトルにしました。
――“招かれざる訪問者が、一見平穏に暮らしている家族を、かき乱して去っていく”というアウトラインは、深田監督の出世作である『歓待』を彷彿とさせますが、2作の関係は?
2006年に、既に『淵に立つ』のシノプシスは書き上がっていたのですが、その時点では、今と比べてもキャリアが浅く、実現は難しいと判断し、前半部分だけを抜き出して、別の映画にしたのが『歓待』なんです。ただ、前半だけで完結させるために、外国人をめぐる問題などもテーマに加えた方が面白いだろうとか、いつの間にか、コメディ要素がどんどん増えていって。2作はコインの裏表のようなもので、ぼくは『淵に立つ』を、“黒い『歓待』”と呼んでいます(笑)。
――金属加工業を営む、3人家族の鈴岡家。一人娘の蛍が演奏する、レトロなオルガンの音色とともに、ヴィジュアル面でも特徴的な冒頭から、自ずと引き込まれますね。
最初のシノプシスを書いた時点で、ファーストカットは、オルガンを弾いている女の子の背中から撮ると決めていました。伝統的な家族観に縛られながら生きてきた家族が、結局みんなバラバラであったことに、それぞれ気づいていく物語だと思っているので、その中心に据えるものとして、現代的なアップライトピアノよりは、昔ながらのオルガンの方が、しっくりくるかなあと思って。
――繊細なバランスを保ちつつ、辛うじて成立している家族関係の脆さや、その後に一家に襲いかかるであろう悲劇を予兆する危うさが、そこはかとなく漂っていました。
家族って、毎日顔を合わせているから、情報交換としての会話は、どんどん減っていくはずなのに、それでも毎日、生活をともにする関係が続いていくというのは、すごく不条理で、不思議な集団だなあと思います。
――ある日突然、鈴岡家に住みついてしまう謎多き男・八坂を、浅野忠信さんがミステリアスに怪演されていますが、彼に次第に追いつめられていく、一家の主・利雄を演じる古舘寛治さんは、『歓待』では、八坂の側の役で出演されていましたよね?
古舘さんには、『歓待』の撮影が終わってすぐに、『淵に立つ』という企画が成立したら、逆の立場の役を演じて欲しいと、声を掛けていたんです。〈青年団〉の舞台などでも、攻める役が得意な方なので、たまには、“変なおじさん”ではない古舘さんも観てみたいと思って。妻の章江役の筒井真理子さんは、『歓待』を観て、一緒に映画を作ろうと声を掛けて下さった米満一正プロデューサーと話すうちに、一緒に仕事をしたい役者として、名前が挙がっていて。その時点では、どんな作品をやるかは決まっていなかったのですが、改めて筒井さんを意識すると、『淵に立つ』の章江役にぴったりだと思い、翌日、米満さんに話を持っていきました。企画が再スタートするきっかけになった筒井さんには、とても感謝しています。
――夫婦役が決まり、最後の最後で、浅野さんがキャスティングされたのですね。
ふたりの間に、誰が入ってきたら面白いだろうかということで、浅野さんにお願いしました。古舘さんと筒井さんは演劇畑出身、浅野さんは映画一筋に活躍されてきた方なので、最初はどうなるかなと思ったんですが、浅野さんの異物感が良い影響を及ぼしつつ、みなさん傑出した役者さんなので、すぐに馴染みましたね。面白かったのが、古舘さんと筒井さんは、根っからの演技バカというか、リハーサル中にも、しょっちゅう熱い演技論を闘わせていて、その様子が、傍からは本当の夫婦ゲンカみたいに見えて(笑)。それを浅野さんが、横からニコニコしながら眺めている構図が、まるで役柄上の3人の関係性のようでもあり、そういう意味でも、良い雰囲気で現場に入れたと思います。
――鈴岡家に、修復し難いダメージを遺し、八坂は家族の前から姿を消す。物語は一気に8年後へと飛び、後半の鍵を握るキーパーソンとして、『ほとりの朔子』以来の深田監督作品となる、注目の若手俳優・太賀くんが、浅野さんに代わって登場します。
太賀くんは、相当プレッシャーだったみたいで、浅野さんも、現場で「あとは太賀くんに任せたぞっ!」と、かなり発破をかけていたので(笑)。前半の撮影がとても上手くいって、すごい画(え)も沢山撮れたので、このクオリティーを、後半まで維持できるか心配だったのですが、存在自体が語りにくい、複雑な役柄を演じてくれた太賀くんも、とても良かったです。
――八坂がいなくなることで、画面の中で彼を、より強く意識させられるようにも感じました。
アルフレッド・ヒッチコックの『レベッカ』(1940)で、劇中に一度も登場しないレベッカという女性の存在が、映画全体を不穏に覆い続けている感じがすごく好きで、後半の八坂を、レベッカのようにしたかったんです。モンスター映画も、実は一番怖いのは、怪物が出てくる前ですよね?八坂が着ていた印象的な赤いシャツは、浅野さん自らイラストも描いて提案してくれたのですが、後半では、赤を随所に散りばめることで、八坂の気配を忍ばせています。脚本を直していく過程で、完成作とは別バージョンの結末のものも1度だけ書いていて、それはそれで結構気に入っていたので、新たに書き下ろした小説版では、そちらを採用しました。
――伏線となる重要なモチーフとして、写真が効果的に用いられていますね。
写真は、瞬間の真実を切り取っているようで、人間の多面性を露にします。笑顔なんて一瞬で作れるわけで、その裏で、実際に何を考えているかは、写真にも映画にも映らない。人間の心自体が、不可視の闇であることを、写真は、簡潔かつ象徴的に表すものだと思います。
――深田監督の作品を拝見していると、人間同士が直接交わす言葉よりも、その後の沈黙であったり、微妙な間合いや空気のようなものを、とても大切にされている印象を受けます。
究極にやりたいと思っているのは、本音を語らない人たちの話です。ぼくたちは普段、本音をむき出しにして生きてはいないし、本音のつもりで話していても、それが本音かどうかは、自分にさえ分からない。人間社会自体が、すれ違いから成立していると思うんです。
――確かに、同じ悲劇を体験した鈴岡家でも、夫婦の間で、受け止め方が随分違いますよね。
ひとは、事故や自然災害、何の因果関係もない暴力などに、さらされながら生きています。利雄はその中に、“罪と罰”を見出すような発言をするんですが、章江はまったく共感できない。夫婦や血縁でさえ、すれ違ってしまう孤独な他者である。そんな世界観が好きなので、お客さんが、登場人物の本心を想像するための余白として、沈黙や間も重要だと考えています。
――分かりやすさや共感を追い求めがちなエンターテインメントとは、対極にある世界観にも思われますが。
お客さんの想像力を信じつつも、信じすぎない。想像してもらいながら、それを、少しずつ裏切っていく。そんな綱引きをどうするかを、常に意識しています。映画という芸術は、ひとの心を掴み、共感させるというのも魅力であるとは思いますが、戦時中には、思想統制に利用されてきた歴史があるので、多文化共生時代を生きる今、映画制作に携わる者として、そういったプロパガンダ性には、十分注意を払わなければいけないと。観た人それぞれに考えてもらい、そのためであれば、時にはカタルシスを犠牲にしても構わないと思っています。
――それでは最後に、これから映画をご覧になる方に、一言お願いします。
夫婦や家族で観に行ってもらって、観終わった後に意見が分かれ、ケンカになったりすると楽しいかなと(笑)。気まずい感じになってくれると嬉しいですね。
取材・文/服部香穂里
(2016年10月 4日更新)