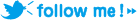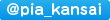ホーム > インタビュー&レポート > 『江戸の青空』シリーズ第2弾がいよいよ大阪上陸! 本作で舞台初出演にして初主演となる歌舞伎役者 坂東巳之助と、本シリーズ仕掛け人の松尾貴史による 製作会見レポート&巳之助単独インタビュー!
『江戸の青空』シリーズ第2弾がいよいよ大阪上陸!
本作で舞台初出演にして初主演となる歌舞伎役者
坂東巳之助と、本シリーズ仕掛け人の松尾貴史による
製作会見レポート&巳之助単独インタビュー!
(2/2)
――今日は『江戸の青空 弐 ~惚れた晴れたの八百八町~』のキャンペーンで来阪されましたが、いろんなところでお話されてきたと思います。そしてこれが本日最後の取材となりますが、まず取材とか、どうですか?
坂東巳之助(以下、巳之助)「僕、取材とかインタビューが大好きなんです。基本的に具体的に考えて行動するタイプではないので、それをこう、言葉で表現しなきゃいけない、具象化しなきゃいけないとなると、やっぱり考えるじゃないですか。あの時はどうだったとか、今は何を考えているのかということを言葉に置き換えるために考えると、“ああ、あの時、そういうつもりで自分がいたんだな”ということが何となくはっきりする気がするので、こうやって言葉にしなきゃいけない機会はすごくありがたいですし、楽しいですね。なので、今日はすごく楽しかったです!」
――なるほど。では本日最後の取材、よろしくお願いします。そして、舞台のことをお伺いする前に、巳之助さん、すごく素敵な髪の毛の色だなと思ったんですが、なぜその色にされたんですか?
巳之助「……長くなりますけどよろしいですか?」
――は、はい……(ゴクリ)。
巳之助「今回、プロモーション活動をさせていただくにあたって、写真も撮られるから金髪にしたら目立つんじゃない?って思ったんです。で、お世話になっているヘアメイクさんにも相談したら『いいんじゃない』と言われまして金髪にしたんです。しかも2011年の歌舞伎納めが8月で、それ以後は『江戸の青空 弐』に専念させていただくことになっていましたので、時期的にもいいだろうと金髪にしました。割ときれいな金髪だったんです。で、このキャンペーンの前にちょっとしたパーティーに出席しなければならなくなって、洗い流せるタイプの黒染めスプレーをかけて、パーティーに出席しました。そして帰宅してお風呂に入ってシャンプーをしたところ、黒が落ちきらなかったようでございまして、このような色になりました!」
――そうなんですね。この色はなかなか、出せない色だと思いますよ。
巳之助「偶然の産物です。不幸中の幸いですかね」
――では、本題に入りたいと思います。先ほどの製作会見で、G2さんの舞台に声がかかって、その時の気持ちを「遂に来たか」とおっしゃっていましたが、その心境についてもう少し詳しく教えていただけますか。
巳之助「5年ほどの前に初めてお会いしてからというもの、G2さんが先輩の(中村)橋之助さんや、うちの母(寿ひずる)とも舞台をされていたので、ちょくちょく観に行ってはお会いしていて、そのたびに“何かやれたらいいね”みたいなことをおっしゃってくださっていたんです。で、一度、本当にお声かけをいただいたんですけども、歌舞伎の舞台のタイミング的に“申し訳ございません”というふうになってしまったので、悔やまれるなぁと僕の中でずっと思っていたんです。そしてやっと『江戸の青空 弐』のお話をいただいたので、“やっとできるな!”という意味での“遂に来たな!”です!」
――1回目の『江戸の青空 Keep on Shackin' 』はご覧になったんですか?
巳之助「はい」
――では、そのときのご感想をお聞かせください。
巳之助「すごく面白いなと思いました。歌舞伎にも『文七元結』がありますが、文七というキャラクターをああいうふうに描いたり、捉えたりすることもできるんだなと、すごく新鮮でしたね。ストーリーの中で落語の要素がぽつぽつと見受けられて、“もう、本当に面白かったなぁ”って、ちょっと幸せな気持ちになって帰った記憶があります」
―― 今回はその第2弾となります。先ほど、演じられる徳三郎の人物像について、“主体性があまりなく周りのアドバイスに振り回される人”というお答えしていらっしゃいました。そこをもう少し詳しく、徳三郎について教えてください。
巳之助「人間の感情は何かしらきっかけがあって動くものなんですが、徳三郎は本当に、登場人物の誰かしらに影響されて行動したり、気持ちが芽生えたりするというキャラクターで、自主的に何かをするということがないんですね。こと、おせつさんにアプローチするときも、自分発信で何かするということがあんまりなくて。で、周りの人たちにやいのやいのとされて、二転三転、七転八倒して、最終的にどこにたどり着くのやら…と。思うに、徳三郎以外の登場人物は、何かこう、主人公に据えても面白いと思うんです」
――その人たちが主役でも…。
巳之助「成り立つし、もちろん脇でもいいし。他の人はみんな人物自体が面白いんです。でも徳三郎には主人公以外のポジションがあり得ないんですよ。脇の人に動かしてもらわないと何もしないので。例えば別の誰かが主役で立っていて、徳三郎が脇で出てきたら何もしないただの通行人だと思いますね。そういうところも含めて僕は、徳三郎は何色にでも染まるという意味合いで『何の変哲もない町人の男の子』という認識をしています」
――その徳三郎に共感を覚えるところはありますか。
巳之助「恋愛ベタなところですかね。極めて億手で、見当違いなアプローチをしてしまったりとか、上手じゃないというところは似ているというか…(笑)」
――巳之助さんご自身も過去にそういうことがあり…。
巳之助「そういうことしかないです」
――そこは男として共感を覚えますか?
巳之助「そうですね。かわいそうだなって思いますね…(笑)」
――今回、初舞台であり、主役でもあります。G2さんもメッセージで、台詞の量も多くて、ずっと出ずっぱりなので大変だとおっしゃっていました。先ほどもの会見でも“ワクワクしている”おっしゃっていましたが、改めてこの舞台へのお気持ちを聞かせてください。
巳之助「本当に何もわからないので。比較対照があるわけでもないし、何か類似した経験があるわけでもないので舞台に対して全く見当はつきませんが、自分がやりたいと思っていたこと、今までやったことのないことができるというワクワクだけがあって。ネガティブな意味でのプレッシャーはあんまり感じてはないですね」
――性格的にも、普段からそのように捉えがちですか?
巳之助「そんなことないんですよ。あがり症のはずです。でも基本的に楽しいことが大好きなので、楽しいことが控えていると割と周りが見えなくなるタイプですね」
――先ほど、同じ舞台でも歌舞伎と演劇の違いはという質問に、“女性が女性の役をされている”とおっしゃっていました。そのご発言についてなんですが、歌舞伎では女形の役者さんがいらっしゃいますよね。その方は男性ですよね。で、演劇の舞台には実際に女性が立っていると。それはどんな感覚で見えるんでしょうか。
巳之助「いや、違いますでしょう、それは(笑)! 本当にあの…、これはいつも、いい加減、言うのやめようかな、言うのやめようかな、会うと気まずくなるなって思ってるんですけど、役の上で男女で恋をしますわ、そら。作品の中で。1つの物語の中で男女で恋をしますけど、歌舞伎役者は女形とは恋をしないですよね。ねぇ!? これは芝居の中での恋ですけど、相手は女性ですから、お芝居じゃなくても恋ができるじゃないですか…(笑)」
―― 相手が女性だと、意識してしまいますね…。
巳之助「……そういうことです! そういうこと…、そういうことです…。何だか“巳之助さんのことはお伝えしてますよ”みたいなご報告があって、僕は思わず素っ頓狂な声を上げていました!」
(スタッフ)「そうやってみんなが温かく稽古場で待ってますよということです」
巳之助「生温かくね(笑)」
―― (笑)。すみません、追求しすぎてしまったかもしれません。では、話を改めまして、今回落語を題材にされていますが、落語も、歌舞伎も、一つの物語を何百年と語り継いでいます。そういう視点で、物語としての魅力を教えてください。
巳之助「僕は噺家さんではないので落語はわからないですけど、歌舞伎に限って言えば、作品以前に色彩美など視覚的なインパクトがまずあって。実際に“話はよくわかんないけど”って美の部分だけ楽しんで歌舞伎をご覧になっているお客様もたくさんいらっしゃいます。舞台美術だったり、道具だったり。しかも、当時からほぼ変わらず受け継がれています。そして本に関して言えば、いわゆる七五調など、音としての台詞。それは、あえて言うならミュージカルに近いような節回しで。歌舞伎は400年以上、続いていて、その間に余計な部分は削ぎ落とされ、必要な部分は継ぎ足されてきました。そしてここ最近、至るべきところに至ってきた時代だと思いますね。江戸から明治へと移り変わる時期も、戦中、戦後も歌舞伎は経験していて、時代の移り変わりをたくさん経てきました。そして今やっと、洗練され尽くして、落ち着いてきたんじゃないかなと。当たり前のことを言えば、伝統として残っているものも400年前は新作だったわけで、そのことをずっと繰り返してきて、一つの到達点にいると。そういう時期に役者としてやるにあたって、自分自身、どうやってやっていくかというところでも面白いタイミング、シーズンだと思います。そしてご覧になる方も、すごく楽しめるんじゃないかなと思っています」
――なるほど。では、ドラマや映画も含めて、歌舞伎以外の舞台に出て、そこで得たものをどのように歌舞伎に還元されていますか?
巳之助「具体的にどうというわけではないですけど、何かしらの変化はあった気がするし、知らず知らずのうちに出ているところもあるかもしれないですね。あと、本当に単純なことですけど、歌舞伎は25日間ずっと同じサイクルでやり続けるので、スタッフさんたちの大切さやありがたさを忘れがちになるんですが、違う現場に行くと改めてその存在の大切さ実感しますね。最初にドラマに出たとき、歌舞伎の舞台でもスタッフの方が陰ながら支えてくださって、毎日毎日、お世話になっていること、その有り難味を忘れがちになっていることを思い出させてもらって、それはすごく大きなことでしたね」
――そういう意識はすごく大切なことですよね。そうして、松尾貴史さんをはじめいろんな方と出会って、たくさんの刺激をお受けになっていると思うんですが、そういう中で、今後どういった役者になりたいと思っていらっしゃいますか?
巳之助「何も決めておりません。というのも、近々の目標はいいと思うんですけど、将来どうなりたいということは特に考えていないというか、強いて言うなら役者をやっていてよかったなと思って死んでいきたいぐらいで。そのぐらい先の話です。歌舞伎役者は引退もないし、まあ、板の上で死ねれば本望だと、本当にそういう人生だったらいいなぁぐらいで。僕は最終的に歌舞伎役者として生きていくつもりでいるので、その中でどういう役者になるのか、こと歌舞伎に関しては経験を積んでいかないとわからないですね」
――歌舞伎役者になってよかったという、そういう人生であればいい。
巳之助「そうですね。他には別に何も望まないです。何を目指すわけでもないですし、お父さんを超えたいとか、ああいうふうな人になりたいという気持ちは、ないですね」
――それはいつからですか?
巳之助「もともと、そういうことを考えるタイプではないですね。どうなりたい、どうやっていきたいということはあんまり…。目標を定めてそこに向かって進んで行くことはすごく合理的だし、プラスになることもたくさんあると思うんですけど、役者をやっていくにあたって経験して無駄なことって絶対にないので。何もしないことが唯一の無駄だと思うので、例えば飲みに行くにしても、友達と遊ぶにしても、何をしていても絶対、“今していること”を頭の隅に置いて、体が経験してればそのうち生かせる機会が来ると思うんです。ましてや一生、役者として生きていくのであれば。RPGみたいに“ボスのいるところに向かって行くけど、こっちに道草したらすごくいい武器が入った宝箱があるかもしれない”って思うと、目標をはっきり定めるという気にならないですね」
――そうなんですね。これから先のご活躍も楽しみです。では最後に『江戸の青空 弐 ~惚れた晴れたの八百八町~』の見どころをお願いいたします。
巳之助「面白い人たちが集まっているので、面白い舞台になると思います。もし僕を見てくださるのであれば楽しそうだなと思っていただければと思います」
――その“楽しそうだな”というのは、どういう感じですか? 振り回されている姿がとか、ですか?
巳之助「何ていうのかな…、お客様が観てくださって“楽しいな”と思っていただけたら、それは出ている役者全員が楽しかったということだと思うんです。そう思って観ていただければと思います!」
――なるほど、今日はありがとうございました!
(2011年11月24日更新)
Tweet Check

●公演情報
「江戸の青空 弐」
発売中
Pコード:413-706(公演日前日まで販売)
●11月26日(土)13:00/18:00
●11月27日(日) 18:00
シアターBRAVA!
全席指定-6800円
[劇作・脚本]千葉雅子
[演出]G2
[出演]坂東巳之助/植本潤/松永玲子/戸次重幸/朝倉あき/吉野圭吾/柳家花緑/松尾貴史
※11/26(土)18:00公演は、公演終了後アフタートークあり。出演者未定。
[問]梅田芸術劇場[TEL]06-6377-3888
※未就学児童は入場不可。
●あらすじ
江戸時代、白木屋の奉公人の徳三郎は主人の一人娘、おせつと将来の約束を交わした…つもりであったが、どうやらそれは勘違い? 町の風呂屋では「おせつが結納するらしい」と噂話で持ちきりだ。それを聞いた徳三郎、所詮は叶わぬ恋かと思わずカッとなり、刀屋へ飛び込み「2人ほど切れるのを売ってくれ!」。穏やかではない徳三郎に刀屋の主人は「事情を聞こうじゃないか」と耳を傾ける。そして徳三郎はそれまでの経緯を切々と語り始める…。花のお江戸を舞台にうら若き男と女が繰り広げる惚れた晴れたの恋物語。周りはなにやら奇妙な人間ばかりで、徳三郎は振りまわされる一方で。果たしてこの恋、成就するのか!? それは見てのお楽しみ。
●見どころ
江戸落語のエッセンスを紡ぎ、一つの物語に仕立てている「江戸の青空 弐 ~惚れた晴れたの八百八町~」。ここで、今回、登場する江戸落語を紹介しよう。
「おせつ徳三郎」
前半の花見小僧と後半の刀屋のエッセンスが冒頭から登場。大店の娘おせつと奉公人徳三郎がいい仲になっていると聞きつけた主人だが、ふたりの花見に同行した小僧からその様子を聞きだそうにも簡単には口を開かない。そこで少しずつ餌を与えて誘導すると、小僧はいとも簡単に口を割ってすべてを話してしまう。カンカンに怒った主人は徳三郎に暇を出す。暇を出された徳三郎はおじさんの家へと預けられる。その間におせつが婿をとり婚礼を挙げると知って刀屋へ…。そのうちおせつが婚礼の席から逃げ出したと聞いた徳三郎。両国の橋の上で手と手を取り合い「南無妙法蓮華経」と川に飛び込むが…。
「宮戸川」
将棋に夢中になって父親に締め出しを食らった半七。隣家のお花も帰宅が遅いと母親から閉め出しを食らっていた。仕方なしに半七は叔父の家へと泊めてもらいに向かうのだが、お花も行くあてがないとついてくる。そして叔父の家。早合点で思い込みが激しいと有名な叔父だけに、ふたりがいい仲だと勘違い。布団は1組しか用意されず、ふたりは帯で仕切りを作って小さくなって寝るのだが…。
「紙入れ」
今夜は主人が帰らないからとお得意先の奥さんに誘われた新吉。旦那には世話になっているけれど、奥さんにも随分ひいきにしてもらっているから断るわけにはいかないと弱り果てるも留守宅にあがり込んで酒を飲み、床をのべてもらったその矢先、主人が急に帰ってくる。何とかその場を切り抜けたものの、旦那からもらった紙入れをうっかり床に置き忘れた。しかもその中には奥さんからの手紙も入っている。絶体絶命、覚悟を決めて翌朝、新吉は主人の元へ行くのだが、どうにも気づいてない様子。それを確かめたくて新吉は夕べのことを「知り合いの話」として話し出す。
「駒長」
借金ばっかりを背負っているが呑気な亭主の長兵衛は、借金取りの丈八が女房のお駒に惚れているに違いないと考えて、ひとつ芝居を打って出る。お駒に「丈八に惚れている」という手紙を書かせ、わざと落とさせる。それを長兵衛が拾い上げ、丈八が来た頃を見計らって夫婦喧嘩を。間男の証拠、ここにあり!と丈八に手紙を見せて懐の金をそっくり巻き上げる算段だ。嫌がるお駒を相手に芝居の稽古をつけていたところ案の定、丈八がやってくるのだが、お駒が予期せぬ行動に打って出て…。
「三年目」
病床に伏せている女房は、夫が後添いを取ることが気がかりで臨終できないという。それを聞いた夫、「生涯独身で通す。もしも後妻をとるような時には、婚礼の晩に幽霊になってでてきたらいい」と約束。それを聞いた女房は息を引き取る。やがて時は経ち、夫のもとへ再婚の話がちらほら。断りきれずにとうとう後妻をとり、婚礼を挙げるのだが、先妻の幽霊は待てど暮らせど出てこない。「バカにしてやがらぁ」と夫は新しい妻をかわいがることに決めた。そして再婚から三年、先妻の墓参りへ行った晩、ついに先妻の幽霊が現れる。
「唐茄子屋」
吉原通いが過ぎて勘当された若旦那、威勢良く飛び出したもののやがて行くあてを失い吾妻橋で身投げをしようとしたそのとき、偶然通りがかった叔父さんに止められる。そして翌朝、叔父から天秤かついで唐茄子を売りに行けと言われた若旦那は、通りすがりの人に助けられながらも何とか売りさばき、残すところあつ2つとなった。売り声の掛け声を練習しながら歩いているうち、とある長屋で質素なおかみさんに声をかけられる。聞けば亭主から送金がなくここ2日ばかり何も食べていないと言う。幼い子どももいるおかみさんを気の毒に思った若旦那は唐茄子どころか自分の弁当、売り上げ金まで渡して叔父の家へと帰ってくる。ことの顛末を最後まで聞いた叔父は不審に思い、若旦那をおかみさんのもとへ案内させるが長屋は大騒動。若旦那が渡した金は大家に取られ、おかみさんは首をくくったというのだ。怒った若旦那は大家のところへ殴りこみに行くのだが…。
●プロフィール
松尾貴史
まつおたかし●1960年生まれ、兵庫県出身。大阪芸術大学卒業後、デビュー。テレビ、ラジオはもとより、映画、舞台、声優、エッセイ、はたまた折り顔など幅広い分野で活躍中。テレビ番組『情報ライブ ミヤネ屋』(YTV)、『住人十色』(MBS)、『モーニングバード!』(EX)などに出演中。京都造形芸術大学芸術学部にて映画学科客員教授も務める。
坂東巳之助
ばんどうみのすけ●1989年、十代目坂東三津五郎の長男として出生。1991年、歌舞伎座『八代目坂東三津五郎十七回忌追善狂言』の『傀儡師』の唐子で守田光寿を名乗り初お目見得。1995年、歌舞伎座『蘭平物狂』の繁蔵と『寿靫猿』の小猿で二台目坂東巳之助を襲名し、初舞台。2009年にはテレビドラマデビュー、2010年には映画『桜田門外ノ変』(佐藤純彌監督作)で映画デビューを果たした。