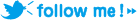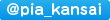ホーム > インタビュー&レポート > AI・HALLで上演される新作『gutter』について 物語の成り立ちや、その演出方法など dracom主宰の筒井潤にインタビュー
AI・HALLで上演される新作『gutter』について
物語の成り立ちや、その演出方法など
dracom主宰の筒井潤にインタビュー
(1/2)
9月30日(土)より伊丹AI・HALLにてdracom祭典2011『gutter』を上演するdracom。'10年に上演した『事件母(JIKEN-BO)』では、「録音された台詞と俳優の演技のズレ」というユニークな演出方法を取り入れ、賛否両論を巻き起こした彼ら。'11年の本公演(=祭典)では、その手法をさらに大胆に発展させ、『俳優の生声と身体のパフォーマンスのズレ」を披露するという。そんな演出を用いて描くのは、ある老人の物語。老いて自由の効かなくなった生活に嫌気がさした老人が、自殺を試みる。しかし、それは、体力不足ゆえに未遂に終わるのだが、老人は自分はすでに死んでいることを強く主張し続けるのだった。図らずも生きながらえてしまった老人と、老人を取り巻く家族や近所の人々の物語を、ユーモアを取り入れながら紡いでゆく。本作のベースになったものや描きたい世界観など、作・演出を手がけるdracom主宰、筒井潤に話を聞いた。
―― ぴあ関西版WEBです。今日はよろしくお願いします。まず、dracomさんの舞台の特徴やこだわりなどを教えてください。
筒井潤(以下、筒井)「dracomは身体的に挑戦的なことをしていて、なおかつ台詞に重きも置いているという舞台づくりをしているんですが、こういう団体は関西ではほかに、あんまりいないですかね。2007年に京都芸術センター舞台芸術賞をいただいたときの作品は、台詞はあらかじめ録音したものを使って、俳優は無言でやり取りをするというものでした。無言でやり取りをするので、相手がそのとき台詞のどの部分を喋っているのかわからないんですね。だから、コンタクトをとるためにサインとして頭を掻くとか、よその方を向く仕草をするとかやっていたんです。そのサインがだんだんデフォルメされて、大きくなって、もはや全然関係ない動きになっていったというのが、身体表現の流れとしてあります」
―― 筒井さんはダンス作品にも多く出られていますよね。
筒井「はい。ダンス作品にも出させてもらって、体が面白いと思ったりして。それで、一時期はダンスカンパニーになるんじゃないかというところまでいって、僕自身も危惧しました(笑)。そのときはダンスの方が枠組みも広いし、いろんな意味で自由だなと思っていたんです。今となってはそれが若干逆転している節があるんですが、当時はダンスの方が圧倒的に自由だなと。ただ、いい意味でも悪い意味でも、今のdracomのメンバーはダンスができないので、台詞を取っ払うことなく演劇という形で続けてきたんですね。そうすると、やっぱり無理が出てくるんですよ。何でこの身体で、この台詞なのかということが出てきたりするんですけど、僕は矛盾している感じの方が納得がいくというか…。ただ立って喋っているというものよりかは観ていられるので。それで、体と声のアンバランスさを面白く見せるということをやっています。ただ、それを始めたとき、チェルフィッチュ(※関東のカンパニー)とよく比較されました。同じカテゴリーの中に入れられたというか。それは周囲が言うんですよね。『ハカラズモ』という作品で初めて東京公演をさせてもらったときに、チェルフィッチュ主宰の岡田利規さんとお会いしたんです。作品も見てもらって、しゃべったりもしたんですけど、本人同士はちゃんと違いをわかっているんですけど、観る方はざっくりと見て同じカテゴリーに入れて、比較するということがありました(笑)。まあ、経験を積むと興味いろいろと変わってきますね。最近は、じーっと立って喋っている人にすごく興味深くなりつつあって。以前、俳優さんがぴくりともせずにただ喋っているという舞台作品を見たんですが、それが終始飽きずに1時間半、観続けられたんです。それってパフォーマンスとしてすごい強いなと思うんです。飽きずに見られるということは実は難しいことだなと思って、そういう表現にも興味が出てきました」
―― では、演劇という枠でどういったことを表現したいと思われていますか?
筒井「どの作品にでもあるんですけど、僕が素朴に思っている疑問です。今回は、自殺しようとしたおばあさんがドブにはまったという話ですし、『事件母(JIKEN-BO)』のときはもう少しテーマが重くて、母親を殺した息子のことです。その息子が『誰でもよかった』と供述したんですね。そこで誰でもよかったという感覚でお母さんを殺せるだろうかと素朴に思って書き始めました。基本的には僕のそういう疑問です。それが作品まで考えが至るのはなぜかというと、僕自身、作品の中で可能な限り疑問に対して答えようとするんです。でも、どうしても答えが出ないんです。なので、その疑問の入り口から僕が考えているところ、『大体ここまではわかるんですけど』というところまで提示したいという思いがあります。舞台は割りとパフォーマンスの方が見られがちで、そういう部分はあまり見られないですけど、そういう素朴が僕が本を書く動機ですし、舞台を観てもらいたいという気持ちの湧き出る場所だと思います」
(2011年9月29日更新)
Tweet Check

公演情報
AI・HALL 提携公演dracom祭典2011『gutter』
●9月30日(金)19:30
●10月1日(土)15:00/19:30
●10月2日(日)15:00
※各回、受付開始および整理券の発行は開演の45分前、開場は開演の30分前
AI・HALL(伊丹市立演劇ホール)
一般 当日2800円
学生 当日2300円 ※要学生証提示
[作・演出]筒井潤
[出演]穴見圭司/村山裕希/筒井潤/小島聖子/佐伯有香(Monochrome Circus、双子の未亡人)/松田早穂(ベビー・ピー)/他
[問]dracom制作部[TEL]06-6499-4522
プロフィール
dracom
どらかん/'92年、大阪芸術大学の学生であった主宰の筒井潤を中心にdracomの前身となる劇団ドラマティック・カンパニーを旗揚げ。5年後の'97年の第7回公演『空腹者の弁』から作風が一変。「劇団」と名乗ることや、「ドラマティック・カンパニー」といったネーミングに大きなギャップが生じ始め、また演劇以外のジャンルへのアピールを考慮し、'98年1月に「ドラカン」という集団名に改名。年に1回の本公演(=「祭典」)と、同集団内の別ユニットによる小公演を不定期に行っている。近年の祭典は『もれうた』('07年)、『 ハカラズモ 』('08年)、『bloiler’s song』('09年)、『事件母(JIKEN-BO)』('10年)。'07年には、京都芸術センター舞台芸術賞を受賞した。
公式サイト
http://dracom-pag.org/