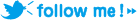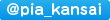ホーム > インタビュー&レポート > 真夏の會と極東退屈道場が初演時に高評価を得た 『エダニク』『サブウェイ』をこの夏、同時再演!
真夏の會と極東退屈道場が初演時に高評価を得た
『エダニク』『サブウェイ』をこの夏、同時再演!
(1/2)
8月11日(木)より伊丹アイホールにて、関西を拠点に活動する『真夏の會』と『極東退屈道場』がそれぞれ、代表作を再演中だ。原真が代表を務める真夏の會の『エダニク』は、売込隊ビームの座付作家である横山拓也の書き下ろしであり、第15回日本劇作家協会新人戯曲賞を受賞した注目作だ。演出はスクエア代表・演出・役者の上田一軒。この2人がタッグを組み、“関西の会話劇の現在形”を描いていく。そして、極東退屈道場代表の林慎一郎が手がける『サブウェイ』は、振付に原和代を迎え、モノローグとダンスで地下鉄での7日間を描いた作品。映像、ダンス、言葉を巧みに用い、重層的な世界を展開する。真夏の會と極東退屈道場。それぞれ異なる世界観で魅せる2組が行う合同再演。なぜ、このような動きが生まれたのか、その経緯や互いの印象など、原真と林慎一郎に話を聞いた。
―― ぴあ関西版WEBです。今日はよろしくお願いします。この『真夏の極東フェスティバル』ですが、まず、なぜこのタイミングでの合同再演なのでしょうか。
真夏の會・原真(以下、原)「2組で話し合って決まったのではなく、お互い別々で再演を検討していたんです。先に真夏の會が伊丹アイホールさんで『エダニク』を上演することが決定していて、その打ち合わせでアイホールさんに行ったとき“『エダニク』の東京公演もしないのか”というような話になったんです。そのとき、東京に行ったことのない劇団を果たして観てもらえるのかという不安もあって、せっかく行くなら何かいい方法はないかと考えたんです。それで、自分たちで企画を持ち込もうと思いついて。私は以前、極東退屈道場の『サブウェイ』を拝見しておりまして、“タイプがまったく違う関西のお芝居を1日で両方見られますよ”という形で東京に持って行ったら面白いんじゃないかなと思いまして、その打ち合わせ中に林さんに電話をかけて“一緒にやりませんか”と打診したのが始まりでした」
―― そのお話を受けて林さんは?
極東退屈道場・林慎一郎(以下、林)「『サブウェイ』を初演したときに、王子小劇場の芸術監督が偶然、見に来られていたんです。僕たちのことはまったくご存知なかったんですけど、観終わってすごく気に入ってくださって、“王子でもやりませんか”というオファーをいただいたんです。ただ、プロデュースという形もあってスケジュールとか、金銭面での体力的な問題で難しいかなと思っていたところだったんです。そのタイミングで原くんから連絡をいただいたので、そういう形で一緒に行ったら面白いかもとその企画に乗らせていただきました」
原「もろもろの調整は後で。とりあえず面白そうだし、やろう!という感じで決まりましたね」
―― なるほど。では、ちょっと話が前後しますが、ここでそれぞれ劇団の特徴を教えてください?
原「真夏の會は元クロムモリブデンにいた役者の夏と富永茜と僕との3人で作ったユニットです。以前、何かの芝居で一緒になったときに、もうちょっと継続的に作業をしてみようという話になったことがきっかけで組みました。コンセプトは作・演出をそれぞれ毎回、外部から呼ぶこと。なんですけど、実を言うと、まだ『エダニク』しかやっていません。ただ、外部から作、演出の方にそれぞれ来てもらって、スタッフワークもなるべくシンプルにして、お客さんには『役者と本と演出』を観てもらえるように芝居を作っていくということをコンセプトに立ち上げました。その第1回目で、売込隊ビームの横山拓也さんに脚本を、スクエアの上田一軒さんに演出をお願いして、『エダニク』を上演しました。そしたらすごくいい作業ができましたし、横山さんも日本劇作家協会の新人戯曲賞を受賞されて、次の作品を作る前にまず『エダニク』を再演しましょうということになったんです」
林「うちは、一応“極東退屈道場”としていますが、僕一人でやっています。上演の都度、作品を書いて、一緒にやりたい役者さんを集めてやっています。前は劇団をやっていたんですけども、それも5年くらい前にやめまして、こういう形に切り替えました。それで原くんに出てもらったり、原くんの劇団『水の会』と合同公演をしたこともあります」
―― では、次はお互いの劇団をご紹介していただけますか?
林「真夏の會は『エダニク』を観ての印象になるんですけど、さっき原くんが言ってはったように、スタッフワークとかも極力シンプルにして、本と演出で力のある人を呼んで、役者だけで見せるという舞台を観たとき、すごく刺激的だったんです。演劇の一番の原点を見せていると思って。虚飾を排しているというか。僕は割と虚飾を排さない、虚飾する方なので(笑)、芝居の面白さをすごくストレートに伝えてくれるお芝居だなと思いました。他の地域のことはわかんないんですけども、そういう出会いを生み出して作品を作る。しかもクオリティを高い作品を作るところはあまりないだろうなと。あと、プロデュース能力というか、横山さんと上田さんを組み合わせようということは誰もやっていなくて、それがすごく衝撃的で。それで作品を作るということも。あの二人が作・演出で、これから始まる舞台には役者さんが3人という状況で、それを見ただけで何かが起こりそうという予感を孕んでいて。そして見せてもらうものは虚飾を排した、本当にこれぞ芝居というもの。役者の体があればできますよということを見せてもらえて。横山くんも上田さんも、そのユニットでしかできないことをすごく理解している感じで、作品自体もかなり突っ込んだというか、存分にやっている感じがすごく出ていて、それは面白かったですね」
―― 横山さんと上田さんの組み合わせは誰も思いつかなかっただろうと林さんがおっしゃいましたが、原さんが“この組み合わせでやってみたい”と思われたんですよね。
原「そうですね。横山さんはウィットに富んだ会話、そしてシステマティックというか、すごくきれいに組み合わされた脚本を書かれる方なんですけど、上田さんはむしろキャラクター造形というか、スクエアさんのお芝居でも人にすごくこだわって作業される方なので、横山さんの会話劇と上田さんのキャラクターにこだわった、人間臭さを組み合わせたら面白いだろうなと最初に考えました。そして、2団体さんとも大阪でコメディをされているので近い感じがするんですけど、僕がお願いをしたときに“気になるけど一緒にしたことがなかったんだよ”と、お二人とも、まず二人で作業できることをすごく喜んでくれまして、そこは幸せだなと企画して思いました」
―― 実際に上演されたとき、はまったという感じでしたか?
原「その目算はきっちりはまったので、すごく嬉しかったです。その感触は稽古の段階からありましたね」
―― 目論見どおりかつ、それを上回る手ごたえがあったということですか。
原「そうですね。お二人もまだ行ける!って思ってくださったみたいです」
―― 『エダニク』は書き下ろしですが、もちろん真夏の會のために、ですよね?
原「図々しいですが、横山さんに“1本書いていただけないでしょうか”とお願いして…。“ええ!?”とかって言われながらも(笑)、やりますよと引き受けてくださいました。“どういうタイプの本がいいですか?”と聞かれて、売込隊ビームさんは幅広いお芝居をされているんですけど、ポップじゃないことも書かれているので、“横山さんのポップじゃない方でお願いします”と。そしたら“あ、そっちですね”となりまして、『エダニク』を書いてくださいました」
―― 外部の劇団の方に本を書いてもらったり、演出をしてもらったりという動きは、よくあることなんですか?
林「俳優自らがプロデュースして、作・演出を探すというのは結構、珍しいかもしれませんね。僕もそうですけど、自分が書いて演出する作品にいろんな人を呼んでというのはあると思うんですけど、根っこの部分をコラボレーションしてみようというコンセプトで作品を作るのは、そんなにないような印象ですね」
原「あら……ちょっと図々しかったですね(笑)」
―― “この方に書いてもらい、あの方に演出してもらう”というのは、俳優冥利につきそうですね。
原「そうですね。わがままな企画ですね。しかも、お二人とも、親密にお付き合いしていただいてたわけではなくて、“ご挨拶はします”というぐらいの距離だったので、勇気を出してお願いしてみました」
――では、真夏の會さんから見た極東退屈道場さんを教えてください。
原「割と極東さんもふり幅の広いお芝居をされていて。ただ、圧倒的に数が多いのが、虚飾を盛り込んだ、虚飾にまみれた(笑)お芝居ですね。その虚飾も“どうや!?”っていう豪華さではなくて、虚飾なのに冷めている…」
林「“虚”が多い」
原「何か虚無感があるんですね。特に『サブウェイ』は神話的な部分があって、その表出として虚飾にまみれた感があるので、すごく面白いです。情報としてノイズが多い表現で、やっていること自体も、果たしてそれが真の部分かというとそうじゃなかったりしますし。あとは、音としての言葉が見ていて非常に心地いいです。出ている役者さんもそれを十分に理解してやっておられるからだと思うんですけど、音が気持ちいいですね」
―― それは言葉の響きですか?
原「響きというより、リズム。特に『サブウェイ』にはそれを感じますね。基本モノローグで綴られて、その中で音とリズムが非常に重要になってくる。そこの部分がすごく気持ちよく聞こえてきますね。そしてビジュアル的にいろんなものが展開されているという。誰かと話していたんですけど、“『サブウェイ』はニコニコ動画みたいだね”って。いろんなところで情報が飛んでいて。これまで舞台でインターネットを表現しようというものはあったけど、感覚としてニコニコ動画をポンってぶつけられたことってあんまりなかったので、すごく楽しめましたね。終わってすぐ“再演した方がいいですよ、東京に行ったほうがいいですよ”って言っちゃいましたからね。東京に行ったことないのに(笑)。そしてまさか、一緒に行くことになるとは思ってなかったです」
―― その虚飾を盛り込むことの意図することは何ですか?
林「(ソフトの)イラストレーターなんかでもレイヤーを重ねるじゃないですか。あんな感じで、何枚レイヤーを重ねられるかみたいな感覚なんですね。この間、俳優としゃべっていたんですけど、“自分が舞台で何をやっているかはわかるけど、全体としてどう見えているのかわからない”って。それは、自分のやっていることにもう一枚、勝手に重ねられることが結構あるので、重なったときに見えている絵がどうなっているかあんまりわからないと。確かにそうだなって。今回もダンスや振付をお願いしているんですけど、ダンスシーンの振付というより、作品全体にダンスというレイヤーを重ねてみようという試みをしているので、芝居との重なり具合をはじめ、演技、美術、照明、音と、いろんな層が重なった見え方になっているんです。お客さんには1つの絵として見てもらっているんですけど、一つ一つは別々という作り方にしています。それは図らずも、僕が今までも試してきたものがクリアーに出ている作品だなと思いますね」
―― お客さんは俯瞰で見ていますけど、実際に中にいる人には見えづらい部分もあるんですね。
林「字幕も出るんですけど、字幕の向こうで俳優は演じていたりして。もちろん台本に書いているのでどんな字幕が出ているかはわかってるんですけど、見たときに自分の芝居と字幕とがどう重なって見えるのか。それでお客さんが何を想像しているのか、さっぱりわからない状況みたいです(笑)」
―― お客さんもそれぞれ、観るポイントが異なるんでしょうね。
林「感想をいただいたとき、割と“笑った”って言ってくれるんですけど、でも客席からそんなに笑い声が上がってなかったんですよ。観るポイントがバラバラなので、“今、むっちゃ笑いたいけど、他の人が笑ってないからこらえた”とか、そういう緊張感を強いられていたみたいでね」
原「笑いは起こっても“沸く”という感じじゃなかったですね」
林「だからわからない(笑)」
(2011年8月12日更新)
Tweet Check
Infomation

真夏の會
元クロムモリブデンの俳優・夏と、水の会代表の原真、女優冨永茜が結成したユニット。音響・照明・美術などのスタッフワークは極力シンプルに、台本、演出、役者だけでどこまで魅せられるのか、を追求している。その機動性の高さで、「いつでもどこでも高品質」をコンセプトに作品を製作。
第15回日本劇作家協会新人戯曲賞受賞作品
『エダニク』
作:横山拓也(売込隊ビーム)
演出:上田一軒(スクエア)
'09年2月、TORII HALLにて初演。
舞台は東京近郊のとある町の屠場。超大型黒豚「伊舞黒豚」の生産に成功した(株)伊舞ファームは、通常の加工ラインの規格外であるその品種の専用屠場として、ミートセンター丸元(株)を関連会社化していた。ミートセンター丸元は、会社の規模こそ小さいが、歴史が古く、腕のいいベテラン職人や若く質のいい職人を数名抱え、工場長やライン主任も有能であった。ところがある日、ミートセンター内で黒豚解体の際に不正があったと、伊舞ファームの社長が跡継ぎを連れて丸元の屠場に直々に乗り込んできた。工場長と社長の話し合いが始まり、暇を持て余した伊舞の息子は『屠場一日体験』と銘打って、職人たちの休憩所にもなっている研磨室に現れた。そして休憩所は、とても休憩ができる空間ではなくなり…。立ちこめる熱気と臭気。「生」がたちまち「死」に、「生体」が次々と「物体」と化していく空間の中、目前で失われるエネルギーに抗うかのように、メンタル面でもフィジカル面でもひたすら力強くある職人たち。そんな彼らの中で、突如、「死」のイメージが膨張していく瞬間を描いてゆく。

極東退屈道場
(劇)ミサダプロデュースの作・演出として活動していたミサダシンイチ=林慎一郎が主宰する演劇ユニット。公演ごとに俳優を集めるプロデュース形態をとっている。『サブウェイ』では、映像、ダンス、セリフ劇を巧みに構成、実験性に富んだ作品で高い評価を得た。
『サブウェイ』
作・演出:林慎一郎
振付:原和代
'10年11月、ウイングフィールドにて初演。
地下鉄を巡る7日間のドラマ。外国の映画監督が日本の地下鉄を舞台にしてドキュメンタリー映画を作るというエピソードを導入にし、無言の満員電車を利用する7人のエピソードが点描されていく。都市に暮らす故郷喪失者たちの噂やため息がチューブの中でこだまし、絡み合いながら、この国のサブウェイは走り続ける。歴史の積み重なりが創りだした地面の下に深く潜り、景色の見えない車窓と膨大な広告に囲まれながら、ただ目的地を目指す人々の空虚でナンセンスなつぶやき。それは確かに時代の空気をはらみ出していく。やがて1週間が過ぎたとき、神も同じく地球をつくりあげる。そしてまた、新たな月曜日がやってくる…。
公演情報
『真夏の極東フェスティバル』
■伊丹公演
8月11日(木)~14日(日)
アイホール(伊丹市伊丹2-4-1)
前売2500円
当日2800円
2公演通し券4500円
平日マチネ割引(11日(木)、12日(金)15時公演)2000円
11日(木)15:00(極)/19:30(真)
12日(金)15:00(真)/19:30(極)
13日(土)14:00(真)/18:00(極)
14日日11:00(極)/15:00(真)
■東京公演
8月25日(木)~28日(日)
王子小劇場(東京都北区王子1-14-4 地下1F)
前売2500円
当日2800円
2公演通し券4500円
平日マチネ割引(25日(木)、26日(金)15時公演)2000円
25日(木)15:00(真)/19:30(極) ※1
26日(金)15:00(極)/19:30(真) ※2
27日(土)14:00(真)/18:00(極) ※3
28日(日)11:00(極)/15:00(真)
☆公演終了後、昼夜ともアフタートークあり。
※1=ゲスト:楫屋一之(世田谷パブリックシアター劇場部長)
※2=ゲスト:中屋敷法仁(柿喰う客)
※3=ゲスト:竹内佑(デス電所)×丸尾丸一郎(鹿殺し)
各日とも開演の40分前受付開始、開演の30分前開場。
【チケット取扱】
ライトアイ[TEL]06-6647-8243 http://righteye.jp
(伊丹公演のみ)アイホール[TEL]072-782-2000
[問]ライトアイ[TEL]06-6647-8243