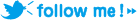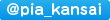ホーム > インタビュー&レポート > ただいま大阪松竹座にて大好評上演中の『七月大歌舞伎』。 仁左衛門、孝太郎、愛之助が演目それぞれの見どころを語る!

ただいま大阪松竹座にて大好評上演中の『七月大歌舞伎』。
仁左衛門、孝太郎、愛之助が演目それぞれの見どころを語る!
大阪松竹座にて現在、上演中の『七月大歌舞伎』。昼夜それぞれ、見どころたっぷりの演目を上演、中には関西では戦後初の登場となるお話もある。それらは歌舞伎ファンにとっては思わずにやりとなるラインナップであり、初心者にとっては歌舞伎の世界にすっと入り込めるものばかり。@ぴあ関西では、片岡仁左衛門のお話も交えながら、それら演目のあらすじなどご紹介! また、先日行われた船乗り込みや片岡孝太郎、片岡愛之助による“姫路めぐり”の模様もレポートいたします。
 「早いもので今年も7月がやってまいりました。毎回、言ってることなんですが、大阪で歌舞伎の公演をなかなか打てなかった頃に、関西・歌舞伎を育てる会さんのお力を借りて、大阪で複数の月に歌舞伎を上演することができるようになりました。その元になっている7月公演は、私にとって大変、大事な位置を占めております。また、関西での公演が増えたと言いましても、東京に比べればまだまだ少ないです。私が子供のころのように、関西歌舞伎が盛況だったころにもう一度戻したいと思っております。そのため、特に『七月大歌舞伎』においては、気軽に楽しめるお芝居を、初めてご覧になるお客様にもわかりやすいお芝居を、そして楽しい狂言立てをと考えておりまして、今年の企画もこういうような演目になりました。初めてのお客様にもお御足をお運びいただきますように」と、片岡仁左衛門。
「早いもので今年も7月がやってまいりました。毎回、言ってることなんですが、大阪で歌舞伎の公演をなかなか打てなかった頃に、関西・歌舞伎を育てる会さんのお力を借りて、大阪で複数の月に歌舞伎を上演することができるようになりました。その元になっている7月公演は、私にとって大変、大事な位置を占めております。また、関西での公演が増えたと言いましても、東京に比べればまだまだ少ないです。私が子供のころのように、関西歌舞伎が盛況だったころにもう一度戻したいと思っております。そのため、特に『七月大歌舞伎』においては、気軽に楽しめるお芝居を、初めてご覧になるお客様にもわかりやすいお芝居を、そして楽しい狂言立てをと考えておりまして、今年の企画もこういうような演目になりました。初めてのお客様にもお御足をお運びいただきますように」と、片岡仁左衛門。
下記のあらすじなどをご参考に、ぜひ一度、大阪松竹座で歌舞伎体験を!
昼の部
1.播州皿屋敷(ばんしゅうさらやしき)
| 浅山鉄山 | 愛之助 |
| 岩渕忠太 | 亀 蔵 |
| 腰元お菊 | 孝太郎 |
秘蔵の皿を割った咎で主人に惨殺され、井戸に投げ込まれた腰元お菊の怨霊が皿を数えるという「皿屋敷伝説」を素材にした怪談劇。
細川巴之介の家老・浅山鉄山は、天下を狙う山名宗全と通じ、邪魔になる巴之介暗殺計画を企てる。そんな中、腰元お菊が将軍家に献上する唐絵の皿10枚を受け取り、鉄山の屋敷へと届けにやってくる。かねてよりお菊に横恋慕していた鉄山はお菊に言い寄るのだが、きっぱりと断られてしまう。悪事も知られ、恋も叶わぬ恨みから、鉄山は皿を1枚盗んでお菊に罪を着せるのだった…。
関西では戦後初の上演となる本作、浅山鉄山を片岡愛之助が、腰元お菊を片岡孝太郎が演じる。『七月大歌舞伎』開幕前には『播州皿屋敷』ゆかりの地である姫路を訪れた孝太郎と愛之助。その模様はこちらをご覧ください!
「岡本綺堂さんの『番町皿屋敷』が有名ですが、こちらは『播州皿屋敷』。めったと出ないお芝居です。私は昭和46年に、若手歌舞伎の第1回だったと思うんですけど、新橋演舞場で(坂東)玉三郎さんと勤めさせてもらいました。これも思い出深いお芝居です」(仁左衛門
2.新歌舞伎十八番の内 素襖落(すおうおとし)
| 太郎冠者 | 三津五郎 |
| 鈍太郎 | 亀 蔵 |
| 次郎冠者 | 巳之助 |
| 三郎吾 | 萬太郎 |
| 姫御寮 | 梅 枝 |
| 大名某 | 秀 調 |
狂言の『素襖落』に能の『八島』の世間狂言である「那須語」を挿入して構成された作品で、狂言を基にした松羽目舞踊の嚆矢となった作品であり、新歌舞伎十八番の一つ。
伊勢参宮を思い立った大名が、かねてから約束していた伯父を誘おうと、伯父の館へ太郎冠者を向かわせる。あいにく伯父は留守だったが、太郎冠者の門出を祝おうと酒を振舞う娘の姫御寮。そして、姫御寮に所望され源平合戦の「那須の与一」を語った太郎冠者は、素襖まで頂戴して帰路に着く。酩酊状態の太郎冠者は、いただいた素襖だけは渡すまいと必死になって隠すのだが、大名の前で落としてしまって…。
素襖を隠そうとする太郎冠者と、それを見透かしている大名、鈍太郎の喜劇味あふれるやり取りがおかしい舞踊劇だ。
「(坂東)三津五郎さんが太郎冠者のお役でお出になります。踊りは苦手、よくわからないとおっしゃるお客様にも楽しんでいただけるお芝居です」(仁左衛門)
3.江戸唄情節(えどのうたなさけのひとふし)
序幕 芝居茶屋伏見屋より
大詰 村山座の舞台まで
| 杵屋弥市 | 杵屋弥市 |
| 芸者米吉後に女房お米 | 時 蔵 |
| 坂東彦三郎 | 三津五郎 |
| 市村家橘 | 愛之助 |
| 俵屋娘おいと | 梅 枝 |
| 隣家の女房お留 | 吉 弥 |
| 番頭平助 | 竹三郎 |
| 小揚げの七兵衛 | 彌十郎 |
| 伏見屋女将おふさ | 秀太郎 |
昭和14年、東京歌舞伎座で初演。川口松太郎が十五代目市村羽左衛門にあて書きした作品だが、歌舞伎以外でも新派や長谷川一夫、勝新太郎などが演じている人気作。
やくざ上がりながらもその腕を認められている長唄の三味線弾き杵屋弥市。恋人の芸者米吉には小揚長屋の七兵衛という親分がついており、伏見屋の女将もそのことを心配している。しかしついに二人の仲が露見、七兵衛に斬られそうになるのだが、弥市の腕を見込んでいる歌舞伎役者の坂東彦三郎の嘆願により、二人で江戸を出ることを条件に許しを得る。それから3年の時が過ぎ、小田原に身を寄せる弥市・お米夫婦の下に彦三郎一行が近くで興行を打っている知らせが届き、江戸で彦三郎の『連獅子』がかかるとの噂も。舞台が忘れられない弥市と、労咳を患ったゆえ芸人の女房として夫の芸を聴きながら死ねれば本望と言うお米は、江戸の地を踏めば斬るとの七兵衛と約束を知りながら、再び江戸へ戻ることに…。
平成7年の南座で評判を取った片岡仁左衛門(当時・孝夫)の弥市と中村時蔵の米吉という名コンビで再び登場。劇中劇で弥市(仁左衛門)が実際に三味線を弾く場面も見せ場となっている。
「『江戸唄情節』は私が若いときに父(十三代目片岡仁左衛門)が中座で演じました。その時、私も大きくなったらやりたいなと思っていたお芝居なんです。以前、私が大病をしたあとに舞台に復帰しましたときに、お祝いにと父が使っておりました三味線を私にくれたんです。その父が亡くなってから、この三味線で舞台を務めたいと思いまして、まず、中座で上演しました。それは若手の勉強の会でもあったんですが、私が三味線を弾いて、あとの方が歌を歌ってやったんです。冷房のなかった時代でしたけど、早くからお客様が並んでくださって、中座は超満員になりました。上階では人いきれで温度が上がりすぎて、倒れた方もいらっしゃったくらいでした。その翌年、南座で演じました。『三味線やくざ』というタイトルでしたが、当時、『やくざ』というタイトルがよくないと、それで『江戸唄情節』となりました。そのときの私の気持ちとしては、心の中で父を偲んで演じさせていただいた、思い出深い狂言です。お話としては、夫婦愛、男女の愛を見ていただきたいですね。そして、ちょっと泣いていただきたいですね(笑)」(仁左衛門)
夜の部
1.菅原伝授手習鑑(すがわらでんじゅてならいかがみ)
車 引
| 藤原時平公 | 我 當 |
| 舎人桜 丸 | 孝太郎 |
| 舎人杉王丸 | 巳之助 |
| 舎人梅王丸 | 愛之助 |
| 舎人松王丸 | 進之介 |
敵、味方に分かれることになった3兄弟の悲劇を描いた歌舞伎三大名作の一つ『菅原伝授手習鑑』の三段目。
梅王丸と桜丸は、互いの主人である菅丞相を左遷した藤原時平に恨みを晴らすため、吉田神社に参拝に来た時平を乗せた牛車の前に立ちはだかる。その車を守るのは松王丸。3つ子の兄弟は一歩も引かず、力任せに車を引き戻そうとしたため車が壊れ、中から時平が現れる。梅王丸と桜丸は狼藉を働こうとするが、それを防いだ松王丸に免じて助かり、父の賀の祝いの後に決着をつけることを約束して別れてゆく。
登場人物の扮装、動きや台詞、多彩な鳴物など、歌舞伎の様式美が凝縮された華やかな一幕だ。
「いとこ3人で梅王丸、松王丸、桜丸を務めさせていただきます。関西の役者のいとこ3人が七月大歌舞伎で演じさせていただくというのもうれしいです。私と父の最後の競演が顔見世での『車引』きだったんです。私が松王丸、我當が梅王、秀太郎が桜丸、そして父が時平公で出てくれました。今回、私は出ませんが、そういう意味でも、片岡家で固められる『車引』というのは、ひとしおの思いがございます」(仁左衛門)
通し狂言
2.伊勢音頭恋寝刃(いせおんどこいのねたば)
相の山/宿屋/追駈け/地蔵前/二見ヶ浦/油屋/奥庭
| 福岡貢 | 仁左衛門 |
| 油屋お紺 | 時 蔵 |
| 料理人喜助 | 三津五郎 |
| 奴林平 | 愛之助 |
| 油屋お岸 | 油屋お岸 |
| 仲居千野 | 吉 弥 |
| 徳島岩次実は藍玉屋北六 | 亀 蔵 |
| 藍玉屋北六実は徳島岩次 | 秀 調 |
| 油屋お鹿 | 彌十郎 |
| 今田万次郎/仲居万野 | 秀太郎 |
| 藤浪左膳 | 我 當 |
阿波の国家老、今田九郎右衛門の息子万次郎は、紛失した名刀青江下坂を探すため、伊勢へと足を運んだが、古市の遊女お岸に入れあげて通いつめてしまう。そして、刀を探し当てたものの、遊ぶ金欲しさに質入れし、鑑定書である折紙まですり替えられてしまう。この事で、万次郎の後見役の藤浪左膳から助力を乞われた福岡貢と、万次郎を陥れようとする敵方の様子を伺う奴林平は、手がかりとなる密書を手に入れる。しかし古市の油屋へやってきた貢は、手に入れた刀をすり替えられてしまい…。
1本の刀を巡って伊勢古市の廓油屋で実際に起きた事件をモデルに書かれた世話物で、寛政五年、道頓堀で初演された。『夏祭浪花鑑』と並ぶ代表的な夏狂言で、伊勢の風情や季節感あふれる作品となっている。また、後半に訪れる殺しの場面では歌舞伎ならではの凄惨な美しさも見どころだ。七月大歌舞伎では、通し狂言で上演する。
「『伊勢音頭恋寝刃』は、『相の山』からやりますと非常にわかりやすい。最近は通しと言いましても、大抵『追駈け』からになります。『七月大歌舞伎』では、普段なかなかできないことをやれる月でもありますので、通しで上演いたします。以前、上演したときも父から『こうしたらどうだ』という案を出してくれまして、父は、今回我當が務めます藤波左膳を務めてくれてまして、大変思い出深いお芝居でございます。この作品には、父がいろんなことを加えましたので、私は父のやり方でやろうと。そう言うと恐らく『私はそんなことはしてへん』と怒らはると思うけど(笑)、父の形でやらせていただきます。衣裳は、父はよく浅葱を使ってまして、父は浅葱が似合うんです。でも私はどうも浅葱が似合わないので、白でやらせてもらおうと思います。そういった衣裳くらいの違いで。もちろん私なりに変えているというか、変わったところはありますけども、父から教わったものを踏襲して演じたいと思います。また、今回は万野を(兄の)秀太郎が演じてくれるのですが、どういう万野を演じてくれるか…。油屋は万野次第なんですね。万野がよければ油屋は面白いお芝居になりますし、万野が悪かったら貢やお紺がいくらがんばってもどうしようもない。要は兄が握っています(笑)」(仁左衛門)
(2011年7月15日更新)
Tweet Check
船乗り込みレポート!

6月29日(水)、『七月大歌舞伎』に出演する俳優らが参加して、恒例の「船乗り込み」が行われました。大阪の夏を告げる風物詩でもあり、天満橋の八軒家浜船着場で行われた式典でも、多くの歌舞伎ファンが訪れていました。役者たちを乗せた船は、大川をくだり、道頓堀へ。そして大阪松竹座のふもとである戎橋までを約50分かけて移動。対岸や橋の上からは「松嶋屋!」「萬屋!」「大和屋!」などの掛け声や、紙ふぶきなどが舞い、道頓堀沿いの医院からは看護士さんたちからの花束の贈呈もありました。戎橋では口上が行われ、大阪松竹座のエントランスでもセレモニーが。役者たちへの花束贈呈や片岡仁左衛門の挨拶、そして“撒き手ぬぐい”が行われ、最後は片岡我當による大阪締めで、賑々しく締めくくりました。
公演情報
七月大歌舞伎〈関西・歌舞伎を愛する会 第二十回〉
発売中 Pコード412-445
▼開催中~27日(水)
昼の部 11:00
「播州皿屋敷/素襖落/江戸唄情節」
夜の部 16:30
「菅原伝授手習鑑/伊勢音頭恋寝刃」
大阪松竹座
1等席15000円
2等席8000円
3等席4000円
【出演】片岡仁左衛門/片岡我當/片岡秀太郎/中村時蔵/坂東三津五郎/片岡孝太郎/片岡愛之助/他
※未就学児童は入場不可。
[問]大阪松竹座[TEL]06-6214-2211
チケット情報
http://ticket.pia.jp/pia/event.do?eventCd=1117951
大阪松竹座
http://www.shochiku.co.jp/play/shochikuza/