
ホーム > インタビュー&レポート > 結成10周年を駆け抜けるlynch.の 3ヵ月連続リリースを締め括る無敵の轟音 『D.A.R.K. -In the name of evil-』! 玲央(g)と晁直(ds)がバンドの今を語るインタビュー&動画コメント

結成10周年を駆け抜けるlynch.の
3ヵ月連続リリースを締め括る無敵の轟音
『D.A.R.K. -In the name of evil-』!
玲央(g)と晁直(ds)がバンドの今を語るインタビュー&動画コメント
結成10周年記念ベスト盤のリリースに初の単独ホールツアーを行うなど2015年の上半期を駆け抜けたlynch.だが、その動きはまだまだ止まらない! シングル『EVOKE』を皮切りに8月から3ヵ月連続リリースを敢行。そのトリを飾る第3弾として、「多面体のようなアルバムになった」(g・玲央)約1年半ぶりとなるオリジナルアルバム『D.A.R.K.-In the name of evil-』を完成させた。今回は玲央(g)と晁直(ds)という珍しい組み合わせの2人が登場し、裏話も含め最新作からツアーまでを語ってくれた。
玲央(g) 「メンバー発信で3ヵ月連続リリースを組んだんですけど、プロモーションの時間を多分に用意していただいている分、制作と被ってきちゃうんです。第1弾シングルの『EVOKE』の発売後のプロモーションと、次の『ETERNITY』の制作が被っていたので、頭の中が結構…どっちの話をしているんだ?っていう感じで(笑)。そういう目まぐるしさはあるんですけど、とりあえずこの8、9、10月はlynch.のことでファンの方の頭をいっぱいにしたかったという。尚かつ11月までのツアーも含め、1年のうちの3分の1をlynch.に使ってもらおうかなと(笑)」
玲央 「MVに僕らは出ていないですからね(笑)」
玲央 「これはアルバムのリード曲でもあり、一般の方と一緒にコーラスをしたんです。Twitterでの『EVOKE』MV拡散キャンペーンに抽選で当選した方と、普段コーラスをやらない晁直とかも一緒に交じって歌ったので、これはこれでレアかな。参加した方にはすごく喜んでもらえたので、次回以降もこういった機会があれば是非やっていけたらと」
(2015年11月 4日更新)
Tweet
Movie Comment
私生活と大阪での怪現象を語る(笑)
玲央(g)と晁直(ds)からの動画コメント
Release
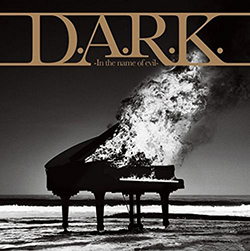
重く、激しく、美しい
メロウな轟音奏で疾走する最新作!
Album
『D.A.R.K. -In the name of evil-』
発売中 2778円(税別)
キングレコード
KICS-3256
<収録曲>
01. INTRODUCTION
02. D.A.R.K.
03. ANTARES
04. EVOKE
05. GHOST
06. ILLUMINATI
07. ETERNITY
08. FALLEN
09. BEAST
10. INVADER
11. COSMOS
12. MELANCHOLIC
13. MOON
Profile
リンチ…写真左より、悠介(g)、明徳(b)、葉月(vo)、晁直(ds)、玲央(g)。’04年8月に葉月、玲央、晁直の3人によって結成され、12月27日に名古屋クラブクアトロ公演(シークレット)からライブ活動をスタート。’06年に悠介が加わり、’10年に明憲が正式加入し、現在の5人編成となった。’11年6月にアルバム『I BELIEVE IN ME』でメジャーデビュー。’14年12月には10周年記念ライブを開催し、’15年3月11日にはインディーズ・メジャー問わずメンバーが選曲した36曲を収録した10周年記念ベストアルバム『10th ANNIVERSARY 2004-2014 THE BEST』をリリース。5月には東名阪での初のホールツアーを開催。そして、8月に『EVOKE』、9月に『ETERNITY』と2枚のシングルを経て、10月7日にアルバム『D.A.R.K.』を発表と、3ヵ月連続リリースを果たした。
lynch. オフィシャルサイト
http://lynch.jp/
Live
リリースツアーも後半戦に突入
大阪は初のなんばHatchワンマン!
『TOUR'15
「DARK DARKER DARKNESS」』
【広島公演】
▼10月11日(日)広島クラブクアトロ
【滋賀公演】
▼10月13日(火)U★STONE
【神奈川公演】
Thank you, Sold Out!!
▼10月15日(木)新横浜NEW SIDE BEACH!!
【宮城公演】
▼10月17日(土)仙台Rensa
【新潟公演】
Thank you, Sold Out!!
▼10月18日(日)
LIVEHOUSE 柳都 SHOW!CASE!!
【埼玉公演】
Thank you, Sold Out!!
▼10月20日(火)
HEAVEN'S ROCK さいたま新都心 VJ-3
【福岡公演】
▼10月24日(土)Fukuoka BEAT STATION
【鹿児島公演】
▼10月25日(日)鹿児島SRホール
【熊本公演】
▼10月27日(火)熊本Django
【島根公演】
▼10月29日(木)APOLLO
【香川公演】
▼10月31日(土)高松MONSTER
【高知公演】
▼11月1日(日)高知X-pt.
【愛知公演】
▼11月3日(火・祝)ダイアモンドホール
Pick Up!!
【大阪公演】
チケット発売中 Pコード266-701
▼11月6日(金)19:00
なんばHatch
オールスタンディング4320円
夢番地■06(6341)3525
※未就学児童は入場不可。
【北海道公演】
▼11月14日(土)ペニーレーン24
▼11月15日(日)CASINO DRIVE
【東京公演】
▼11月22日(日)TOKYO DOME CITY HALL
【沖縄公演】
▼12月19日(土)桜坂セントラル
Column1
結成10周年に贈る美しき轟音ベスト
『10th ANNIVERSARY
2004-2014 THE BEST』
そして初の東名阪ホールツアーへ!
悠介(g)&明徳(b)が10年の裏話と
バンドの志を語るインタビュー
Column2
泣く子も黙るへヴィなサウンドで
遂にメジャーフィールドへ進出!
lynch.が語るデビューアルバム
『I BELIEVE IN ME』制作秘話
Comment!!
キングレコード大阪宣伝
三十木桃子さんからのオススメ!
「名前も名前だし、何だか黒い人たちだ…と怖い印象を持つ人がいるかもしれませんが、まずはその先入観を捨ててください! 最近流行のポップでノリのよいロックと違って、男臭くてワイルドで、でも腰にくる葉月(vo)の低音のイイ声に耳を撫でられたかと思うと、激しいデスボイスに転換。たまらないです。私も初めは実を言うと“ちょっと怖いな…”と思っていたのに今やこの有様。今作のアルバムはlynch.らしい激しい曲あり、バラードあり、ライブで盛り上がる曲あり。けれど、これだけタイプの違う曲があるのに“あぁlynch.だね”と安心感をくれる、彼らの10年を経た“今”を聴かせてくれます。数々のライブを繰り返したどり着いたなんばHatchで、皆で笑顔になれることを期待しています」



























