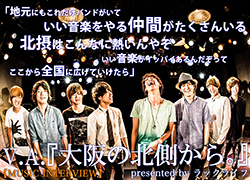世は、フェス対応のビートを武器にフィジカルなパフォーマンスに特化したバンドが主権を握る、歌モノ受難の時代である。そんなロックシーンで、キャリアと絆が培ったグルーヴ×言葉の1つ1つが伝わる力強いメッセージ×熱い血とヒットポテンシャルを湛えたメロディと、王道のポップソングを届けるライブで大阪を拠点に全国で奮闘するロックバンド、ラックライフが4thアルバム『正しい僕の作り方。』をリリースした。20代半ばにして10年に迫ろうという経験値とは裏腹に、高校時代からの仲であるメンバー間の空気は、いまだ失われぬ音楽への情熱とまだ見ぬ未来に、活き活きと躍動している。現在はリリースワンマンツアーの真っ只中、来年の4月26日(日)には主催イベント『GODD LUCK vol.33』を大阪なんばHatchにて開催することが決定したラックライフのソングライターでありフロントマンのPON(vo&g)に、これぞバンド人生な現状を語ってもらった。
「自分たちしか知らなかった曲を誰かに受け取ってもらって、今はそれをTwitterとかでビシバシ感じられるじゃないですか。もうそれを夜な夜な検索しては(笑)、“ありがとう、ありがとう”って思いながら。やっぱりそれが一番嬉しいことですよね」
「『正しい僕の作り方。』でもするし、自分1人でいろんなところにキャンペーンで廻っているときは、“PONさん”とか(笑)。見知らぬPONさんまでめっちゃ検索に引っかかってきますけど(笑)。暇さえあればしてますね」
「正直…最初はあんまり信用してなかったというか(笑)。今回のキャンペーン中に、そういう人たちといっぱい話す機会があって。ちゃんと想いを持ってラックライフを一緒に作ってくれてるのがやっと分かって。半信半疑やったんですよ。やっぱり人間そんなにすぐに理解し合えるものではないし、“俺らの音楽のこと、ホンマはどう思ってんねやろ?”とか思ってたんですけど、僕の曲とか言葉を信じて一緒にやっていくのって、こんなに素敵なことやったんかって。そう思うと、今まで9年くらい一緒にやってきたメンバーが、ものすごい存在やったんやって気付いたという」
「一緒にいることが普通やと思ってたんですけど、それを9年当たり前のように続けてこれたのはすごいことやなって。それってラックライフの強みやなって思ったし、それがまた広がって、みんなの先っちょに自分がいるこの環境が嬉しくて。これから先がすごく楽しみになったというか、日々ワクワクしながらやれている気がします」
「最初はコンセプトもなく何となく作ってて、何か括りを考えなあかんなぁみたいなときに書いてたのが、リード曲の『plain』(M-2)で。音楽だけじゃなくて普段生活しててもそうですけど、いろんな人と一緒に生きてるし、今の自分の考え方になるようなことをいっぱい教えてもらったし、こう言われたからこう思うっていう、気持ちのキャッチボールじゃないですけど、いろんな感情をくれるのは周りの人たちやなぁって。=自分が作った10曲は、人からもらったものとか、人に向けて歌いたいことばっかりやった。それに気付かせてくれたのが『plain』で、この曲でアルバムがギュッとまとまったというか」
――『plain』自体はどうやって生まれたの?
「元々はチャリンコをに乗りながら鼻歌を歌っていて。そう言えば、父ちゃん母ちゃんに歌った曲が1曲もなかったんで、そういう曲を作りたいなぁと思って歌詞を書いてたら、自分を作るのは父ちゃんと母ちゃんだけじゃないっていう気付きがあって、この曲はみんなに歌おうって」
――“誰かと言葉を交わす度 僕は新しい僕に変わるよ”、“誰かに貰った 大事な僕なら”という歌詞も、最初は“あなた”だったものを“誰か”に変えたと。これで1人1人それぞれにとっての誰かになったというか、この歌がみんなのものになったなぁって。ただ、父ちゃんと母ちゃんの曲はまだないっていう(笑)。
「そうなんですよ(笑)。だから改めて書こうと思ってるんですけど」
――この発想はすごくいいきっかけやったなと。例えば、ムカつくことを言われても、それに対してムカつくと分かった感情が、自分を形成してると。
「そうなんですよね。どんなことを言われたとしても、それに対して自分が何か思ったのなら、その時点で自分がちょっと変化したっていうことなんで。だから、言葉を交わさなくてもライブで目が合うだけでも、あの人は今こっちを真っ直ぐに見てくれてるからもっとちゃんと伝えたいと思ったり、ブログとかTwitterでも、そういう言葉だけだとしても、いろいろな人が今の自分を作ってくれてるんだなってすごく思いましたね」
――そう考えたら、ちょっと生き方が変わりますね。
「そうなんですよ。それに気付いたときは衝撃的で。”もうこんな自分はやってられん!”みたいに自暴自棄になったとき、好きな人の顔がたくさん浮かんできた瞬間があって。その人たちで自分が出来ているのなら、自分を嫌いとか言ってられへんと思ったんです。自分のことをもっと好きにならなあかんし、みんなが好きって言ってくれる自分に、自信を持てたというか。自分の中での大きなターニングポイントでしたね」
名前も分からへんような人のためにそんな距離を走って
30分必死に声を枯らして歌う。こんな美しいものはないんじゃないかって
――PONくんは挫折のエネルギーが曲を作らせるみたいなことを言ってましたけど、それは変わりました?
「それは結局変わらないです(笑)。何かこう、モヤモヤしてるときだったりとか」
――いつもモヤモヤしてるよね。Twitterとか見てたら、何かまたモヤモヤしてるなって(笑)。
「アハハハハ!(笑) モヤモヤしたがりなんですよね。長い間1人でいたりとかすると、もうダメ(苦笑)。だから、1人で過ごす休みとかは絶対に作らないようにしてるんですけど。気付いたら何か考えて落ち込んじゃうんですよね。ネガティブ発信なんです、常に」
――でも、それには強烈な原因があるわけじゃないんや。
「そうなんですよ。そういう曲も何曲かあるんですけど(笑)、何にモヤモヤしてるかも分からへんし、この感情をどこにぶつけていいかも分からへんっていう」
――あと、今回のアルバムを聴いて思うのは、安威川(=大阪府北摂津地域を流れる一級河川)とライブハウスが、PONくんの創作物に大きな影響を与えてるなと。
「そうですね。もう僕の生きる場所みたいなぐらいですから(笑)、川とライブハウスって。何かあったら川に行くし、何かあったらライブハウスに行くし。弾き語りとかで先にアルバムの曲をやったときに、“この曲ってきっと安威川で生まれたんやろな”みたいにお客さんにも言われて(笑)。ビックリしましたね」
――京都の鴨川とかもそうやけど、川が自分の生活圏にあるのって、音楽に影響あるなぁと。物思いにふけられる場所というか。そして、先行シングルの『ハルカヒカリ』(M-9)、あと『ローグ』(M-6)『フールズ』(M-10)とかもそうやけど、ライブハウスで観た景色からもらったものは大きいよね。
「あんなにいろんなことを感じる場所なんかそうないし、たくさんの人が集まるある意味非現実的な空間やのに、僕らにとっては日常になりつつある場所なんで。やっぱりそこで感じることが曲になっちゃうんですよね。曲を書いてるとそのことが頭をよぎるというか」
――PONくん自体も人見知りやし、そんなにすぐに人を信用しないとさっきも言ってましたけど、ライブハウスで会う人に対しては絶対的な信頼感みたいなものがあるよね。
「あれこそ…最強の信頼関係みたいなものやと思うんですよ。ホンマに好きじゃないと観に行かんやろうし、ホンマに観て欲しいと思わないと、わざわざ遠くまで行ってライブせーへんやろうし。名前も分からへんような人のためにそんな距離を走って、30分必死に声を枯らして歌う。こんな美しいものはないんじゃないかって」
――自分たちの音楽を持って旅が出来るって、すごい素敵なことというか。
「そうですね。そんな生き方選んでしまいましたね」
――『フールズ』なんかはまさにツアーで旅する光景だし、『ローグ』はそれこそ地元のライブハウス、高槻ラズベリーホールの。
「そうですね。もう完全にラズベリーに向けた歌です」
完成した段階ですごく幸せやなぁと思った作品やし
リリースして幸せやなぁと思えた作品やし
きっとワンマンツアーを廻って、それがもっと色濃くなっていくんかなぁって
――あと、『僕と月の話』(M-5)はすごい大事な曲のような気がして。言葉数も少ないし、曲調然り、メッセージ然り、ハッキリ物言いしないのが意味深というか…(笑)。
「アハハ!(笑) 個人的には一番好きな曲ですね。夜中に自転車で安威川に行って(笑)、缶コーヒー持って、煙草を吸いながらボケーッと小一時間、自分の頭の中の物事を整理するときに書いた曲なんですけど。もう、世の中には分からんことが多過ぎるし、人の気持ちも何ぼ接しても分かり切らんし、言いたくても言えへんこともあるし、絶対に言いたくないことだってあるしっていうのを、ちょっとだけ聴いて欲しかった…みたいな曲です(笑)」
――あと『パラボラ』(M-7)は、秦 基博のコード進行を元に作られたという(笑)。この軽やかさとか、煌びやかさとかはまさにで。でもやっぱり、コード進行が一緒でも、曲を書く人が違って、歌う人が違って、言葉が違えば変わるんやなって。
「最初はスタジオでイコちゃん(=イコマ・g)が指弾きで弾いてて。“そのオシャレなコード進行何~!?”って言ったら、“これ秦 基博”、“それやろ!”みたいな(笑)」
――あのロン毛長身の男が秦 基博を弾いてるっていう絵(笑)。でも、そういうのもちゃんとチェックしてるんや~。おもしろいですね。
「イコちゃんとかはホンマに、僕と発想が真逆なんですよ。全然違うベクトルの人で、『雨空(あめそら)』(M-1)のイントロのギターとかを最初に聴いたとき、えぇ〜!?って思いましたし。最近になってようやくメンバーに対して“何か個性的なんかな? この人たち”って思い出したというか、個性と受け取れるようになってきたというか」
――そういう意味では、PONくんの視野も広がったのかもね。広がったことによって、身近な人がスペシャルだったことに気付くというか。
「そうですね。そんなフレーズ思いつかへんし、やっぱいいなぁこの人、みたいなことを今回のレコーディングではたくさん思いましたね」
――あと、今作の曲順も、ドラマチックな先行シングル『ハルカヒカリ』でキレイに終わればいいものを、その後にドタバタのロックチューン『フールズ』が入ってるっていうところがね、やっぱりすごくおもしろいというか。
「もうそれがやりたかったというか(笑)。やっぱアホなことをしていたいよねって。『ハルカヒカリ』で締めるのがキレイやなぁとも思ったんですけど、聴き終わったときに“あぁ、よかったなぁ…”ってなるか、“いやぁ、よかったなぁ!”って言えるかどうかみたいなところで、『フールズ』みたいな曲が最後にあれば、みんなポジティブに終われるかなぁと思って。『ハルカヒカリ』は、ちょっと真面目過ぎるんですよね(笑)」
――先行シングルやのに(笑)。
「もう前回のツアーを廻って思いました。真面目過ぎる!って(笑)。普段の自分のキャラクターとのギャップというか、それももちろん俺なんですけど、もっとフワフワしてたいし、もっとアホなことをしたいし、もっと普段の自分に近い言葉選びとか楽曲のカラーで出来たらいいなと思って作ったのが、『フールズ』だったんで」
――今作が出来上がったときって、何か思いました?
「マスタリングも終わって、いいスピーカーで10曲通して聴こうみたいなとき、僕が一番いい席で聴いてたんですけど、曲を聴けばやっぱりいろんな人の顔を思い出すし、後ろにメンバーがいて、スタッフさんがいてみたいな中で聴いてて、何かこれ…えぇなぁ!って感動しちゃって(笑)、1人で泣きそうになりながら10曲聴いてました。完成した段階ですごく幸せやなぁと思った作品やし、リリースして幸せやなぁと思えた作品やし、きっとワンマンツアーを廻って、それがもっと色濃くなっていくんかなぁって」
ノリと勢いで始まったバンドやし、そこを忘れたら終わりかなと
――あと、ラックライフって北摂のバンドを集めたコンピ『大阪の北側から。』とか、なんばHatchでの主催イベント『GOOD LUCK』もそうやけど、まぁ言ってしまえば面倒くさいことというか、大変なことをやるよね。
「それをあんまり大変やと思わないタチというか、これやったらおもろいんちゃうん?って、やっぱり信頼出来る仲間がたくさんいるからこそ、その人たちの力も当たり前に使えるもんやと思ってるし(笑)」
――アハハハハ!(笑)
「協力してくれるもんやと思ってるから先陣を切って。そういう楽しみを自分たちで作り出していかないと、普通にやっててもやっぱりおもしろくないのもあるんですよね。“コレやりたい、アレやりたい。アイツらは力貸してくれるよ、大丈夫大丈夫”みたいな。そういう意味でも周りには助けられてるなぁって思うし」
――言ってしまえば、なんばHatchなんか集客大変やんとか、自分たちのことだけしっかりやって大きくなっていったらいいやんとか。ラックライフは結構いろんなことをやるやんか(笑)。
「やっぱりそれがおもしろいんですよ。もう少年ジャンプみたいなバンドになりたいんですよ(笑)。たくさん仲間がいて、無理をも超えていっちゃうストレートさみたいな。そういうバンドでありたいし、人間でありたいなってすごい思います。やっぱりノリと勢いで始まったバンドやし、そこを忘れたら終わりかなと」
――俺のPONくんへの第一印象は、なかなか心開かへんなぁっていう(笑)。
「アハハハハ!(笑) すごい疑り深いタイプ(笑)」
――そんなPONくんでも、時間はかかるけどいざ信頼したら、そうやってラックライフだけで上を目指すんじゃなくてもう、みんなで行くっていうね。
「そうですね。ホンマはそれがしたいんです。ただの目立ちたがりやと思うんですよね。そもそもの始まりがそこやったし、楽しい輪の中で一番目立ちたいみたいなところもあるし。やっぱりみんなが好きなんですよね。アイツらと一緒に、あの人のバンドと一緒に、お客さんもそれをなんばHatchでやるって言ったらビックリするやろうし。そのサプライズ感というか“うわー! すげぇー!”とか言わしたいんですよ。それが第一ですかね。もうね、全国を身内にしてしまえばこっちのもんみたいな繋がりも広がりつつあるし、やっていく自信もあるし。大阪の北側から始まって、それがどんどん“日本のド真ん中から”って言えるぐらいになれたらいいなって思います」
――いずれ、大阪城ホールの追加公演で、高槻ラズベリーっていうね。
「いや、それね、むっちゃやりたいんですよ! それはもう、夢ですね」
――何年後かにね、これ前に言ってたやつやん!って話が出来たら。
「そうっすね。それは絶対やりますんで!(笑)」
――本日はありがとうございました!
「ありがとうございました~!」
Text by 奥“ボウイ”昌史