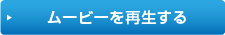絶望という強烈な孤独と、希望という捨てられないつながりの中で
迷える現代社会にLyu:Lyuが放つ4年越しの初フルアルバム
『君と僕と世界の心的ジスキネジア』!
コヤマヒデカズ(vo&g)インタビュー&動画コメント
出会いは忘れもしない’09年の『MINAMI WHEEL』。鋭いギターリフとハスキーで切ない歌声、ハイスピードからミドルの楽曲までに感じる叙情と衝動。全くの無名ながら会場に衝撃を与えた3ピース。そんなLyu:Lyuとのファースト・コンタクトから4年。ライブと作品を積み重ねるという何の成功の保証もなく、しかし確実にバンドの血となり肉となる活動を真摯に続けてきたロックバンドは、昨年『SUMMER SONIC 2012 OSAKA』にも出演。ジワジワとフォロワーを増やしていく中、遂に1stフルアルバム『君と僕と世界の心的ジスキネジア』をリリースした。“ストレイシープ(迷える羊)の代弁者”とも称される、現代社会に付きまとう得も言われぬ不安と苦悩の中から僅かな光をすくい取るような楽曲の世界観が、すさまじい熱量と技量で展開するネクストレベルな今作は、これぞLyu:Lyuと言うべき音像を鳴らし切った1枚だ。そこで、最近ではボーカロイドを使用して楽曲制作するソロプロジェクト“ナノウ”としても話題のコヤマヒデカズ(vo&g)に、彼自身の音楽のルーツからバンドのケミストリーまで、Lyu:Lyuの歴史と現在地についてたっぷりと語ってもらった。
コヤマヒデカズ(vo&g)からのエエ声動画コメント!
――付き合いが長い割には、こういうインタビューはなかったね。初めて。
「はい(笑)。そうなんですよね」
――1stシングル『カッターナイフと冷たい夜』('09)の頃から考えたら、スゴく状況が変わりましたね。当時、長澤(知之)くんとかを呼んだイベント『叫ブ詩人ノ会in逢坂』にオープニングアクトで出てもらったりもして。
「一番最初に奥さん(=筆者)にライブを観てもらってたときって、多分俺らも大阪に行き始めたぐらいで、Lyu:Lyuのことを知ってる人なんてまだ全然いなかったんですけど、あの頃に比べて今では大阪でワンマンがやれるようになったというのは、ホントに何かが変わったんだなと思いますね」
――東京だとクアトロをソールドさせたりもしてるもんね。ホントに着実に着実にやってきて。
「これまでも自分はいろいろとバンドをやっては解散し、やっては解散しで活動してきたわけなんですけど、過去の自分のバンド歴だったり今までの音楽人生から考えても、このバンドを組んでからの4~5年間っていうのは、ホントに自分が今まで経験したことのないことばっかりだったというか、スゴく濃い5年間だったなと思ってるんです。そもそも自分のバンドでワンマンが出来るようになること自体、ホントになかったことなんで。自分の作った曲だったりバンドの音楽が、ホントに徐々に徐々にその人たちに届いてる実感は、3人ともスゴく感じてるというか」
――小さいステップながら1つ1つ感じてこられた。だから続けられたのもあると思いますけど。
「ただ、この5年の間にバンド内とか自分の中で、悪い方にハマってた時期もあって」
――俗に言う“落ちる”というか。
「これでもし自分たちが発表した作品なり音楽が全く聴かれてなかったとしたら、とっくに誰かの心が折れてただろうなっていうタイミングが、思い返すと何度かあったと思うんです。そういうときにもライブに来てくれる人たちだったり、ネットでも直接でも感想を言ってくれる人たちとかの存在のお陰で、ここまでやってこれてるなっていうのは、ホントに思いますね」
――不思議ですよね。他のインタビューでの発言や歌詞の世界感とかもそうですけど、社会と共存&適合出来ない不安に自分が揺さぶられることがテーマの軸にはなってるけど、同時に音楽を続けられてきたのもその他者とのつながりで。結局自分が生かされているっていう。
「そうですね。バンド内でもたまにそういう話はするんですけど、自分らがやっている音楽には、その集団だったり社会に適合出来ていない自分が確実にいるんです。ただ、自分が強烈に感じている孤独を音楽に乗せて、吐き出したいだけ吐き出して、あとはもう別に聴きたきゃ聴きゃあいいよっていうよりも、結局心のどこかでそれを誰かに聴いて欲しかったり、分かって欲しい気持ちが絶対にあるんですよ。つながりに対して恐怖感があるんだけど、一方でやっぱりつながりを捨てることは出来ない矛盾を感じてる。もう無限ループみたいな話です(笑)」
このバンドの音楽は、もう自分だけのものではないような意識が出てきた
――さかのぼってコヤマくんの音楽人生を聞いていきたんやけど、そもそも音楽との接点はどこから?
「自主的に音楽を聴いたのは多分中学3年か高校くらいのときで、それまでは兄弟とか姉が持ってたCDをただ何となく聴いていて。高校に入って知り合った友達にニルヴァーナとかを教えてもらって、エレキギターやロックにスゴい興味を持って。ギター自体は中学3年生ぐらいでアコースティックギターを始めてたんですけど」
――それは何で?
「中学生当時、Jリーグが世間でめちゃめちゃ盛り上がってたんで周りがみんなサッカー部に入って、俺も最初は流れで入ったんです。でも練習がめちゃめちゃキツくって、そこでもうちょっと嫌気がさして(笑)。そうこうしてる間に、いろいろあって中2ぐらいでサッカー部が廃部になったんですよ(笑)」
――え~! そんなに盛り上がってたのに!?(笑)
「はい(笑)。一応、学校の決まりで何かクラブには入んなきゃいけなくて、俺はさっきの練習のせいで運動がとにかくイヤになってたんで、見た感じ一番楽そうだった吹奏楽部に入ったんです。その内、音楽準備室にクラシックギターが置いてあったんで、それを引っ張り出して遊びで弾いてたら、単純にギターっておもしろいなって思うようになって。中学3年の頃に安いアコギを買ったんですけど、高校でニルヴァーナとかを聴くようになって、アコギがエレキになって、自分も歌うようになって、それでバンド始めて、ちょっと曲でも作ってみる?みたいな話になったと。もう断片的にしか思い出せないんですけど、当時初めて作った曲が歌謡ポップみたいな曲で、メンバーに大爆笑されたんですよ。それが俺の若干のトラウマになって(笑)、曲作りに対してネガティブなイメージが植え付けられたというか、“もう二度と曲なんか作んねぇぞこの野郎!”って(笑)。ただ高校3年の卒業間際ぐらいに、また自然と曲を作ってみたいテンションになってきた。でもあの記憶があったから(笑)、もう誰にも聴かせないようにひたすら自分で作って自分で聴いて、いい曲だな~って満足してるみたいな。そうやって全然人に聴かせることもなく、高校を卒業して音楽専門学校に行くんですけど」
――じゃあ何かしら音楽はやりたいっていう気持ちはずっとあったんやね。
「高校の頃からもう、音楽を本気でやっていきたいってだんだん考えるようになってましたね。専門学校に入ってしばらくしてから、講師の人にこっそりダメ元で曲を聴かせて、そこから周りの人にもちょっとずつ聴かせるようになって。でも、最初はいいねって言ってもらえても、それが全然理解出来なかったというか。そもそも自分が気に入るようにしか作ってないから自分がいいと思うのは当たり前で、あなたがいいと思うようには作ってないよって(笑)。半信半疑でしたね。それがこのバンドを始めて、自分の発したものが届いて、それに対してリアクションが返ってくるという経験を徐々に知ったというか。だんだんと自分が今作っている歌とか歌詞とか、このバンドの音楽は、もう自分だけのものではないような意識が出てきた。自分たちの出す音を楽しみにしてくれる人たちがいたり、救われましたって言ってくれたり、そういう人たちに対して、かつて自分がニルヴァーナとかそういう音楽に鬱屈した気持ちが救われたように、今度は自分が聴いてくれている人たちにいったい何が出来るんだろう?って。初めて自分以外の人に向けて音楽を発信することに自覚的になれたのはありますね。ホントにここ1~2年ぐらいのことなんですけど」
――自分のためのものだった曲が、それだけじゃなくなっていくのを自覚せざるを得なくなった。
「そうですね。当時に自分にとっては、良くも悪くもだったんですけど。反応が返ってきて、何かを期待してもらえること自体はスゴく嬉しかったんですけど、ただやっぱり、自分だけのものであったはずの音楽がそうではなくなって、いろんなことを求められる葛藤みたいなものはやっぱりありました。それはまぁ今でもあるんですけどね」
音楽が間に立ってないと、俺は世界と関わっていけないんですよ
――今回のアルバムが出来るまでの過程では、スランプにもなったみたいで。
「作っても作っても全然いいと思わない、みたいなことが多々ありましたね」
――自分を満たすために曲を作っているはずなのに、自分が満たされない。
「前回のミニアルバム『プシュケの血の跡』('12)を出した直後ぐらいから、既に兆候はあったのかなぁと。だんだんと自分の曲がいいかどうかさっぱり分かんなくなってきたというか、自分がいかに感動出来るかがボーダーラインだったんですけど、何をどう考えても満たせなくなってしまった。今まで基準としてきたものが自分の中で完全に崩壊しちゃって、不感症になっちゃったんじゃないか? もしかして音楽が嫌いになっちゃったのか?みたいな。そうなると曲を作ることが苦痛になってきて、一旦完全に筆を置いたというか、とにかくライブに集中したんです。当然、自分が音楽活動を続けていく限りはそのままではいられないわけですよ。ただ、何とかしなきゃって思うほど、余計どうすりゃいいか分かんない。ある意味底の底まで行って、そもそも何で自分は音楽を始めたのか、自分が別に作らなくたって世の中には他人が作った音楽が溢れてる。わざわざこんな苦しい思いをして曲を作る理由って何だろう?って考えたんです。結局、自分の過去にうまくいかなかったこと、言えなかったことがたくさんあって。何であのときあの人にああ言えなかったんだろう?とか、逆に何でああ言ってやらなかったんだろう?とか、そういうことばかりが積もり積もった人生だったんですよね。それを自分の中で浄化したくて、ずっと音楽をやってきた。ある意味覚悟を決めたというか、自分が思うようにやったとき、それを聴いた人はもしかしたらガッカリしてしまうかもしれない。でももうそれでも構わない。もう一度自分に問いかけながら、“ホントに自分が救われるのか”だけを考えて、曲を作ろうって腹を括ったんです」
――でも、世の中には他にも楽しいことがいっぱいあるわけじゃないですか。何で音楽なのかな?
「俺、出身が東京なんですけどめちゃめちゃ田舎で、保育園から中学校まで周りのメンツが一切変わんなくて全員幼馴染みたいなところだったんで、ある意味14~15ぐらいの自分にとっては、そこで世界が完結してたんです。でも、高校で初めて地元からちょっと離れたところに行って、地元のメンツは散り散りになって、当然ほとんどが初対面。自分の世界は完成していたはずが全然そんなことはなくて、そこで初めて自分のいろんな一面を知ることになって、本来人付き合いがとても苦手で、喋るのが下手な自分と向き合わざるを得なくなったんですよね。その結果、周りの話題についていけない、溶け込んでいけない自分がいたわけなんですよ。単純に言うと、ホントに友達がいなかったんですよ(笑)。自分はウォークマンでひたすら音楽を爆音で聴きながら1人で登下校みたいなヤツだったんで、ずっと音楽が唯一の友達みたいな感じだったんですよ。なのにその当時流れていたJ-POPの歌詞は、自分にとっては全くリアリティがなくて、別世界の出来事のような気がして全然いいと思えない。自分が好きになったそれこそニルヴァーナとかSyrup16gみたいなバンドの言ってることの方が、自分にとっては遥かにリアルだったんですよ。俺みたいに考えている人が他にもいたんだって。そこで初めて外の世界に理解者を見付けたような気がしましたね。音楽をやり始めてからはいろんな人と知り合って、徐々に友達みたいな人も出来ていくんですけど、それもやっぱり音楽を介した関係だと自分では思ってます。結局、音楽は自分が外の世界と接するときの窓口みたいな役割がスゴいあって、音楽が間に立ってないと、俺は世界と関わっていけないんですよ。その想いはずーっとあったと思います」
“これが俺が組む最後のバンドだと思う”
――コヤマくんの音楽って、Lyu:Lyuというバンドで表現してるわけやんか。でも、極論言えば曲を書いて歌うことに関してはアウトプットがバンドじゃなくてもいい。Lyu:Lyuとして音楽をやることに関してはどう?
「やっぱり…元々聴いたのがバンドだったのもあって、自分がやる側になったときにも、何の疑いもなくバンドをしていたというか、自分の中で音楽で大成するとしたらバンド以外有り得ないって、信じて疑わなかったんですよね。やっぱりバンドが好きだし、自分の中でバンドっていうものがスゴくカッコ良かったんですよ。ただ、やってみると問題になってくるのが人間関係で、元来の人付き合いの下手さみたいなものが出るわけなんですよね(笑)」
――だったら1人でやった方が絶対楽じゃんって思うよね。
「そうなんですよね(笑)。周りからも、1人の方がのびのびやれるし絶対合ってるよってずっと言われてて。それでもやっぱり、バンドに対する憧れの方が自分の中で勝っていたというか」
――元来苦手な人付き合いで苦しむことよりも、憧れが強いってことか。
「はい。結局、専門を出た後に組んだバンドだったり、その後にも幾つかやりましたけど、全部が人間関係で解散してる(笑)。それを繰り返してるとさすがに俺も、バンド向いてないのかな?って思い始めるわけですよ。なので、Lyu:Lyuの前のバンドが解散したとき、1年ぐらいは1人でやってみたんです。けど、やっぱり自分の中でバンドへの憧れみたいなものが、どうしても消えなかったんですよね。だからある意味ケジメを付けるためにも、もう1回バンドがやりたいと思い立って、今のメンバーに“俺は今まで幾つもバンドをやってきて、幾つも解散してる。もし、このバンドでダメだったら、俺はもう二度とバンドをやらないと思う”って、最初に言ったんですよ。“これが俺が組む最後のバンドだと思う”って」
――スゲェ重いスタートやな(笑)。そら2人も頑張んなきゃいけないね。何で他のバンドはダメだったのに、Lyu:Lyuは続いてるだろうね。
「前にやってたバンドとかって、俺の超絶ワンマンだったんですよ。もうホントにそこが原因だったというか。自分が作った曲に対するプライドが高過ぎて、メンバーに俺の好みと違うことをやられると、それ違うから!みたいな」
――じゃあソロでやれよっていう(笑)。
「アハハハハ!(笑) やっぱりメンバーもそこまで言われると、別に俺じゃなくたっていいじゃんってなるので。このバンドでは最初からそういう過去の話もしてたんで、バンドが長続きしなかったのは何でだろう? 今までうまくいかなかったところを1つ残らず解消していこうって。それもあったのかもしれないです」
――Lyu:Lyuという船が沈まないように、一緒にきっちりプランニングしてくれて。Lyu:Lyuもそうやけど、コヤマくんの守備範囲が広がることによって、それこそ曲も広がって、お客さんも広がって。自分が変われば、世界が広がっていく。今回のアルバムの曲からも、確実に新しい風が吹いていて。『君から電話が来たよ』(M-7)なんかは、今までLyu:Lyuにおいてタブーだった恋愛を歌うこともそうなんやけど、音色やボーカルにしても全てが新しい。
「さっきも言ったように、自分が作る曲に対する強いイメージがあって、例えば恋愛絡みの歌を自分が歌うなんて、もう気持ち悪くて聴いていられないみたいな、マイナスのイメージがスゴくあって。でも今回、1回底まで落ちて開き直ってやるぞとなったとき、表現する1人の人間としてタブーなんか作ってる場合じゃない、恋愛だろうが何だろうが、もう全て言っていくって、その時点で腹を括ったというか」
――表現者としてもっともっと自分のディープな部分を掘り下げていかないといけない時期に来たというか。さっきの守備範囲が広がる話じゃないけど、自分でも可能性を感じたんじゃないですか?
「多分『君から電話が来たよ』みたいな曲は、今までの俺らだったら絶対途中で挫折してお蔵入りになってたと思うんです。でも最終的に、この楽曲の能天気さに対してこの歌詞の内容だったり、ちゃんと自分たちの世界を作れるようになってきた。これはバンドとしてのレベルアップだと思うんですけどね」
今回はホントに初めて、一切の言い訳なしで
“どうぞ! 聴いてください!!”と言えるモノが出来た
――今回は過去の曲も新録されていて、『暁』(M-10)なんかはまさに最初期の曲で。
「このアルバムは、今までで一番いいものをというのと同時に、今までの活動をまとめるものにもしたいということで、過去作から1曲ずつ再録したんです。『暁』なんかは、作った当時は全然難しいことを考えず、バーン!と合わせて作った曲だったんですけど、今改めて聴いてみても最初期に作ったにしてはやけによく出来た曲だなって(笑)。一時期は躍起になってもう過去の曲は、『暁』とかはライブでやらねぇみたいなこともあったんですけど(笑)、今になって考えれば、昔からLyu:Lyuを知ってくれている人たちも、今好きになってくれた人たちも、変わらずいいって言ってくれてる曲が作れたのが単純に良かったなぁとは思います」
――コンスタントにリリースもしてきて、今回が1stフルアルバムっていうのが意外でもあったんですけど、出来上がったときに自分たちの中で達成感はあった?
「今までのシングルだったりミニアルバムって、どうしても自分たちのイメージに技術が追いついてなかったり、そもそもレコーディングすることに不慣れだったりして、思うようにいかなかった部分も多々あるんですよね。当然そのときに出来るベストとして納得して出してはいたんですけど、それを名刺代わりに聴いてもらうときに、どこかで言い訳したくなる気持ちがないわけでもなかったというか(笑)。今回はホントに初めて、一切の言い訳なしで“どうぞ! 聴いてください!!”と言えるモノが出来たという実感は、3人とも感じていたと思いますね」
――それは音楽家としてはスゴく幸福なことですね。バンドを続けて良かったよね。
「そうですね。過去の自分からしたらまず、ここまで続いてること自体が(笑)。メンバーに対して、俺も丸くなったなぁみたいなところはありますよ(笑)」
――純一(b)くんも何かで“コヤマも丸くなった”みたいなことを書いてたような気がするわ(笑)。
「アハハハハ!(笑)」
――そもそも何でこの2人やったの?
「純一は元々一緒にバンドをやっていたんですよね。前のバンドが解散してしばらくして、たまたま会う機会があったんですよ。そこでいろいろ話をして、“実は俺はまだバンドを続けたかったし、この先もしベースが必要になったらいつでも弾くよ”みたいに言ってくれたのを何となく覚えてて。それで最初に声を掛けたんですけど。純一とは聴いてきた音楽は全然違ったんですけど、例えば“バンドってどうあるべきだと思う?”みたいなところで、不思議なぐらいウマが合うというか。“やっぱバンドってそうだよね!”みたいな話で結構盛り上がってたんですよ(笑)」
――こんなにいろんな人とウマが合わないコヤマくんに、合うヤツがいたと(笑)。
「アハハハハ!(笑)」
――やっぱコヤマくんは“バンドとは”ということに対して、スゴく強い意識があるよね。有田(ds)くんは専門学校の後輩とか言ってたよね。
「そうやって純一には声をかけたんですけど、ドラムに知り合いが全くいなかったわけですよ。そこで、専門学校時代の数少ない友達に電話したんですけど、その友達が有田のことをよく知っていて。俺は当時組んでたバンドで1回対バンしたか何かで、ライブも個人的に何回か観に行っていたものの、それ以上関わることはなくて。その友達は俺の性格とかも知ってたんで、“有田だったら人当たりもいいし、多分うまいことやれるんじゃないの? 誘ってみたら?”みたいな。で、連絡先を聞いて電話してみたんですよ。向こうも突然声が掛かってビックリしてましたね。“え? 俺っすか!?”みたいな(笑)」
(一同笑)
「それで3人で初めてスタジオに入って、意外にも普通に楽しかったというか、特に気兼ねない感じでやれて。スタジオが終わった後に、“2人がよければバンドとしてやっていきたいと思ってるんだけど”って話をし。俺と純一はほとんど喋んないヤツだったし、有田のそういうところも、当時からスゴく助かりました」
――これでもう1人同じようなヤツだったら、全員でモジモジしてたね(笑)。
自分の歌をウワァーッ!って歌いたかったけど
ライブで人前に立つのは怖い(笑)
――曲を書くことに関しては聞いたけど、歌うことに関してはどうですか?
「元々物心付いたときから、歌うことは楽しいっていう記憶があって。小さい頃にラジカセに自分の歌を録音したりとか。自分は初めてバンドをやり始めた頃からもうずっと、ギターボーカルしかやったことがないんですよ。まぁそれには偶然もあって、高校の頃バンドに誘われたとき“ギターとボーカルがいない”って言われて、じゃあ俺やるわみたいな感じで(笑)自然とそうなって、それからずーっと。当時は歌に対してそんなに意識してなかったという」
――まぁ好きだし、やろうかみたいな。
「はい。そこからだんだん自分で曲を作るようになって。そこで初めて、自分の鬱屈した気持ちをガーッと書きなぐった歌詞を、自分で作った曲に乗せて、ライブでウワーッ!!って歌うことで、スイッチが入ったような感覚というか…むしろ普段は全然上手く言えないようなことを、ここぞとばかりに言いまくった記憶があって。自分にとって歌は、ホントに自分の鬱憤を晴らすための手段でしかなかったというか。人が聴いていようがいまいが、歌になっていようがなかろうが関係ない。言いたいことを叫んで終わり。ずっとそんな感じだったんですけど、こうやって聴いてくれる人がだんだんと増え始めて、自分がボーカリストであることに自覚的になったんですけど。それも、このバンドを始めて1~2年経ってからだから、やっぱりこのバンドが起因だと思うんですけど」
――でも今となっては、ギターを弾いて曲を書くだけじゃ満たされないよね?
「そういう意味ではスゴい矛盾してますね。自分の歌をウワァーッ!って歌いたいけど、ライブで人前に立つのは怖い(笑)。それは今でも怖いんですけど、正反対な気持ちも常にありますね。怖いけど出たい、みたいなね(笑)」
Text by 奥“ボウイ”昌史
(2013年8月 2日更新)