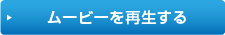実験と挑戦を繰り返し生まれた
どこまでも美しく、どこまでも気高い『GIFT』
THE NOVEMBERSがオーケストラを迎えた幸福な意欲作と
バンドのパーソナリティを解明する、貴重な全員インタビュー!
作品ごとにその世界観をためらうことなく更新するクリエイティビティで、シーンに波紋を、聴く者には新たな刺激と気付きを与えてくれるTHE NOVEMBERSが、ためいきが出るほど美しい新作『GIFT』を届けてくれた。オーケストラを迎えてライブレコーディングされたサウンドを土台に再構築された今作は、昨年2枚同時リリースされた驚異のアルバム『To (melt into)』&シングル『(Two) into holy』を経て、穏やかに、そして高らかに、まるで余白を描くような澄み切った開放感を鳴らしている。そこで、一心不乱に作品を高めていく4人に、実験作であり意欲作である『GIFT』の世界を問うインタビューを敢行。普段はバンドの中枢を成す小林祐介(vo&g)がスポークスマンとなることが多いのだが、今回の貴重なメンバー全員インタビューでは、エッジィなサウンドをぶっ放すクールな一面とはまた違い、彼らが紛れもなく“バンド”である体温を感じさせてくれる。対象が変わらなくとも、自分が変わることによって対象の見え方が変わるように、新しい世界はあなたのすぐ傍にある。THE NOVEMBERSからの新しい音楽=『GIFT』を受け取る幸福を、じっくりと味わって欲しい。
メンバー勢揃いのレアな動画コメントはコチラ!
――メンバー4人でインタビューって珍しくないですか?
小林(vo&g)「すごい珍しいです」
――今回の『GIFT』のリリースなんですが、言っても1年以上経ってるはずなのに、早いなと思ったんですよね。前回同時リリースされた3rdアルバム『To (melt into)』、1stシングル『(Two) into holy』の2作が強烈に印象に残っていたんで、次のTHE NOVEMBERSをどう見せていくんだろうと。
小林「海外のバンドと違って、日本のバンドってコンスタントにリリースすることがいい方に転ぶ業界だったりするじゃないですか。普段から曲作りを習慣的に行っているのもあったし、そういうのも含めて自分たちは割とコンスタントに作品を出せたらいいなと思ってたんですね。とりあえず自分たちで何か面白いことをやりたくて、WEBで僕が作った曲に対してのリアクションを作品でもらうプロジェクト『Moiré.0』とか、3ヵ月連続でイベント『Moiré』をやっていく中で、その一環として『Moiré』で大所帯編成のライブをやろうと。せっかくだからライブ録音もしておこう、ライブ録音するんだったらいいものを作りたい、いいものを作るんだったらお客さんに聴かせたい、っていう発想になっていって…自分たちのやりたいこととかやるべきことを、すごく素直に実行出来た感じですね」
吉木(ds)「『Moiré』のプロジェクトは、3回のライブ含めてこれはバンドにとって絶対によいことだと思ってたんで、そこに乗っかって自分も最大限楽しむというか」
――小林さんが提案していくことに乗っかれば、面白いことが起きるっていうのはみんなが感じるところというか。
ケンゴマツモト(g)「それはすごく感じましたね。あと『Moiré』のライブのための試みと、レコーディングのためのそれが同時進行していたので、ワクワク感を保ちながら制作に臨めて。本番とCD制作が一緒にやってくるみたいな感じは、すごく新鮮だし楽しかった。充実してましたね」
――大所帯編成でやってみたい願望は、元々自分の中にあったんですか?
小林「僕も含めて、自分たちの音楽的表現への好奇心は昔から各々にあったと思うんですけど、以前は4人で出来ることの限界とか楽しさに目がいってて。今回はいろんな人と関わったり、関わってしまったことも含めて、それをいい方向に転がしていくことはすごく素敵なことなんだって気付いて。楽しいと思えるんだったら率先してやろうと。元々メンバーはみんなアーケード・ファイアとか、ブロークン・ソーシャル・シーンとか、シガー・ロスとかが好きで、大所帯編成に憧れがあったのもありつつ、以前台湾のフェスに出演したとき、万能青年旅店っていう中国のバンドを観てすごく感動したんですよ。トランペットがフワって鳴った瞬間に、景色がガラッと変わってお客さんが盛り上がって。そういう祝祭感のある風景を観て、ますますやりたくなったっていう」
――それで言うと今作は、大所帯でやることを前提とした曲作りだったりフレーズ出しってことですよね。それによって今までと何か変化はありました?
吉木「余白を作ることを常に意識してましたね。他の音が入ってくる=それだけやっぱり要素が増えるってことなんで。自分はその人たちが入れるところ、落としどころを増やすというか」
小林「難しいなと思ったのが、エレキギターだったりいわゆるバンドサウンドの持っている特性が、オーケストラとは相性があんまり良くないんですよね。アコースティックのバイオリンとかそういう楽器に対して共存することがすごく難しくて。だからさっき吉木くんが言ったように余白を開けることとか…それは音もフレーズも含めてなんですけど、今までだったら“あってもいいな”と思っていたようなフレーズとか鳴っちゃってる音とかも、“あってもいいな”ぐらいならない方がいいに決まってる。あるべきものしか残しちゃいけないんだって思ってましたね」
ケンゴマツモト「僕もアレンジを詰めていく中で、当初やろうと思っていたことでも、やっぱりいらないなって思うことが増えてきて。そういう他の楽器の要素で曲が変わっていく面白さがあって、すごく嬉しかったですね」
――あと、僕はTHE NOVEMBERSのベースラインが好きなんですよね。めちゃくちゃカッコイイと思うんで。
高松(b)「本当ですか!? 曲にもよっちゃうんですけど、『Moiré』(M-1)なんかはすごく多くの楽器が入ってるので、そういう曲に関してはシンプルに、とは言え躍動感を出したいときはやっぱり動いた方がいいし、そういうメリハリは特に気をつけましたね」
――シンプルにしていく中でも自分らしさ、THE NOVEMBERSらしさ、オーケストラと一緒にやる新しさ、も必要となったら、突き詰めて突き詰めて本当に大事なものだけを残していくような作業ですね。
小林「そうですね。だから、せっかくやった試みだから残したいとか、実験したんだからなくしたらもったいないとか、そういう考えは一切捨ててました。やっぱりどうしても後ろ髪引かれる思いがあったりもしたから、それがすごく難しくて。ライブレコーディングして面白かったとは言え、作品としてうまく転がせなかったらきっとリリースはしなかったと思うし、各々が各々のやり方で、いい方にいい方にと努力出来たことが一番よかったことなのかなって思いますね。普段だったら“いやいやちょっと違うだろ”と思うようなことも、どうしたらこの作品が報われるのかを第一に考えられたのは、成長出来たところかなと思います」
今回の『GIFT』で僕がやりたかったのは
これが善だとか悪だとか、美しいとか醜いと区分することじゃなくて
それをあなたがあなたのやり方で選んで欲しいっていう投げかけだったり
“どう思う?”っていう問いかけなんですよ
――ブログや媒体資料にも掲載されていた“「GIFT」によせて”では、XTCの『アップル・ヴィーナス Vol.1』(‘99)にインスパイアされたという一文がありましたけど。
小林「この作品は21とかそれくらいの頃に出会って、元々好きな作品ではあったんです。ふとXTCでオーケストラが入ってる作品って何があったかな…といろいろ思い巡らせているときに、このアルバムを思い出して改めて聴いて。XTC自体が実験とか試みにすごく意識が向いてる人たちだし、その変化作と言われた『アップル・ヴィーナス Vol.1』のジャケットにある“Do what you will but harm none”=“何をしてもいいけれど、人を傷つけないこと”っていう言葉…。“「GIFT」によせて”で、リスペクトも込めて『アップル・ヴィーナス Vol.1』のことに触れたのは、この文章によるところも結構大きくて。これは綺麗事とかそういう話じゃなくて、“何をしてもいいけれど、誰も傷つけないっていう状況を、このCDを聴くあなたは想像出来るか?”っていうXTCからの問いかけだと僕は思ってて。今回の『GIFT』で僕がやりたかったのは、これが善だとか悪だとか、美しいとか醜いと区分することじゃなくて、それをあなたがあなたのやり方で選んで欲しいっていう投げかけだったり、“どう思う?”っていう問いかけなんですよ。僕はこう思うんだけど、これはあくまで僕が思ったことだから迎合しないでねっていう作品だと思ってるんです。それがXTCのイメージとすごく通じるところがあったっていう」
――他のインタビューでも言ってましたけど、今作で手を差し伸べることはしないけど、リスナーがアクションしたことに対しては背中を押すっていうのは、THE NOVEMBERSらしい距離の取り方だなぁと。
小林「手を差し伸べるっていうのは、要はその人が自分では立ち上がれないって思ってるわけじゃないですか。その人の力を見くびっている。癒しとかヒーリングって言うと聞こえはいいんだけど、すごく見下している考えだと思ったから。僕はそういうのはあんまり好きじゃないなって」
――このアルバムはやっぱり、“美しい”という表現がぴったりというか。でも、ただキレイというわけじゃなくて、“美しい”が持ってるいろんな要素…その奥にある怖さも含めて鳴らしてるというか。
小林「嬉しいですね。他にも激しい曲とかダークな曲も同時進行で書いてはいたんですけど、問いかけとか贈り物みたいなものを作りたいと思ったとき、それに見合う曲が自然と集まってきたという」
――それこそ曲作りとかリハの段階から結構ワクワクしませんでした?
小林「実際に(外部の人が)入ったときの方がさ」
ケンゴマツモト「そうそう。本物の音になったときの感動はすごかった」
小林「やっぱり生で人が演奏してくれてると、わけが違って」
――本番に向けて音合わせはみっちり出来たんですか?
高松「全員が集まったのは実は1回もなくて。それまでに何回か…何回だっけ?」
吉木「3回かな」
――弦だけ来たりとか?
高松「そうですね」
小林「あとはデータ上のやりとりとか。すごい時間がかかりましたね、やっぱり」
――弦のフレーズとかは普段は書かないパートだと思うんですけど、イメージとして鳴っているものなんですか?
小林「鳴っているものもありつつ、偶然性を肯定したところもあったり。何となくパソコンでフレーズを組んでて、マウスを動かしたときにズレちゃったりとか。その音を流したら“あれ? いいな”って(笑)。じゃあそのフレーズに変えちゃおうとか、そういう“うっかりどうにかしちゃったもの”も、結構残してたりするんですよね」
――当日はやっててグッとくるものはあったんじゃないですか?
高松「ありましたね~やっぱり」
小林「感無量だった、本当に」
高松「既存の曲とかにも入ってもらったんですけど、すごかったですね」
ケンゴマツモト「『Misstopia』(‘10年リリースの同名の2ndアルバム収録)とかをストリングスを入れてやったとき、小林くんの書く楽曲そのものが持っている受け皿がすごく大きいんだなって感じましたね。普通、バンドが作った曲に素直にストリングスとかを当てはめても合わなかったりすると思うんで、それもすごい嬉しかったよね」
小林「その日のライブは二部制で、一部の後半くらいから弦が入って、それが終わったらLOSTAGEの岩城さんが入って、ツインドラムでちょっとゴリゴリのグランジゾーンみたいな時間も作って。そこにまた管楽器とかが入ってきて、全員で『Moire』を演奏して本編が終わって、アンコールでは2曲またやって」
――あと、今作の最後には、その際のライブのMCも入ってて。
小林「本編最後の“ありがとう”っていうね。言ってみればライブレコーディングしたっていうこと=自分たちにとってはお客さんありきの演奏だったんですね。そのドキュメントというか物語の落としどころとして、ちゃんとお客さんの存在を残したかった。今回しかそういうことも出来ないだろうし、やろうと思わないだろうなと思ったので」
――そういう意味では、すごく素直な感謝の意というか。
小林「今回は本当に何のてらいもなく、すごく素直に作りましたね」
――前の2作『To (melt into)』『(Two) into holy』があったから、新作はもっと過激にぶっ飛んだものになるかもしれないとも、ちょっと思ってたんで。
小林「みんな“そっちなんだ!?”みたいな感じで(笑)」
――前回のインタビューでも言ってましたけど、THE NOVEMBERSがいろんな人と関わっていくことに喜びとかやり甲斐を感じ始めているのが興味深いですね。
小林「それを与えられたというよりは、自分たちで“見い出そう”という気持ちになってるのがよかったのかな。自分たちが配慮も何もなくボーっと与えられてばっかりだったら、そうしてくれる人たちがいなくなった瞬間に、1人では何も出来なくなると思うんです。つまらないとか、意味がないと言われているものから、いかに価値とか楽しさを見い出して大事にするのか。音楽以外の日常生活でも常に考えているので、それが作品にすごく出た気がしますね。教わることと学び取ることの違いみたいな」
――小林さんのインタビュー中の言葉とかもそうなんですけど、そういう物事の裏側とまでは言わないですけど、違った観念を目覚めさせてくれる部分がいつもあるなと。
小林「バスガイドさんは右を差しながら“左に見えますのは”って言いますからね(笑)。絶対的な右はないんだぞと」
――そうそう、そういうところ(笑)。善と思えるものがある人にとっては悪だったり…そういう部分があり得る。THE NOVEMBERSの言葉と音楽は、そういうことに気付かせ、考えさせてくれるようなね。
小林「メロディとか音があるから、言葉に情緒が宿りやすいってことですよね、きっと」
暇なのはいいんですけど、退屈なのは本当に嫌なんですよ
――今の時代、『GIFT』っていうのもすごく潔いタイトルな気がします。
小林「僕らの作品の中では、すごく分かりやすいタイトルですね。今までがあまりにも分かりにくかったから(笑)」
――あと、『ウトムヌカラ』(M-4)は、CHARAさんが歌うことを勝手に想定して作ったらしいですね(笑)。
小林「ものすごい一方的に(笑)。CHARAさんは小学生の頃からずっと聴いてて。一回聴かなくなる時期とかって普通あるじゃないですか? 僕そういうのがないんですよね。CHARAと川本真琴とラルクとかDIR EN GREYはずっと聴いてますね」
吉木「ユーミンもね」
小林「高松くんもラルクは一瞬も離れたことないでしょ」
高松「一瞬もない(笑)」
小林「毎回すげぇと思わせてくれるし、ファン心理云々を飛び越えても作品として良い!ってなるからすごい」
――他にもそういうバンドはいるんですか?
ケンゴマツモト「僕はTHEE MICHELLE GUN ELEPHANTとかBLANKEY JET CITYがすごい好きで。この夏、dipのトリビュートライブでチバ(ユウスケ)さんに初めて会って…もう緊張し過ぎてブルブル震えながら話すことを探して、“チバさんモデルのサングラスが売り切れてて買えなかったんです”みたいな話をしたら、“送ってやるよ”って。そしたらその後すぐ、事務所にホントに届いてて。カリスマに社交辞令はないんだって、すごい感動しました。あれは嬉しかったな…」
――カッコよすぎる! それはシビれるな~。
小林「もうヒーローだよね」
――それこそさっきの話じゃないですけど、バンドを続けていればどこかで接点が出来てくる可能性があるという点では、小林さんがリスペクトするdipとの関係もすごく美しい光景だなと。“同じステージに立つなんて!”みたいな。
小林「いや~本当に!」
吉木「そう考えると、僕はバンドを始めてからはLOSTAGEはずっと聴いてますね」
小林「岩城さんがドラムヒーローみたいなもんでしょ」
――そんなに世代が離れてないような感じがするのにね。
吉木「何かLOSTAGEを見てると、バンドやりたくなるんですよね」
小林「あ~そうそうそう!」
吉木「バンドってやっぱカッコイイみたいな。ライブを観るとやっぱりドラムを叩きたくなるし、いい影響を与えてくれるバンドです」
――『GIFT』ってそもそも、そういう刺激とか感動とか出会いとか、音楽が持ってる要素と言えますよね。今回はライブレコーディングの音を活かしつつ、音を抜き差しもしてと、なかなか特殊な作り方だったと思いましたけど、出来上がったときに何か思いました?
高松「印象的な歌詞とかフレーズのリフレインが多いなって。それがすごく頭に残って、覚えやすいわけじゃないんですけど、なんかいいなって」
吉木「あと、今作はライブ録音とスタジオ録音を重ね合わせたものなので、今までの作品とは空気感が全然違って、そこにまず感動しましたね。それにホーンとか、トランペット、バイオリンとかも入ってるし、ライブでやって、改めてスタジオで聴いてまた感動して」
――自分たちが生み出している音にちゃんと感動していけてるのはいいでですよね。
小林「そうそう。楽しさとか感動がないと、束の間は活動出来るけど続かなくなっちゃう」
吉木「今回はライブ中でも鳥肌の立つ瞬間がやっぱりあったので」
ケンゴマツモト「あったね」
吉木「良くなる確信はあったんですけど、それを遥かに飛び越える瞬間がすごいあって。やってて本当に楽しくて、自然と笑顔になっちゃうというか」
――いいですね。だってみんなそんなに笑顔にならなさそうなバンドなのに(笑)。
一同「ハハハハハ!(笑)」
小林「面白いこととか楽しいことに対して渇望してるところがあるというか、普通に喋ってても、何がしか面白くしようみたいな。だからつまらない話になってくると、本当に不機嫌になり始める(笑)。普通に会話してるだけなのに“え、それのどこが面白いの?”みたいな」
吉木「“お前着地点見えて話してんだろうな?”みたいな(笑)」
ケンゴマツモト「別に面白いことを言うのがコンセプトじゃないのに(笑)」
――(笑)。楽しいことに対しての欲求が強いっていう。
小林「楽しいこととかキレイなこととかワクワクすることを探すのに、割と脅迫的に必死なところがあって。僕、暇なのはいいんですけど、退屈なのは本当に嫌なんですよ。退屈への嫌悪じゃないですけど、いい方にいい方に楽しもうとするハングリー精神というか。退屈に慣れちゃったら、多分何も作らなくなっちゃう気がする」
――だから自分に刺激を与え続けられる作品を、いかに作り続けられるかみたいな。
小林「今回はすごく長く感じましたけどね。ライブまでにまず1つの締切があって、そこからレコーディング終わりまでがもう1つの締切というか。その都度実験を繰り返してたのもあるし、考える時間が本当に長かったから、『GIFT』はかわいくてしょうがないんですよね」
――他にも新しい要素はありました?
小林「音源以外のところで言うと、ジャケットに初めて色が入ったりもあるんですけど、例えばシャウトしている曲とか激しい曲を入れないとか、アンサンブルの実験も本当に多いんですよね」
ケンゴマツモト「ギターが歪んでる曲が少ないとか」
――これらの曲がライブのセットにどう入ってくるのかも楽しみですね。
吉木「それがですね、今結構ね」
小林「さんざん好き勝手にやった結果、4人じゃ無理だって(笑)」
――ハハハハハ!’(笑)
ケンゴマツモト「本当にそうなんです(笑)」
小林「『Moire』『ウトムヌカラ』『GIFT』(M-6)とかは他の楽器ありきの風景ではあるので、それがないならないなりに楽しもうと思ってるんですけど、それって=ライブでは聴けないから、作品の価値が上がることだとも思うんですけどね。『Moire』に関しては1曲目だし、みんな楽しみに来るだろうけど」
吉木「これは無理ですね(笑)」
小林「僕たち自身もどういう風にしていいか分かんないから、今は置いといている(笑)。手間がかかるし、特別なときに出てくる赤飯みたいな感じです(笑)」
――ハハハ! ライブでは当面やらないんですか?
一同「やらないです(笑)」
小林「やれる人は“やらない”って言えるけど、俺らは“出来ない”だから(笑)。出来ないからやらないっていう(笑)」
――まずこれは音源として楽しんで欲しいっていうのと、スペシャルなライブのときにまたやれたら、ですね。あと、ブログを見たら次のRECの話も出てましたが、『GIFT』を経てTHE NOVEMBERSがどう進んでいくのかが、また分かんなくなりましたね。
小林「現時点の素直な気持ちで言うと、『GIFT』への反動がまんま出てる。例えば『GIFT』が語りかけるような口調とか表情だったとしたら、次はすごくエッジィなものというか、突き付けるものを作りたいという感じですね」
――なかなか毎回いい意味で“なんじゃこりゃ”っていう作品を出してくれるバンドも少ないと思うんで(笑)。
小林「言ってみれば、毎回賛否両論の嵐ですからね。でも、それが楽しいんですよね。『GIFT』って、ドイツ語だと“憎悪”とか“毒”っていう意味があるらしいんですね。そういう風にいろんな捉え方をされたいし、出しゃばっていきたい気持ちはあるんですよね」
――次の作品がすごく楽しみになる作品でしたよ。
ケンゴマツモト「ありがとうございます」
小林「頑張ります(笑)」
――本日はありがとうございました!
Text by 奥“ボウイ”昌史
(2012年11月28日更新)