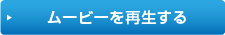ガーリーロックのニューフェイス bómi が
メジャー1stミニアルバム『キーゼルバッファ』を携え
8/10(金)OSAKA MUSEで自主企画ライブ!
新世代のポップアイコンの素顔に迫るインタビュー&動画コメント
とにかくクリエイティブ、そしてアイディアマン。インタビューを通じて感じた彼女の第一印象はそれ。韓国人の両親の元ニューヨークで生まれ、幼くして実の親元を離れ、大阪で育ったボーダレスでキュートなロックガール、bómi。大学進学と共に上京、森山直太朗との楽曲制作でも知られる御徒町凧と出会い、“宝美”としてアーティスト活動をしていた彼女に転機が訪れたのは’11年。現在のサウンドプロデューサーwtf(ダブリューティーエフ)と出会い、所在なき心情を吐露した儚い世界観は、その景色を劇的に変える。タワーレコード限定で先行リリースされた2作のミニアルバム『Gyao!Gyappy!!Gyapping!!!』『OH MY POOKY!!!』で聴かせた、クールでスタイリッシュなトラックに仕掛けられたひと筋縄ではいかないポップでエレクトロなサウンド、クセになる独特の語感と言葉のチョイスが降り注ぐリリック、そしてそのしなやかな歌声が縦横無尽に化学反応を巻き起こす楽曲にリスナーの期待感もグッと高まる中、bómiがミニアルバム『キーゼルバッファ』で遂にメジャーデビューを果たした。但し、そこで鳴らされているのはただの最先端の音楽ではなく、彼女が歩んできた音楽家としての、人としての、揺れ動く曖昧な感情が滲み出た愛すべきハイブリッドなポップミュージック。そこで、同作に伴う自主企画ライブ大阪編を前に、彼女が今の率直な想いを語ったインタビューをお届け。インタビュー当日も、直前まで自らイベント出演者のブッキングに奔走していた彼女。キュートなだけじゃない。人肌の音楽を生み出すシンガーの横顔が、少しでも垣間見れたなら嬉しい。
bómiがいろいろ語ります! キュートな動画コメント
――自主企画のメンツも、実際に自分で電話かけて直で誘ってるんやね。
「そう。大人に誘って貰うよりかは…逆に自分が誘われてもホントに思ってんのかなぁ?ってなるじゃないですか。何か僭越な感じがしちゃうっていうか」
――アーティスト同士が繋がってたら話が早いというか、実現はしやすいよね、やっぱり。
――でもホンマ、内容的にはインタビューの最後に聞くような話やったけど(笑)。
「あー!!(笑) 今ホントに電話してたからそうなっちゃいました(笑)」
――ちゃんと自分で声かけて、目の前でスケジュールを聞いてるのが…。
「今かなりリアルでしたよね(笑)」
――メジャー1stアルバム『キーゼルバッファ』が6月に出たところですけど、今の率直な気持ちとかってあります?
「これを作ったときに、結構自分の根に近い部分をゴロッと出しちゃった曲が多かったので、自分の中でいいとか悪いとかの判断があんまりつかなくて、“大丈夫かな?”みたいなニュアンスがすごくあったんですけど、今までの中で一番好きって言ってくれる人も多くて、ちょっとホッとした部分もありますね。まぁでも今の心境って言われたら正直、どれくらいCD売れるかな?みたいなところなんですけど(笑)。だからちょっとCD屋さん覗きに行ったり(笑)」
――展開されてるなぁ~とか。
「あ、外国の人が視聴してるとか(笑)。この間ホントにあったんですよ、渋谷で」
――ちょっとソワソワする感じ。
「リリース前日と当日、友達にソワソワしてるって言われましたね~。“どんだけ浮き足立ってんだよ!!”って(笑)」
――今回がメジャーデビューというのもあってさかのぼって聞きたいんやけど、以前“宝美”名義で活動していたときに、ライブ中にふと“今ままでやってきたような音楽性はもういいかな”と思ったというエピソードが資料にあって。それって突然思ったの?
「うん。何か歌ってるときに、すごく解離してたの。“自分”と“歌ってる自分”が。ガーって歌ってるのにすごく冷めた感覚になった瞬間があって、そのときに“あ、もうこのスタイルは違うかも”って思った。無理しちゃってるというか、“全世界の悲しみを私がしょっちゃった感”は、もうないなって気付いちゃったの」
――沸々とそんな予感があったのではなく、いきなりハッと気付いた?
「沸々とはありましたね。陰と陽があったら陽に向かい始めてはいたから。一番最初はそれこそMCも全くしないくらいで、曲名言って歌って帰る。それがライブの正しいスタイルだと思ってたんで。黒いワンピース着て、青いアイシャドウとかガーっと入れて、もう『ブラック・スワン』みたいな感じで歌ってて(笑)。でも、ある意味それは分かりやすいアウトプットであり。最初は余裕のない切迫感みたいなものがあっても、続けてるとどうしても余裕が出てきちゃうじゃないですか。多分そこにちょっと嘘が生じちゃうというか。だから常に、表現のアウトプット、今の自分を疑うというか。ちょっと前までの自分をつい音楽にしがちなんですけど、今自分が何に興味があるのか、今自分は何がしたいのかをいつも忘れないようにしていたいのはあるんですよね」
――例えばバンドだと、解散してまた次のバンドを組むみたいなところやけど、ソロアーティストで名前を変えたり、音楽性をガラッと変えることに対する怖さとかはなかった?
「特になかったですね。ライブを重ねていたのはあったけど、サウンド面で何かを確立したわけではなかったので。だから、新しい方向性のサウンドを提案されたときも、まぁやってみようじゃないかって。名前は別に変えるつもりはなかったんですけど、漢字の“宝美”だと、ロゴを作ったときに中華飯店みたいな…(笑)」
――アハハハハ!(笑) 確かに。
「何かお箸の袋に印刷されてそうな印鑑みたいなロゴが幾つか上がってきて(笑)、これはちょっと違うかもって。そしたら周りのスタッフに、“じゃあボーちゃん、ちょっと名前変えてみない? 例えばLittle Soulとか”って言われて、“いやぁ~Little Soulはちょっと大丈夫ですぅ~!! 英語表記に変えるだけにしましょう!”って(笑)。そしたらかわいいロゴも上がって、音楽性にも合ってて。ただ私の中では、姿勢の部分で変化したことは何もないし、逆に言うと宝美時代のことを別に資料に書かなくてもいいのに書いてるわけじゃないですか。それは隠すことじゃないし、自分の中で何も変わってないから。だから、改名って言われるとちょっと恥ずかしいというか」
――そんなにたいそうな感じじゃ…。
「ないんですよね。そうそう」
――むしろデザイン的な問題(笑)。
「ホント。漢字がムカデっぽかったから(笑)」
――宝美からbómiへと音楽の形態が変わっていく中で、さっき言ったその変わらない部分っていったい?
「そのときの自分に嘘をつかないことかな。昔はね、それがもうちょっと尖った感じだったけど、根っこの部分は変わってなくて。この人の曲を聴いたら悲しいけど救われるとか、楽しいとか、もちろんそういう両極の方が分かりやすいけど、そうじゃない部分で構成されているのが人間のグチャッとしたところだと思うし、それがデフォルメ=誇張された陰とか、全くの陽である必要がないと思うのが今かな。どっちもあるというか。それが自分にとって一番リアルなのかなって」
――やっぱり割り切れない曖昧な感情は絶対にあるもんね。自分の中にも世間にも。ない混ぜの感情が人にはある。
「例えば、高校生の頃とかって、将来に対して夢を抱いたり、“私はこんなところに留まる人じゃない!”とか(笑)自己顕示欲が強くて、“頑張れ!”って言われたら“頑張るぞ!”って素直になれた。でも、ちょっとずつ歳を重ねて、頑張ってうまくいくんだったら、もう今頃スゴイことなってたよ…みたいな。でも、ちょっと心が弱くなってしまうと買ってしまう“大丈夫、君は頑張らなくていい”みたいな類の本も(笑)、何かちょっと違うんだよなって。頑張りたくないかと言うと、そんなことはなくて。そのどっちでもない、でもこれってどこに落としどころがあるんだろう?っていう感情。頑張ったっていいことばっかじゃないって分かってるけど、それでもやっぱり明日は信じたいし、いいことあるって思いたい。それが私の今の率直な気持ちというか。もしかしたらそこに共感してくれる人ってたくさんいるんじゃないかなって思ったの。とりあえず今日、まぁ明日は頑張ってみようとか、日々をつないでいくくらいのことかも知れないけど、そこに対して背中をちょっと押すぐらいのことは出来るんじゃないかって。今に救いはなくても、共感って救いだから」
――どこかで“頑張ろう”派と“頑張らなくてもいい”派を選ばなきゃいけない風潮があって、どっちにもハマらない自分にモヤモヤするかも知れないけど、でも実はそんな風に思ってる人はいっぱいいるんだって、音楽で伝えてあげられる人はもしかしたらそんなにいなかったのかも。
「しかもそれが、人間が人間たる人間らしさだと思うんですよね」
――みんながみんな、“俺はこうなんです! この道で生きていくんだ!”っていう強烈な意思を持ってるかと言ったら、そうでもないというか。俺もこの仕事を続けてるけど、“これが天職や! このために生まれてきたんだ!”って心底思えてるかと言えば、そうとは言い切れないもん。
「そうなんですよ。一言で割り切れることばっかじゃない。もっと単純なんだけど複雑だと思うんですよね」
――そういう曖昧な感情も含めて、今回の『キーゼルバッファ』には込められている感じがしますね。
「逆に言うとそこが今の自分の表現したいことだったりするから。素の自分の考えてることに近い。どこにいても違和感を感じる私って、どこに落としどころがあるんだろう?みたいな(笑)。その先の光は見付けられてないんだけど、それを見付けられたらすごい革命なんじゃないかって個人的には思ってるんだけど。とにかく泣けるんだよとか、とにかく笑えるとか盛り上がれるとか、もちろんそれも素敵だけど、何かウマく説明出来ないけどスゴい! とりあえず一緒にライブに行こうよ!っていう空間が作れたら、一番オモシロいんじゃないかなぁ。それって得てしてアングラの方向だったりするんですけどね(笑)」
――その場所に連れて行くのがめっちゃ難しいもんね。
「難しい! でもそれが確立したら、それをしかもメジャーのフィールドで確立出来たら、相当オモシロいと思うんですけどね。ただ、分かりにくいっていうのはありますけど(笑)」
その人から本当に滲み出す言葉だったら、どんな言葉でも説得力を持つ
――昨夏からタワレコ限定でミニアルバム『Gyao!Gyappy!!Gyapping!!!』『OH MY POOKY!!!』と2作出してきたけど、『キーゼルバッファ』はそこからもすでに変化していってますね。
「毎回ストックを出し切っちゃう感じだから、次がどうなるかがホントにいつも分かんなくて、そのときのモードがすごく出る。いい曲だったら取っておいていいタイミングで出したいっていうのももちろん分かるけど、生まれた曲の旬や新鮮さを考えると、そのときに出してあげるのが曲にとって一番いいことなんですよね。そういう意味で言うといいペースというか、もうそろそろ打ち止めが来そうですけど(笑)。取りあえずやってみようぜ!っていう1枚目の『Gyao!Gyappy!!Gyapping!!!』から、最初から最後まで統一感のあるキラキラ・エレクトロポップを作りたいっていう2枚目の『OH MY POOKY!!!』があって。歌モノじゃなく遊んだ曲も多かったけど、やっぱりbómiの売りは声で、今までのサウンド+その良さを引き出そうよっていうのが今回だったので」
――『Someday』(M-5)なんかはすごく素直というか、今のbómiにとって鍵になる曲のような気がします。
「そうですね。例えば、“傷付くことを恐れないで”なんてフレーズは世の中に溢れてるけど、じゃあ何でそれがリアリティを持つかと言ったら、本当にそう思ってるから。その人から本当に滲み出す言葉だったら、どんな言葉でも説得力を持つ。そういう意味で今にピッタリな曲なのかなって」
――今までだったら、J-POPの常套句みたいなものを歌詞に使うのに拒否感があったけど、そう思ってるのにわざと外すのも、それもまた違う。やっぱり自分が本当に思ってることが=リアルなんじゃないかと。
「うん。その中でもラインは探ってますけどね。やっぱりどこかストレンジでいたい気持ちはあって。小~中学校の頃からその感覚はあって、でもアウトプットがうまくいかなくて浮いちゃったり、何かよく分かんない色のカバンを持って行ってみたり(笑)。それこそ今は別に意図はないんですけど、昔から前髪がすごく短いっていうのがアピールだったり(笑)、五本指ソックス流行らせようとしてみたり。何もかも全く流行らなかったんだけど(笑)。いろいろやってみたもののイマイチしっくり来なかったんだけど、音楽だと素直みんなに認められた感覚があって、すごく嬉しかったのは覚えてますね。“あ、私ここだったんだ!”って。ただ、元からある形に沿わせていく方が聴く人にも認識されやすいけど、そこからは外れたいというか。だから意地でも王道のちょっと脇を走って…そこでうまく道を作れたらオモシロいんじゃないかなって。そこに私は可能性を感じてるんで」
――謎のプロデューサーwtf氏とは、そもそもどういうきっかけで出会ったんですか?
「私が漢字表記で坊主頭だった宝美の頃に(笑)、サウンドプロデューサーを探してて、人に紹介されて会ったんです。そしたらアレンジが全然上がって来なくて“何だよヤル気あるのかよ”って思ってたら、“ゴメン。アレンジは出来なかったんだけど新曲3曲作って来たから”って」
――アハハハハ(笑)。
「もう確信犯じゃん!って感じだけど、聴いてみたらすごく世界感のあるサウンドだったの。私じゃ絶対作らない曲だなって。それが1年半前くらいかな? 普通に生きてたら全く出会わないタイプの人ですよ。もうミュージシャンの中のミュージシャンみたいな人だから。話がすっごい合うかと言うと違うわけ。私はどっちかって言うともっと文科系な、いわゆるちょっと頭の切れる人だったり何かヘンな人が好きなんで(笑)。(wtfは)もう単純にホントにオトコ前な“ミュージシャン”な感じで、価値観が全然合わないぐらい逆の人なんだけど(笑)、音楽の部分ではすごく相性がいいんですよね。それはもう自分ではちょっと測れないというか、ホントに科学反応的な感じなのかなぁ」
――そんな人がbómiをちゃんと遊ばせてくれるというか、サウンド的なオモシロさを引き出してくれるんやもんね。引き合わせてくれた人の嗅覚もスゴいね。今回の制作の中での発見というか、改めて感じることはありました?
「何だろう。改めてその…私ってダサイなぁみたいな(笑)。私生活から超カッコいい、クールで変わってる自分でいたいし憧れがあるんだけれど、『天使にラブソングを2』みたいに熱く歌い出しちゃう様に単純に泣いちゃったりする。そういう自分をあんまりカッコいいとは思わないし、出来れば隠していたいところがあったんだけど、もうそろそろ認めてやんなきゃいけないなぁと(苦笑)。それも含めて自分なんだって。何かそれをすごく思った。『Someday』みたいな自分の中での直球ド真ん中みたいな曲を書いたのもあるし、やっぱこれが私だなぁみたいな。すごくリアリティがあるから」
――リアリティが1つの軸?
「ひと言で言うと“等身大”みたいなことになっちゃうけど、そうなると何かまたよくある感じでちょっと違うんですけどね~」
――“等身大”ってすごくキャッチーな言葉やけど、それもホントはもっと曖昧やろうね。その感覚に関して見付けられてる言葉、真っ先に浮かぶ言葉が“等身大”なだけで。
「そう。等身大にも種類があって、“私にもっと愛の言葉を”とか、“会いたくて会えなくてでも会いたくて”とかは、成長がない等身大なのかも知れない。何かすごく悪いこと言っちゃった? 大丈夫?(笑)」
――(笑)。
「私が思うのは人が何かを続けていく限り、葛藤しながらでも成長したいと思うわけで。そこから言うとちょっと稚拙というか…難しい、言葉にするのが」
――そうやね。等身大以外の言葉を発明せなあかんね(笑)。今回のアルバムが出来上がったとき、何か思いました?
「うんとね…何かすごい私なんだけどどうしようっていう戸惑いがあった。さっきの“認めた”っていうのはそこからなんですけど。熱い=カッコ悪いみたいに思っちゃうところがあるんだけど、その熱さは私の中にずっとあるし、そこを含めて私らしさなんだなぁって。例えばちょっと昔は、
相対性理論がすごい好きで、あの一行の共感性というか、言葉にあんまり意味を求めない感じがすごくいいなって。最近で言うと
宇宙人とかもそうですけど、ああいうのが結構好きなんですよ。だけど、自分はそうはなり切れない、もうちょっと熱い部分、主張したい自分がいるってことをそろそろ認めないとって。それが私らしさなんだぞということを思ったかなぁ今回」
――bómiを見てるbómiが、いつもいるね。
「うん。いる。いつも考えてる。主体と客観じゃないけど、うん…いる(笑)」
いつも探してる。カッコよくて、新しいモノ。
――今作のタイトルは『キーゼルバッファ』で、生まれて初めて聞いた言葉です。鼻の中の毛細血管が集まってる場所の名称らしいけど、それをアルバムのタイトルにしたアーティストは前代未聞では?(笑) 鼻のそんな部分にこんないい感じの名前が付いてるんやね(笑)。
「ドイツ語で…確か博士の名前だったかな? 響きがよかったから、いつか使いたいなぁと思ってて」
――この言葉はどこで見つけたの? そもそもよく鼻血が出るのが発端らしいけど(笑)。
「ホントに鼻血がよく出るから、ちょっと私病気かもしれないって(笑)病院に行ったの。そしたら、キーゼルバッファ帯っていう場所がちょっと弱ってて。その“キーゼルバッファ”っていう言葉がすごく頭に残ってて、意味は後付けですね。“鼻血が出る程”っていうことにしようかなって(笑)。こないだ取材中にも1回出たんですけどね(笑)。感情的になったときとか、チョコを食べたときにもなるんです。泣きそうになったときとかに、タラーッて」
――アハハハハ! 紛らわしいわ!(笑)
「最近ディレクターに、“大陸の人だからねぇ~血の気多いよね~”みたいにすごく言われるの。怒ったり笑ったり泣いたり、喜怒哀楽が激しいというのはあるけど。まぁ女性的っていうことで(笑)」
――そして、『キーゼルバッファ』のリリースに伴ってライブもあって。それこそ一番最初に話したけど(笑)。
「で、来場者全員にオリジナルテッシュをプレゼント!(笑)」
――それライブ中にみんなが使ってたらすごい絵面やね(笑)。ステージから見て全員…。
「血まみれ(笑)。ちょっと心配になる」
――多分それを見たらbómiも確実に鼻血出るやろうなぁ(笑)。自分の企画ライブは今までもやってたの?
「東京では結構やってるんです。“bómiはこのタイプ”ってあんまり種別出来ないから、イベントに出てもよく分かんない感じでまとめられることが多くて(笑)。だったらもう自主企画でこのアーティストとbómiが組んだらオモシロいってアピールしていくしかないなって。まず最初にやったのが、
(小南)泰葉とのツーマンライブ『結婚式の御案内 ~小南家 bómi家 お披露目パーティー ~』('11年11月)で。『OH MY POOKY!!!』はダンスミュージック寄りというかエレクトロポップだったから、
The Flickersとか
QUATTROをリリースパーティーに呼んだら結構アツいんじゃないかって、自分でライブを観に行って、CD渡して“やりたいんですけど”って」
――おぉ! すごい行動的。
「1回会うと何かみんな心をパッと開いてくれるというか。4月に『Zipper』の読者モデルの青柳文子ちゃんと一緒に『zipnight』っていうイベントもやったんですけど、そこには
Czecho No Republicは相当アツいしこれからキそうだぞって誘って。あとは『Zipper』のモデルをしながら歌を歌ってる
タカハシマイちゃんに、
撃鉄を組み合わせたらオモシロいかなぁって。それは出てくれた人からもお客さんからも評判で、私ってブッキング能力ある!?みたいな気持ちになってきてるんだけど(笑)。8月10日(金)のOSAKA MUSEに出てもらう
キドリキドリは、音源がすごくカッコよくて私の音楽性に合いそうだなと思ってたら、向こうから“bómiと対バンしたい”ってTwitterでつぶやいてくれてたみたいで、それがリツイートで回り回ってやり取りが始まって。トイトイ(=
Sentimental Toy Palette)は昔から知ってて、歌モノだけど世界観があってすごく好きな人たち。あとは
ゆれるとかもカッコいいんじゃないかな~」
――すごいね。よくチェックしてる。
「うん(笑)。いつも探してる。カッコよくて、新しいモノ。で、何かちょっとストレンジなことをしようとしてる人を。あとさっき言った『zipnight』のvol.2をまた夏にやるんですけど、それはまず決まったのが
パスピエ」
――押さえてるね~(笑)。
「ちょっと尖ってる人をウマく集めて、普通じゃないことをやりたいなぁって。例えばバンドじゃなくて、
でんぱ組.incが入ったらすごいオモシロいんじゃないかとか。どう崩して、カオスだけどオモシロいものを提案出来るか。イベントにしても、ちょっと真ん中からズラす。常にそう来たかー!みたいな風にはしたいなぁとは思ってます」
――歌であれ音であれ、自分のイベントでもそう。すごく一貫してるね。
「そういう存在で居たいんですよ。ド真ん中王道よりちょっと脇を行くというか。例えばマドンナじゃなくて、スザンヌ・ヴェガ。キャロル・キングじゃなくてジャニス・イアンみたいな。ちょっと脇なんだけどカッコいい、キレたことやってるというか、キッチュな感じ。そういう人たちに対する憧れというか…もちろんマドンナになれたらいいけど、私は独自の道を築く。例えばリッキー・リー・ジョーンズとかもそんな感じがするんで好きなんですよね。でも、それがサブカルチャーって言われるとまた違うんですけどね。サブカルって言葉自体が今はもうちょっと何!?っていう感じではあるんで。いつもどこかストレンジな部分を手放さないようにしようと思ってる。逆にこだわってるところはそこしかない」
――今までの一連の話を聞いてたら、まさにそこやね。
「このジャケにしてもそうです。ん?っていうニ度見感(笑)。顔のサイズがおかしいぞっていう」
――まずは関西では8月10日(金)OSAKA MUSEですな。それでは改めてライブでお会いしましょう!
「ハイ! ぜひ遊びに来てください。ありがとうございました!」
Text by 奥“ボウイ”昌史
(2012年8月 9日更新)