
ホーム > インタビュー&レポート > 2月にザ・フェニックスホールで 演奏生活60周年を記念するリサイタルを行う 左手のピアニスト、舘野泉インタビュー

2月にザ・フェニックスホールで
演奏生活60周年を記念するリサイタルを行う
左手のピアニスト、舘野泉インタビュー
(3/3)
■舘野さんはずいぶん若いうちにフィンランドへ向かわれましたね。何か思うところがあったんですか?

■インタビュー:2021年1月12日 キョードー大阪にて。
(2021年1月22日更新)
Tweet Check
演奏生活60周年
舘野泉 ピアノ・リサイタル
2月23日(火・祝)14:00開演
あいおいニッセイ同和損保
ザ・フェニックスホール
全席指定:5,000円 Pコード 189-152
【プログラム】
J.S.バッハ(ブラームス編曲)
:シャコンヌ ニ短調 BWV1004より
A.スクリャービン
:「左手のための2つの小品」
Op.9より “前奏曲” “夜想曲”
光永浩一郎
:左手ピアノ独奏のためのソナタ
“苦海浄土によせる”
第1楽章.海の嘆き
第2楽章.フーガ
第3楽章.海と沈黙
新実徳英:《夢の王国》
左手ピアノのための4つのプレリュード
Ⅰ.夢の砂丘
Ⅱ.夢のうた
Ⅲ.夢会談
Ⅳ.夢は夢見る
パブロ・エスカンデ:『悦楽の園』
ヒエロニムス・ボスのトリプティック
(三連祭壇画)による自由な幻想曲
導入部:天地創造の第三日目
(閉じられたトリプティック)
パネル1:楽園でのアダムとイヴ
パネル2:悦楽の園
パネル3:地獄
舘野泉オフィシャルサイト
:https://izumi-tateno.com/
【問い合わせ】
リバティ・コンサーツ:06-7732-8771
舘野泉 最新CD(発売中)
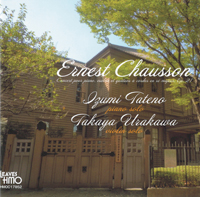
エルネスト・ショーソン/
舘野泉×浦川宣也
ヴァイオリン、ピアノと弦楽四重奏のための協奏曲 ニ長調 作品21
■独奏
ピアノ:舘野泉
ヴァイオリン:浦川宣也
■弦楽四重奏
第1ヴァイオリン:舘野晶子
第2ヴァイオリン:林瑤子
ヴィオラ:白神定典
チェロ:舘野英司
録音:1959年春、旧東京音楽学校奏楽堂。
※演奏家名は当時のもの。
発売元:ヒビキミュージック 2,000円+税

























