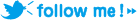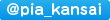ホーム > インタビュー&レポート > 女方舞踊の大曲『京鹿子娘道成寺』 情感あふれる名作『沼津』 様式美に富んだ『吉例寿曽我』を上演!
女方舞踊の大曲『京鹿子娘道成寺』
情感あふれる名作『沼津』
様式美に富んだ『吉例寿曽我』を上演!
「大阪松竹座開場100周年記念 七月大歌舞伎 関西・歌舞伎を愛する会 第三十一回」昼の部は、『吉例寿曽我』『京鹿子娘道成寺』『沼津』の三作を上演している。
女方舞踊の大曲 尾上菊之助が大阪で初上演
中でも華やかなのは『京鹿子娘道成寺』。花道から振袖にひらり帽子(江戸時代の女性用かぶり物のひとつ)姿の白拍子花子にふんした尾上菊之助が登場するや美しさに息を呑む。
再興した撞鐘の鐘供養が行われる紀州の道成寺に鐘を拝ませてほしいと訪れた白拍子花子。女人禁制だが、美しい花子に惹かれた僧に舞を舞うことを条件に入山を許される。
金色の烏帽子を被り舞う鐘づくしの舞は厳かで格調高く、烏帽子を脱いでからの娘の恋心をテーマにした踊りが楽しい。幼気な少女が手鞠をつくさまや花笠踊り、胸につけた鞨鼓(かっこ)を打ちながらの踊り、衣裳の引き抜きなど歌舞伎らしい演出で華やかに展開し、鐘に近づいていく。 恋しい修行僧の安珍に裏切られた清姫が鐘に隠れた安珍もろとも焼き尽くした安珍清姫の伝説をもとにした道成寺伝説の後日譚。鐘供養の噂を聞いてやってきたのは、清姫の亡霊に取り憑かれた花子だった。
恋しい修行僧の安珍に裏切られた清姫が鐘に隠れた安珍もろとも焼き尽くした安珍清姫の伝説をもとにした道成寺伝説の後日譚。鐘供養の噂を聞いてやってきたのは、清姫の亡霊に取り憑かれた花子だった。
曽祖父の六世尾上菊五郎が確立した音羽屋型を継承する菊之助の『京鹿子娘道成寺』は大阪で初めて、待望の上演となった。花子がどのタイミングで鐘への執着を見せるかが見どころでもある。執心に固執しないで品よく可愛く、僧と問答する花子も色っぽい。
のどかさと悲しみが入り混じる情感あふれる名作
中村扇雀 祖父、父が磨いた十兵衛に初役で挑む
『沼津』は、中村鴈治郎と中村扇雀兄弟が生き別れになっていた親子の再会と別れを演じる。
第一場「沼津棒鼻の場」は、東海道の宿場町沼津の里近くの茶店で一休みしていた呉服屋十兵衛(扇雀)と、宿場や街道で荷物運びをする雲助の平作(鴈治郎)のほのぼのとした出会いを描く。途中で出会った平作の娘お米(片岡孝太郎)に一目惚れした十兵衛は、勧められるままに平作の家で一泊することになる第二場「平作住居の場」で、平作と十兵衛、お米、それぞれが抱える事情が明らかになる。そして第三場「千本松原の場」で、武家の仇討ちに巻き込まれた庶民の悲哀が描かれる。

年老いた平作が無理を言い、荷を担がせてもらったものの危なっかしい様子や十兵衛と共に舞台から降りて劇場内を歩くくだりは愛嬌たっぷりで、ふたりのやりとりが微笑ましい。父の故・坂田藤十郎が得意とした男気のある十兵衛を初役で演じる扇雀、父の十兵衛とも共演した鴈治郎の平作。片岡孝太郎の情の深いお米。三者三様の心の機微が細やかに演じられている。父の仇を探すお米の夫の家臣・池添孫八を松本幸四郎が演じている。
様式美に富んだ華やかなひと幕
市川染五郎が大阪松竹座初お目見え!
『吉例寿曽我』は、歌舞伎の様式美がふんだんに盛り込まれている。第一場「鶴ヶ岡石段の場」の近江小藤太成家(中村隼人)と八幡三郎行氏(中村虎之介)の美しい型の立ち回り。さらに両人が石段に立ったままの大道具を裏返しにする「がんどう返し」は迫力満点。

続く第二場「大磯曲輪外の場」は、父の仇の工藤左衛門祐経に対面する曽我十郎祐成と曽我五郎時致兄弟の演技が上方の和事と江戸の荒事で演じられる。今回は若手ふたり、片岡千之助が十郎、市川染五郎が五郎を初役で演じる。それぞれ家の芸を継承していくふたりの挑戦が初々しい。ベテランの坂東彌十郎が工藤役で芝居を引き締めている。
取材・文/前田みつ恵
(2023年7月13日更新)
Tweet Check
大阪松竹座開場100周年記念 七月大歌舞伎
〈関西・歌舞伎を愛する会 第三十一回〉
チケット発売中 Pコード:519-533
▼7月25日(火)まで上演中
〈11:00〉『吉例寿曽我』『京鹿子娘道成寺』『沼津』
〈16:00〉『俊寛』『吉原狐』
大阪松竹座
1等席-18000円 2等席-9000円 3等席-5000円
[出演]片岡仁左衛門/中村鴈治郎/中村扇雀/坂東彌十郎/片岡孝太郎/松本幸四郎/尾上菊之助/中村亀鶴/大谷廣太郎/中村米吉/中村隼人/中村虎之介/片岡千之助/市川染五郎
※日時・席種により取り扱いのない場合あり。4歳以上は有料。
※7/10(月)・18日(火)は休演。
[問]大阪松竹座■06-6214-2211