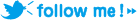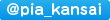ホーム > インタビュー&レポート > ミュージカルの指揮者、塩田明弘が 作曲家フランク・ワイルドホーンの魅力を語る 「珠玉の曲を次々と生み出す感性の人」
ミュージカルの指揮者、塩田明弘が
作曲家フランク・ワイルドホーンの魅力を語る
「珠玉の曲を次々と生み出す感性の人」
ミュージカル指揮者のパイオニアとして、演劇界を牽引する塩田明弘。レパートリーは40作品を超えるという彼のエネルギッシュな指揮と、人懐っこい笑顔をオーケストラピットで目撃したことがある観客も多いはず。『ジキル&ハイド』『アリス・イン・ワンダーランド』『デスノート』『ルドルフ』などで知られる作曲家、フランク・ワイルドホーン(以下フランク)が、ブロードウェイやヨーロッパで活躍するミュージカルスターと共演するコンサート「フランク・ワイルドホーン&フレンズ ジャパンツアー」が12月に開催されるにあたり、フランク作品の音楽監督や指揮を務め、親しい友人でもある塩田に、彼の魅力を聞いた。
――まず初めに、フランクさんとの出会いを聞かせて下さい。
1997年にアメリカのブロードウェイで、フランクの代表作であるミュージカル『ジキル&ハイド』が開幕したときにリハーサルを見学する機会があって、そこで彼と出会いました。もう18年来の付き合いですね。その後、2001年日生劇場で『ジキル&ハイド』を上演したときに、フランクが初来日して。フランクに会えたことが起点にもなり、その後、文化庁の在外研修員としてブロードウェイに留学したんです。フリーパスで舞台を見たり、ピットの中や照明ブースに入ったり、色んな場所で学ぶことができました。稽古場でも指揮させていただきました。自慢していい?(笑)、文化庁からミュージカルの指揮者として行かせてもらったのは、僕が初めてなんですよ。
――素晴らしい経験ですよね。フランクさんの音楽の魅力は、塩田さんから見て何でしょうか。
音楽というのは、「音を楽しむ」と書きますよね、フランクの音楽はまさにそのまま。どうしても音楽は「音を学ぶ」という感覚が日本にはまだあって、勉強することだと思いがちなんです。皆、楽しんでいないときもある。でも、フランクの曲は、劇場を出た後に口ずさめるものが多い。優美で甘美でドラマティックでもあるけれど、一番の核は楽しくてキャッチー。彼はもともとポップス系のピアニストだったので、キャッチーな曲が多いんです。キャップを被ってTシャツを着た普通のおじさんなので、一見、作曲家には見えないけれど、一旦、ピアノの前に座ったら、珠玉の曲が数々生まれて来る。『デスノート』や『シラノ』で、彼の作品に携わらせてもらったときに、「譜面がないけどどこにあるの?」と聞いたら、「ははは! 俺の頭の中だ」と言うんですよ。彼がいろいろ曲を弾き、僕も一緒にピアノを弾きながら譜面を書きました。

――いつもそのスタイルなのでしょうか。
ヨーロッパではヨーロッパの、ニューヨークではニューヨークの音楽監督がいて、日本では僕。その時々ですが、僕の時はそうでした。白羽の矢が立って音楽監督をさせてもらえるのは嬉しいですね。彼がピアノを弾いているのを見ると、鍵盤がキラキラと光ってみえるくらい。彼の頭の中は宝石箱です。今回のコンサートではその宝石箱を生で見られますよ。
――奥さまの和央ようかさんが「テレビを見ながら作曲する」とおっしゃっていました。
感性で生きてる方なんでしょうね。作曲家は色んなことを考えながら弾くんですけど、僕から見れば、フランクはその時に感じたことを音にする。今、しゃべっているとしたら、それもピアノで弾いてしまう。生きていることや、世の中の動向、空気までもが音符やリズムに変わっていく。例えば、新しいミュージカルのBGMをお願いして、どういうシーンかを説明すると、1曲ではなく、10曲ぐらい弾き始めて「好きなの選んでいいよ」と。ビックリしますよ。名曲は恋愛をしている時に生まれる!なんて言われているんですよ(笑)。もちろん恋だけではないのですが…。例えば、ベートーベンの「ジャジャジャジャーン♪」というフレーズで有名な「運命」という曲は、打ちひしがれている時にできた曲ですよね。このように、その時その時の自分の立たされている状況や立場によって、神が舞い降りて芸術が生まれる。作曲家って素晴らしい仕事ですよね。その芸術を僕ら指揮者が調理する。指揮者はいわゆるコックさんなんです。絵画で表すと、キャンバスが曲でアーティストが絵具。赤・青・緑などいろんな個性があり、その絵具をパレットの上で混ぜ合わせ、キャンバスに重ねていく。それが指揮者の役目です。
――とても面白い例えです。フランクさんもご結婚されましたから、これからますますいい曲が生まれるのでしょうね。
いい意味で影響はあるでしょうね。いい環境にいるとポジティブになれますから。それに元ポップスミュージシャンだから、もともと明るいテイストの曲が多いんです。最近のミュージカルは、人が亡くなってしまう作品が多いのですが、「アリス・イン・ワンダーランド」を始め、ハッピーな楽曲が多い。現代において、幸せな曲を作れる数少ない作曲家の一人ですね。
――今回は「フランク・ワイルドホーン&フレンズ ジャパンツアー」として、彼と彼のバンド、ミュージカルスターが来日します。
フランクの音楽を理解して、表現できるミュージシャンが集まっています。フランクに選ばれて、一人だけ日本人のミュージシャンも出演しますし、ヨーロッパやブロードウェイの実力派スターが揃っていますよ。
――塩田さんともお知り合いである、日本からの出演者の和央ようかさんについてはいかがですか。
まず、存在感がありますよね。立ち振る舞いや身のこなしにキレがありますし、声にもドラマがある。僕の理論としては、音程の正確さや音域の広さなどだけが、いい歌手の決め手ではないと思っています。その要素を持ち合わせた上で、声にドラマがあることが最も大切なことだと思います。和央さんも日本を代表する素晴らしいアーティストのひとりです。

――塩田さんもドラマのあるオーケストラを目指されています。
オーケストラでも淡々と演奏するのではなく、テンポを変えたり、強弱をつけることでドラマが生まれる。テレビドラマで色んなシーンが自然にリンクするのは、音楽がドラマを語っている部分があるからなんです。それを引き出すのが僕の仕事です。登場人物の心情や物語、セットの転換、大道具、衣装を見て、それにマッチする、もしくは反比例する音楽を奏でるのがドラマのあるオーケストラなんです。フランクの曲はドラマティックな曲が多いけど、普通に演奏すると、普通に終わってしまう。例えば、オペラでいうと、モーツァルトやベルディの古典派は、音符が確立されていて、音符の通り演奏することで十分に表現できる。でも、プッチーニやベッリーニは音楽を我々が表現すると、よりドラマが生まれてくる。ロイド=ウェバーの曲は、音符通りに歌ったり、演奏することでドラマが生まれる。フランクは譜面から感じ取って表現者の個性が加わることで、自由にドラマが出てくるんです。
――ロイド=ウェバーはそれを意図して譜面を書いているということではないんですよね。
ないです。作曲家の個性なんです。話していて、この人には通じるけど、ほかの人には通じないのと一緒です。方言みたいなもの。関東弁で話したら分からないけど、関西弁なら分かるというのは、ロイド=ウェバーやフランクと同じ(一同笑)。本人たちは自然なんですよ。
――こっちが感じ取らなくてはいけない。
プッチーニやベッリーニは、ベリズモオペラの作曲家に属します。フランクは“ベリズモミュージカル作曲家”ですよね(笑)。また、フランクの曲は地声を使って歌わなきゃいけないものが多い。だから喉の筋肉と体力をすごく使う。フランクの曲を歌うと俳優は皆、ヘトヘトになります。エネルギーを抜いて歌うと伝わらないからね。俳優さんたちは「彼の曲を歌うのは闘いを挑むことだ」と言いますね。
――闘いを挑む楽曲は作曲家のスティーヴン・ソンドハイムかと思っていました。
ソンドハイムは音符やリズムで闘いを挑むんですよ。変拍子で心の動きや背景を表現しているから難しい。フランクの作品は、転調が有効に使われていて、それが心の高揚に繋がって行きます。例えば『ジキル&ハイド』の『This is the moment 時が来た』は、音が途中でドンドン上がっていくのですが、歌手はものすごく辛いはずなんですよ。日本では地声と裏声としか区別しませんが、ブロードウェイでは、チェストボイス、チェストミックス、ミックスボイス、ベルティング、フェイクベルト、ヘッドボイスなど色々な声の出し方があるんです。ほとんどベルティング(地声)を使わなきゃいけないのがフランクの曲の特徴です。だからすごくエネルギッシュでドラマがある。いぶし銀ですね。今回、演奏予定のホイットニー・ヒューストンに提供した大ヒット曲「Where do Broken Hearts Go」も見所です。
――なるほど。いぶし銀をチェックしながら聞いてみるのも楽しめますね。
そうですね。ハードルが高いと感じるのはなく、ざっくばらんにジーパンやTシャツを着て、野外のロックコンサートに行くノリでいいと思います。皆さん、フランクのように、キャップを被って来てくださいね(笑)。楽しかったら、座っていないで立ち上がってもいい。お客さんとフランクが家族に、ホール全体が一つのファミリーになるコンサートだと思います。フランクのことをよく知らない方でも、このコンサートを見ただけで、彼の魅力が分かる。劇場を出た後は、きっと歌を口ずさみ、楽しい気分になっているはずです。


取材・文:米満ゆうこ
撮影:奥村達也
(2015年12月15日更新)
Tweet

塩田明弘
『フランク・ワイルドホーン
&フレンズ』
Pick Up!!
【大阪公演】
発売中 Pコード:443-563
▼12月23日(水・祝) 12:00/17:00
梅田芸術劇場 メインホール
S席-12000円 A席-6000円
学生当日引換券-5000円
[出演]トーマス・ボルヒャート/ジャッキー・バーンズ/アダム・パスカル/和央ようか/サブリナ・ヴェッカリン/フランク・ワイルドホーン(p)/ジュリア・ペダーソン(b)/デイヴィッド・マン(sax)/クリント・デ・ギャノン(ds)
※未就学児童は入場不可。出演者は予定のため変更の可能性あり。出演者変更に伴う払戻し不可。
※学生当日引換券は、ご観劇日当日開演30分前より「当日引換所」にてチケットと学生証をご提示のうえ座席券とお引換下さい。引換時に学生であることが確認できない場合は差額をお支払い頂きます。座席は事前にご用意しており、先着順ではございません。
[問]梅田芸術劇場■06-6377-3800