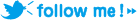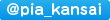ホーム > インタビュー&レポート > 約1年半ぶり! 劇団鹿殺しの新作『ランドスライドワールド』 関西公演を前に演出家・菜月チョビに聞く!
約1年半ぶり!
劇団鹿殺しの新作『ランドスライドワールド』
関西公演を前に演出家・菜月チョビに聞く!
2013年10月より1年間、文化庁新進芸術家海外派遣制度により1年間、カナダに留学していた劇団鹿殺しの演出家・女優の菜月チョビ。そのため、劇団鹿殺しも充電期間として本公演を休止し、『ジルゼの事情』『山犬』など作家の丸尾丸一郎によるプロデュース公演の上演や、劇団員も個々に活動を行うという、これまでにない時間を過ごした。そして菜月が帰国し、復活公演が決定。2009年に上演した音楽劇『ベルゼブブ兄弟』を原案にし、大胆な翻案で挑む新作『ランドスライドワールド』を東京、大阪で上演する。山間の旧家に住む四兄弟を中心に、かつてこの家で絶大な権力を振るった父親や、謎に包まれた母親など、“わけあり”の家族が願う幸せを描いた物語だ。
本公演は約1年半ぶりとなる劇団鹿殺し。カナダで過ごした日々をどのように劇団へと還元していくのか、菜月にこの1年のこと、本公演のことなどを聞いた。
--まずは、おかえりなさいませ。あっという間だったなという感じがしますが。
あっという間でしたね。行く前は不安でしたけど…。
--行かれる前に心配されていたホームシックは?
なんか回避できました。日本からもメンバーが会いに来てくれたりとかして。
--最初にカナダの話をお伺いしたいのですが、どういうふうに過ごされていたんですか?
バンクーバーでは、ちっちゃな劇団に参加させてもらって、基本裏方で、本番もちょっと出るみたいなこともやって。モントリオール側では、受け入れ先の劇団があるんですけど、そこのリハーサルを中心に、いろんな劇団のリハーサルを見せていただいたりしていました。
--日本との違いはありましたか?
どうだろう…やっていること自体はそんなに違うってことはないんですけど、カナダは歴史が新しい国なので――シルク・ドゥ・ソレイユを筆頭にカナダから世界に輸出するようなものを新しく作り上げようと国と街と企業とが本気の助成金を出していて。私の受け入れ先になっていただいた7 Fingers--サーカスの劇団なんですけど、ここもブロードウェイでサーカス部分の演出をされていたりとかして、ちゃんと援助が成功しているので、それはすごくいいなと思いました。
--助成金の遣い方に相違が?
そうですね。例えば、ケベック・シティーはすごくちっちゃい街で人口も少ないから、チケット代でお芝居が賄えないということで、保護という意味の助成金もあって、そこは日本と似ているところもあります。お客さんが入るかどうかじゃなくて、作品にだけ集中できるっていうところは、そこはどうかな? 作り手にとってあんまりいいことだけじゃないんじゃないかなって思いましたけど、一方でちゃんと育てようっていうタイプの助成がきちんと身を結んでいるシルク・ドゥ・ソレイユやサーカス学校などの例は素晴らしいと思います。日本は、助成するにあたり、プロフェッショナルが選んで育てて、実際に世界に出すところまで実践的に使える団体を作ろうとか、そういうことじゃないですよね。広くにふわ~っと渡しすぎているから、成果が出にくい形になっちゃってるなっていう。海外での公演を支援してくれたりとかもあるんですけど、継続的に、日本から海外にどんなものを持っていくのか、人材の育成や団体の維持まで、そういうことまでは意識して助成しているわけじゃないから、一回づつやって終わりというか。公演自体の製作は各団体がそれぞれが単独でやってしまっているので。そういうところは日本よりかカナダの方がうまいなって思いました。実際、シルク・ドゥ・ソレイユを全世界に通用するように作り上げていますし。
--カナダでは具体的にはどういうことをされていたんですか?
基本、演出部みたいな感じで、一緒に演出を考えたり、人が足りなくなったら一緒に影絵で出演して。子どもたちに見せるお芝居を実際にやっていましたね。そこは家族経営の劇団で、お母さんが音響さんをやっていて。スタッフさんの話とかも聞かせてもらって、年間通してどんなふうに活動しているんだろうとか、いろんなお話を聞かせてもらいました。モントリーオールはサーカスとか、花火とか、いろんなフェスティバルがあるので、なるべくほかのジャンルのフェスティバルに行くようにして、どんなものが人々の日々の楽しみになっているかっていうのを見ていました。
--ちなみに現地の皆さんはどういうものを楽しみにされていましたか?
週2回くらいのペースで一ヶ月くらいにわたり花火のフェスがあるんです。もちろん野外であるんですけど、30分間、音楽と完全にシンクロした一つの舞台みたいなものを作っていて。お客さんはイヤホンで音楽を聴きながら花火を観るっていう、劇場で見るようなエンターテイメントになっていました。そのフェスに毎週、なるだけ行っていて。花火と音楽がシンクロして、ストーリー仕立てとまではいかないけど、音楽が持つ気持ちを揺さぶるような物語を花火でも表現しているので、単に打ち上がってすごいって観ていたものが、例えばジョン・レノンの曲とか流れて、それに合っていたりしたらメッセージを受け取れるじゃないですか。“花火大会だ、わー!”ってみんな来ているんだけど、そこで違う感覚を得るということを自然と与えてくれる、音楽と体で感じるドーンという音と光が合わさると何かを感じるんだなっていう体験をちゃんと与えているので、すごくいいなぁと思いました。
--それは面白いですね。
日本の花火のレベルは世界的にもすごいからきっと、より美しいものができそうなので日本でもやってほしいなと思いましたね。とても素敵でした。
--そんな1年間を経て、ついに復活公演ですね。復活公演については、まず過去に上演した『ベルゼブブ兄弟』が思い浮かんだそうですが、それはどのタイミングですか?
夏ぐらいですね。2014年も半分が過ぎて、丸尾とスカイプでミーティングしていて。何しようって。日本に帰ってすぐ、稽古っていうスケジュールだったので、みんなの変化も稽古をしながら、“こうなったんだ”って感じながらの作品作りになると思って。そのときに完全な新作を作るよりは、過去の作品でどんなふうに自分たちが変わったか自分たちでも感じながらやりたいなと思って、原案のあるものにしようと提案しました。『ベルゼブブ兄弟』は家族というすごく狭い世界の話なんですけど、劇団員がみんな散り散りにいろんなところで活動して、いろんな広がりを感じながら帰ってきているので、そのメンバーでこの作品をしたら、狭い世界をぎゅーっと描くというより、そこから広い世界のことが描けるんじゃないかなと思って。だから一番狭い世界の話をした『ベルゼブブ兄弟』をやりたいなと。この作品を原案でいこうと。
--原案にしつつも、違うところはどこですか?
今回の本公演のタイトルが『ランドスライドワールド』とあるように、自分の立っている場所というか、ここはどこだっていう。ここじゃないとダメだと思っているものが、傍から見ると全然大事じゃなかったりとか、立っている場所は良くも悪くも確かじゃないっていう感覚をすごく感じていて。児童文学に『蝿の王』という作品があるんですけど、『ベルゼブブ兄弟』は元々そこからインスピレーションを受けた作品でもあって。兄弟たちが田舎の狭い世界で生きていながら、そこから逃避して自分の好きな世界を思い描いたときに、同じ場所でも虫眼鏡で覗いたら、ハエがものすごくでかくて、ものすごく気持ち悪い怪物に見えたりするような。『ベルゼブブ兄弟』は、単純に兄弟たちがいじめていた蝿が復讐心を持って人間の愚かなところを狙っているというような話だったんですけど、その蝿自体が自分の見方一つで生まれてきたものであってという…、一つの場所からどこかに飛んでいくというファンタジーはよくやっていたんですけど、同じ場所でもめくると見え方が違う、裏返せば全然違うものにも見えてくるという、そういう見せ方が加わります。そんな感じです、うまく言えないんですけど(笑)。
--虫の眼で見たとき、逆に広がっていくような?
今回は家族の話だから、どんな人も幼いころに今の自分とは違う自分を思い描いて、ファンタジーの世界に飛んでいっていたと思うんです。演劇でファンタジーと言うとすごく遠い話というか、演劇の手法として出てきているようにすごくこむずかしく見えちゃうと思うんでうすけど、観ているお客さんに“こういうときに、こういうファンタジーに飛ぶことってある”ってより実感してもらえるというか共感してもらえる、もっとたくさんの人たちにとって地続きのものに見えるようにしたいなと。
--今回も兄弟、家族のお話で?
そうですね。前は私が妹で男女4人兄弟だったんですが、妹を弟にしてそれを木村了くんにやってもらって。男兄弟4人とお父さんの話です。
--丸尾さんの作品は兄弟や家族のお話が多い印象です。丸尾さんは家族や兄弟に対して何か特別に思うところがあるんでしょうか?
丸さんはいとことも一緒に住んで、兄弟みたいに育てられたそうで。家が工務店で、家族じゃない人も一緒に住んで、家族を形成してきたという実体験があって。だから、丸さんの親とかに見せるのはどうなんだろうっていうくらい(笑)、『ベルゼブブ兄弟』は割と実話に近いですね。丸さんは、みんな幸せでいたいっていう気持ちを持っていて、でもうまくいかないっていうこととか実際に少年時代に体験していて。あと、丸尾家はすごく個性豊かなので(笑)、家族というのは丸さんの人格形成にめっちゃ影響しているんだなぁって。
-- “普通”に考えると、丸尾さんの家族構成は一般のそれとはちょっと違いますよね。
それを変だとは思ってなかったようなんです。そういうものだと思っていたみたいで。でも何かうまくいかないなって。
--なるほど。家族とか、兄弟とか、どういうふうに捉えられているのか、気になったんです。
丸さんは、すごく家族を大事にする人なので、いっぱい見てきたんだろうなと思います。家族としてうまくやっていくために、みんながどういうふうに間を取り持ちあっているのか、壊れないようにやっているのかっていうことを、末っ子の丸さんは一番下から見てたんじゃないかなぁ。
--そしてゲストが木村了さん、今奈良隆行、美津乃あわさん。
美津乃さんは3回目。今奈良さんは4回目ですね。
--じゃあ、お二人とも劇団をよくご存知で。
そうですね、信頼の置けるお二方ですね。劇団の形というものも込みで愛してくれて、稽古場を作ってくださるので。
--木村さんはどうですか? フレッシュな感じですか?
フレッシュっていうか、ものすごく頼りになりますね。こんなに若い方で頼れる役者さんってなかなか、いないなって。安心感がすごいし、オレノ(グラフティ)が了くんと共演したときも言ってたんですけど、意外と座長体質というか、この場所は自分で作んなきゃって思ったら、結構場の雰囲気を作ってくれるんです。劇団の稽古の形に自分を合わせてくれて、楽しんでくれるので、すごくいいですね。…めっちゃいいな。稽古帰りも「了くん、めっちゃいいな」ってみんなで言いながら帰るっていう(笑)。
--どういうきっかけで声をかけられたんですか?
最初はオレノと共演している舞台を私が観て、すごく若いのに土臭いというか…。イケメンと言われていますが、土臭さだったり、人間の芯がしっかりしているところがはみ出て見えてくるというか。人間らしさがあって、味のある人だなあって。きれいな演技をしながらでも、自然とそういう芯が見えてくる人なのでいいなって思っています。とても責任感を持って舞台に立ってるなっていうのが客席から見ていても分かる、お客さんに対しての責任をちゃんと自分が背負って舞台を引っ張っているのが分かる演技をしていたので、客席で観ていて、たぶんきっと信用できる役者さんなんだろうなと思ってましたね。だから、合う作品があったらぜひ出てほしいとずっと思っていて、毎回名前は挙がっていたんですけど、今回の設定が4兄弟で、年のころとしてもいいなと、今だなということで声をかけました。
--では、劇団員の方とも一年ぶりですが、稽古場などどうですか?
そうですね、留学中、日本では丸さんがいろんな形で公演をやっていて。演出も丸さんと私はやり方が違うので、みんな(私のやり方を)忘れてんなぁっていう(笑)。ただ、離れてみるまではお互いみんないるのが当たり前になって、コミュニケーションが雑になっていると感じていたのもあって、カナダから結構メールで個人的にやり取りをしたりして、これからも活動を続けていくんだったら、お互いにどうしたらいいのかっていう話を劇団員たちとたくさんしたんです。
--カナダに行かれる前までは、そういうコミュニケーションは?
全体で“みんなで気をつけていこう”とは話してたけど、個人個人ではしてなくて。そういうことについて個人がどう思っているかという話はたくさんは聞けなかったですね。後から劇団に入ってきたメンバーは既にあるところに入ってきているという感覚があるから、自分で何か変えていこうという発想自体がなくて。自分の気持ちを伝えること自体、あんまりしない癖がついちゃってたんですよね。でも意外と上の人は、ついてきてくれるだけだと寂しいもんだよって。もうちょっと話して、弱音とか、“そんなこと考えてたんだ”っていうのをお互いに話す機会があったので、そこは帰ってきてからすごく変わりましたね。ちょっとしたメールにもちゃんと返事するとか(笑)。ちっちゃなことなんですけど、お互い感謝をしたり、思ってることを言うっていう。
--そういったコミュニケーションを通じて新たな発見はありましたか?
人って自分の気持ちを口に出していかないと、気持ち自体なくなるんだな、本当に何も思わなくなっちゃうんだなって。何でもいいから、「了解」だけでもいいから、自分で言葉にする。日常的に自分で表現するという意識を持ってしないと、自分の表現でなくなっちゃうんだなっていうのは思いましたね。
--よく分かります。どうでもよくなりますよね。
どうでもよくなって、どうでもいいままついていける。「ついていこう」なら「ついていこう」でいいし、「同じでいいです」なら「同じでいいです」でいいから、自分の言葉で話さないと、自分の表現をする幅がなくなっていっちゃうんだなっていう。だから、何でもいいからしゃべろうっていう(笑)。海外の人たちは表現するのがもともと得意な人が多いじゃないですか。そこへいくと私も表現するのがあんまり好きじゃないなって思うんですけど。そんなにぐいぐい言うほど自分のしゃべりたいことがなかったりするから苦手だなと思ったりするんですけど、ボーっとしたことでもいいから言葉にしないと、思考すること自体なくなっちゃうなって思います。
--外国の人とか、さらっと伝えるのが上手そうなイメージがありますね。
とりあえず何でもしゃべっとく、何か声を発する。カナダに行って最初にカルチャーショックというか、お店に入ったらいらっしゃいませ的な感じで「How are you doing」って、「どうだ?」って聞いてくるじゃないですか。「どうだ?」って聞かれたら「まあまあです」みたいな、何か答えなきゃってなるじゃないですか、日本人的には。でもあれって聞いてる方もどうでもよくて。日本は「いらっしゃいませ」を一発目で言う。それが文化の違いだなって。日本だと黙ったまま過ごせちゃうんですけど、(カナダでは)“自分はこう思っている”ということをとりあえず言わなきゃっていうのがすごくあるので、無駄なことでもとにかく言うんですよね。本当に言いたいことを自分の中でしっかり考えて言うっていう日本人の良さもあるなと思いますけど、ただ、咄嗟に言えないっていうのは…。黙ったまま過ごせちゃうっていうのがやっぱりよくないところもあるなって思います。
--日本人の美徳というか、自分の言葉は一旦飲み込んで譲るというところがあると思うんですけど、最近はそれでも自分の言葉で言う機会を作っていかないとダメなんじゃないかなと思うこともあります。
黙っていても伝わるということが通用しない時代になっているかなって。だから言わないとわかんない人がすごく多い。お互い話し合わないとだめなんだなって。劇団が大きくなってきたら、若手のメンバーのことを気にする分だけ時間もストレスもめっちゃかかるので。それでかなり疲れて、これに構ってたら自分が成長する時間がない、中堅以上だけで団結すべきかとか、(カナダに)行く前にすごく悩んだんです。だけど何を思っているかわかんない人を連れて歩くという方が私はできないなって。逆にそこまでの愛情はないなと。“誰だ、お前”ってなっちゃうから。こっちは頑張って劇団を守ってるのに、なんでそーっとついて来ちゃうんだって思うので、それはないなと。じゃあ、その都度、集まるプロデュース公演をするほど、私はそんなに演劇好きじゃないなって(笑)。やっぱり自分でこの場所を作って、ずっと賭けて。“こういう表現をする”という気持ちを持った人たちと、お互い育てあって作る場所を1個持っておきたいなって思ったので、ちょっとしんどいけどやっぱり話そうと。それで、一人ずつとしゃべったんです。
--では、最後に、月並みですが公演に向けてメッセージをお願いします。
兄弟が争っていて悲しい話になったりするんですけども、根本的に描きたいのは愛し合いたいっていう、どんな家族であろうと本当はこういう家族がいいって思っている希望の部分で。すごく狭いけれども、そこから世界が見えてくるような、広がりのある作品になっていると思うので、きっと楽しい、カラフルな作品になると思います。虫眼鏡の中のハエたちは楽隊が担っていて、いろんな音楽を奏でて、いろんな世界に連れていってくれたりします。あと、某ヴィジュアル系ロックバンドのコピーをしていたことが兄弟たちの思い出なんですけど、すごくバカな思い出で、バカな音楽もたくさん出てきます。原案になっている『ベルゼブブ兄弟』も、バンドマンの友達に一番評判がよかった作品だったりするので、毎回言ってるんですけど、演劇を観たことのない人にのびのび楽しんでほしい作品だと思うので、ぜひ楽しみに来てください!
(2015年1月19日更新)
Tweet Check

なつきちょび●5月3日生まれ、福岡県出身。劇団鹿殺し座付き演出家。感情の開放と音楽が合致したミュージカルとは異なる音楽劇を確立。2013年10月より、野田秀樹、長塚圭史らが派遣された文化庁新進芸術家海外派遣制度でカナダにて1年間の留学を経験。次世代を担う演出家として注目を集めている。また、俳優としても活躍し、劇団鹿殺し本公演においては数多くの作品で主演をつとめる。主な外部出演作に舞台『A MIDSUMER NIGHTʼS DREAM』(G2プロデュース)、『燻し銀河』(作・演出 松村武)
●公演情報

劇団鹿殺し
『ランドスライドワールド』
発売中
Pコード:440-642
▼1月29日(木)19:00
▼1月30日(金)19:00
▼1月31日(土)14:00/19:00
▼2月1日(日)14:00
ABCホール
全席指定-4900円
[作]丸尾丸一郎
[演出]菜月チョビ
[音楽]入交星士/オレノグラフィティ
[出演]丸尾丸一郎/オレノグラフィティ/山岸門人/橘 輝/傳田うに/円山チカ/坂本けこ美/鷺沼恵美子/浅野康之/近藤茶/峰ゆとり/有田杏子/木村了/今奈良孝行/美津乃あわ/他
※未就学児童は入場不可。
[問]キョードーインフォメーション
[TEL]06-7732-8888
劇団鹿殺し公式サイト
http://shika564.com/