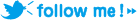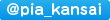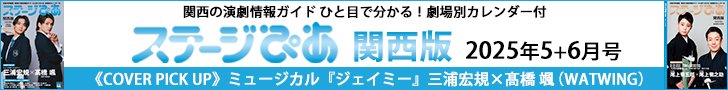ホーム > インタビュー&レポート > 「討ち入りの日にできる今が一番聴き頃、食べ頃!」 月亭八方自慢の“忠臣蔵落語”を兵庫芸文で披露!
「討ち入りの日にできる今が一番聴き頃、食べ頃!」
月亭八方自慢の“忠臣蔵落語”を兵庫芸文で披露!
12月14日、赤穂浪士討ち入りの日に、月亭八方が『忠臣蔵』にちなんだ落語会を、赤穂浪士のふるさと 兵庫で開催する。だがそれは「いざ、討ち入り」とはちょっと異なる抱腹絶倒の創作落語「AKO47―新説赤穂義士伝」。月亭八方に噺の魅力などを聞いた。
--「賞味期限」のある噺
「忠臣蔵落語」を12月14日にやるのは初めて、一門会を兵庫でするのも初めてです。赤穂浪士を(AKB48にかけて)「AKO47」と見立てていることもあって、この噺には賞味期限があるんです。昨年作った新作ですが、最近のAKBの話題も反映して進化しています。例えば、前田敦子さんの卒業を受けて「この討ち入りをもって、卒業する」と言う人が出きたり。さて、大島優子さんは、どんなふうに登場してもらおうかな、と考えたり…。でもね、「会いたかった~会いたかった~会いたかった~、吉良に~」という、ここだけは新しい歌には変えられないんですよね。
--忠臣蔵を知っている人にこそ
「忠臣蔵」はいろんなジャンルで、いろんな作品になっているでしょ。取り上げ方も、女性だけとか、四十七士のうち一人だけとか…。あらゆるものの基礎になる「バイエル」みたいなもの。他にもそういう類のものがないかなと思っても、なかなかここまでのものはない。描き方も、例えば、講談はヒーローをヒーローとして描く。でも、落語ではヒーローにも失敗してもらわないとね。「忠臣蔵」で笑いが起こる、こんな描き方もあるのか、という意味で、忠臣蔵をご存じのすべての人に聴いて頂きたいですね。
--落語は「伝統継承模倣芸」
歌舞伎や能は「伝統継承芸」の意味合いが強いけれど、落語はそこに新しい要素が入る「伝統継承模倣芸」だと思っているんです。面白いことをそのまま継承するのではなく、「この人で」感じたいという。そこに、噺し手のオリジナリティが含まれていきます。落語がサゲのある「落とし噺」になる前は「誘笑芸」、その源には「真似」がある。「真似」「模倣」する対象は人だけでなく「今の時代」や「流行」も入ります。この『忠臣蔵落語』は賞味期限がある噺と言いましたが、今がピークかもしれません。12月14日、討ち入りの日にできる今が一番聴き頃、食べ頃! ぜひ、お楽しみください。
(2012年10月25日更新)
Tweet Check