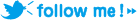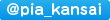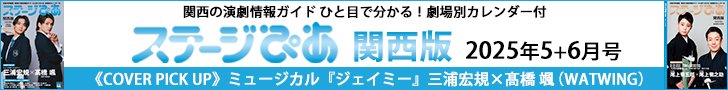ホーム > インタビュー&レポート > 「縁日の懐かしい雰囲気の中で怪談を」 稲川淳二、20年目の“怪談ナイト”が開催!
「縁日の懐かしい雰囲気の中で怪談を」
稲川淳二、20年目の“怪談ナイト”が開催!
怪談の語り手としておなじみの稲川淳二が、1993年より20年間、ライフワークとして続けてきた“怪談ナイト”。今年は8月17日より大阪・森ノ宮ピロティホールで開催。2月に前立腺ガンの手術をし、無事復帰を果たした稲川が、20年の節目となる今年は過去最多となる35か所41公演を敢行する。「今年はスタートの年に」という稲川が、どんな話を聞かせてくれるのか、話を訊いた。
「毎年新しい話しかしていないんですよ。そうすると、昔からのファンの方に「生であの時の話が聞きたい」というリクエストをたくさん頂くんです」と語る稲川は、19年間で391本の話を披露してきた。それでもまだ話していない怪談があるという。
「同じような話が3つあったとして、そのうちのひとつをやろうと思っても、他の話とシチュエーションやオチが似ていると辞めてしまうんですよね。それがやらないままになっちゃってて。なので、そういう話の中から使えるものを持ってこようと考えています。面白いことに怪談って、若い頃に怖いと思って話していたものが、年を取ると目線が変わって別のものを怖いと思うようになるんですよね。65歳にもなると、バランス良く物事が見えてくるので、そういう感覚も取り入れながら話したいと思っています。昔の話を今話すとどうなるのかなっていう楽しみもありますね」。
毎年、ツアーで用意している怪談は約20本。その中から8本ほどを選んで話していく。
「状況によって差し替えていくんですよ。ツアーが始まったときと終盤では順序も変わったりしますね。あと、毎年素晴らしい舞台美術を作ってくださるんですが、今年は20周年のお祭りのような雰囲気になりそうです。縁日のような、懐かしい昔のお祭りの風情を漂わせて、会場全体がそんな雰囲気の中で、楽しんで頂けたらなと思っています」
今や稲川淳二といえば怪談、怪談といえば稲川淳二と思われるほどにイメージが定着。当初は怪談を商売にするつもりはなかったが、日本の文化であり、教えである怪談を残していきたいという思いは強い。
「怪談とホラーを一緒にされることが多いんですが、全く別物なんですよ。怪談は話を聞いているうちにジワッと汗をかいていたり、思わず隣の人の手を掴んだりするようなものですが、ホラーはショック話ですよね。今は“都市伝説”なんていう言葉も作られていますが、あれは怪談そのものですよ。昔からある七不思議というものが怪談になったわけで。怪談の方がはるかに質が高いし、難しいんです。それが間違って伝えられて、Jホラーにされていたりするんですよ。例えば「開かずの間」というのは、中で人が殺されたとか幽閉されたとかいろんな話があるじゃないですか。でも実はあれは、覗いてはいけない、開けてはいけないことをいうんですよ。本当はみんな知っているけど、言ってはいけないんですよ。なぜならそこは子供ができない嫁のためにお姑さんが用意した部屋だから。夫ではない人がそこで待っていて、夜中になったら嫁をその部屋へ行かせるんですよね。怪談の根底にはそういう文化的背景があるのに、知らない人が多いんです。そういうところがなんとなくわかってくれたら嬉しいなという思いはありますね。怪談って駄菓子みたいな存在でいいんですよ。表通りにあるようなシャレた洋菓子屋じゃなくて、子供も大人も、おじいちゃんおばあちゃんも懐かしい味だなって思うような。それが怪談だなって思うんです」
そんな怪談の語り部、稲川が目指すのは“怪談爺ぃ”だ。
「世間で嫌がられながらも、割とどこかで役に立ってるような、そんな爺ぃになってみたいなと思っています(笑)。ですから、そのスタートがいよいよ始まるんですよね。楽しみです。大阪のファンの方は特に盛り上げ方がうまいので、余分に喋っちゃうんですよ。始まる前に必要以上に盛り上がってくれるのがすごく嬉しいですね」
(取材・文/黒石悦子)
(2012年8月16日更新)
Tweet Check

いながわ・じゅんじ●1947年、東京生まれ。桑沢デザイン研究所を経て、タレント・工業デザイナーとして、ふたつの顔で活動している。かつては日本テレビ『ルック ルック』、NHK大河ドラマなど、多くの番組に出演。1993年8月13日(金)、クラブチッタ川崎で行った怪談トークライブ『ミステリーナイト』をきっかけに、20年間開催している。今年、8月13日が「怪談の日」と日本記念日協会に認定された。