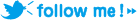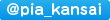ホーム > インタビュー&レポート > 陸軍大将・乃木希典について馬たちが口々に語る 井上流ユーモアも散りばめられた舞台『しみじみ日本・ 乃木大将』について風間杜夫にインタビュー!
陸軍大将・乃木希典について馬たちが口々に語る
井上流ユーモアも散りばめられた舞台『しみじみ日本・
乃木大将』について風間杜夫にインタビュー!
日露戦争の英雄、乃木希典の真の姿に迫る井上ひさしの初期作品『しみじみ日本・乃木大将』が、21年ぶりに上演される。「聖将」と神格化される一方で、「愚将」とも評された乃木大将を「愛馬の足」の目線から語ってゆくという、井上ひさしのユーモアがたっぷりと盛り込まれている本作。初演は1979年、小沢昭一主宰の期間限定劇団、芸能座に書き下ろされたもの。そして、第14回紀伊國屋演劇賞個人賞、第31回読売文学賞を受賞するなど大きな評価を得た作品だ。21年ぶりの再演となる今回、演出を手がけるのは“世界のNINAGAWA”こと蜷川幸雄。そしてキャストは舞台や映画で活躍する名優たちが一堂に。蜷川が井上作品にどのような新しい光を当て、実力あるキャストたちがいかに見せてくれるか楽しみなところでもある本作。中でも蜷川演出舞台には初登場となる風間杜夫に、作品へかける思いや意気込みを聞いた。
33年前に書き下ろされた『しみじみ日本・乃木大将』だが、台本には詳細に、井上によるト書き(脚本で、俳優の演技や照明、音楽、効果などの演出を記した文章)が書かれているという。それを踏まえて稽古場では、ト書きどおりに進められていったそうだ。一言一句、井上が残したものとは。まずは井上戯曲の魅力について尋ねた。井上作品には1989年と1992年、太宰治を取り巻く人間群像を描いた舞台『人間合格』に出演している。
風間杜夫(以下、風間)「井上先生の初期の頃はそれこそ、石川啄木、小林一茶、樋口一葉と、実在した歴史的な人物を取り上げていますよね。乃木希典も同じく、とにかく一人の人間の戯曲を書き上げるまで膨大な資料と格闘しながら、年譜まで作られて、実際にあったエピソードも丹念に拾い上げて、井上ひさし流の味付けをして、浮き彫りにしていかれます。そこにすごい情熱を感じますね。『しみじみ日本・乃木大将』もきっと、格闘しながら書かれたと思います。それだけに台詞の量も半端なく多くて。そしてト書きも厳密に規定されていて、そのとおりにやってみると確かにそれが面白い。その緻密さに圧倒されますね」
井上ひさし流の味付けとは、例えばどんなところに感じるのだろうか?
風間「『人間合格』では太宰治に対して、“あんた、一生懸命生きたじゃない”というような、温かい眼差しで人を救い上げていく。井上先生にはそういう目があると思いますね。『しみじみ日本・乃木大将』に関しては、列強に追いつけ追い越せという、日本国が近代国家になるためいかに軍隊というものを強固なものにしていくかという、そんな明治という時代の終わりが舞台で。この時代に、日本人の原型が作られたと思うんです。ある種、決まりきった型みたいなもの。それが常識みたいになってへばりついている日本人。そういう日本人に対して、もっと自由に、のびのびした生き方ができないものだろうかというメッセージを受け取っています。軍国主義に走ろうとした歴史の批評性もあるでしょうが、このお芝居からは“本当に人間らしく生きようよ”という井上先生の声が聞こえているような気がしています。その部分もお芝居で照らし出せたらと思います」
そして、そんな“日本人の原型”が生まれたと考える明治時代を駆け抜けた乃木希典という人間については、どう見ているのだろう。
風間「お芝居には“連隊旗が陛下の分身である”と描かれています。天皇陛下は満遍なく戦場にお顔を出すことはできないけど、連隊旗がはためく下には常におられるという、一つの軍人の思想が書かれています。井上先生のことですから、いろいろ史実を調べられた上での話と思いますが、乃木希典の場合は陛下のためにという大義の上で殉死をする。それが賛美される部分と、ナンセンスだと言われる部分の両者があると思うんです。井上先生がどういうおつもりで書かれているのか分かりませんが、その後、日本は軍国主義に走り、第二次世界大戦に突入していきましたが、この本にはそんな日本の“芽”が出てきたところが描かれていると思います。さらに根底には天皇制と言うものに対する批判も見え隠れするところがありますが、僕自身は天皇制を批判する芝居よりも、あくまでも人間・乃木希典という、その美意識みたいなもの、明治という時代の終わりに自決をしなくてはならなかった男の悲運や、切なさ、哀れみなど、いろんなものを感じながらこのお芝居をやっていきたい。笑いが多い芝居ですが、そんなところもお客さんが感じてくれたらいいなと思いますね」
時代が大きく変わってゆく中、天皇陛下への忠誠心を持ち続けた乃木大将。戯曲中、乃木大将が発する言葉などで、印象的な台詞はあるのだろうか?
風間「“天皇陛下は西遊記の孫悟空じゃないんだ”という台詞があります。これは井上先生が書かれた戯曲ですが、やっぱり乃木大将もそう言われたんだろうと僕は思います。陛下の分身を作ることができないから、戦場にも万遍なく顔を出すことができない。だから、この連隊旗こそ天皇陛下の分身なんだ、この旗のはためくところには必ず天皇陛下がいる。そういうつもりで連隊旗を大切にしろと。多分、それを生真面目に信じた軍人じゃないですか、乃木希典という人は。ただ、その旗で鼻をかんだり、こぼれたお茶をふいたりして、そういうところが井上さんらしいと思いますね」
物語はまず、殉死を決意した乃木大将と静子夫人が、愛馬に別れを告げるシーンから始まる。だが、やがて馬たちは人格ならぬ“馬格”をあらわにし、その馬格も前足と後ろ足の二つに分かれてゆく。そして舞台には1頭の馬から生まれた2つの馬格がそれぞれ、乃木大将を語り始めるのだった。
風間「僕は最初、乃木大将役で出てきますが、途中から馬の壽(ことぶき)号の“こと”を演じます。壽号は、前足が“こと”で、後ろ足が“ぶき”。物語は明治天皇がお隠れになった大正元年九月十三日、明治天皇大葬の日の午後六時から午後八時までの2時間を描いたお話なんですが、馬たちが過去に遡って、陸軍少佐だった頃の乃木希典とか、あるいは萩の乱が起こった時のこととか、そういうことを演じます。ですから、乃木希典そのものを演じる部分と、馬が乃木希典を演じている部分との二つに分かれています。時代背景や時系列などは、井上先生が非常に克明にお調べになっているので、その時代や状況がどうだったか、そういうことをいかに演劇的に表現していくか、そういう課題を持っています」
劇中、馬の中に入り、馬の足を演じるシーンもある。リアリティを出すコツなどあるのだろうか?
風間「馬の足は難しいんですよ。後ろ足とのコンビネーションで足並みが揃ってなきゃいけないし」
風間とともに壽号の後ろ足を演じるのは吉田鋼太郎だ。まずは二人一組で息を合わせ馬となり、壽号を演じる。
風間「前足と後ろ足で馬格が分裂する前は1頭の馬として出て、二人同時に同じ句読点、同じ調子で台詞を言わなきゃいけない。そこが難しいですね。でも、そこもまた見せ場ですね。一つの台詞をあくまで一人が言っているように演じているところを楽しんでほしいです。あと、馬の足をやってみてわかったのですが、芝居の下手な人間は馬の足もダメですね(笑)。うまい役者がやるとそれらしく見える。誰が上手にできるか、役者同士で競い合っています(笑)」
蜷川幸雄の演出作品には初めて参加する風間。“蜷川組”の印象については?
風間「毎日、熱っぽい稽古を繰り返しております。熱くてスピード感があって。芝居もものすごく楽しいものですし、必ず皆さんに喜んでもらえるお芝居になるだろうと思っています。シアターBRAVA!を満席にしたいと思います」
話は変わって1997年頃より落語にも取り組んでいる風間。落語と芝居、交互にフィードバックするものはあるのだろうか?
風間「落語が面白いのは自分で演出ができて、ダメだしができるところ(笑)。自分で相手役を選べるし、登場人物の多い噺ではキャスティングもできる。他に相手役のいる芝居だとリズムが合わないことがありますが、落語は自分で演出できますから、ぽんぽんと掛け合いもできて。そして語りの芸だからこそ、いかに言葉に表情をつけて語る世界をお客さんに想像してもらえるかというところがあります。僕は舞台で台詞を言うとき、いかに台詞に表情をつけるかということを考えています。芝居は、最前列と最後列では見えるものも見えなくなります。でも台詞が届いて、その台詞に表情があれば見えないものが見えてくる。それが落語から演劇に持ち込めるものだなと思いましたね」
では最後に、改めて演劇の魅力について聞いた。
風間「僕の恩師であるつかこうへいがよく言っていたことなのですが、テレビや映画と比べて、一番効率が悪いのが演劇だと。複製は効かないし、そこに行かなきゃ観られない。でも、そこに行って観るということは観客の意志じゃないですか。何日の何という芝居のチケットを買って、当日にそこに行って“よし、観てやろう”という観客の意思がある。だからこそちゃんと腰を据えてやれって。そしてこれも、つかさん独特の表現なのですが、“客はだまされたくて来てるから、気持ちよくだましてやれ”と。そういうことだけは忘れていないですね。その劇場で触れられる、生ものの面白さというのかな、それをぜひ体感してほしいです。芝居を観て、自分が劇場に身を置いていることを“ここにいてよかったな”って思ってほしい。そう思ってもらうにはもちろん、こっちにも責任があるわけですが、“今日、ここに来てよかった。ここに座って見届けてよかった”という思いが必ずあると思うので、それを体感してほしいです」
(2012年7月31日更新)
Tweet Check

かざまもりお●1949年東京生まれ。1959~66年子役として活動。早大演劇科、俳小附属養成所を経て、1971年「表現劇場」を創立。1977年より、つかこうへい作品の主軸俳優として人気を博す。1982年映画『蒲田行進曲』で一躍脚光を浴び、日本アカデミー賞最優秀助演男優賞をはじめ、多数受賞。1983年テレビ『スチュワーデス物語』で若い女性層の人気を得て、「教官」が流行語大賞にノミネートされるなど、広くお茶の間に浸透する。以来その演技力に対して高い評価を受け、数多くの演劇、映画、ドラマ、CM、
●公演情報

『しみじみ日本・乃木大将』
▼8月2日(木)18:30
▼8月3日(金)13:00
▼8月4日(土)13:00/18:00
▼8月5日(日)12:00
シアターBRAVA!
全席指定-9500円
学生席(高校生以下)-3500円
(当日指定、整理番号付)
[劇作・脚本]井上ひさし
[演出]蜷川幸雄
[出演]風間杜夫/根岸季衣/六平直政/山崎一/大石継太/朝海ひかる/香寿たつき/吉田鋼太郎/他
※未就学児童は入場不可。
[問]シアターBRAVA![TEL]06-6946-2260
当日券情報も、こちら!
シアターBRAVA!公式サイト
http://theaterbrava.com/
●あらすじ
明治天皇大葬の日の夕刻。大帝に殉死することを決意した陸軍大将乃木希典が、夫人の静子様と共に、自邸の厩舎の前で3頭の愛馬に最後の別れを告げている。そこへ、出入りの酒屋の小僧である本多武松少年が現れ、この家の書生になることを志願する。実はこの少年、かつて日露戦争で乃木の軍にいて戦死した兵士の忘れ形見で、その後乃木本人とも因縁浅からぬ縁ができていたのだ。
一行が立ち去った後、夫妻のただならぬ様子に異変を感じた愛馬たちが、突如として人の言葉で喋りだす。そして、あろうことか3頭それぞれが前足と後足に分裂し、併せて六つの“人格”ならぬ“馬格”となって騒ぎだす。そこに近所で飼われている2頭の牝馬も加わり・・・。
(公式サイトより)