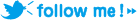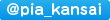ホーム > インタビュー&レポート > 京丹波町・和知に伝わってきた人形浄瑠璃の世界から “田舎”での創作活動まで、山口茜にインタビュー!
京丹波町・和知に伝わってきた人形浄瑠璃の世界から
“田舎”での創作活動まで、山口茜にインタビュー!
昨秋より、京都府の京丹波町に滞在し、フィールドワークを行ってきたトリコ・Aプロデュース代表・演出の山口茜。彼女がこの町に住む人々とのコミュニケーションや暮らし、自然のうつろいなど、体験したこと、五感で感じたものを作品にし、『和知の収穫祭』と題して発表するプロジェクトを、9月から行ってきた。
大迫でのオープニングセレモニーから始まり、9月末には京丹波町・明隆寺観音堂での『Fete-祝祭-』の上演。そしてフィナーレが京都市の元・立誠小学校 講堂で行われる京都公演「React upon-反応しあう-」だ。
モチーフはかの地に江戸時代末期から続く和知人形浄瑠璃の演目「長老越節義ノ誉(ちょうろうごえせつぎのほまれ)」。義人藤田猪兵衛・おこん夫婦の物語を安積三響が脚色作曲した物語を、京都公演では時代背景を現代に移行し、“出会わない男女”の物語として上演する。そして舞台の外では浄瑠璃を思わせる演出や、ピアノやコントラバスなどの生演奏、季節を歌う男声合唱が作品を彩ってゆく。
そこで、本公演目前にした今、作品について、そして京丹波町での暮らしなど、山口茜に話を聞いた。
―― こんにちは。ぴあ関西版WEBです。今日はよろしくお願いします。まず、京丹波町に移住されて約1年とのことですが、どうですか?
山口茜(以下、山口)「私は都会育ちなので、新鮮に感じてすごく幸せです。ただ、私には新鮮でも住んでいる方にとっては当たり前で、その辺の温度差も面白かったりします。おばあちゃんの農作業着がすごいオシャレなんですけど、おばあちゃんは『汚いから写真撮らんといて』とか言ったり(笑)」
―― 今回は『和知の収穫祭』と題して、お住まいの集落である大迫でオープニングセレモニーや観音堂での公演をされてきました。
山口「オープニングセレモニーはトウガラシ畑で行うはずだったのですが、天気が悪かったので私の住んでいる家で上演して」
―― どんなおうちなんですか?
山口「古民家です。かなり広くて、1階と2階合わせて8部屋ぐらいあります。丘からの景色が縁側から見えて、向かいの集落を見下ろす感じで、癒されますね。後ろには山もあって」
―― そうなんですね。京都公演は「React upon-反応しあう-」と題して行われますが、作品について改めて教えてください。
山口「和知人形浄瑠璃の『長老越節義ノ誉(ちょうろうごえせつぎのほまれ)』という作品は、村の重税を軽くするため、ある旦那さんがお上に直訴しに行くのですが、その途中で死んでしまう。そこで、その思いを果たすため、奥さんが長老山という大きな山を越えて行く。それで思いは果たされたのですが、山を越えたときには既に、おぶっていた息子が背中で死んでいたというお話です」
―― なぜこの演目をモチーフにされようと思ったんですか。
山口「人のために動く方はたくさんいますが、日本の社会を大きく変えるためには、自分の身を犠牲にして救うということがないと容易には変わらないという感覚があって。この作品には何か、そういうことを学べるなと思ったんです。あと、3月の震災でいみじくも現代社会における危機がかなりリアルに感じられたので、そういった危機も含めて、もう一度、『長老越』みたいに誰かが自分の身を呈して社会を救う話を書いてみたいなと思いました」
―― 人形浄瑠璃は京丹波に住まれてから出会ったのですか?
山口「浄瑠璃自体は元々、知っていました。和知浄瑠璃は他と違って、人形の顔がめちゃ大きいんですよ。そして、普通は3人で動かすのですが、一人で動かします。きっと、江戸時代に誰かが町で見て、『こんなんやってたし、俺らもやろうぜ』って出来上がったのではないかと」
―― 独特の進化を遂げているんですね。
山口「そうなんです。それが面白くて。和知には伝統芸能が結構残っていて、太鼓もあるんです」
―― 昔はどういう場所で上演されていたんでしょうね。
山口「たぶん、公民館とか、そういうところだと思います。今、私が住んでいる家が、人形浄瑠璃発祥の地のまさに真横なんです。そこに白い蔵が建っていて、人形はその中に収納されています。そういう蔵であるとか、観音堂でも行われてきたのではないでしょうか。観音堂では、昔は村人たちが集まって夜が明けるまで踊っていたというお話も聞きました。お話を聞いていくうち、偶然の一致みたいなこともあって、私はこの土地に呼ばれたのかなって思うこともありましたね」
―― お芝居の上演中には生演奏もあるそうですね。
山口「新井洋平さんというコントラバス奏者が本当に共鳴してくれているというか、作品づくりの上で何でもやってくれる頼もしい方です。作品がより重厚的になって、面白くなっていると思います」
―― 先ほど、「土地に呼ばれたのかも」とおっしゃいましたが、実際に住まれて作品を作るというのは、どんな感じですか?
山口「正直、温度差はあります。町の人たちは舞台よりテレビドラマを多く見られているということもあって。しかも、私が作るものは現代劇なので、わけがわからないと思うんです。『舞台』と聞くと、すごくわかりやすい作品を想定されていますし。ただ、そこも面白い課題やと思います」
―― 集落の方々が作品をご覧になって、何かリアクションはあるんですか?
山口「ありますね。『説明してくれたからわかったけど…』とか、いろいろ言ってくれます」
―― 大体、どのくらいの年齢の方がご覧になっているんですか?
山口「60歳、70歳の方ですかね」
―― それはすごいチャレンジですよね。ドラマが主流、その上で、その年代の方にわかっていただこうというのは。
山口「ご本人たちも言いたいことの一割も言っていないと思います。ほんまは『ええ!?』って思っているかもしれないですけど、オブラートに包んで喋ってくれますね。上演中、ずっとしかめ面で見てはる人もいはったし…」
―― 若い世代の方はいらっしゃらない?
山口「たまに見かけますが、それでも30歳以上の方ですかね。町で若手と呼ばれている人は大体、50代ですね。それはもう限界集落ですが、これから高齢化社会がますます加速しますし、ちょうどいいんじゃないかなとも思ったりもします。80年代の熱狂といいますか、劇団も盛り上がって、ぴあも盛り上がっていて、天井知らずの熱狂がありましたよね。『もっと上、もっと上!』という。私は、ああいう時期はもう訪れないと思うので、違う方向で何か見つけないといけないと思います。『将来の日本はみな、65歳以上が80%を占める限界集落になる』と誰かが本に書かれていて、和知は既にそうなので、ある意味で非常に先進的な場所だと思います」
―― 既に高齢化社会のコミュニティが成立している。
山口「和知のある京丹波町は、人が住んでいる場所が全面積のうちの1.5%なんです。後は山や田畑です。その1.5%に住んでいる人のうちの70%が、60歳以上なんです。自然と老人しかいないという」
―― その町で暮らして、作品への影響はどのように出ていると思われますか?
山口「それがあんまり自覚がなくて。今は身体的に刺激がなさ過ぎて、逆に感度が上がっている感じがすごくします。嫌な刺激もないから、気持ちも解放されていて。台本も書きやすいです。潜在的には何かが変わっているかもしれませんが、今は全くわからないですね」
―― なるほど。ところで、京都公演でモチーフにされている「長老越節義ノ誉(ちょうろうごえせつぎのほまれ)」ですが、実際、上演される際の物語の舞台は現代ですよね。
―― なるほど。ところで、京都公演でモチーフにされている「長老越節義ノ誉(ちょうろうごえせつぎのほまれ)」ですが、実際、上演される際の物語の舞台は現代ですよね。
山口「現代よりもうちょっと、未来ですね。今から4、50年後のお話です」
―― その4、50年後の社会を山口さんはどう考えますか?
山口「今、世界中でエネルギー問題が勃発していて、力を持つ人が少しずつシフトされていますよね。それに伴って、今まで有価値だったものがどんどん、無価値とされてきています。4、50年後の社会はそういうことがもっと加速しているんじゃないかなと思うんですが、それでもきっと、京丹波町はあんまり変わらないんじゃないかと。私たちは地位とか名誉とかお金とか、幻想を欲して、幻想に価値を見出しているけど、ここの人たちは確かなものを持っている感じがするんです。水、田畑、作物と目に見えるもの。そして、子孫を繁栄させるために全力を注ぐあたりも、すごく正しいと思って。あと、80歳のおばあちゃんが衛生委員とかやっているんです。求められているんですよ」
―― それは高齢化社会だからという理由もあるでしょうが、そうやって仕事でも何でも、求められることは生きがいになりますね。
山口「そうですね。そういうところもこの町はすごいなと思いますし…。端的に言えば、この『和知の収穫祭』も、みんなもっと田舎に住んだらいいのにと思う気持ちをどうやって作品にするかという試みで(笑)」
―― 『田舎に泊まろう』的な。
山口「はい。移住はなかなか難しいけど息抜きするにはよい場所だとか、ちょっと滞在して自分を取り戻すとか、そういうことがもっと認知されたらいいなと思っています」
―― なるほど。今日はありがとうございました。
京丹波町・和知の風土も真空パックにしてお届けする『和知の収穫祭』フィナーレ、京都公演「React upon-反応しあう-」は、10月28日(金)より元・立誠小学校にて上演される。山口が感じた土地の温度、空気、匂いをぜひ、劇場で一緒に体感してほしい。
(2011年10月21日更新)
Tweet Check

公演情報
トリコ・A 「和知の収穫祭」
発売中
Pコード:414-541
●10月28日(金)~31日(月) 19:00
元・立誠小学校
自由席2500円(整理番号付)
[劇作・脚本][演出]山口茜
[演奏][音楽]新井洋平
[出演]岩田由紀/筒井加寿子/鈴木正悟/仲野毅/松本芽紅見/中嶋やすき/古屋正子
[問]トリコ・A プロデュース[TEL]080-3792-9906
プロフィール
トリコ・Aプロデュース
'99年、山口茜の劇作・演出で演劇を上演する団体として京都で結成。'03年、名称をトリコ・Aに変更し、同年『他人(初期化する場合)』(脚本:山口茜)で第10回OMS戯曲賞大賞を受賞。'07年には『豊満ブラウン管』で「若手演出家コンクール2006」最優秀賞を受賞した。2007年には文化庁新進芸術家海外留学制度派遣員(フィンランド)に山口が選抜され、日本での活動を休止。そして'09年の帰国後より、活動を再開。現在に至る。