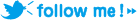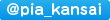ホーム > インタビュー&レポート > 「怪談はただ、怖いだけじゃないんです」 稲川淳二に怪談の魅力についてインタビュー!

「怪談はただ、怖いだけじゃないんです」
稲川淳二に怪談の魅力についてインタビュー!
今年で19年目を迎える稲川淳二の『怪談ナイト』。関西には、8月20日(土)・21日(日)に行われたシアターBRAVA!での公演を皮切りに、奈良、京都、滋賀に登場する。『怪談』と聞くと、ただ単に『怖い』というイメージを抱かれる方も多いかもしれないが、そこには、ただ怖いだけでなくエンタテインメント性や時代性など様々な要素が含まれており、なにやら相当“楽しそう”なのだ。そこで、稲川淳二から直接、怪談の面白さ、魅力を聞いた。
'93年から始まった稲川淳二の『怪談ナイト』。夏から秋にかけて日本全国を回り、怪談という手法で人の心や風土、時代などを語り継いでいる。熱烈なファンも各地に存在し、毎年、稲川がやってくることを楽しみにされている方も多いという。
そんな『怪談ナイト』はもちろん、東北地方にも毎回、訪れていた。が、今年は3月11日に発生した東日本大震災の影響で、東北各地のホームグラウンドにしていた会場が使えなくなったり、開催を断念した県もあったそうだ。
稲川淳二(以下、稲川)「震災でいつも使っている会館もやられちゃったんですよ。あれは使えない、これは使えないって。これは(開催は)無理だって言ってたんですけど、『こういうときだから稲川さんの怪談を聞きたい』、『稲川さんの顔が見たい』っていう声があって。こんなジジイの顔ですよ。この舞台では、家の中のセットと自然のセットを隔年で置いているんですね。私はいつもそのセットの中のジジイなんですよ。田舎のジジイ。夏になったら、田舎のジジイのところに皆さんが都会から遊びに来るんですよ。で、ちょうどお昼を食べ終わった頃にジジイがぽつぽつと怖い話をしていくというシチュエーション。だから、私は、話し手というよりも、田舎のオヤジなんですね。昔、親やおじいちゃん、おばあちゃんが孫に聞かせた、そんなシチュエーションでやっているんですね。自分としてもそうなりたいし、そうでありたいし。どうやらみんなもそう思っているみたいなんですよ」
―― 怪談を通じて“故郷”のような存在となっている稲川。自身がそれを痛感したのが、例年行われる『稲川祭り』なんだそうだ。
稲川「夏の前に『稲川祭り』というのをやるんですよね。今年で9年経ったのかな。私が企画したわけじゃないんだけど、自然にできちゃった。ファンの方が大阪とか、名古屋とか、北海道とかから来るんですよ。今年はそれで三浦半島の方面に行きましたけど、何もしないんですよ、イベントもしない。ただブラブラして、バーベキューして、おしゃべりするだけ。でもとってもまとまってるんですよ。みんな仲良くなっちゃって、親類同士みたいな感じがするんですよ。葬式の時とかそうでしょう、じいさんやばあさんが亡くなったときって、亡くなった人がいるわりには、『しばらくだねぇ』とかやってないですか。あんな感じなんですよ。私、思ったの。もし私が亡くなったら、この人たちは(葬式に)来てくれるだろうと。それで『しばらくだねぇ』ってやってんだろうと思いました」
―― さらに、その光景から見えたものがあるという。
稲川「そういうことが怪談にもあるようですね。怪談は人をつなげるみたい。怪談って年齢だとか人格だとか、立場だとか、全部超えちゃうのね。不思議だなぁと思ってねぇ。自分が怪談を話していながら、教わることが多いですね。たぶん、怪談ってそうなんですよ。だから、僕はホラーじゃないんですよね。ホラーは襲ってくる恐怖ですし、実際には起きない。『もしあったら』という世界ですから。怪談には自分がふっと振り返ると『あったよな、子供の時こんなことが』とか、『あそこのあれはそうだよな』とか考えさせることがあったりするから、怖かったりするんじゃないかなと思うんですよね」
―― 年に一度、“田舎のオヤジが待つ場所”へ訪れることを楽しみにしている人がたくさんいる。特に今年は、仙台、青森公演においては、例年以上にチケットの売れ行きが早いそうだ。
稲川「(東北の方から)手紙が来ちゃったんですよ。『今年は被災しちゃったんで夏は行けそうにない』って。『でも、冬に来てもらえないだろうか。それだったら自分も立ち直って、行けると思うから』って。もう、胸が痛みますよね。こんなね、小汚いジジイが怪談を話してるんですよね。私なんかほとんど妖怪の世界ですからね。ほんと、ありがたい。もったいないくらいですよ」
―― この怪談ナイトの舞台美術は、前述したように、隔年で屋内、屋外のシチューションにしている。その舞台美術も見どころの一つだ。
稲川「この舞台だけは自慢しているんですよ。いろんな舞台を観に行くけど、私の舞台ほどよくできているものはないですよ。去年は土手で、それが本当によくできていて。土手の脇に電信柱が立っていて、大きな橋が架かっていて、その下には川が流れていて。私はその川のところで喋っているんだけど、空の色がだんだん変わって、月も動いているんですよ。それ、僕は見えないんですよ。僕は客席の方を向いているから。その前の水車小屋の年なんかは感動だったな。本当に水車がぎーっと音を立てながら回っていて……。ぎーっ、ぎーっ、ギャー!!! 舞台は楽しいですね」
―― 今年は屋内にあたる年。どんな舞台美術になるのだろう。
稲川「闇っていうと、暗いのは当たり前ですけど、まあ、雪もそうだけど、物を隠すじゃない。ホラーって見える恐怖、襲う恐怖があるんだけど、音が聞こえない恐怖、何も見えない恐怖ってありますよね。それ、日本人が持っている絶対的な文化というか、そういう資質なんでしょうね。見えないからこそ、そこにいるのかもしれないという気持ち。それで、逆に見えなかったものが見えてしまうという怖さを話そうかなと。で、順番からいくと、去年は屋外だったから今年は屋内なんですよ。今年は屋内なのに、私はその家にいないんですよ。でも屋内っていうのはわかる。窓が開いているから。窓が開いているから、客席からは室内が見えるんですよ。そういう状況なの。実際にドラマがあるのは、家の方なんですよね。結構いい感じですよ。闇になったら窓のところだけ明るくなって。あとはどうなるか、わからないですよ。楽しみなんですよ、毎回。今回は、状況が変化する室内の前で私が話をするという設定にしようと思ってます」
―― また、毎年変わらない世界観もそこにはあるそうだ。
稲川「昭和中期、オールウェイズの世界の前で怪談をするという。いつも大体、あの時代なんですよね。無意識でやっているんだけど、舞台美術を考えてくれる江頭良年先生もそういうのが好きみたいで。ずっと昭和の時代。私らが子供のころ、駆けまわったり、幽霊が怖いとか言っていたり。懐かしいですよね、本当にね」
―― 『怪談ナイト』はもちろん、関西でも公演を行ってきた。関西という土地柄においては、ほかの地域にはない反応や手ごたえなど、あるのだろうか?
稲川「格段いいですね。ほかの地域ももちろん、みんな本当にいいんですよ。でも、やっぱりね、関西の影響って相当大きいと思うんですよね。阪神タイガースのファンの方が風船を飛ばしたりすると、みんな真似したりするでしょ。あんな感じ。今、波及してどんどん広がっていますよ。私の知り合いでも『東京の公演ってすごい盛り上がるね』って言うの。でも、『いや、大阪はすごいんだ』ってあまりにも聞くもんだから、その話を聞いた東京の人間が大阪のファンを観に来ますもんね。面白いですよ。すごいノリようですよ。それが始まった瞬間、すごい勢いでもって声援が飛びだして、初めて見る方なんかは『これ本当に怪談?』って言いますよ」
―― そんな中、大阪ならではのエピソードもあり…。
稲川「今はね、会場が大体決まっていますけど、前は大阪はいろいろな会場でやったんですよ。以前やったところ、あれはどこだったかな、公演が終わったらさ、暴走族がダーっと並んでるんですよ。そしてみんなが私が乗ったタクシーを追ってきたんですよ。で、最後に一台ずつ手を振ってきて。20何台、いましたね。それとか、ぶらぶら歩いていたら昼間から酒を飲んでるホームレスの人がいて。私を見て『稲川さん、がんばってください!』って。そして舎弟みたいな方に『稲川さんに酒あげろ!!』って言うの。それで酒を出したら、『バカ野郎! 新しい酒だよ!』とか言うんですけど、新しい酒も古くてね(笑)。それで『がんばってねー! 怪談がんばってねー!』って。うれしかったなぁ」
―― 温かな声援をはじめ、大阪は力をもらえる場所と言う稲川。そして、舞台を行う上でも大阪ならではの感触を得るとも。
稲川「野暮な真似はできないですね。だませないんですよ。だから夢中でやりますよね。というより、やらされちゃう、こっちが。怪談というのはどうやら聞かせるでもなく、見せるでもなくて、あれは見る側(観客)がうまいんですよ。どんどん引っ張っていくから、こっちがどんどんやらされちゃう。どんどん気持ちよく乗ってきますよね。そうすると、普段だったら3つしかない言葉が5つも6つも出てくるんです。言葉も状況も。大阪で舞台をやったらぐんっとノリますよね。芸人でもそうですよ。大阪のテレビ番組なんかに出ると、とたんに話がうまくなって帰ってきますよ。大阪ってそういう土地柄なんですよ、きっと。縁起のいいところじゃないですか」
―― そんなことを経験しているからこその怪談観もあるようで…。
稲川「私、思うんだけど、怪談って暗くて寂しいイメージがあるでしょうけど、逆ですよ。怪談ってけっこう楽しくて、縁起がいいんですよ。楽しいときしかやらないですから。幽霊を見るときって幸福度が増しているときなんですよ。自然体でリラックスしているのに、気がついたら興奮している。そうしたときに人間は幽霊を見たりするんですよ。で、幽霊を見たら出世するっていうことが昔はあったんですね。歌舞伎役者なんかは特に。幽霊を見るぐらいの感性がないとダメだってことを言われていたりもしたんですね。役者として。だから決して、怪談というのは悪いことじゃないですよね」
―― また、“怪談の現場”や、その成り立ちも語る。
稲川「怪談をやっていて、楽しいこと、心が癒されること、豊かになることは多いですよ。というのは、楽屋で分かるんですよ。私も若いころは、暴れたり、笑ったりするのが好きだったんですけど、笑う仕事というのは意外と楽屋は神経ピリピリなんですよね。笑いをやる人は大変ですよ。本番前はナーバス。大声で何度もネタを繰る声が聞こえてくるし、じーっと考えている人もいるし、何かピリッとしてますよ。でも怪談はすごいんですよ。うるさくて。楽屋でもギャーギャー、ワーワー騒いだり、悲鳴を上げたりするんですよ。ひどい時は本番なのにスタッフが悲鳴を上げたりするんですよ。でも許しちゃう。みんな幽霊のせいにしちゃうんですよ。『私じゃない、幽霊だ』って。しまいには幽霊も怒りますよ。だから、意外に怪談で笑ってますよ。人間というのは、怖さを共有するのが楽しいんでしょうね。学校の怪談と同じですよね。怖さを共有するって楽しいんですよ、結構。で、怖い方が面白いんです。家に近くに謎のスポット、異次元があるような。家のそばに池がある。あの池には何かあるんじゃないかとか、家のそばにこんなものがあって怖い。昔はそういうものがたくさんあって、それが結構、楽しかったんじゃないですか。故郷に帰るとあったりするじゃないですか。『あのお地蔵さんとこの階段、何段目は上がっちゃいけないよ』とか、『誰々さんの後をついていっちゃいけない』とか、『この場所を3人通ったらいけない』とか、あるじゃないですか。あれ、楽しいですよ。子供って自分で作るんです、そういうことを。その延長に『怪談ナイト』があると思ってくれたらいいですね」
―― そして、怪談をあるものにたとえて…。
稲川「こういう言い方はおかしいけれども、喜劇じゃないかっていうくらい盛り上がるんですよ。悲鳴が上がったり、椅子から落っこちたりするんですよ。何人も悲鳴が上がって、そういう連鎖反応が起こって、キャーキャーなって。次に笑いが来ると、これがまた止まらないんですよね。みんなゲラゲラ笑って。で、またシーンとなる。お客さんもそれが楽しいみたいですね。怪談っていうのは駄菓子屋みたいなものがありますからね。懐かしい味というのかな。表通りにあるようなしゃれたお菓子屋じゃないんだけど、横町にある古い駄菓子屋みたいな感じで、子供も大人も、おじいちゃんもおばあちゃんも好きな感じというのかな。年の差も関係なく、つながるものがあるみたいなんですよね。お客さんの年齢差がすごいですよ。上は80いくつ、下は小学生くらいのお子さんがいらっしゃって」
―― 幅広い年齢層に支持されている『怪談ナイト』だが、過去には名物のお客さんもいらっしゃったようだ。
稲川「大阪公演にいつも来るおじいちゃんがいて、いつも一番前に座ってるんですよ。一番前に座っているということは、いつも早くから並んでるんです。こっちもなんとかしてあげたいから、いつもスタッフに『後であの人に声をかけてくれ』って言うんですけど、いつもすっと帰っちゃうんですよ。幽霊じゃないですよ、ちゃんと生きてるんですよ。で、そのおじいちゃん、私が話をしていると失神するんですよ。あれ、怖いですよ。目の前にいるからよく見えるんですけど、盛り上がるじゃないですか、そしたら次の瞬間、バタっと倒れてるんですよ。『うわ~、どうしよう!』って思うんですよ。死んだら困るし。話はやめられないし。で、様子を見て、まずかったらライブをやめようと思うんですけど、生きてるんですよ。ハッと目を覚まして。それでまた途中でバタっと倒れるんですよ。それでね、このおじいちゃんが来るたびにドキドキするんですけど、すごくうれしくて、毎年、会いたい、会いたいって思ってるんですけど、とうとう何年か前からピタッと来なくなった。相当高齢の方だったからなぁ、恐らく亡くなったんじゃないかと思うんですけどねぇ」
―― また、北九州にも印象に残るお客さんがいたそうだ。
稲川「この方ももう亡くなられていると思うんですけど、私がこのツアーを始めたすぐのころに、当時84歳のおじいちゃんが、ご自分が若いころに実際に体験された話を200字詰の原稿用紙にびっしり書いて送ってくれていたんですよ。当時ですから、私は今よりずっと若くて、こんな人生経験の浅い人間に、戦争の時代から生きてきた人が話を書いてくれるのがすごくうれしくてね。大先輩ですからね、人生の。怪談っていうのは不思議だな。きっとそれは、『私の話をあんたがつないでくれよ』ってことだと思うんですけどね」
―― 『怪談ナイト』を通じて、様々な人と出会い、心の交流も行われてきた。しかし、そんな中で時代の移り変わりには抗えないものがあるようで…。
稲川「もう19年もやっていると、ずいぶん変わりましたよ。初期の頃にあった公衆電話の話なんか使えない。公衆電話を知らない人もいるから。ダメですよね。あの頃は、電話のやりとりなんかですごくリアルで面白い話があるんだけど、今は携帯電話があるから、どんなところでも話ができちゃうんだもん。山の中でも。状況が違うじゃない。また携帯電話が出始めたころなんかは、性能が悪いからね、トンネルに入って音が消えてってなるじゃない。今は『え~、何それ~』だもんね」
―― 怪談を語る上での絶好のシチュエーションは他にもあり、そこもまた時代の流れを感じるとしみじみ。
稲川「大体、トンネルも変わりましたよね。昔のトンネルって手掘りが多かったんですよ。今はずいぶん直ったり、使わなくなったトンネルもあるでしょう。昔のトンネルって岩場を掘ってたんですよね。今は違うんですけど。それで、真ん中に行くにつれて狭くなるんですよ。天井が落ちてくる。それは強度のためなんですよ。トンネルって、平らに掘ってしまうと力が真ん中に集まるから潰れちゃうんですよね。ところが、真ん中に行くにつれて高さが狭くなるように掘ることによって、強度が強くなるんですよ。で、そういう掘り方をやっちゃうと、空気の流れが速くなっちゃうんですよ。すると、遠い向こうの声が耳元で聞こえたりする。そういう現象が起こる。だから怖いことがいくつも起こったりするんですよ」
―― 例えば、こんなエピソードが…。
稲川「実際にこんな話があったりね。戦争中なんですけど、ある夫婦がいて、この旦那さんが徴兵を拒否するのに自分の指を落としちゃって。それで村から追い出しを食らうんですよね。そのときに、奥さんが家に一人でいるときに家を焼かれてね、トンネルの方へ逃げるんですよ。村を出ようとして。それで、トンネルに向かって走ってきたトラックの荷台の上にポーンと降りたんですけど、トンネルの真ん中の天井までが狭いもんだから、そこでバーンと体を削られたとか、そんな話があるんですよ。でも、そんな話をしたって、みんなわかんない。みんなが思うトンネルって、電気がついていて、明るいっていう世界でしょう。時代はどんどん変わりますよね」
―― さて、この夏、関西でも様々な節電対策がなされている。最後に、『怪談ナイト』での節電対策はいかなるものか、聞いてみた。
稲川「難しいなぁ。余分な光は要らないけれども、あれこれ使えないっていうのもね…。福岡の公演は能楽堂なんですよ。空調がないんです。おまけに、そこに座布団を引いてびっちり座るんですよ、人が。もうね、くそ暑いんですよ。でも、誰も文句を言わないんですよね。それでもできるもんなんです、やっぱり。昔はそうでしたもんね。だからやればできるんじゃないのかな。まあ、今の家は密閉度が高いから、難しいこともあるけど、私が子供のころなんかは家でエアコンなんて見たことなかったし、扇風機もなかった。でもちゃんと風が来てたしなぁ…。やってみればできるんじゃないんですかね。いい経験になりますよ、きっと。今年は、少し空調を押さえた会場で、ひんやりしてもらえたらいいなって思いますね」
(2011年9月 1日更新)
Tweet Check
MYSTERY NIGHT TOUR 2011 稲川淳二の怪談ナイト
公演内容
舞台は二部構成。怪談が90分、心霊写真解説が30分、それぞれ行われる。怪談は稲川淳二が毎年、1年をかけて集め、まとめあげた新作を披露する。このフィールドワークを通じて稲川は「怪談とは考古学の壺のようなものである」と説く。そして拾い集めた断片的な破片をつなぎ合わせると、一つの形が見えてくるのだそう。そして、心霊写真解説では、大型スクリーンに稲川秘蔵の写真を映し出していく。そこではとにかく怖い、“本物”の心霊写真が見られる。
LIVE DATA
関西公演
発売中
▼9月23日(金・祝)17:00
大和高田さざんかホール
Pコード:619-195
▼9月24日(土)17:30
京都会館 第二ホール
Pコード:619-025
▼9月25日(日)16:00
東近江市立八日市文化芸術会館
Pコード:619-195
[一般発売]全席指定-5000円
※未就学児童は入場不可。
[問]キョードーインフォメーション
[TEL]06-7732-8888
プロフィール

稲川淳二
いながわじゅんじ●'47年生まれ、東京都出身。タレント、工業デザイナー、怪談家とマルチに活動。工業デザインでは、平成8年に通商産業省選定グッドデザイン賞「車どめ」を受賞した経験も。怪談を語らせれば右に出るものなし、エンタメ界を代表するストーリーテラーの一人だ。
9月24日(土) 公演情報
http://ticket.pia.jp/pia/event.do?eventCd=1111886
9月23日(金・祝)・25日(日) 公演情報
http://ticket.pia.jp/pia/event.do?eventCd=1116742
稲川淳二公式サイト
http://www.j-inagawa.com/