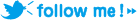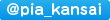ホーム > インタビュー&レポート > 桃園会の最新公演は岸田國士、菊池寛の戯曲を3話上演 作品それぞれの見どころを主宰・深津篤史にインタビュー!

桃園会の最新公演は岸田國士、菊池寛の戯曲を3話上演
作品それぞれの見どころを主宰・深津篤史にインタビュー!
間もなく開幕される桃園会の最新公演は、岸田國士の『動員挿話』『ぶらんこ』、菊池寛の『父帰る』の3話オムニバスを上演する。社会、家族、夫婦と視点を徐々にクロースアップしてかつての時代を描いてゆくのだが、そこには現在にも通じる観念があることに気づくだろう。また、『動員挿話』『父帰る』は、桃園会の主宰であり演出家の深津篤史にとって、自身の演劇史で重要な位置を占めている作品でもあるという。そこで、これら作品を選らんだ理由や作品に対する思いを深津に聞いた。
--@ぴあ関西です。今日はよろしくお願いします。まず、今回上演されます岸田國士の『動員挿話』『ぶらんこ』、菊池寛の『父帰る』の、深津さんからご覧になった魅力を教えてください。
深津篤史(以下、深津)「岸田國士さんと菊池寛さんは、作風はちょっと違うんですけども、いずれも大正から昭和初期ぐらいに描かれた作品で、100年くらい前の古いお話です。100年以上前の本ですが、現在上演しても、例えば言葉遣いが若干古いところもありますが、それでも古めかしいという印象をお客さんにはあまり抱かせないんじゃないかなと思います。特に岸田さんなんかは、台詞が会話体としてとても洗練されているので、そういう印象も少ないんじゃないかなと思いますね。描かれている内容も、夫婦の日常や、家族のお話で、『動員挿話』は戦争のお話でありますが、その中での夫婦の愛とか、そういったお話なので、遠いところのお話ではないですね」
--舞台では時代背景も当時のまま、描かれるんですか?
深津「そうです。『動員挿話』は日露戦争の時代なので1904年の設定です。で、『父帰る』がその後。どちらも明治の末期ですね。そして『ぶらんこ』は、大正ぐらいの設定ですね」
--これらの作品はいずれも、夫婦や家族のことが描かれていますが、個人的には近頃は家族のあり方とか、夫婦のあり方が変わってきていると思うところがあるのですが、そういう部分で現在との共通点や相違点をどうご覧になっていますか。
深津「どうなんでしょうね。夫婦のあり方でいうと、今の夫婦と、昔の夫婦のあり方のどこに違いがあるのか僕はわからなくて。別にそれは変わらないんじゃないのかな。家族のあり方においても、昔は男性主権というか、父親の力が強かったので、そういう意味合いにおいては今とちょっと違うかもしれないですが、でも、『ぶらんこ』に出てくる夫婦も強権的な力を持った夫というわけではないし、『父帰る』の父親は家を出て行く“放蕩したお父さん”で。別にそんな珍しいことではないと思いますね」
--なるほど。逆に今と変わらない。
深津「あるとしたら、親父が放蕩して家族を捨てて、行方をくらますということが、今の時代ではあの時代よりもちょっとスケールが小さくなるという、そのくらいの差でしょうね」
--『動員挿話』と『父帰る』は以前、2005年に上演されていますね。今回はその2作品に『ぶらんこ』を足されています。足された理由は何かあるんですか?
深津「ひとつは単純な理由で、『父帰る』は2005年に、第5回クラシックルネサンスで演出しまして、『動員挿話』は新国立劇場で同年に同じく、演出しました。その後、2008年にまた新国立劇場で再演して、2007年にも関西でやっているので、当時ご覧になっているお客さんはいるだろうと。なので、桃園会の本公演としてやる『動員挿話』と『父帰る』だけではちょっと弱いので、新しく未上演の作品を1本加えるのはどうかと思ったことですね。時間的にも、『ぶらんこ』を足して1時間40分前後でちょうどいいなと」
--内容的にはどうでしょうか。
深津「ほかにもいろいろ探ってみたんですが、『動員挿話』が戦争のお話で、夫婦の愛がメインにあるわけですけど、その夫婦の愛を引き裂いているのが社会であったり、世間体であったりで、個人と社会の関係になる。『父帰る』だと家族の話になって、『ぶらんこ』になると夫婦のお話になる。そういう大きな視点から小さな視点まで、満遍なく入れようと思いました」
--視点の動きが面白そうですね。どういう順番で上演されるんでしょうか。
深津「『動員挿話』、『父帰る』、で、『ぶらんこ』ですね。大きな物語から小さな物語に収斂していく形になります」
--先ほど、岸田さんと菊池さんが似ているところもあるとおっしゃっていましたが、それぞれ作家さんの魅力をもう少し詳しく教えてください。
深津「菊池寛に関しては、私は『父帰る』しか演出していなくて、この魅力に関してはうーんどうかなっていうのもあったりして。魅力を語るのは難しいですね…」
--お話の上では?
深津「単純に親父がいなくなって、その父親が帰ってくるというお話で。母親とその家族は父親を迎え入れるのか入れないのかという。台本上では迎え入れるんですけど、それはやっぱり古い時代の話なので、迎え入れてしまう。ただ、家のお金を全部持って逃げた放蕩親父なので、家族は相当、苦労してひもじい思いもしてきたんですね。特に長男はお父さんの代わりをして、次男や長女を何とかするためにがんばって働いて。小さいときには、一度は一家で身投げをして。でも、助かって。自殺まで試みた家族なんです。そんな家族のもとに20年ぶりに落ちぶれた父親が帰ってくるわけですが、それをすっと許すんです。台本上では最終的にすっと許してしまうんですけど、これを今の感覚として『許せるのか』と考えると、ちょっと難しいよなと。『父帰る』というお話は、『今の我々は、本当に父が帰ってくることを許容できるのか』というところで考えると難しいなと思うんですね。この舞台では、そういうところを描きます。『父帰る』という物語自体にすごく魅力があるわけではないんです。『父親は本当に帰ってきてもいいのか』というところで、出演者も、お客さんも考えるという感じですね」
--2005年に第5回クラシックルネサンスで上演されていますが、当時の演出と変わってくるのでしょうか?
深津「私の『父帰る』は、クラシックルネッサンスでやったパターンとほぼ同じですね。ちょっとは変えてますけど、ほとんど変えずにやります。第5回クラシックルネサンスでは、『台本は一言一句変えない』というものがセオリーとしてあって。台本を変えてもいいとなると、どうしてもそこで楽をする人も出ますから、その骨子としては『近代劇と正面から戦いましょう』という企画であったので、台本は変えちゃダメだったんです。でも、『父親はやっぱり帰ってこれないよね』と私は思ったので、台詞は一言も変えていませんが、父親も出演しません」
--台詞は変えていないけど、お父さんは出て来ない…。
深津「出て来ないので、許すも許さないもわからない。お父さんが出てこない『父帰る』という初演のパターンをそのまま上演します。これは踏襲してやろうかなと。で、岸田國士さんはうちでもしょっちゅうやっていて。『動員挿話』だけちょっと特別で、それ以外の作品は結構、台詞劇というか、長い台詞が少ない、会話体のお話が多いんですね。『動員挿話』はネタが戦争なだけに岸田國士さんの作品の中では異色というか、長台詞が多くて物語が盛り上がるんです。『ぶらんこ』とか他の作品は結構、日常を描いた作品が多くて、話の内面には大きな盛り上がりがあるんですけど、表面上は何か大きな事件が起こるわけじゃない。そんな山場があるわけじゃないんですね。でも『動員挿話』だけ山場があるお話で。だから『ぶらんこ』と『動員挿話』を比べると、タッチが違うといえば違う。『ぶらんこ』には山場がないですから。ただ、旦那さんが夕べ見た夢の話を、朝の忙しい時間にしゃべるっていう、コメディタッチのお話です」
--何も知らずに見たら、同じ人の作品だとわからないかもしれませんね。
深津「かもしれないですね。私も、『動員挿話』はタッチがちょっと違うと思いましたからね」
--『動員挿話』も再演になりますが、こちらの演出はどのようにされるのでしょうか。
深津「6年前とは変えます。初演を新国立劇場でやって、その後、再演でまた新国立劇場でやって。それから名古屋、西宮の芸術センターでやりまして。キャパシティが350とか、400とかの劇場で上演しました。今回はウィングフィールドさんですから、キャパがまったく違います。その分、演出が変わりますね」
--6年前に比べて、深津さんの中で「演出のこういうところが変わったな」とか、自覚される部分はありますか?
深津「ちょうど『父帰る』から『動員挿話』を上演した2005年から2008年ぐらいの3年間が、自分の演出のやり方が変わってきた時代だし、いろいろ実験をしながら、ある程度自分のやり方が固まったときだったりするんですね。なので、最初の立脚点みたいなものが『父帰る』と『動員挿話』であったりして。それで賞をいただいたので、そこから今の流れが始まっているわけです。外部演出の仕事などが増えたのもそういうことですし。今回は最初の立脚点みたいなところに一旦立ち戻って、今の私の原型はこの辺にあったんですよというところを見ていただくのもありかなと。もちろんあれから6年が経っているので、6年分の積み重ねも加えて。でも、元々はこんなところから始まっていますと。例えば、演劇玄人のお客さんに対しては『今の私の演出の手法の原点はここです』と。こんなところから実は始まっていますということを知っていただくことで、『あ、なるほど、だからああなっているのか』ということがわかるだろうし、楽しんでいただくことができるだろうと思います」
--初めて深津さんの作品をご覧になる方はどうでしょう。
深津「『父帰る』初演のときにも演劇素人のお客さんも来たわけで、例えば、こういう近代劇って、たとえですけども悪い言い方で言うと、新劇系の方がちゃんと作り込んで、リアリティのあるセットで、着物とか着て、古めかしいイメージで演じるという固定観念みたいなものが、近代劇をまったく見たことがない人にはあると思うんです。『岸田國士って誰? 菊池寛って誰? 名前は聞いたことあるけど』という人にとっては、新劇の劇団さんがそんな感じでやっているものだと。もちろん、いろんな手法があって、演出家が100人いれば100の手法があるんだけれども、近代劇だったらちゃんと家のセットがあって、そこでしゃべるのかなとか、今回は『動員挿話』から始まるので、『動員挿話』だったら少佐の家から物語が始まるんですけど、畳が敷いてあって、襖があってみたいな、そんなところから始まるのかなって思うでしょうけど、そういうものがほとんどない。一応、現代小劇場演劇をやっている桃園会の上演する近代劇はそういう感じ、それは別に奇異をてらっているわけではないんですが、でも、お客さんがご覧になって、まず古臭さとか感じないだろうと思いますし、セットがほとんどないんだけど、こんなふうにできるのかと思われるんじゃないかと。演劇素人のお客さんの固定観念みたいなものは壊せるかなと思っています」
写真はすべて、
桃園会 第39回公演『a tide of classics 三好十郎・浮標』
~精華演劇祭2010 SPRING/SUMMER・第2回むりやり堺筋線演劇祭 参加公演~
作/三好十郎 演出/深津篤史
於/精華小劇場
2010年8月4日~8日
撮影/白澤英司
(2011年7月 7日更新)
Tweet Check



作品紹介
『動員挿話』作・岸田國士
日露戦争が勃発し、主人である陸軍少佐から、共に戦地に赴かないかと進められる馬丁。しかし、馬丁にはすぐに頷けない理由があった。馬丁の妻は愛する夫を死と隣合わせの戦地などに行かせたくないのである。長年世話になった主人との義理、自分を支えてくれている妻への愛に深く悩みながらも、馬丁が決断したこととは…。そして、夫の決断に妻が起こした行動とは…。
『父帰る』作・菊池寛
小さな都会の中流階級の家。母、長男、次男、長女の四人暮らしでのどこにでもありそうな平和な家庭。だが、その父は20年前、家族と捨てて情婦と共に行方をくらましていた。ある日突然、その父が落ちぶれて帰ってくる。母と次男は年老いた父を迎え入れようとするが、父のいない間、家族を支えてきた長男は断固として受け入れようとしなかった。再び出て行こうとする父に家族はどう向かい合うのか、本来あるべき家族の姿、肉親間の愛憎を描いてゆく。
『ぶらんこ』作・岸田國士
とある夫婦の日常。妻は朝食の用意をしている。夫は起きるやいなや、妻に昨晩自分が見た夢の話を語りだす。調子よく夢の話を続ける夫、その夢の話を拒むかのように現実的な日常を続ける妻。そんな最中、夫を迎えに来た同僚がなにやら妻に頼みごとをしようとして…。夫と妻、男と女の差異とすれ違いを描いたコメディ作。
公演情報
〈第3回むりやり堺筋線演劇祭〉「a tide of classics ~動員挿話・ぶらんこ・父帰る~」
▼7月12日(火) 19:30
初回特別料金2000円
▼7月13日(水)~17日(日)
水木金19:30 土15:00/19:00 日15:00
一般3000円 学生2000円
ウイングフィールド
[劇作・脚本]岸田國士/菊池寛
[演出]深津篤史
[出演]酒井高陽/八田麻住/亀岡寿行/はたもとようこ/森川万里/橋本健司/長谷川一馬/寺本多得子/出之口綾華
※この公演は終了しました。