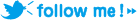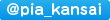ホーム > インタビュー&レポート > 京都と愛知の舞台人たちが集結して 京都舞台芸術協会初のプロデュース作品『異邦人』を上演!

京都と愛知の舞台人たちが集結して
京都舞台芸術協会初のプロデュース作品『異邦人』を上演!
間もなく上演される京都舞台芸術協会のプロデュース公演『異邦人』。インターネットで募った自殺志願者が体験する世界を、時にファンタジックに、時にリアルに描いた、魚灯・山岡徳貴子の戯曲を、烏丸ストロークロックの柳沼昭徳が演出。そして演じるのが関西一円の劇団よりオーディションで選ばれた役者たちだ。京都舞台芸術協会にとっても初の試みともなるこのプロデュース公演について、同協会理事長のごまのはえ(ニットキャップシアター主宰)と、演出家の柳沼昭徳に話を聞いた。
―― まず、初のプロデュース公演作品を山岡さんの『異邦人』に決定された理由を教えてもらえますか。
ごまのはえ(以下、ごま)「僕とアトリエ劇研のディレクターでもある田辺剛のふたりが企画委員ということで、去年の10月くらいに演出家を柳沼くんに決めさせてもらって。そのあと、失礼だけども、あまり知られていないれども面白かった作品はないだろうかという視点で京都の劇作家の作品を3人で探しまして、柳沼くんが『異邦人』を推薦してくれました」
柳沼昭徳(以下、柳沼)「山岡さんと僕は、劇作と演出という劇団への関わり方が一緒で、劇作に関して一番重視しているのも同じく空間性なんです。それは、演劇特有の再現不可能な空間を作ることを目的としていて。で、空気感であったり、温度であったりという要素を演出で加えていくんですけれども、山岡さんの『異邦人』は台本に書かれていないことがすごく多い作品だったんです。'05年の初演も観たんですが、観たときに何て豊かな作品なんだと驚いたんですね。台本だけ読むと普通の、淡々と進んでいくような会話劇なので、『あれ?』と思ったんですが。よくよく読んでいくと『ああそうだ、山岡さんはこういう作り方をする人だったなぁ』と思って。そこに一番強く惹かれましたね」
―― その台本には書かれていない、行間の部分が豊かだったと。
柳沼「そうですね。既成の脚本を使うときには書き直しもあるんですが、そういうことをあまりせずとも、行間の部分と私の演出とを混ぜることでコラボレーションができるんじゃないかと思いました」
―― 初演をご覧になったときに、演出家としてはどう観ていらしたんですか?
柳沼「私も山岡さんも基本、宛書なんですけども、山岡さんは人を見ているところがすごく鋭いというか。俳優さんには自分の魅力を意識してやってらっしゃる方がたくさんいらっしゃるんですけど、山岡さんはその向こう側にある、その人が背負ってきた人生だとか、そういうものを書き起こす方だと思うんです。そこがものすごく鋭い作品だなぁと思って。人に向けられた眼差しもものすごく真摯で、感動的だったんです。実際に泣いてしまうくらい。演劇で泣くなんていつぶりだろうというくらい、じわっと来るものがありました。すごく深みのある作品でしたね」
―― なるほど。先ほど、宛書とおっしゃいましたが、今回はオーディションで選ばれた役者さんが演じられます。その違いはどう捉えていますか?
柳沼「まず、壁があるというのと、もう一つ、違う作法や方法論でお芝居を作っている方が集まっているわけですから、それを統一したいというか。統一するというと型にはめるような感じなっちゃうので、むしろ共通項を探すという感じですね」
―― 具体的にはどうされるんですか?
柳沼「『異邦人』は会話劇なので、会話が成立していないと意味がないですよね。そこで、上手にしゃべることが問題ではなくて、話している内容をどれだけ理解できるかというところに焦点を当ててやっていくと。そうすると、自ずと皆さんのエンタテインメント臭が消えていったりして。あと、この台本には三点リーダー『……』が多いんですね。それを全部カットします。ちょっと専門的になりますが、台本には役者の呼吸が三点リーダーで反映されているんです。その呼吸をカットすることで、その人の固有の空気みたいなものが出てくる。それを大体、1ヶ月くらいかけて慎重に作って、その後、演出をつけていくという段階を踏んでます」
―― その共通項とは何ですか?
ごま「そうですね……、みんながうまい具合になじむというか。そこから稽古場の空気が生まれて、それが共通項になっていると思います。それは、山岡さんが作ろうとしている空気感と同軸のものではないかなと思います」
―― では、改めて、なぜ柳沼さんを演出家として選ばれたんでしょうか。
ごま「京都には個性的な人がいっぱいいますが、プロデュース公演の作品は、あまり前衛的、実験的な作品にはしたくないなという思いがあって。『好きな人は好き、嫌いな人は嫌い』という感じで分かれてしまうものではなく、1人1人の気持ちにしっかり届くもの。面白いか、面白くないかを常識的な範囲で捉えてくれるような、良質な平均値というか…。僕が企画として関わらせてもらえるなら、そういう良質な普通の感覚で、作品自体が人とコミュニケーションするものを作ってくれる演出家が欲しいなと思っていたんですね。そうなると、個性的な人がたくさんいても、その数がぐっと絞られまして。その中で去年、彼が上演した『八月、鳩は還るか』という作品が非常に面白かったので、ちょっとお願いしてみようかということでお声かけしました」
―― では、それぞれの俳優さんについて、どんな方か教えてください。
柳沼「全員、共通しているところは、自分が俳優としてどうなりたいかということよりも、一つの空間に奉仕してくれて、一つの空間の一部として存在してくれて、作品に対してちゃんと向き合って対話ができる人です。まじめに。それぞれ個性はあるんですけども。市川愛里さんは、ごまくん主宰のニットキャップシアターに在籍している俳優さんで、すごく舞台映えする美しさを持っていると思います。僕には妖艶な感じに映ったりしますね。そして、押谷裕子さんは上品芸術演劇団に所属されていて、ものすごくアクティブな演技をされる方です。関西の女優さんってこうだよなと、安心して観ていられる方です。黒木陽子さんは劇団衛星/ユニット美人の方で、コメディをよくされているんですけども、シリアスなストレートプレイも、奇抜な役もこなす、振り幅の広い方です。今回の役者さん中では、キャリアも一番長いです。阪本麻紀は私の劇団の烏丸ストロークロックの人間で、手前味噌なんですけども、一緒にやってきて僕が最も信頼している俳優です。田川徳子さんは神戸の劇団赤鬼に所属されているんですが、今回は、普段されているエンタテインメントな部分を封印して、また違う魅力を見せられるんじゃないかと思います。田中浩之くんは以前、烏丸ストロークロックの作品にも出演したこともあるんですが、今後、成長が期待される草食系男子です。最後に、名越未央さんが最若手、24歳なんですけど、フリーの役者さんです。前回は悪い芝居の『キョム!』に出ていらっしゃいました。彼女も今後、期待される俳優さんですね」
―― ありがとうございました。話はがらっと変わりますが、3月に東日本大震災が起きまして、個人的にはこれは地域の問題ではなく、日本全体で考えなければならない問題であるなと思うんです。震災直後は舞台関係の公演も自粛というムードも漂いましたが、こういうときだからこその演劇の力など、何かお考えであれば教えていただけますか。
柳沼「チラシにも書かせてもらっていますが、今、技術も発達して演劇を映像として残すという方法があるにはあるんですけども、空間を残すことはできないですよね。舞台上では、実際にそこにいないと成立しないことがたくさん起こっています。インターネットであるとか、そういう通信技術の発達でいろんな情報が簡単に手に入ることで、創作物も簡単に手に入る世の中ですが、演劇にはそれでも手に入らないものがたくさん詰まっていると思います。言葉を超えたところにある認識とか、空気を共有して感じることとか、舞台で行われていることはたくさんあって。言葉はすぐ形になってしまうけれども、感覚はずっと残り続ける。そこに僕は演劇の未来があると思うし、人が大切にすべき部分じゃないかなと思っています。震災直後には、いろんな人の言葉が通信機器を通じてうわっと出たましたが、発信する、受け取るという、そういうやり取りを演劇は強く意識させてくれる。そういった意味でも、最初にお話しましたように、山岡さんが書いた『異邦人』の、台本に書かれていない部分の感覚や温かみ、そういうものに触れていただくことで、コミュニケーションをするということの豊かさを感じていただけるんじゃないかと思います」
―― 『異邦人』の上演は、震災前には決まっていたことですよね。図らずも、そういう思いと現実が合致したんですね。
柳沼「そうですね。関西でも、震災発生後の1週間ないし2週間は、なんとなくみんな不安な思いで、元気が出ないことが続いたんじゃないかと思います。その根源には寂しさがあったりして。人って、人とのつながりを感じるだけで楽になれたりするじゃないですか」
―― 不思議ですよね。個室社会が進んでいる中で、そういうつながりを求める人も増えていて。
柳沼「そのどちらも共存しているのが今の現代人なんだなって思うんですよね。この作品にはその両面が描かれています。集団自殺も矛盾してますもんね。死にたいけど、皆で死にたい。ひとりは嫌だという。表面上はすごく拒絶してるんだけども、死を迫られたら…」
―― 人を拒みつつも、死ぬときは求めるのかという。
柳沼「そういう複雑な部分にも目を向けられているところが、山岡さんの鋭さや優しさなんでしょうね」
―― 『異邦人』は初演から6年が経っていますが、作品に時間の経過は感じられないですか?
柳沼「感じられないですね。自殺の仕方が“練炭ブーム”ではなくなったくらいで。今でも色あせず、通用する物語です」
(2011年6月 7日更新)
Tweet Check

プロフィール
■柳沼昭徳
烏丸ストロークロック 主宰/劇作家・演出家・俳優
'76年、京都市生まれ。'99年に近畿大学文芸学部在学中に京都を中心に活動する「烏丸ストロークロック」を旗揚げ。劇作・演出を担当するほか、俳優や映像制作を兼ねる。'01年、第3回大阪演劇祭CAMPUS CUP 2001大賞(『ハニービージャンクション~供養道より』)、'03年、Kyoto演劇大賞(『福音書』)を受賞。'04年からは高校演劇でのワークショップ講師を各地で務める。また、同劇団では、企画ごとにオーディションで選出したメンバーと共にワークショップを重ねる製作形態をとっている。
■山岡徳貴子
魚灯 主宰/劇作家・演出家
京都市在住。劇団八時半(代表:鈴江俊郎)に入団し主に俳優として活躍した後、劇作家・演出家としても活動を始める。同劇団退団後、劇団「魚灯」旗揚げ。'99年、北海道戯曲コンクール優秀賞(戯曲『逃げてゆくもの』)、'01年、第8回OMS戯曲賞佳作(『祭りの兆し』)を受賞。『静物たちの遊泳』('08年)、『着座するコブ』('09年)が岸田國士戯曲賞最終候補に選ばれるなど、注目の作家の一人。