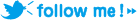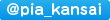ホーム > インタビュー&レポート > 第4回近松賞受賞! 尼崎を舞台にした劇作家・角ひろみ作『螢の光』を上演

第4回近松賞受賞!
尼崎を舞台にした劇作家・角ひろみ作『螢の光』を上演
劇作家・近松門左衛門とゆかりが深い尼崎市が、近松の功績を顕彰するとともに、次代演劇界を担う優れた劇作家を世に紹介し、新たな演劇作品の発掘、劇作家の育成を目的に始めた近松賞。この第4回受賞作品である角ひろみの『螢の光』が、演出に桃園会の深津篤史を迎えてピッコロ劇団によって上演される。
舞台は尼崎の北の突き当たりの市営団地。ここに住む平凡な妻、井上晴子が消えた。同日、近所のコンビニには女の強盗が入ったらしい。そのコンビニのパート主婦・林里美の夫もまた突然消えたという―縫製の内職をしていた晴子のミシンからは、林家の窓が見える。林の夫の書斎に点る灯までよく見える。晴子のミシン机の灯も毎夜点っていた――。
尼崎の市営団地を舞台に、取り残された者たちの営みと心の動きを静かに描いた本作について、角ひろみ、深津篤史、そして出演する役者たちに話を聞いた。
角ひろみ(以下、角)「私は尼崎市出身で、'06年まで関西で活動していました。結婚して現在は岡山市在住ですが、この近松賞という大きな賞をいただきまして、尼崎市の賞を尼崎市出身の私がいただき、尼崎市を拠点とするピッコロ劇団に上演していただくということで、深い縁を感じています。これまで尼崎という故郷をそこまで意識していなかったんですけど、今回、故郷で上演していただけるということで、すごく意識するようになりました。私自身、小さいころは団地に住んでいまして、そこで生活していたことを思い出しながら書きました。今回、この作品を上演していただくにあたって、とても大きなホールで、少ない人数で、それも団地の一室ということで物語が起こるんですけども、すごく濃密で。その中で愛情や命やというものを感じさせる内容だと思いますので、とても楽しみにしています」
―― 角は'05年まで坂道ストアという自身の劇団を主宰していた。結婚を機に劇団を解散。岡山へと移住する。近松賞とは、その引越し準備を行っている最中に出会ったという。尼崎市役所の支所で脚本募集のチラシを手に取り、「私も、劇作家もやっていたけど、後に尼崎に角ひろみという人がいたということを誰にも知られないまま、いなくなるんだなって思って、ぶっちゃけ、この賞がほしいと思って」、ぎりぎりになって応募したという。そして見事、受賞する。
角「賞をいただいたことで、尼崎出身の私が頂戴したというつながりと、このまま創作をやめてしまってはいけない、絶対続けないといけないという運命みたいなものを大きく思ったような気がします」
―― また、常々、人間の弱い部分を描きたいと思っていると言う。『螢の光』というタイトルもそこを意識したそうだ。
角「今回は残される男性と女性を描いています。生きていく中での小さな光を意識して、このタイトルをつけました」
―― では、近松賞ということで、近松門左衛門についてはどう捉えていたのだろうか。
角「書くときには、私のイメージで意識をしました。近松門左衛門の作品をほとんど知らず、一作見ただけなんです。でも近松門左衛門は恐らく、近松の生きた時代、その当時の現代を書いていたように思うんです。現代と、人の生活というか、弱さ、愛情、しがらみとかを書いていた印象があって。私も、現代の愛情とかしがらみと、お金が絡んでいる作品を書きたいと思って、強く意識しました」
―― 前述したように、尼崎出身の角だが、生活をしているころは特に街のことを意識していなかったという。作品に流れる静けさは、そんな角だからこそのだろう。だが岡山へと移住して、外に出て改めて尼崎という街を見るようになって…。
角「尼崎が舞台になっている作品を見ると、労働者の町という感じで書かれているイメージが多くて。住んでいるころはそんな印象は全くありませんでした。でも、尼崎を出て、時折帰ってくると、パンキッシュな街だなと。金髪の子がたくさん走り回ってるし、金髪のお母さもたくさんいて、服がカラフルで。岡山の人は引っ込み思案な感じなんですよ。思っていてもあまり話しかけてこない、空気感だけ伝わってくるという感じなんですけど、尼崎という街は何せ話しかけてくる、ダイレクトな街だなと思います。知らない人に『その服、どこで買ったん?』とか、普通に聞かれたり(笑)、『ほんでなぁ』みたいなところから突然、物事が普通に始まったりして。きっと他人のことを自分のこととして捉える力がすごく強いんだろうなという気がします」
―― それでは、演出の深津篤史より。
深津篤史(以下、深津)「初めてピッコロ劇団さんで演出させていただきます。本を読ませていただいて、内容も近松の心中ものの逆というか、道行で盛り上がってふたりが死んじゃうというお話の逆ですね。残された側なので大変地味なことになって、リアルに考えると湿っぽいとうか、辛気臭いというか、小さなお話になりそうな感じがするんですけど、台本自体は別に小さなお話を描いているわけでもなくて。出て行く者と残される者とのお話をミニマムな世界で描いている。観る者にとって外と内という感覚から広い世界を感じられる舞台を作ろうと思います」
―― 続いて、役者たちにも作品への印象や役どころについて聞いた。まずは、市営団地に住む広告代理店勤務のサラリーマン、井上勉役の岡田力。この井上勉は、妻・晴子に逃げられてしまう。
岡田力(以下、岡田)「奥さんに取り残されてしまう井上勉という役を演じます。舞台転換も何もなくて、特定された団地の一室がずっと変わらずに舞台にあるんですけども、その中で時間経過なり、心情の変化なりを演じるのが非常に難しい作品だなと思っています。でも、作品はとても面白くて、この作品を演じられることを幸せに感じております。難しいん役ですが団地ものに関しては第一人者の深津さんにすべてを委ねて、自分のできることを考えながらやっていきます」
―― そして勉の妻、井上晴子を演じる木全晶子より。
木全晶子(以下、木全)「勉さんの嫁役をやらせていただきます。『螢の光』は、登場人物それぞれに台本の中に書かれていない謎の部分があるところが面白いと思います。例えば、恐らく重要にかかわってくるであろう人物が語られているんですが、その人は登場しなかったりとか。私たちは舞台の外の世界のことをいろいろと想像しながらお芝居をしています。お客様もその謎の部分、もやもやとしたところをいろいろ想像して楽しんでいただけたらいいなと思います」
―― 取り残された勉を訪ねてやってくる幼馴染、小坂鈴子役は京華と道幸千紗のWキャストで。
京華「2010年度は少年役を3役やらせていただきまして、ピッコロ劇団として女性役をやらせていただくのは1年ぶりとなります。鈴子さんは、おろかだし、あほだし、でもすごく愛しく感じています。自分の中の女性と向き合って、鈴子さんの純粋さを表現できればいいなと思っています」
道幸千紗(以下、道幸)「この鈴子という役は、いろんなものを抱えているんですけれども、そんな中で勉くんと会って濃密な時間を過ごします。台本を読んだときに、鈴子はもがきながら一生懸命生きているという印象を受けましたので、私ももがいてもがいて、この役と向き合っていきたいです」
―― 勉と同じく、旦那に取り残された井上家の向かいの団地に住む林家の妻、里美役は亀井妙子が演じる。
亀井妙子(以下、亀井)「稽古の最初の方で、深津さんがとつとつとお話をされていて。『要するに、地に足をつけてほしいです。要するに、生きていてほしいんです』とおっしゃって、本当にそうだなと。そのことが必然でないといけない芝居だなと思っています。舞台で役が生きているのを見たいですし、私もそうでありたいとずっと思っていますので、そのことに向かって日々、あがいております。目標ははっきりとしているんですが、その道のりをどう歩いて行ったらいいのかなということを、この作品と一緒に探しています」
―― 最後に勉の会社の3年先輩の平田健介を演じる保は…
保「演劇界に一石を投じるお芝居になるでしょう!」
―― 深津の「要するに、地に足をつけてほしいです。要するに、生きていてほしいんです」という言葉。この意味合いをさらに尋ねると…。
深津「単純に、テクニックで上手にしゃべっているものを私は観たいと思わないんです。もちろんテクニックも大事なんですが、舞台にいる役者さんは役という服を着て、着飾っているわけなんですが、それが必要最小限であればあるほど一番いいことだと僕は思っていて。だからといって素がいいとも全く思っていませんし、テクニック至上主義でもないので、そのベストなバランスはどこなんだろうかというところを演出で探っていければと思っています。特に、こういうお話はそういうことが大事だなと。お芝居である以上、見られているわけなので、見られているという感覚をちゃんと持った上で地に足のついた、飾らない台詞が会話の中から出てくればいいと思っています」
―― 今回、作品を演出するにあたって、深津から役者陣にちょっと変わった宿題がいくつか出されたそうだ。
岡田「僕と鈴子さん役に出された宿題が、ふたりが幼馴染ということもあって、『小さいころの自分を想像して、お互いにお誕生日会の招待状を書きなさい』と。そして、僕が実際、小さいころに書いた作文なりを添えて出しなさいという宿題でした。あと、もう1つ、『匂いを考えて来てください』という宿題でした。閉塞感とか、喪失感とかに結びつくような、自分の記憶の中で『このとき寂しかったな』とか、『思い出すとすごく寂しくなるような匂いを思い出してください』という宿題がありました」
―― では、これら宿題の意図とは。
深津「役作りをするとき、台本を読んで『こんな性格かな』とか、『こんな気持ちかな』とか考えるんですけど、そのときに役者さんは自分の引き出しの中から引っ張り出して、進行させていくと思うんです。そこでもっと、自分の体とダイレクトに反応して出てくる身体性になってほしいと思って。ここでは、勉と鈴子が幼馴染であったという時間性が見えてこないといけないので、招待状を出し合って擬似的な時間性を作っていただいたりしています。また、何かを思い出すときに、視覚や聴覚である見えたり聞こえたりということも引き金になる大事な情報ですけど、匂いというのは五感の中でも原始的な感覚で、脳みその情報に行かずに、結構ダイレクトに行きやすいということがあると思うんです。あんなものを見たという思い出だと、思考回路を通して『ああいうものが見えたから寂しかったな』とか、頭を通ってしまうんですよね。でも匂いだと、『あれはいったい何の匂いだったっけ』とポーンと出てしまう。そういう人間の根源的な感覚のようなものを使えたらいいなという思いですね。できるだけ役者さんに舞台上で生きていてほしいということのひとつでもあります」
―― そういった演出を通じ、役者たちの作品に対する印象はどう変化していったのだろうか。
岡田「作品の面白さはは、最初に一読したときと変わっていませんが、深津さんの演出にものすごく戸惑うところがありました。僕が慣れている稽古方法は、無理やりにでも動かしていく感じなんですね。でも、すごく静かなんです。動きも、外からつけずに自分の中から出てくるものじゃないと意味がないという感じで。本番ではどうなっているかわかりませんが、僕自身、楽しみにしたいと思っています」
木全「本を読んだときの状態と、稽古が回数を重ねて何が違うかというと、読んでいるときにはあまり考えなかった、想像しなかったものが、自分の体の中で動いていることを感じるという、不思議が感覚がありました。稽古した結果を踏まえて、深津さんが『僕がはこう見えました』とコメントされて、『どう考えてますか?』というように、部分的に確認されたりするんですが、お芝居をすることで深津さんと対話しているように感じています」
京華「オーディションの前に台本を読ませていただいて。個人的なことですけど、20代前半のときに坂道ストアが大好きだったので、角さんの台本だということでミーハー心あふれて読みました。そして、キャスティングしていただいて、改めて読んだら謎がいっぱいで、どうしたらいいのかわからない状態になっったんです。それでも、自分で答えを出して稽古場に行っていたんですが、立ち稽古に入って深津さんからお手紙をいただいて。そのお手紙をきっかけに、頭で考えていただけではわからないこととがわかったような、わかったというのとはまた違うんですけど、そんな感覚になりました」
道幸「今、京華さんもおっしゃっいましたが、通し稽古が始まる前に深津さんにお手紙をいただいて。私も最初は、『これはどういうことだろう』と思いながら稽古をしていたんですが、深津さんが役の深いところを自然と掘り下げていくように誘導してくださっていると感じて、深津さんを信じてがんばっていこうと思っています」
亀井「最初に読んだときとすごく違うかというと、違わないという思いと、先ほどもおっしゃっていたように気づかなかったことに気づいたり、何も引っかからなかったことに引っかかったりということはあります。そうやってだんだん関係性ができている部分を面白く見ております」
保「読んだときの衝撃のまま、日々、連日の稽古も衝撃です」
静かに、生きていることを確かめるように、ほのかな光を灯し続けているこの物語を、観る側はどう受け止めるのか。作家、演出家、役者たちがそれぞれに感じたように、次は観客が何かを感じ取っていく番だ。人々の普遍的な営みを見つめた本作からぜひ、各々の光を見つけていただきたい。「螢の光」はピッコロシアターにて6月3日~8日までの6回公演。この機会にどうぞお運びを。
(2011年6月 2日更新)
Tweet Check
公演情報
兵庫県立ピッコロ劇団『螢の光』
▼6月3日(金)~8日(水)
火14:00/19:00 金19:00 土日水14:00
ピッコロシアター大ホール
[前売料金]一般3500円
大学・専門学校生2500円 高校生以下2000円
[作]角ひろみ
[演出]深津篤史
[出演]岡田力/木全晶子/保/京華/道幸千紗/亀井妙子
※この公演は終了しました。