
ホーム > インタビュー&レポート > アルバム5枚目にして「DYGLの本質が始まった」 “身体性のある音楽”という新基軸が彼らを突き動かす DYGL・秋山信樹 インタビュー

アルバム5枚目にして「DYGLの本質が始まった」
“身体性のある音楽”という新基軸が彼らを突き動かす
DYGL・秋山信樹 インタビュー
インタビュー中、何度となく出てきたのは“身体的”という今後のDYGLの核となるであろうキーワードだった。2012年に大学のサークルで結成され、アメリカやイギリスでの長期滞在を通じて多くの音楽ファンを魅了している全編英詩のギターロックバンド・DYGL(デイグロー)。彼らが今年夏のど真ん中、8月13日にリリースする3年ぶり5枚目のアルバム『Who’s in the House?』は、全曲メトロノームなし・全楽器同時の一発録りレコーディングで制作されたという、ロックバンドの勢いと面白さとかっこよさをグツグツに煮込んで濃縮したような全9曲が耳と脳に響く1枚だ。PCで音楽を作ったりレコーディングに幾重にも音を重ねたりすることも当たり前の楽曲制作工程になった令和の今、メンバーが同時に音を出してレコーディングしただなんてそれを聞いただけでも楽しそうなものだが…インタビューで判明したのは、収録曲全てがセッションを重ねる中生まれてきたものであるということだ。つまりロックバンドがロックバンドをやることを楽しんだ様子を収めたのが、このアルバムなのだと個人的には理解した。この作品を制作するにあたりDYGLに何が起こっていたのか。7月某日、大阪にやってきた秋山信樹(Vo&G)に話を訊いた。
ようやく今回が
真の1stアルバムになった
――現在DYGLはライブシーズンに突入していますが、バンドはどのようなライブをしようというモードにありますか。
「ライブでも音楽制作でも自分たちが好きな音楽は"身体性があるかどうか"ということが大事だと最近気づいたんです。しっかりとビートがあって、ライブならリズムや低音も含めてスポーツのように楽しめるものであるか。クラブミュージックなら当然一番重要ですけど、ロックもそうだよなと。自分たちは実際のところ音楽を聴く時に何に一番高まるかを突き詰めたことで、そのことに改めて気がつきました」
――それは自然に体が動く音楽という捉え方で合っていますか?
「そうですね。参考にしてきた音楽を意識して聴いてみると、メロディとリズムの比重が思っていたよりもリズム寄りな気がして。そういうリズムの部分=音楽の"身体的な部分"がDYGLにはもっとあってもいいんじゃないかというのが最近すごく意識している部分ですね」
――"身体性"というワードが出てきたきっかけがあったんですか。
「実はコロナが落ち着いて久しぶりにロンドンに行って、その時にジェイムス・ブレイクが主催している『CMYK』というイベントに遊びに行ったんです。昼間から次の日の朝まで彼が選んだアーティストが観客をリードし続けるんですけど、会場の規模もサウンドシステムも本場感があって個人的にかなり喰らったんですよ」
――ちょっとお話を聞くだけでも羨ましい体験です...!
「メインじゃない方のステージは、音が特別いいわけではなかったんです。少し離れると低音しか聴こえなかったりして。ステージに向かう間のスペースに至っては、メロディーもよくわからない。でもそこにいた人たちはうっすら聞こえてくる低音のビートだけで身体を揺らして盛り上がっていて、それを見た時に現地の音楽の聞き方が少し見えたというか。あぁ、この感覚はDYGLでも意識した方がいいなと」
――それはいつ頃?
「去年かな。結構最近ですね」
――なるほど。それは今回のアルバムにも関わるお話になりそうですね。8月にリリースされるニューアルバム『Who's in the House?』を聴かせていただいて、「こういうバンドの音が聴きたかった!」と脳が喜ぶ音楽体験をさせてもらいました。言葉を選ばずに言うとただただ「かっけぇ!」という。まずこのアルバムの制作の出発点から聞かせてください。
「実はアルバムを作ろうというスタートではなく、とあるライブのリハでスタジオに入ってる時に、嘉本(康平/Gt.&Dr)が楽器を忘れて取りに帰って。暇だしセッションしようぜって残ったメンバーで音を出していたら、曲のアイデアがバーっとできてきて。嘉本が戻ってきた後も、今調子いいから練習じゃなくてこっちやろうって演奏を続けたんです。それが始まりでした」
――遊びの延長のような感じでいいですねぇ。
「これまでのDYGLの流れに自分達自身で飽きていたことはでかかったと思いますね。それに加えて個人的にはロンドンで『CMYK』に行ったこと、あとはアメリカから来英していたThe Gardenや韓国のBalming Tigerのライブを見れた経験が、とにかくタイミングとしてよかったと思います。彼らは本当に身体性のある、体で感じることのできるライブをしていたので。だからこそ、頭ではなく演奏に根差した自由なセッションをしたいマインドだったというか。自分たちの過去のアルバムを振り返ってみて、耳で聴く曲を書きすぎていたなと思いました」
――特に前作の『Thirst』はコロナ後のリリースでもあるので、耳で聴くモードが反映された作品に仕上がったということもあるかもしれませんね。
「それはあると思います。そもそもあの頃はあまり実生活との繋がりも感じづらくてロックも聴けていなかったりして。アンビエントとか、電子音楽っぽいものの方がしっくりくる感じでしたね。みんなで現場で盛り上がる、みたいな曲にリアリティを持ていなかった分、アウトプットも内省的になっていったと思うんです。でも少しずつ世の中が開いてきて、自然と外に目が向き始めたのかな」
――状況と気持ちが全部噛み合って、セッションがうまく転がっていったんですね。
「ひたすらセッションしました。スマホを置いて3時間くらい録音しっぱなしにして。あの辺のあの曲よかったよね? って振り返って録音時間をメモって、いい曲を切り出していったら40曲分くらいになって」
――すごい量...!
「そうなんです。何かを決めたわけでもなくただただみんなで音を出すことを続けたら、アルバム3枚分くらいのストックができたんです。もちろん1分以下の断片みたいなのもあれば今の完成系に近いのもあって。今回はなるべく深く考えずに自分たちの体で気持ちいいと思うものを先に出して、まず実際の演奏として"よかった"という瞬間を見つけたあとで精査していく方が音楽的に楽しいんじゃないかと。根つめていい曲を書こうとするのはやめました」
――解放的になったDYGLを感じるお話です。
「当時、1stアルバムの時点で良い曲作らなきゃ、と意気込みすぎていたところもあったので。2ndで他のメンバーにも曲を書いてもらって枠を広げて。3rdでも4thでもいろいろ挑戦して向き合い方を変えてきたことはあるんです。でも誰が書いてきた曲も、書いてくるなりまた1回腰を据えてアレンジをまとめ直すような感じでした。でもそもそものバンドの始まりは超適当で、大学のサークルの定期演奏会に1回出るだけのつもりでノリで組んだ感じで。セッションでバーって曲作ったり、最初はギター3人で組んじゃったからドラムの役割は一人ずつ回したり、メロディーもなにもない曲を5曲くらいドンってライブでやってみたり。それが超楽しかったしめちゃ気楽で、当時はとても自然にのびのびした曲を書いていたなと。あれが一番よかったんじゃないか、じゃあ今回は1stアルバムより前の、あの頃の自分たちにリンクし直そうと。いやし直そうとしたというより、自然とそうなったという感じだったかもですね」
――原点回帰ですね。
「そうですね。とは言えバンドとして1stも一つの原点ではあるので、原点より更に一つ前の自分達に帰ったくらいのイメージで。これまで4枚アルバムを制作してきて、ベストは尽くしながらもずっと納得がいっていない部分がどこかにあったんです」
――それはどういう点で?
「音そのものもそうだし、メンバー同士で持っていた熱量や見ている方向、本当にいろんな面で課題があって。一度はバンドをやめようという時もあったけど、それも乗り越えて。今回ようやく全員しっくりくる感覚が見つかった気がしているんです。それもずっと前の自分たちに答えがあったというか」
――元々知っていたはずなのに! と。
「そうですね。アルバム4枚目までずっと寄り道して、ようやく今回が真の1stアルバムになった感覚があります」
――アルバムの紹介文に「1stから4thの音楽的な旅を経て」という一文があって、どういうことかなと思っていたのですが今のお話ですごく理解できました...!
「もちろん、過去出したアルバムも大切なアルバムだし、お気に入りの曲もたくさんあります。その一方で、音楽性が多岐に渡っているので今後どのように過去曲と向き合っていくかには課題を感じていて。そういう意味では、今回のアルバムからの流れの方が、DYGLの本質が始まったんじゃないかとすら感じられています」
――ちなみに今回のアルバム制作前のセッションで面白かったことはありましたか?
「誰かが何かを弾き出して、こういうフレーズにはこう乗っていこう、このリズムならこのフレーズはどうか、というような感じで。自由に音出せたのがなにより楽しかったですね。今回には特にリフがよく思い浮かんだんです。どんどんリフを弾いて、みんなが乗っかってきて。この返しが来ると思わなかったけどいいなって組み合わせが見つかったやつは、しばらく泳がせてみたりして。メロディーが浮かんだら適当な言葉で歌ってみたり。アプローチはいろいろあったけど、本当にどれも面白かったですね」
一発録りでの制作は
全曲想像を超えてきた
――大解放されたDYGLを感じられるエピソードを伺いましたが、アルバム3枚分ほども曲ができた中からどのようにして今回の収録曲はチョイスされたのでしょうか。
「まずは手元にあった40曲ほどを曲の性格ごとの箱を作って分けたんです。ポストパンク箱、オーストラリアインディーぽい箱、メタル箱、というような感じで。今回は更にもうひとつの箱に入れていたものです。これだけ名前のついていない箱でしたね。ガレージロックなのかな、強いて言えば。過去のアルバム制作では、「この時期にアルバムを出したいね」と先に時期を決めて、日程が決まったら作り始める感じでした。そうなると直前に曲が足りなかったりして、焦らないといけなくなったりして、なので世界観の近い曲で絞れず、ある曲を全部入れることで、本来同じアルバムに入れなくてもいいような曲同士も混ぜちゃってたんですよ。でも自分達が好きなバンドのアルバムを聴くと、どの曲を聴いてもそのアルバムの曲としてちゃんとひとつの世界観があるように感じていて。アルバムでどう聴かせたいのかがハッキリしている。俺らのこれまでのアルバムは同じアルバムの中でもあっちこっちいって、軸足を定めきれていない部分もあったというか。今回のアルバムでいうと、収録曲全体でひとつの長い曲のように聴こえるのがいいねという話はしていました。それが仕分けする時に気をつけたところです」
――そもそも出発点もアルバムとしての構築の仕方もこれまでの4枚とは全く違うんですね。
「そもそも40曲の中から選抜しているので、以前とは違ってしっかり一つの世界観を選ぶプロセスができたと思います。」
――そうして選んだ曲を全曲メトロノームなし、全楽器同時の一発録りレコーディングというのもすごい話です。
「俺ら、真面目すぎるところがあるんですよ。いざひとりずつ録りはじめちゃうと、これよくないかもとか余計に考えだしちゃうところがあるので、今回は真面目リミッターをいかに外してどんだけ適当にやるか、あとは同時に演奏をすることで他の人のミスに変に気づかないようにするというのもありました。同時演奏で指摘がないミスはミスでもないと。むしろ良いハプニングだったりもする。そうやって新しいやり方を試してみました」
――一発録りにしようと言い出したのは?
「満場一致で自然とそうなりました。いつもはグリッドに沿って丁寧に演奏していたけど、他人のミスに神経質にならないおかげでライブの雰囲気そのままリアリティもって収められたのもよかったし、全員同時に録るからスタジオ代も安上がりだし(笑)全部が最高でした」
――いいことしかないじゃないですか!
「世の中のバンドみんながやるべきですね。レコーディングの前に準備しすぎないようにもしました。一発録りしたら音はなるべく足さない、ライブでやっていないことは無理に足さないというのも大事にしました」
――その理由は?
「ライブがいいバンドだと自負しているので、それをそのまま出したいと思ったからですね。それによって、自分たちがライブ感のあるバンドだという当たり前のことに気づき直すきっかけになりました」
――一発録りしたことで自分たちの想像を超えてきた曲はありましたか?
「正直、全曲かもしれません。レコーディングに参加してくれたエンジニアのステファニーの腕もあって。アメリカから来てくれたんですけど、日本のスタジオで録ってもこの音になるんだ! っていう驚きがありました。俺らがどの音を出したいか...耳ベースなのか身体ベースなのかでいうと、ステファニーは元々パンク系ライブハウスのPAだったっていうのもあって、一番身体的なバンドの現場でずっとやっていた人なんです。だからどういう音を出したいかを説明しなくても最初から理解してくれている感じがあって。技術もあるけど音楽性の部分で信頼していたし、いざ録り音を聴いた時は感動と驚きがありました」
――個人的に前作を聴いていて感じたのは、バンドの音がすごくひとかたまりになって聴こえるなということでした。それが今作はひとりひとりの楽器がしっかり立っているというか、まとまっているのにそれぞれのパートがしっかり届いてくる感じがしました。それがエンジニアの腕ですか?
「いろいろあるとは思います。前作は...録音なんかは全て自分達でやったんですが単に僕らがマイク立てるスキルもミックスのスキルも低かったし(笑)、音源でいうとシンセ的な音を使って音の隙間を埋めたりもしていたんです。今回は基本はメンバー分5個のレイヤーしか存在していなくて、音にしっかり隙間を作ったというか。隙間があるからこそ音の輪郭が立って聞こえるのかなとも思いますね」
――音で埋めるというのは、ずっとどこかで音が鳴っているようにしていたということですか?
「そうですね。たぶん無意識にそうしちゃった部分もあるし、雰囲気出すためにリバーブを足しすぎちゃったりもしていたかな」
――前作はアンビエントを聴いていた後でもありますし。
「なんか作りたいムードがあったんでしょうね。サウンドに隙間があるのは結構大事だよねとメンバーとも話していました。リズムに隙間がないと地続きの音みたいになって、ちゃんとリズムがリズムとして成り立ってこないというか、リズムを刻めていない感じがして。音の空白があるからこそリズムになる、というのを今すごく感じています」
――ただ今はリズム視点での隙間の話をされていますけど、アルバム内には「ONE O ONE」から「MAN ON THE RUN」の曲が切り替わるところに音の隙間がないというか、音が続いたまま次の曲になるという演出もあります。リズムの話ではないですが、音の隙間が全くない部分が出現するのですが、私はこれが非常に気持ちよかったです。
「ありがとうございます、うれしいです。セッション自体があんな感じで、ほとんど生まれた形そのままなんですよ。セッションで生まれた感じをそのまま出しちゃおうと」
――音の境目がないまま、新しい曲ができていっていたということですか?
「そうですね。「ONE O ONE」の原型になった曲をわーっと演奏していて、曲が終わったかなと思ったところで、みんなまだ演奏ゆるりと続けていたのでじゃあ続けるかと。そうしたらパート2みたいな曲ができたんです。これは曲として別の曲に分けた方が面白いかなとなりました。元は同じ曲だったみたいな感じです」
――最初は呑気に聴いていて気づかなかったんです。何回目かのリピート視聴で、あれ? なんか切り替わった? ってもう1回聴いてわかるという。サブスクでザッピングして1曲ずつ聴いていたら気づかないし、アルバムをトータルで聴いて気づく面白い仕掛けだと思いました。やっぱりトータルで聴いてほしいという想いですか?
「それはやっぱり強いですね。自分は飽き性で、自分らが学生の頃iTunesやYoutubeが出てきて1曲ずつ単曲で聴くみたいのも全然やっていたので、今のTikTokの次々派手な曲を聴く感じも理解できるんですよ。 それも全然良さがわかるんですけど、これだけ音楽を聞き流す流れが早いと聞き疲れしちゃうと思うんです。若い子でも現代のスピードに疲れているという話も聞くし。だから1回落ち着いて、このアルバムの30分間だけはこのアルバムに集中できる時間にしてもらえたらいいなと。一つの世界に没入する時間ってすごく気持ちいいことだと思うから、今回のアルバムもそういう風に楽しんでもらえたら嬉しいですね。」
――今回はアルバムトータルで聴いてほしいと考えた時、曲順はどのように考えたのでしょうか。
「ノリっちゃノリですね。この曲の後にこの曲が来たら気持ちいいなという考え方で。例えばDJをしていたら、この後にこれが来たらいいなという感じで。ライブのセトリを組む感覚にも似ていたかな」
――結局はずっと身体性というワードやライブ、パフォーマンスすること、人に体感してもらうことが制作時から一貫したテーマになっているんですね。
「そうですね。リアルな体験、生っぽさを表現したかった。テコ入れすぎてリアリティを失っちゃうのが一番嫌でしたね。なるべく生まれたまま、産地直送みたいなことができたらいいなと。細かいことを気にし始めるといろいろいじり倒しちゃうので。前のアルバムは同じ曲でボーカル30テイクも録ったり、ボーカルテイクを切り刻んで自分でつなげたりするので、もう大調理パーティーでした。だから今回は真逆ですよね」
――大改革じゃないですか!
「大改革ですよ! だってもう本当にレコーディングが憂鬱だったりしましたもん(笑) 最初からあの作業が待っていると思ったら、歌いたいけど大変だなぁって。今回はめちゃくちゃ健全だったし楽しかったし、最高でしたよ」
――じゃあ今回こそ、音楽を楽しめたアルバムにできたんですね。
「楽しんでナンボですよね。ただ苦しい時期に作ったアルバムもそれはそれでよさがあって、その時の味だったりもして。今の僕らの正解はコレって感じですね」
――ここまでお話を聞いてきたら、かなりライブということがキーワドになっているとも思うんです。なんならアルバムタイトルが『LIVE』でもおかしくないと言いますか。そんな今作に『Who's in the House?』と付けたのはなぜですか。
「一番示唆的な言葉かもと思ってつけたんですけど、収録曲の「Who's In My House?」をもじったのも遊びです。この曲の歌詞は心を自分の家に見立てたものになっているんです。日本で生まれ育ったことによって、この社会の規範みたいなものをすごく意識することがあって。大きい音は出しちゃダメ、ここではボール遊びしちゃダメ、タバコは吸っちゃダメ。社会の中で禁止を目にする機会が多いですよね。そうやってダメに囲まれて生まれ育ってきたから、どう迷惑をかけないかっていうのがインストールされまくっている気がしていて。特に日本は実際のルールが多いだけじゃなくて、それが視覚的に張り出されていたりもするじゃないですか。トイレは一歩前でしろとか。勿論そうやって社会の規範を守れる部分もあるし、良し悪しあるとは思うんですけど。とは言え、ルールの隙間がある場所がないとどうしても生きづらさもある。自分が音楽を書く時には、そういう隙間を意識してテーマとしてどこか混ぜている気がします。どう自由になれるか、みたいな。誰に言われているわけでもないのに自分の限界を無意識に決めてしまったり、お前は若いからまだ無理とか、そういう言葉が自分の内側から聞こえてきても、自分でやりたいことは自分で選ぶ。知らない間に自分の心に住みついたその声は誰だ?というのがこの曲のテーマで、それをアルバムにも示唆的に使いました」
――なるほど。今回新しい方法でアルバム制作に挑まれましたけど、今後も続いていきそうなアイデアはありましたか。
「考えすぎず感覚でいいと思ったものをちゃんと見逃さないで、それをとにかく大事にすること。考えすぎることでよかったはずのアイディアを消さない、正直な音をそのままの形で録る・出すことですかね。ロックバンドのロマンに憧れてDYGLを結成したので、そこに足場を置くことで表現できることを突き詰めていきたいなと思いますね」
――そして今年の夏はたくさんのフェスへの出演も決まっていますね。
「はい。DYGLを知らない人に届く場所にどんどん出ていきたいですね。ようやく自分たちのコンフォートゾーンを出ることができてきたというか。このアルバムができたことで、ようやくそのゾーンを出る準備ができたのもあると思います。このアルバムのリリースも、いろいろなフェスへの出演も、自分たちの基盤が変わったような気がしているのも、全て繋がっている感じがする。土台が固まったからこそ、今まで以上にこっちから切り込んでいけるっていう」
――特に今回のアルバムは、初めてDYGLに出会う人もライブハウスで興奮している様子が想像できます...!
「アルバムのリリースツアーではもちろん今回のアルバムの収録曲は全部やりたいし、過去曲も今のモードで新しいアプローチを探してみたいなと思っています。だからこそ更にその先のアルバムに入れたい曲もやっていこうかなと。それこそ次のアルバムも遠くないうちに届けられるかなと思っています」
取材・文/桃井麻依子
(2025年8月12日更新)
Tweet Check
Release
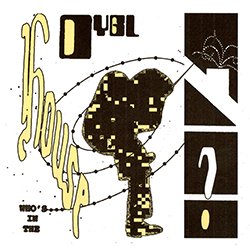
5th Album『Who’s in the House?』
8月13日(水)配信開始
Easy Enough
《収録曲》
01. Big Dream
02. Just Another Day
03. Do I Really Want To?
04. Everyday Conversation
05. Let Me Be
06. One O One
07. Man on the Run
08. This Minute
09. Who's In My House?
Profile
デイグロー…2012年に大学のサークルで結成。アメリカやイギリスでの長期滞在を通じて多くの音楽ファンを魅了している全編英詩のギターロックバンド。洗練されたサウンドと鮮烈なパフォーマンスは、国内外を問わず高い評価を受けている。1stアルバムはAlbert Hammond Jr. (The Strokes)がプロデュースし、期待のインディロックバンドとして多くのメディアの注目を集めた。2ndアルバムは2019年にリリースされ、約6ヶ月に及ぶ53都市のアルバムツアーを 遂行し、日本のみならず北京、上海、ニューヨークでチケット完売となる快挙を達成。そして、3rd アルバム『A DAZE IN A HAZE』は「Sink」や 「Half of Me」といった話題楽曲が収録された万人に愛される作品となった。昨年2022年には完全セルフプロデュースアルバム『Thirst』が世界中で大きな反響を呼び、タイで開催された『Mahorasop Festival』に出演、そしてUSツアーを行った。2025年夏には数々の野外フェスへの出演、そしてアルバムリリースツアーも予定されており活動が活発化している。
Live

DYGL “Who’s in the House?” TOUR
【石川公演】
▼9月15日(月・祝) 金沢AZ
【愛知公演】
▼9月17日(水) 名古屋クラブクアトロ
PICK UP!!
【大阪公演】
▼9月18日(木) 19:30
梅田クラブクアトロ
スタンディング-5000円(整理番号付、ドリンク代別途要)
スタンディング(U-22)-4000円(22歳以下、整理番号付、ドリンク代別途要)
スタンディング(U-18)-2000円(18歳以下、整理番号付、ドリンク代別途要)
※未就学児童は入場不可。入場時に生年月日の確認を実施いたしますので必ず身分証をご持参下さいませ。身分証を忘れた場合、チケット代の差額をその場にていただきます。
[問]SMASH WEST■06-6535-5569
【新潟公演】
▼9月23日(火・祝) 新潟CLUB RIVERST
【東京公演】
▼9月26日(金) Spotify O-EAST
【北海道公演】
▼10月1日(水) cube garden
【福岡公演】
▼10月19日(日) The Voodoo Lounge
【香川公演】
▼10月23日(木) TOONICE
PICK UP!!
【京都公演】
▼10月24日(金) 19:00
磔磔
スタンディング-5000円(ドリンク代別途要)
スタンディング Under22-4000円(ドリンク代別途要)
スタンディング Under18-2000円(ドリンク代別途要)
※未就学児童入場不可。入場時に生年月日の確認を実施いたしますので必ず身分証をご持参下さいませ。身分証を忘れた場合、チケット代の差額をその場にていただきます。
[問]キョードーインフォメーション■0570-200-888
Link
DYGL Official Site
https://dayglotheband.com/
Instagram
https://www.instagram.com/dayglotheband/
YouTube
https://www.youtube.com/@DYGL

























