
ホーム > インタビュー&レポート > 名曲誕生から31年、初の試みとなる琉奏でのデュエットで 『島唄~琉奏~』を配信。同曲がテーマ曲の 『大阪・大正 沖縄フェスティバル2023 ~沖縄からの風~』が 10月9日(月・祝)開催! 宮沢和史インタビュー

名曲誕生から31年、初の試みとなる琉奏でのデュエットで
『島唄~琉奏~』を配信。同曲がテーマ曲の
『大阪・大正 沖縄フェスティバル2023 ~沖縄からの風~』が
10月9日(月・祝)開催! 宮沢和史インタビュー
今年で二回目となる『大阪・大正 沖縄フェスティバル2023 ~沖縄からの風~』。同フェスのテーマ曲となる『島唄~琉奏~』(宮沢和史 with 親川遥)が9月13日にリリースされた。今回のような琉球古典音楽の楽器演奏によるデュエットという形は意外にも初めて。その元となる『島唄』が最初に世に出たのは1992年。生みの親である宮沢和史がボーカリストとして活動していたTHE BOOMのアルバム『思春期』の中に収録されていた一曲で、その後にシングルとしてリリースされると国内での大ヒットに止まらず世界的に知られる名曲となった。今回、ぴあ関西版WEBでは『島唄』を30年以上歌い続けてきた彼の思いから新たに『島唄~琉奏~』が完成するまでの経緯はもちろん、『大阪・大正 沖縄フェスティバル』を立ち上げた理由について訊いた。南米やヨーロッパなど世界各国で歌い、音楽を通して人と文化をより深く繋げて行こうとする彼自身の原動力とは何なのか。心を掴む真摯な言葉と共に、時代を超えて受け継がれる『島唄』と沖縄の魅力に触れてほしい。
『島唄』は器みたいな曲
聴いてくれる人が自分の経験から思いをのせる
――最初に『島唄』のお話からお聞きします。この曲はリリースから30年以上経ちますが、宮沢さんは常に新しい曲と思って歌ってきたそうですね。
「自分が作った歌を繰り返し歌うのが仕事なんですけど、『島唄』に関しては、繰り返すっていう感じがあんまりしないんです。ちょっと大袈裟かもしれませんけど、生まれ変わるっていうか、今日初めて歌うんだっていう気持ちになるんですよね。さあ始めるぞって(構えた時に)、どうやって終わるんだろうっていう感じで、もう1回ドキドキするというか...。それは1人でやっても、バンドでやってもそうなんですよね。そういう意味で自分の中で古い歌にならないんです」
――大ヒットした曲を歌い続けることが嫌になる方もいらっしゃると思うんですけど、宮沢さんは『島唄』を歌うときにそうはならなかったと。
「そういう時がなかったわけじゃないんですけど。新しいチャレンジをしようとしてる時は過去がちょっと邪魔になる時もあるじゃないですか。だから、今やりたいこととちょっと違うなという時もなくはなかったんですけど...。『島唄』には沖縄の永久(とこしえ)の平和を獲得することであるとか、(第二次世界大戦下)沖縄で亡くなった20万人の命への弔いの気持ちを込めています。さらに、この30年間の間にはいろんな悲劇がありました。阪神淡路大震災、東日本大震災、湾岸戦争やアメリカの同時多発テロもありました。だから、沖縄への思いで作った歌なんですけど、毎回、歌う意味が変わってくるというか。東日本大震災の時には、あそこで亡くなった行方不明者も含めた2万数千人の人たちへの弔いの気持ちが歌ってると生まれてくるし、そういうことで常に新しく感じていたのかもしれないですね」
――聴き手も『島唄』には時代時代でいろんな思いが重なってくるんでしょうね。
「『島唄』ってシンプルなメロディーで、歌詞もシンプルだし、器のような曲であって、そこに聴いてくれた人がいろいろのせてくれるっていう、そんな歌なのかなと思うんですよね。たとえ言葉が違う国で歌っても、聴いてくれる人が自分の経験の中からものをのせる、 そういう器みたいなものだと解釈してます。いろんな国で歌ったり、いろんな人とコラボレーションしてこの歌を歌うと お客さんが喜んでくれるんです。例えばポーランドで歌うと、昔のドイツから迫害とか虐殺を受けた彼らの悲しみが、『島唄』という歌に乗っかってくるのだと思います。それは歌う前に現地の言葉でこの歌はこういう悲劇があって生まれた歌ですと、説明するからなんですけど。そうすると、お客さんは、自分たちの歴史の中にある悲しみとか、そういうものと重ねて聴いてくれると思うんですよね」
発表から31年を経て原点に帰ろうと
すべて琉球古典音楽の楽器で演奏した
『島唄~琉奏~』(宮沢和史 with 親川遥)
――『島唄』が最初に収録されたのは宮沢さんがやっていたTHE BOOMの『思春期』(1992年発表)というアルバムで、その後シングルとしてリリースされました。そして今回、新しくレコーディングされた『島唄~琉奏~』が届きました。
「『島唄』自身も僕自身も、いろいろ旅を経てきて、いろんな国で歌いましたし、日本全国いろんなところで、子供の前で歌ったり、お年寄りの前で歌ったりしてきて。発表してから31年が経ちました。もともとロックバンドが三線を持つというスタイルが『島唄』でしたけど。ここへ来て、ちょっと原点に帰ろうと、今度はすべて琉球古典音楽の楽器で演奏する『島唄』を作ってみようと思いまして。『島唄』が旅をしてきて、いろんなことがあって、沖縄に帰ってきたというか、そういう仕上げにしようと思いまして、沖縄の琉球古典音楽をやってる若い演奏家たち、僕の子供ぐらいの世代の子たちにアレンジも演奏もしてもらいました。だから、すごく感慨深いものがありますね。今まで発表してきた『島唄』で一番沖縄らしい琉球の音楽になりました」
――それで今回は、『島唄~琉奏~』とタイトルに表記されているんですね。演奏されている楽器について教えてください。みなさんが正統派の沖縄古典音楽家なんですね。
「そうですね。歌う人と三線は一体なので、歌三線、箏、胡弓(クーチョー)、笛、太鼓です」
――親川さんの凛とした美しい歌声と宮沢さんの深みと説得力がある声が重なることで今までにない感動を与えてくれます。今回、琉球古典音楽演奏家の親川遥さんとデュエットという形で歌うことになった経緯というのは?
「沖縄のRBC琉球放送で『時の首里彩画』という番組がありまして(※沖縄の古都・首里を舞台に、史跡、伝統、人、芸術など、その魅力を余すところなく伝える番組)。その番組の音楽を親川さんが担当していて、古典音楽を1曲歌うんです。僕はナレーションをしてまして、その番組を通して出会ったんです。それがきっかけで、昨年の『大阪・大正 沖縄フェスティバル』に出演してもらって意気投合して。今回一緒にやることが実現しました。そして、演奏家とアレンジャーを決めて、沖縄で録音しました」
――宮沢さんご自身は、レコーディングの時はどういう気持ちで臨まれたのでしょうか。
「とにかく若い子たちの自主性に全部任しました。迷ってたらなにか言ってあげるくらいな感じで」
――仕上がった曲を聴いて、どういうようなお気持ちになりましたか。
「『島唄』は琉球古典音楽ではないので、あくまでも現代の音楽ですけど。それが本当にいつの時代の歌なんだろうっていうぐらい...原点に帰れてるし。そういう意味では時を超えたところへ到達したなぁ...っていう感慨深さはありましたね。2023年の発表ですけど、いつの時代の音楽かもわからない感じですよね。何百年も前の楽器の演奏と同じ演奏をしてるわけですから。そういう意味では、この世に今までなかったものが誕生したっていう感慨もありますよね。これから改めて沖縄の人にも聴いてほしいですし、沖縄の楽器ってこういうものなのかっていうのを本土の人間にも聴いてほしいですね。あと、そういう古典音楽に携わっている沖縄の若い子たちがたくさんいるっていうことも、これを機会に知ってほしいなと思います。伝統を守っていく意思のある子がやっていて、それが具現化された作品だと思うんですよね」
――今回の配信で初めて聞かれる若い方もいるかもしれないですね。ロシアのウクライナ侵攻など不穏な世界情勢ですが、戦争はしたくないし、今の時代を生きている人間に平和への祈りが込められた『島唄』が届いてほしいですね。
「沖縄でも戦争体験者が毎年少なくなっていく中で、戦争を知らない若い子が増えてることを実感しますので、この歌をきっかけにどんどん掘り下げてくれるといいなと。ま、今はインターネットの時代だから、調べようと思えばいくらで深く知ることができるので、そのきっかけに改めてなれば、この歌の役割もまだあるのかなって気がします」
『大阪・大正 沖縄フェスティバル~沖縄からの風~』では
より民謡とか伝統音楽に近いものを発信していきたい
――『島唄』は未来に伝えていかなければいけない歌ですよね。この曲が、今年開催される『大阪・大正沖縄フェスティバル2023~沖縄からの風~』のテーマ曲にもなっていますね。会場がある大正区は宮沢さんご自身もお馴染みの場所ということで?
「そうですね。沖縄は貧しい時代が長かったので、海外に移民として渡り、関西では尼崎、大正、関東では横浜の鶴見に出稼ぎに来ました。大正区は沖縄の人が集まって街を作って、最初に来た人が後から来た人の家を作ってやったりしてきた歴史があります。沖縄は年中行事がとても大事で、正月は旧正月だったり、シーミーという春の墓参りがあり、お盆にはエイサーがあるので。そういう年中行事を大正区ではきちんとやられています。そういうところなので僕はすごく好きで、ずっと応援をしていたつもりなんですけど、この機会に、沖縄にある各自治体のお祭りみたいなことが再現できないかなと思って、去年立ち上げました。大正区の沖縄の人たちは昔は結構苦労されています。大阪とは文化も違うし、言葉も違うし、大変な時代を乗り越えられてきた方々なので、ずっと応援してたんですけど、その話を大正区と沖縄県人会に話したら、ぜひ一緒にやろうと言ってくださって。キョードーさんやFM COCOLOさんも協賛という形で大阪・大正 沖縄フェスティバル委員会みたいなの作りました。誰が主催っていうよりもみんなでチームを作ってやってるんです」
――会場の平尾公園は普段は地元の人が野球をしたりする場所で、そこに屋台が出たりする素朴さを残したフェスですね。今年はどのような内容になりますか。
「二部構成になっていて、一部は地元の沖縄県人会のグループでエイサーや舞踊、民謡やポップスなどを披露して、二部はプロが出ます。それぞれの歌い手が素晴らしいし内容的には相当濃いものになると思います。去年は沖縄出身者(沖縄本島)が基本的に多かったんですけど。今回はいろんな島に渡っていて。沖縄民謡と言ってもいろんな島の唄が聴けるというのが、前回との1番大きな違いですかね。大城クラウディアはアルゼンチン出身ですし、親川遥さんは沖縄本島、城南海さんは奄美大島(鹿児島県)、鳩間可奈子は八重山の鳩間島出身、宮良康正さんは与那国島出身、ゆいゆいシスターズは沖縄本島。宮良康正さんは沖縄で初めて 日本の民謡大会で優勝した人ですね(※与那国民謡の第一人者。八重山古典民謡技能保持者で無形文化財)」
――そんな実力派が大正区で一堂に会するというのはとても貴重ですね。
「はい、貴重だし、それも大正区で聞けるっていうのがものすごいことだと思います。だからそんなに沖縄に詳しくない大阪の人も、ぜひふらっと来てもらって、沖縄の民謡にもいろいろあるんだなと、いろんな島によって違うんだなというところが楽しめると思います」
――宮沢さんご自身はどういう演目を考えていますか。親川さんとのデュエットも聴けますか?
「はい、考えています。去年は本当に裏方みたいな感じでしたけど。僕はオーガナイザーでもあるので、全体の演出を考えながら、自分の歌も去年よりちょっと多く歌うかもしれないですね。まだ決めてないんですけど」
――それは当日のお楽しみということですね。では、改めて今回の見どころや初めて行かれる方に向けてメッセージをお願いします。
「沖縄をテーマにしたフェスティバルっていうのは日本全国いろんなところで開催されていて、それぞれ素晴らしいフェスがあるんですけど、どちらかというとポップスが多いんですよね。ウチナーポップっていうか。それはそれで良いんですけど。僕らがやるのは、より民謡とか伝統音楽に近いものをなるべく発信していきたいので。そこは他のフェスとちょっと違うところですかね。だいたい沖縄フェスティバルというと沖縄ポップスの人が集まるという感じになりがちなんです。だからもっと民謡の素晴らしさとか、本当の島唄っていうのを聴いてほしいなと。聴けば絶対に魅力はわかってもらえるっていう自信があるので。そういう場を作っていきたいなっていうのがこの『大阪・大正 沖縄フェスティバル』ですね。それと、大阪の人でも大正区に行ったことがない人もいるかもしれないので。これをきっかけに大正区に来てくれたら大正区の人も嬉しいだろうなと。大正区の人たちと話してみるとふたつのふるさとがあるっていうか、遠い沖縄への思いと大阪人としてのプライドと、皆さん両方持ってらっしゃいます。そういうのを知ってほしいし、なんで僕がこんなに沖縄のいろんなところから大正区に人を連れてくるかっていうと、やっぱ彼らにも知ってほしいんですよ。関西にこんなに沖縄を愛してる人たちがいるんだよっていうことを、それを沖縄の人に伝えてほしいっていう思いもあるので。沖縄の人には大正区を知ってほしいし、大阪の人にはここにも沖縄があることを目撃してほしいというのがテーマです」
――そういう橋渡しというか、人や文化を繋げたいという熱い思いが宮沢さんの中にあるんですね。
「うん。僕は南米とかハワイとか、沖縄の人たちだけじゃないんだけど、移民で渡った人たちの文化と深く関わってきたので、沖縄っていうのは沖縄だけにあるんじゃないっていうのは、もう肌身でわかっています。先月もブラジルとアルゼンチンとペルーをまわって、沖縄県人会の日系の人たちと深く交流してきてるんですけど。彼らはものすごく沖縄を大事にしています。大正区もそうで、そういうことを僕は見てきたので、みんなに伝えてあげたいなって。沖縄の人にも、ブラジルではこんなに伝統を守ってるんですよ、こんなに上手い人がいるんですよと。これに参加した人もまた沖縄に帰って、こんなだったよって言ってくれるといいかなと思います」
――そのために国内だけでなく海外にまで出て行かれるモチベーションになっているのはやっぱり宮沢さんご自身の使命感みたいなものから?
「いや、使命感っていうほど重くは考えてないですけど、好きなんでね。人と関わってお祭りを作るとかフェスティバルをやるのが。8月にブラジルに行ったときも県人会と一緒に民謡のコンサートをしたんです。一部は僕の解説と民謡の唄をライブでやって、2部は地元のエイサーとか舞踊と一緒にコラボレーションするっていう構成で。南米では僕が行き始めた30年前と今では状況が全然違ってるんですけど、たとえ(沖縄の)言葉が喋れなくても、琉球舞踊を習ってたり、空手習ってたり、エイサーをやってたりするんです。BEGINの歌とかみんなよく知ってるけど、民謡は聴いても意味がわからないと。だんだん世代もそうなってきていて、それは沖縄でもいえることなんですけど。民謡の説明をしながら歌をやるっていう歌会みたいなのを開くと、みんな本当に喜んでくれるんですよね。あ、そういうことだったんですか、こういう歌だったんだとか。大正区でもそうなんですけど、ちょっとした橋渡し役みたいなことを してあげると、より文化がどんどん深く繋がっていくし、(伝統を引き継ぐことを)志す若者が増えてきたり、子供たちが興味を持ってくれたりするので、 そういうことをしてるのは好きなんですよね。そして、種を蒔いて、また実って、あの時の出会いがこうなりましたみたいなことがいっぱいあるんです。沖縄の日系人の世界は世界中に広まってますから、音楽を通してそこが繋がったりするのは、すごくやりがいがあります」
――その文化の中心には音楽があって、それを通して歴史も学びますしね。
「そうですね。だから、新曲を書いて発表して、それを売ってツアーしてっていうのが楽しいんですけど、僕は音楽家としてそれだけじゃ物足りないというか。こういうことしてるのは僕の音楽活動だし、これが一番僕の最先端の音楽活動。そういう感じで日々やってますね。だからこの人たちの歌を聴きにきてほしいですね。すごいクオリティですから」
――沖縄の音楽を野外で生で体感するとより大きな感動がありますね。
「特に大正区で聴くとね、しみじみするよね。あの仮説ステージで聴くと」
――そもそも、このフェスを実現したプロジェクトは、2021年にリリースされたアルバム『沖縄からの風~沖縄から生まれた名曲たち~』(宮沢和史、夏川りみ、大城クラウディア)がきっかけで生まれたんですね。
「そうなんです、だから夏川りみもこれに出なきゃいけないんですけど、タイミングが合わなくて。いずれ出てもらいます」
Text by エイミー野中
(2023年10月 2日更新)
Tweet Check
Release
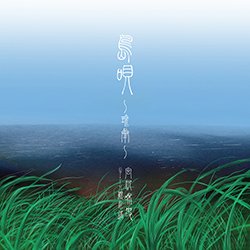
Profile
1966年山梨県甲府市生まれ。THE BOOMのボーカリストとして1989年にデビューして以降、類い稀なる探究心と行動力で、生命力あふれる音楽の源泉を求め国内外を巡り、これまでに、THE BOOMとしてアルバムを14枚、宮沢和史としてアルバムを4枚、多国籍バンドGANGA ZUMBAとしてアルバムを2枚リリースしている。代表曲のひとつである『島唄』はアルゼンチンでの大ヒットを(2001年)をはじめ、各国のミュージシャンにカバーされており、国境を超えて今なお世界に広がり続けている。デビューのきっかけとなったTHE BOOMは25周年を迎えた2014年3月31日、長いバンド活動の歴史に幕を閉じることを発表。作家としても、SMAP、小泉今日子、矢野顕子、喜納昌吉、友部正人、夏川りみ、MISIA、中島美嘉、岡田准一(V6)、石川さゆり、坂本冬美など、多くのミュージシャンに詞、曲を提供している。『島唄』のリリースから30年を迎えた2022年には、『島唄』が誕生した背景やその後の体験を書かれた自身のエッセイと対談で構成された『沖縄のことを聞かせてください』(双葉社)が刊行。さらに、2023年9月13日に『島唄~琉奏~』(宮沢和史 with 親川遥)が配信された。今回のような琉奏というスタイルでのデュエットは初の試みとなる。10月9日(月・祝)には『大阪・大正 沖縄フェスティバル2023 ~沖縄からの風~』(大阪市大正区平尾公園グラウンド)が開催される。
宮沢和史 オフィシャルサイト
https://www.miyazawa-kazufumi.jp/
Live
『大阪・大正 沖縄フェスティバル2023~沖縄からの風~』
チケット発売中 Pコード:247-508
▼10月9日(月・祝) 13:30
大阪市大正区 平尾公園
一般(中学生以上)-3900円(ブロック指定)
一般(中学生以上)+子供1名-3900円(ブロック指定)
一般(中学生以上)+子供2名-3900円(ブロック指定)
[出演]宮沢和史、大城クラウディア、親川遥、城南海、鳩間可奈子、宮良康正、ゆいゆいシスターズ、他
[MC]加美幸伸(FM COCOLO DJ)
※雨天決行(エリア内での傘は使用不可)、荒天中止。
※エリア内レジャーシート持ち込み可。
※中学生以上有料。小学生以下のお子様は保護者1名につき2名まで無料。申込時にお子様1名か2名を選んでください。保護者さまと同時入場となります。(子供同士のみの入場は不可。)
※販売期間中はインターネット販売のみ。1人4枚まで。チケットの発券は、10/2(月)朝10:00以降となります。
[問]キョードーインフォメーション
■0570-200-888

























