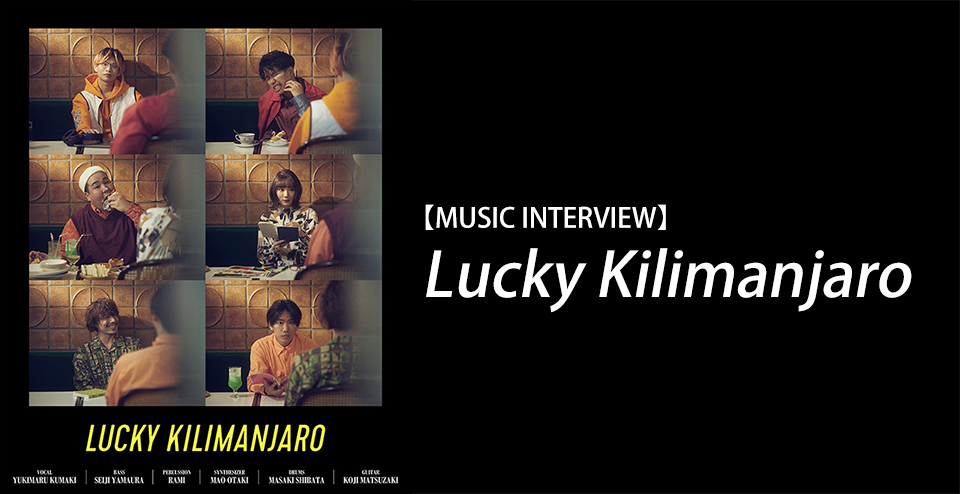“悲しい時こそ、おどる選択を”
シングル『ファジーサマー』で提案する、変化の中での自由
Lucky Kilimanjaroインタビュー
同じ大学の軽音サークルで出会った6人によって2014年に結成された、Lucky Kilimanjaro(以下、ラッキリ)。「世界中の毎日をおどらせる」というテーマを掲げ、2018年にメジャーデビュー。2021年4月には日比谷野外音楽堂での初ワンマンを大成功で終え、春と秋には2度にわたる全国ツアーを完遂。今年3月には3rdアルバム『TOUGH PLAY』をリリースし、バンド史上最大規模の全国ツアーを終えたばかり。そんな彼らが7月13日にニューシングル『ファジーサマー』を配信リリース。どんな時でも「おどる」ことを提唱してきた熊木だが、今回は日々の生活でどうしても避けられない、暗く気持ちが落ち込んだ時、弱さが顔を覗かせた時に「おどる曲」にフォーカス。カップリングの『地獄の踊り場』も同様のテーマで、サウンド面に於いてもダンスミュージックの可能性と使い方を深く追求した楽曲だ。しっとりとした質感ながら心地良く踊ってしまうのは、さすがラッキリ。今回はボーカル・熊木幸丸に、シングルについて、9月から始まるツアーについて、そして大阪のオーディエンスについてたっぷりと話を聞いた。
『ファジーサマー』は翻弄される気持ちに対して
どのように踊るかの1つの提案
――まずは、ご結婚おめでとうございます!
「ありがとうございます。バンド内での結婚とはいえ、別にバンドの活動が変わるわけじゃないし、引き続き皆さんが楽しくなれるような音楽を届けていきます。こうやってお祝いいただいて、純粋に嬉しいですね」
――これから作られる音楽も変化するかもしれませんね。
「自分の経験がそのまま歌詞になったり、自分の思考が全部音楽に出てくるので、結婚が音楽に影響がないかといったら絶対そんなことなくて、何かしらの影響は多分あるだろうなと思うけど、それも含めて自分の変化を楽しんでる最中だと思います」
――今「変化を楽しむ」というワードがありましたが、シングル曲『ファジーサマー』は、変化し続けている中で翻弄される感覚を歌にされています。今年6月に行われたアルバム『TOUGH PLAY』リリースツアー(『Lucky Kilimanjaro presents.TOUR“TOUGH PLAY”』)ファイナルのパシフィコ横浜で新曲のリリースを発表されたそうで。その時曲は完成していたんですか。
「もう曲はできていたんですけど、冒頭の歌い回しをちゃんと音源で届けたいなと思ったので、ツアーでは曲はやらずに発表だけしましたね」
――今までもそういうパターンだったんでしょうか。
「前年度のシングル『踊りの合図(2021年リリース)』は、ツアーのシークレットでずっと演奏していて、そのままリリースという形もあったり。その曲がどういうふうに受けとられて、どういうふうに皆の中で大事な曲になっていくかという過程をよく考えて、リリースの形を決めていますね」
――今回に関しては音源で聞いてもらいたかったと。
「あとはもうちょっと暑くなってから聞いてほしいなと。最初に皆に音源を聞いてもらうタイミングって、多分自分のパーソナルなスペースだと思うんですけど、この曲を最初に皆が吸収するにはそこがいいのかなと。ちゃんと踊らせる曲としても機能させたいけど、まずは皆が1人になれるタイミングで聞いてほしいと思いました」
――テーマに関しては、何かキッカケがあって作られたんですか。
「今年はロシアとウクライナの戦争が勃発したり、コロナ禍でライブができるようになっても難しい状態があったり、感染者数がすごく増えたり。単純に理解しきれない複雑な状況が続いて、自分も複雑な気持ちがたくさん芽生えた2022年前半だったなという印象があります。それで自分の心が不安定になった状態が多かった時に、人間は日常生活の中で心が安定してる状態って実はそんなにないんじゃないかと思うようになって。この不安定な状態を安定させようとするんじゃなく、変化し続ける毎日の中で、“不安定な状態で踊る選択ができるんじゃないか”と思ったことがキッカケです」
――なるほど。
「僕は、悲しい気持ちや虚しい気持ち、苦しい気持ちを乗せて踊れるからダンスミュージックが大好きなんですね。踊る行為は本当はもっと悲しい時にも使うことができるんですけど、こと日本においては、踊りがそういう対象として見られていない側面がある。悲しい時こそ踊る選択をすることをもっと広めていきたいし、そういう文化を根付かせていきたいです」
――確かに日本人は、悲しい場面で笑ったりすると不謹慎だとか言われますもんね。
「“踊る=皆でワイワイするもの”だと思ってる。当然そういう楽しさもあるんですけど、僕は1人で部屋の中で踊りながら聞くミュージックが成立すると思っているし、僕の中ではごく自然なことなんです。そういう感覚を日本の音楽文化の中にどんどん入れ込みたいですね」
――日本人は真面目な人が多いですしね。全体的に歌詞を読んで、ネガティヴな出来事で感情が翻弄されるんだけど、それが嫌だという感じは全く受けませんでした。
「自分の気持ちが外部の事象に掻き乱されるストレスは当然あって。さすがに楽しいまではいけないんですけど、でも生活ってそういうものというか。他者とのコミュニケーションの中で自分の気持ちが変化するのは当たり前のこと。それ自体をないものにはできないからこそ、翻弄されることに対してどのように自分が乗りこなすことができるかという“提案”をしたいなと。僕はダンスミュージックにその機能があると思っています。特に『ファジーサマー』は翻弄される気持ちに対して、どのように踊っていくかの1つの提案です」
――なるほど。聞いた人にはどう受け取ってほしいですか。
「不安の形は人それぞれだと思うんですけど、気持ちがグラグラしてるタイミングに踊れる曲があると思ってもらえたらいいなと。そういう曲として皆の中で大事な曲になってくれたら、すごく嬉しいですね」
――サウンド面で言うと、質感的には前作『TOUGH PLAY』よりも重たい感じがしますね。
「『TOUGH PLAY』は、自分の中ではカラッとしている明るいサウンドが多くて。トーン的には暗い曲もありましたが、『ファジーサマー』はよりしっとりした曲になったなと思います。皆の心の中で踊れるダンスミュージックはどんなサウンドがいいかというところで試行錯誤した結果、こうなりました」
――特に苦労された点はありましたか。
「気持ちの不安定さをどうサウンドで表現するか。もやっとしている柔らかいビートの部分と、しっかり踊れるビートの部分のコントラストをつけるところで、柔らかい部分は柔らかいながらも、どうやったら体が動くものになるだろうと。はっきり踊るところとゆったり踊れるところをどう住みわけて、でもそれぞれが分離しないで必然性を持たせられるか、お互い必要なものとして作れるか、すごく悩みました。2つとも別のパートっぽく聞こえちゃよくないですし、急に展開が変わりすぎちゃうのもよくないなと。コントラストをつけるバランスにすごく苦労しました。差し引きしたりして、“ここだな”と思うところを落とし込みました」
――結構時間をかけられたんですか。
「今回はかかったかな。やっぱりジャッジが難しいところがあって。自由度があった分、本当にハマるものを探すのが大変でした」
――自由度があったというのは?
「ビートにはいろいろなサウンドの作り方があって。選択肢はものすごく多いんですけど、どう噛み合わせるのが1番気持ち良いのか、そしてこの曲のテーマに合うのかを探す作業に時間がかかりました」
――作業する中で、参考にした音楽はありました?
「今年はアフロビートのダンスミュージックがすごく多くて、去年から南アフリカのダンスミュージックをたくさん聞いていて。それとハウスミュージックの融合が1番自分の中でしっくりきて。“ここかもな”というところで制作はスタートはしてましたね」
――『ファジーサマー』からは、翻弄される中で生きる美しい生命力も感じました。
「それこそちょっとした不安の動きの中にも、できるだけそれが絵としてじゃなく動画として存在するように音を散りばめていて。変化というものは時間軸の話なので、常に音が変わり続けている状況が見えるといいなと思って作り上げて、自分の歌い方も声のトーンの変化をたくさんつけるようにしています。そうやって全体のテーマの“変化していく状態で踊る”をサウンドで表現しました」
誰にでも闇がある。ギャルだって、いつだって明るいわけじゃない
――カップリングの『地獄の踊り場』は、ものすごい肯定の曲だなと感じました。
「自分の中では何を肯定とするか難しい部分はありますけど、気持ちのアップダウンはどんな人でも絶対あると思っていて。ダウンしている状態から無理にアップしなくちゃと考えるのはあまり良くない。絶対に現れる周期の中でダウン自体も味わったり、ダウン自体に自分の中で意味を持ちたいというのがあって。気持ちの沈んだタイミングで踊れる曲をちゃんと書きたいと思って書きました」
――起きたことも感情も否定しない、感情の波で落ち込んで自分を責めるのではなく、沈むことすらも認めるという肯定の仕方ですね。
「そうですね。涙を忘れるんじゃなくて、涙そのものの味をちゃんと噛みしめようねという曲。そんな曲がもっとあっていいと思います」
――歌詞に“寄りかかれるベースがないと 漏れる弱さの住所がないと”とありますが、まさにこの曲自体が“寄りかかれるベース”なんじゃないかなと。
「住所、ベースって“自分の拠点”という意味もありますけど、ドラムンベースを参照したのもあって、ダブルミーニングでベースを使ってます。低音のベースと居場所としてのベース、ふたつの意味があります」
――人は1人では生きていけないんだということも同時に感じました。
「僕も人とつながる中で生きてる感覚があって。でも、それが自分の気持ちの不安定さを生み出している。その中でどんなふうに気持ちの変化に対して対応していくか、どのように乗りこなしていくか。『ファジーサマー』も『地獄の踊り場』もそこがテーマになっています。そういうことを歌いたくなっているタイミングなのかなと」
――2曲のテーマが近いことに関して、意図はしていなかったんですか。
「敢えて重ねようとは思ってなかったけど、自分でしっくりくる歌詞を書いたらこうなった感じですね。自分自身すごく気持ちの変化が多くて、ずっとアップの状態ではいられないんだという実感があって。その変化に対してどうダンスミュージックを当てていくかを考えた時期でした」
――あと「ギャルじゃない」という歌詞がすごく気になりまして。
「“気持ちの無敵性”みたいなことを、“ギャル”で代弁させられるなと思って。ただその意味で僕が歌詞で入れていいのかなと思ったんですけど……自分の気持ちが強くないタイミングを説明するのに“ギャルじゃない”と表現するのは、歌詞全体がカジュアルダウンして良いな、と。暗い曲に聞こえすぎちゃうとこの曲の本意が伝わらない感じがあるから、やっぱりギャルを入れたいとなりました。」
――私は結構ギャルのマインドが羨ましいなと思う時があるのですが、熊木さんはいかがですか。
「羨ましいとも思いますし、別にギャルだって、いつだって明るいわけじゃないというか」
――確かに。
「“ギャル=明るい”みたいなイメージは、多分明るいタイミングを僕が見ているからであって、闇の瞬間もあると思う。すごく楽しそうな人でも、1人になったらどんな気持ちでいるんだろうとか。そういう意味で、“いつだってギャルじゃない”という歌詞は、本当はギャルにも当てはまると思って。どんな人にでも絶対暗さがあるというのは、いつも感じてることですね」
――皆に地獄の面があると頭の隅に置いておけば、優しくなりますよね。
「そう、人に対して優しくなれる(笑)」
――熊木さんは昔から、ご自身の状態のアップダウンを認めることができていたんですか?
「状態の変化自体は当たり前にあるなって、ここ何年かずっと思うことがあります。そこで、暗くなる時間をなくすのは無理だと考えるようになり、じゃあどうしようと開き直ってる感じではあります。まだ暗い気持ちに対してイエスとは言えないですけど、存在はするよねっていう状態にはなっています」
――暗い気持ちの期間が長かったりした?
「長いかどうかは覚えてないんですけど、暗い気持ちをうまく自分の中で消化できないことは多かったなと思いますね。今も消化できてる感覚はないですけど、昔よりも自分なりの乗りこなし方を少しずつ覚えてるのかなという感じがします」
――熊木さんの乗りこなし方でいうと、具体的には?
「暗い気持ちの時こそ、机に向かって曲を書いたりします。自分の中で1番良くないのが、何もしない状態。停滞してる状態が1番沈みが続きやすい。落ち込んでいるからこそ、その気持ちを曲にすることで違う意味を与えられたり、他の人が共感できる曲になったり。少なくとも暗い気持ちだけど動こうとは思っています。暗い気持ちに対して動きを与えたいというのがテーマになりましたし、聞いてる人にも、暗い気持ちを明るくしなくてもいいから動きを与えたいというのがあります」
――ラップの部分で“ぐらつくなら踊れ 取り持つよ闇との関係”というリリックがありますが、今おっしゃられたことに近いのかなと。
「そうですね。不安定な状態を安定させようとすると、負のスパイラルに入っちゃう気がして。だからこそ、ちょっとスピードを上げてみるということを、この音楽でお手伝いできればなと思います」
――歌詞には前作のアルバムタイトル『TOUGH PLAY』が入っています。
「僕は結構、過去の曲のタイトルや歌詞を入れたり引用することで地続きの日々の表現ができるかなと思っています。『TOUGH PLAY』自体は、自分の好きなものを大事にしようというパワフルなメッセージが多かったんですけど、『地獄の踊り場』では、それとはちょっと違った自分の弱さにフォーカスしました。“『TOUGH PLAY』できるばかりじゃない”、という対比が面白いかなと」
――強さと弱さの対比ですね。
「強い部分を歌うことは、当然僕は大事だと思っていて。でも同時にどうやって弱い部分に向き合うのかも伝える。僕はそういうことを考えてしまう人間だし、それをちゃんとダンスミュージックで伝えられた方がいいから『地獄の踊り場』では、そこにフォーカスしているのかな」
――『TOUGH PLAY』から、さらに内部に潜っていくような。
「外側にも内部にも行けるものを作りたいというのがあって。『ファジーサマー』と『地獄の踊り場』は、『TOUGH PLAY』よりもある種、皆とつながろうという想いがすごく強いです。皆の大事なダンスミュージックになろうという感覚はあるから、意識は外に向いているけど、曲自体は内を向いている。それが今の自分の心情なのかなとは思います」
ダンスミュージックは皆の気持ちに寄り添える、ソウルフルなもの
――ジャケットは初めて熊木さんお1人でのポートレートを使用されていますね。
「自分のアップのポートレートは初めてですね。シンプルに、聞く人の受け取り方によって化学反応の仕方が違うだろうと思って。僕、この曲にそんなに“こうしてほしい”というメッセージはあまりなくて。“状態の変化や、気持ちのゴロゴロはあるものだよね”ということを歌っていて。皆の気持ちのゴロゴロとどう反応するかは予想がつかないんです。それも含めてあまり希望的なジャケットにしたくないなと思って。単純に自分は自分の歌だけを伝えるという点で、シンプルなジャケットがこの曲に合うのかなと思って、今回ポートレートにしました」
――目線やポーズは。
「色々撮っていくつかの候補から選びました。服もCGじゃなくて変な形の服なんです。流動性があるように感じて、絵自体がちょっと動いてるように見えるので、それはいいなと」
――こういうお洋服にしたいとリクエストされたんですか?
「特に指定はなかったんですけど、テーマは伝えていて。その上でスタイリストさんが面白い服あるよと提案してくださいました。良いジャケットになったと思います」
――『ファジーサマー』と『地獄の踊り場』を聞いて、「自分らしさ・ありのまま」という単語が浮かんできました。自分の好きなものを“好き”と言って大切にする気持ちや、暗い闇のような気持ちすら認める。それは何も否定しないことなので、「自分をありのまま認める」ことなのかなと感じたんですが、熊木さんは、自分らしさやありのままについてどういう考えをお持ちですか。
「音楽家という職業で、特に僕なんかは本当に好きなことをやっているだけなので、自分らしさが皆と一致するのかもあまりわからないですが、自分の気持ちの反応に正直であるのが自分らしさかなと思っています。でもそれだけだとうまくいかないというか、僕らは人との関係性の中で生きている。だからこそ、他の人とのコミュニケーションで自分らしさを作っていくのが大事だなと。なので、“自分の好きなことだけやればいい”とは思っていなくて、僕も他の人と踊るからこそできているダンスミュージックがあるから、人との関わり方に自分らしさを見つけていきたいと思っています。ここら辺は今も本当にやっていく最中で、回答は都度変化しているんですけど、自分らしさというものが、個の自分だけで形成されるのではなく、他者との関係性の中で形成されているものだと最近は思っています
――ラッキリのライブに行くと、“私ってこんな一面あったんだ”みたいな、自分の中に確実にいる知らない自分が引き出される気がします。それはラッキリの音楽だからこそできるんじゃないかなと思いました。
「ダンスミュージックって、自分の隠してた自分がちょっとオッケーになれるというか、ちょっと強気になれる気がするんですね」
――確かに!
「自分の中で自由になれる。それが続いた方が本当は良いと思うけど、そういう瞬間が今までの人生で2%ぐらいしかなかったのが、5%、10%ぐらいになったら、ちょっと人生が楽しくなる。そういうふうに僕らのライブや音源が、皆に届いてくれればいい。僕もどちらかと言うと暗いことを考える方が多いので、ダンスミュージックに引っ張ってもらってる部分はあります」
――ダンスミュージックはチャラいものだ、ファッション的だと思ってる人、たくさんいますよね。
「どうしてもここ10年ぐらいだと、EDMとかいわゆるチャラい人がめちゃくちゃ踊ってるイメージがあると思うんですけど、むしろダンスミュージックは抑圧された歴史の中で生まれた背景があって。本当は皆の気持ちに寄り添える、ソウルフルなものなんですよ。そこをちゃんと僕らの音楽で伝えたいです。楽しく踊るのもすごく好きだから、それも伝えたいですけど。皆がロックミュージックを聴いているように、ダンスミュージックも本当は泣けるし、人生において大事な曲になる可能性がある。二面性を伝える活動をしていきたいです」
より“踊ること”にフォーカスした『YAMAODORI 2022』
――そして『Lucky Kilimanjaro presents. TOUR ”YAMAODORI 2022”』が9月11日(日)の大阪城野外音楽堂を皮切りに始まります。大阪城野音は初めてだそうですが、意気込み的はどうですか。
「僕ら東京では日比谷野音をやったことがあって映像作品も出してるんですけど、Lucky Kilimanjaroの音楽は野外で皆で踊るのがすごく似合うと思うので、そういう空間を他の場所でもやりたいよねと。まずは大阪城野音というステージ、僕もまだ出たことはないですけど、すごく良い場所だと聞いていますので、夏を締め括る会場として、僕らもこの夏よく踊ったなと思える場所として今準備してます」
――大阪のお客さんの印象はどうですか。
「大阪のお客さんはワンマンもフェスもそうなんですけど、基本的にホットです。こっちがやられそうなくらい割と血圧高めにめちゃくちゃ答えてくれます。エネルギーがすごいんですよね。良いコミュニケーションしている印象があります。大変ですけど、楽しいです」
――大変ですか(笑)。
「どの会場でも、どういうふうにお客さんの熱量を回していこうかと考えながらパフォーマンスするんですけど、大阪はその熱量がすごい。“わ、ここでめっちゃくるんだ!”とか、そういうのに僕も乗っかったり、逆に自分が方向性を変えていったり。その波を作るのが楽しいですし大変でもあります(笑)」
――大阪は好きとなった瞬間に、全部の扉を全員がバッと開ける瞬間がありますね。
「でもこっちがちゃんとギア入れてないと答えてくれない」
――そうそう(笑)。
「いかにちゃんと僕が皆と“コミュニケーションを取ろうとするか”が、そのまま全体の空気につながるので、僕が涼しい顔でやったらもう全然ダメ(笑)」
――2021年は野音ワンマンと2本の全国ツアー、今年春には史上最大規模のツアーを経た『YAMAODORI』、どんな感じになりそうですか。
「各地で何回もライブを重ねてきて、皆の踊る自由度がどんどん上がってきてる印象があります。ただやっぱりまだフェスや僕らを知らない人の現場に立っていると、踊ることが当たり前ではない感覚がある。もっと自由に踊って、自分の気持ちを乗せていくことを僕らは伝えられるという想いがあるので、今回のツアーはより“踊ること”にフォーカスしようと思ってます」
――より、フォーカスするんですか。
「今までよりも、ポップスとダンスミュージックのバランスで目の前の人が踊る状態をどんどん作りたいと思っています。なかなか難しいんですけど(笑)。簡単に言えば、皆がよりダンスミュージックの面白さを知れる感じですかね。そういうライブをどんどんしていきたいし、今はそういうモチベーションです」
Text by ERI KUBOTA
(2022年8月31日更新)
Check