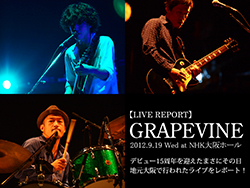ホーム > インタビュー&レポート > 「新境地になるのか、割といつもみたいな感じになるのかは(笑)、 やってみないと分からない」 人生に答えではなく問いかけをくれるGRAPEVINEという希望 『新しい果実』田中和将(vo&g)×亀井亨(ds)インタビュー

「新境地になるのか、割といつもみたいな感じになるのかは(笑)、
やってみないと分からない」
人生に答えではなく問いかけをくれるGRAPEVINEという希望
『新しい果実』田中和将(vo&g)×亀井亨(ds)インタビュー
1曲目の『ねずみ浄土』からその未体験の衝撃と感動に言葉を失うGRAPEVINEの最新アルバム『新しい果実』は、デビューから24年もの歳月を音楽に捧げながらもいまだに更新され続ける底なしのクリエイティブに、ロックバンドの理想形であり続ける揺るぎなきスタンスに、絶えることなき音楽的探究心と時代を投影した示唆に富んだメッセージに、このバンドの代わりなどどこにもいないと改めて思い知る孤高の1枚だ。現代社会で常態化する歪みや違和感が、ニューノーマルというお手軽なホットワードで丸め込まれそうな昨今。コロナ禍であぶり出された現実から目をそらさず、旧約聖書や文学作品からの巧みな引用=生きるヒントのような至言とユーモアを、ため息が出るほど美しいメロディと変幻自在のオルタナティブサウンドに乗せ、シーンにおもねることなく活動し続けるGRAPEVINEの田中和将(vo&g)と亀井亨(ds)が、リリースツアーの渦中に円熟という名の進化をやめない現在を語るインタビュー。人生に答えではなく問いかけをくれる音楽を。毎回恐るべきクオリティの作品を世に問い続ける妥協なきバンドが、またもとんでもないアルバムを生み出した――!
参考にしたものに寄せていこうというよりは
田中「この曲は自分らとしても手応えを感じているし、そう言っていただけるのは非常にうれしいですね。僕はブラックミュージックが好きでよく聴いてて、そういう音楽から触発されてデモを作るわけですけど、この曲の料理法に関してはバンドでやれるかどうかもそもそも分からなかった。“今までにやってない感じの曲を持っていったら面白くなるかな?”という気持ちで常に作っていますが、それが結果的に新境地になるのか、割といつもみたいな感じになるのかは(笑)、やってみないと分からないんですよね」
(2021年6月24日更新)
Tweet
Release

80s、R&B、ソウルetcも飲み込む
約2年ぶり17枚目の至高のオルタナ盤
Album
『新しい果実』
【初回限定盤2LIVE CD付】
発売中 5500円
SPEEDSTAR RECORDS
VIZL-1895
<収録曲>
01. ねずみ浄土
02. 目覚ましはいつも鳴りやまない
03. Gifted
04. 居眠り
05. ぬばたま
06. 阿
07. さみだれ
08. josh
09. リヴァイアサン
10. 最期にして至上の時
<LIVE CD収録曲(2枚組)>
『FALL TOUR 2020 at Nakano Sunplaza』
01. HOPE(軽め)
02. Arma
03. 豚の皿
04. また始まるために
05. 報道
06. すべてのありふれた光
07. The milk(of human kindness)
08. そら
09. 指先
10. here
11. Alright
12. 片側一車線の夢
13. 光について
14. CORE
15. 超える
16. 1977
17. NOS
18. ミスフライハイ
19. アナザーワールド

【通常盤】
発売中 3300円
SPEEDSTAR RECORDS
VICL-65501
<収録曲>
同上
Profile
グレイプバイン…写真左より、亀井亨(ds)、田中和将(vo&g)、西川弘剛(g)。’93年に大阪にて活動開始。バンド名はマーヴィン・ゲイの『I heard it through the grapevine』(’67)から借用。自主制作したカセットテープが注目を浴び、’97年にミニアルバム『覚醒』でメジャーデビュー。’99年には2枚のヒットシングル『スロウ』『光について』を含む2ndアルバム『Lifetime』がオリコン週間チャート3位に。’14年にレーベルを移籍し、『Lifetime』再現ライブ『IN A LIFETIME』を開催。’17年にはデビュー20周年を迎え、15thアルバム『ROADSIDE PROPHET』をリリース。’19年には16thアルバム『ALL THE LIGHT』をリリースし、音楽評論家や専門誌から高い評価を受ける。’20年11月に約1年ぶりとなる有観客でのホールワンマンツアー『GRAPEVINE FALL TOUR』を神奈川・神奈川県民ホール 大ホール、大阪・オリックス劇場、東京・中野サンプラザにて開催し、全公演のチケットが即ソールドアウトに。’21年3月には約2年ぶりの新曲『Gifted』を配信。4月には東京・日比谷野外大音楽堂にてワンマンライブ『GRAPEVINE LIVE AT HIBIYA PARK』を開催。『ねずみ浄土』『目覚ましはいつも鳴りやまない』の配信を経て、5月26日には17thアルバム『新しい果実』をリリース。キャリア24年目を迎えてもとどまることなく精力的に活動し、唯一無二のオルタナティブなロックサウンドで、シーンにおいて不動の存在感を放ち続けている。
GRAPEVINE オフィシャルサイト
https://www.grapevineonline.jp/
オフィシャルTwitter
https://twitter.com/news_grapevine
オフィシャルInstagram
https://www.instagram.com/news_grapevine/
オフィシャルFacebook
https://www.facebook.com/abandcalledgrapevine
オフィシャルYouTube Channel
https://www.youtube.com/channel/UC1IvZIgFhRCHlzAQiYTQ1tg
Live
リリースツアー開催中!
大阪公演はZepp Namba(OSAKA)で
『GRAPEVINE tour2021』
【福岡公演】
▼6月12日(土)DRUM LOGOS
【広島公演】
▼6月13日(日)広島クラブクアトロ
【岡山公演】
▼6月18日(金)CRAZYMAMA KINGDOM
【静岡公演】
▼6月20日(日)SOUND SHOWER ark
Pick Up!!
【大阪公演】
チケット発売中 Pコード195-945
※販売期間中はインターネット(PC・スマートフォン)でのみ販売。通常電話での予約受付、店頭での直接販売はなし。
▼7月2日(金)19:00
Zepp Namba(OSAKA)
全席指定5300 円
サウンドクリエーター■https://www.sound-c.co.jp
※未就学児童は入場不可。
【愛知公演】
▼7月3日(土)日本特殊陶業市民会館
ビレッジホール
【東京公演】
▼7月8日(木)Zepp DiverCity(TOKYO)
【新潟公演】
▼9月4日(土)NIIGATA LOTS
【宮城公演】
▼9月5日(日)チームスマイル・仙台PIT
【東京公演】
▼9月15日(水)LINE CUBE SHIBUYA
Column
『Best of GRAPEVINE
1997-2012』を引っ提げた
GRAPEVINEのデビュー15周年
アニバーサリーライブ!
キャリアを辿る濃厚にして
ベスト・オブ・ベストな地元大阪
NHKホールをレポート!!('12)
Recommend!!
ライター奥“ボウイ”昌史さんの
オススメコメントはコチラ!
「自分がこの業界に入る前から活動しているバンドが、今でも驚かせてくれること。取材前に歴代のアルバムを聴き直したときもそのクオリティに心底感心しましたが、傑作とか唯一無二とか、安易に言いたくない言葉が何度も思い浮かぶ『新しい果実』、すっげーわ。一貫したスタンスを保ちつつそのサウンドは絶え間なく形態を変え、かつバインでしかないメッセージと音楽になる。土下座です。涙が出るほど美しい。意図せず聴いた『ねずみ浄土』にぶっ飛んだ後に決まった今回の取材に、運命を感じましたわ。“ダーリン”と“降臨”と“ころりん” で韻を踏んでこんなにキマる歌い手が、この世に他にいるだろうかと(笑)。今年聴いて衝撃を受けたのは、KO NAKASHIMAの『Emanon』と間違いなくこの曲で。『新しい果実』、俺的今年度暫定No.1アルバムをぜひ聴いてください」