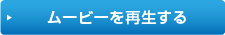バンドの暗黒期をブレイクスルーしてたどり着いた
THE NAMPA BOYSの闘争宣言たる2ndミニアルバム『バトルズ』
負け犬たちのプライドを懸けて挑むバンド人生を語る
小林聡里(vo&g)インタビュー&動画コメントが到着!
15歳、長野県松本市の少年たちは、今やメジャーの登竜門となった10代限定フェス『閃光ライオット』でファイナリストに。19歳、ドラマ『クローバー』のオープニングテーマに大抜擢、シングル『プランジ』でメジャーデビュー。そして現在、メンバー全員まだ20歳。こうやって挙げ連ねると申し分のない足跡と輝ける未来が待っていそうなTHE NAMPA BOYSも、’05年の結成から早8年、決して短くはないバンド人生の中で、メンバーの脱退から解散から再結成から育成契約から契約解除まで経験済み(笑)。特に昨年7月にミニアルバム『froM』のリリース以降は、小林聡里(vo&g)曰く「暗黒期」というかつてない苦悩と葛藤の日々を過ごしていたという。そんな彼らから遂に届いた1年3ヵ月ぶりの2ndミニアルバム『バトルズ』は、“Wordsプロデュース”にいしわたり淳治を迎えたのも見事機能し、サウンドのパンプアップと共に言葉にも明らかな変化がもたらされ、傷も涙も力に変換するタフさと覚悟を高らかに鳴らす、現在のバンドのテンションを見事に刻み込んだ1枚となっている。そこで、関西でのワンマンライブ、そしてカウントダウンライブを前に、当初のリリースを延期してまで決死の想いでたどり着いた『バトルズ』の制作過程に迫るインタビューをお届け。フロントマンの小林は、今作で自らを“負け犬”と呼んだ。だがその目には、今にも噛み付きそうな情熱を宿していた。そう、闘いは続くのだ。
小林聡里(vo&g)の割としっかりとした動画コメント!
――昨年はデビューも含めていろんなことがあったと思いますけど、率直に今までを振り返ってみてどうですか?
「’12年の初めに事務所の社長に、“ドラマのコンペに出したら(オープニングテーマに)決まった。どうする?”みたいに呼ばれて。僕らは前の年から上京はしてたんですけど、とりあえず’12年は育成期間で、ライブを重ねて’13~’14年くらいのデビューを目指していこう!みたいな話だったんですけど、いきなりそんな話がきて。戸惑いながらも断る理由もないので“やります!”って(笑)」
――いい話ですもんね(笑)。
「まぁ実力試しというか、バンドのこれからの成長を思って始まった’12年で、リリースからトントンと進んで、その余韻が10月くらいまであったんですね。さて次をどうしようっていう話になって、本当は今年の春くらいにもう1枚出したいねとは言ってたんですけど、ライブをやっていてお客さんに届いている実感があんまりないというか…柵前50cmの人たちを奮い立たせることが出来ない。そういう歯がゆさがすごくあって」
――結成は’05年とバンドとしてある程度のキャリアがあっても、改めてそういうことを感じたんですね。
「デビューしたらトントン拍子で人気者になれるのかなとか淡い考えがあったんですけど、なかなかそういうわけでもない。甘くないんだなって痛感して。そういう状況でCDを出しても1枚目の『froM』の焼き直しというか、ストック放出みたいな感じになっちゃうなって。10年20年先に繋がっていくものがあるかな?って思っちゃったんですよ。思っちゃったからには、絶対に出さない方がいいって。もうレコーディング始めるかどうかみたいなところで、“本当にすいません!”って。そこで言われたのは、“出さないという選択肢にはそれなりの覚悟が必要だよ”って」
――制作、宣伝、流通…すでに動き出してるこの流れを止めるということは。
「でも、そこで妥協して一生残っていくものを出すんだったら、そこは覚悟の上で、“本当に申し訳ないですけど、ちゃんと1からやり直します”って。そこからが暗黒期というか(笑)」
――リリースを延期する、仕切り直す判断をしたのはいつ頃だったの?
「今年の2月とか3月ですかね。ライブもうまくいかないし、お客さんがつくわけでもないし、今思えば何だったんだろうっていう感じなんですけど、自分の意識がバンドを責める方向に向いてて。“お前のドラムがよくないからうまくいかないんだ”とか、“お前のギターが”って」
――よく見るバンドの崩壊していく姿ですね(笑)。
「そうなんですよ(笑)。そんなことやりながらもライブをしてたんですけど、その内いろんなバンドの楽しいライブを観ていたら、それがすごくちっぽけなことに思えてきて。自分はクールなバンド像というか、言いたいことを包み隠して届けることが美しいと思ってやってきたんですけど、それをTHE NAMPA BOYSがやったところでカッコよくないな、面白くないなと思ったんですよ。そこから生まれたのが『MAKEINU SONG』(M-1)で。まず自分を負け犬と呼ぶ。その上で、でも俺は絶対負けないからなって言う。自分たちは負け犬だと認めてしまうなんて、今までのバンドの歴史上なかったことなんで。それから始まったのが今回の『バトルズ』で、ある意味『MAKEINU SONG』は起死回生の曲っていう感じなんですけど」
――傍から見たら10代でドラマのタイアップでデビューして、レーベル主催のカウントダウンでは1万人とかいる前でライブとか、めちゃくちゃ順風満帆に見えるけど、そう簡単にはいかないということやったんやね。
「『MAKEINU SONG』に“闘いは続く”っていう言葉があるんですけど、一番のキーポイントはこれだなって。それこそ傍からTHE NAMPA BOYSいいじゃん、人気出てきてるじゃんみたいに思ってた人も、日々の生活の中で戦いはあると思うし、バンドもギリギリのものですから、ずっと戦ってる。そういうことを俺は歌いたいんだって。その1つの証しとして『バトルズ』を出したいっていうテーマが決まって、そこからすごくバンドが楽しくなってきて」
――面白いね。状況的にはそのまま普通に出してたら、誰にも迷惑をかけずに済んだ。こうやって戦うことを選ぶのって苦しいやん。でも、それを選ぶことによってバンドが楽しくなっていく。
「こうやって今『バトルズ』を出せたことに俺はすごい満足していますし、THE NAMPA BOYSとしてのスタイルを示すことが出来たのが単純に嬉しい。今はすごく、ホッとしています。スッキリした気持ちです。どんどんこれから楽しくなっていくんだろうなって。もちろん、まだまだいろんな衝突もあるとは思うんですけど」
マイナスの気持ちをエナジーに変えていくのが自分のスタイル
――今作は『MAKEINU SONG』から始まっていったとのことやったけど、それには何か強いきっかけがあった?
「自分の原動力はマイナスのところから始まっている。マイナスの気持ちをエナジーに変えていくのが自分のスタイルだって、吹っ切れた瞬間があったんですよ。例えば、暗黒期に着の身着のままみたいな感じで渋谷の街を歩いてたときに、お姉ちゃんが“アハハ”と笑ってて。何かそれが無性にムカついて、ムカつくからそれを叫ぶ曲を書こう、それをみんなと共有したい、歌いたい、それを俺らが高らかに歌ったら面白くね?ってふと思って、そのときに気持ちがポップになった気がしたんですよ。実際そのお姉ちゃんもそんなこと全然思ってないと思うし(笑)、俺を笑ってたのかどうかも分からない。でも、いざその気持ちを曲にしてライブでやってみたら、みんな歌ってくれたんですよ。それで、今のTHE NAMPA BOYSのカッコいいはこれなのかもって」
――この曲をきっかけにバンド自体も道が開けたというか、閉塞感を打破出来るかもみたいなムードがメンバー間にも出てきたと。
「そうですね。俺も自分がバンドに与えられるものは何だろう、逆にメンバーから俺が与えられているものって何だろうっていろいろ考えたとき、バンドでしか出来ないことをやろうとしてるのに、何で自分でバンドを傷付けるようなことをしてたのか。それは自傷行為でしかないと気付いて。もちろんぬるくなっちゃいけないんですけど、俺が出来ないことを彼らのせいにするんじゃなくて、そこを認めて、このバンドで何が出来るのか。下手くそかもしれないけど、カッコいいことが出来るんだって、バンドの一番いいところを音で見せていきたい意図があって、RECもみんなで一発録りでやっていった感じですかね」
――そう考えたら、バンドにとってめちゃくちゃ重要な作品やね。
「いいタイミングだったのかなって。もし何となく売れてそれなりの感じになってたら、つるっとこのバンドは終わってたかもしれない」
サウンドに引っ張られて言葉も強くなっていったのはあると思う
――前作『froM』も聴かせてもらって思うのは、今回は明らかに詞が違うよね。要は小林くんの言葉というか、人が見える。分かりやすくなったって言ったら、ヘンな言い方かもしれないけど。
「お客さんに対して親切になりたい。多分そこが今まで一番足りてなかったところだと思うんですよね。今までの包み隠して言うバンドのスタイルに対しても、確固たる自信はなかったんですよ。ただ、何となくやりやすいじゃないですか。選びやすい言葉を当てはめていってね。でも、そうじゃなくて、ストレートに投げて、自分の言いたいことを言って、お客さんに問いかける。それが一番親切というか、ライブをやっていく中で、そこに寄り添っていきたいなと思ったんですよ」
――歌詞に関しては、全曲変わったと思いましたね。小林くんが何に心が動いたかが明確に音楽で分かるというか。その辺は、言葉に引っ張られて楽曲が強くなっているのか、楽曲の強さに引っ張られて言葉も強くなったのか。
「サウンドはすごくデカいと思いますね。前作では音楽的に美しいものは何かを突き詰めてやってたんですけど、今回はそこじゃない。“ロックとして”って簡単に言うのはあまり好きじゃないけど、このタッチミスはイケてるとかそういうのも全部ロックという言葉にうまく当てはめて消化しちゃう。狙ってやったわけじゃないけど、したたかになる。それがTHE NAMPA BOYS的には面白いなと思って。若干意地悪いなと思うんですけど(笑)。サウンドに引っ張られて言葉も強くなっていったのはあると思う」
――今回のソングライティングは曲先? 詞先?
「まちまちですね。『MAKEINU SONG』なんかは渋谷からの帰りにiPhone片手にサビを叫んで。サビが先に出来ちゃったんですよ。そのフレーズがボンとあって、でもオーオーオーオーって言いたくて、無理やりのリズムチェンジを(笑)。こんなことやっていいのかな?とか今までならずっと気にしてたんですけど、そういうのも取っ払って、カッコいいものはカッコいいからって」
――完全にサビでテンポ変わるもんね(笑)。今回はいしわたり淳治さんが“Wordsプロデュース”ということやけど、実際に作業してみてどうでした?
「例えば『MAKEINU SONG』の“お高いスーツの姉ちゃんが笑う”は、最初は“スニーカーを履いた姉ちゃんが笑う”だったんですよ。それは俺の実体験に基づいてたんですけど、それって分かりづらくね?って。淳治さんは“例えばそれは本当じゃなくてもいいんだよ”って。お客さんに対して見せるのは俺の悩んでいる姿じゃなくて、俺に限りなく近い人物かどうなのかで、それはフィクションでも全然いいんです。“お高いスーツ”の方がお姉ちゃんを高尚な人物として見せられて、自分を負け犬としている対比が明らかに出来る。そこってすごい重要なところで、“それが親切になれるかどうかだ”っていう話を聞いて、なるほどな!って。それってすごく分かりやすいし、俺が体験したことに嘘をついてるわけじゃないし。スゲェな~って」
――伝えたいことは“スニーカーを履いているかどうか”じゃないもんね。ホンマに先生って感じやね(笑)。
「国語の授業だわって(笑)。そこはめちゃくちゃ勉強になりました。歌詞は学ぶものでもないと思うんですけど、“メソッド”はあるんだなっていう感じですね」
――いしわたりさんはどういう方ですか?
「面白い人でしたよ。最初は結構怖い人なのかなと思ってたんですけど。こないだ実家に帰って掘り出してきたんですけど(笑)、SNOOZERのスーパーカーの解散インタビューのイメージがずっとあったんで(※バンドの内情を語った衝撃的な内容が当時話題に)。俺からしたら、“スーパーカーの淳治”なわけですよ。やっぱり緊張はしたんですけど、そこは負けたらダメだなと。いざ話してみたら、“THE NAMPA BOYSは真面目だよね。音はすごくカッコいいし、長くやってきてるからスタイルも確立されていると思うけど、真面目にやり過ぎちゃうと、どうしても真っ直ぐしか見えなくなっちゃうから。もっと広い視野で楽しんだらいいんじゃない? その方がお客さんも絶対に喜ぶと思う”って。確かにそれって暗黒期のときに自分たちでも薄々思っていたことだったというか。自分たちが向かっている方向と淳治さんが思っていたことが合致したので、いいタイミングだったなと。だからすごくスッキリする言葉と、スッキリする曲になっていったっていう。ウジウジしてる場合じゃねぇなと」
――だからこそ、このアルバム特有の風通しのよさとか明快さがあるのかもしれませんね。
みんなYouTubeで1曲聴いただけで“このバンドを知ってる”って
分かるわけないだろって
――あと、今作では東京に出てきた者ならではの目線があるなと思って。
「あ~。田舎者ですからね(笑)」
――東京生まれ東京育ちでも書けないし、松本に住み続けてても出てこない言葉というか。
「そこはやっぱり俺もシティボーイに憧れますし(笑)、でも、そこも負け犬と一緒なんですよ。なれないんだなって自覚したからこそ、自分のスタイルが出てくる。そこでじゃあダメだっていうことじゃなくて、何がカッコいいのかを模索していくのが、バンドの面白いところだと思うので」
――ちなみに『ネイヴァーリンの音楽家』(M-4)の“ネイヴァーリン”って?
「架空の街なんですけど、造語です。これは言わないようにしてたんですけど、“粘り”の音楽家っていう(笑)」
――なるほど! “スリーコードで粘った未来”というフレーズもあるもんね。
「最初は、まだ俺は粘るんだ!っていう音楽家の歌だったんですけど、『ハーメルンの笛吹き男』みたいな、ドイツの街っぽい感じにしたくて“ネイヴァーリン”(笑)。ちょっと恥ずかしくて」
――ググっても出てこなかったから(笑)。この曲はギターも粘りがあるよね(笑)。
「実はこの曲、結構大事だと思ってるんですけど、昌孝(g)が初めて書いた曲なんですよ。自己再生じゃないですけど、バンドマンに対して自分も含め鼓舞していくというか」
――あと、『バトルズ』というタイトルについても、改めてここで話してもらえれば。
「言葉の響きは某バンドからまんま取ってたりするんですけど(笑)、今って情報は何でも入ってくるし、YouTubeでパッと見れるし、新しいバンドが出てきたらささっとチェック出来る。でも、松本にいた頃はSNOOZER読んで、地元の中古CD屋『ほんやらどお』でCD買って聴いて、音楽を掘っていくのって楽しいなと思ってた。バトルズもそういう流れで知って、訳分からんなと思って聴いてはいたんですけど(笑)。簡単に全部入ってこないのは、田舎の強みでもあると思うんですよ。逆に楽しいことがそれしかなかったのも、よかったなと思うんですけど」
――いい意味での抑制が、田舎というフィルターでかかるという(笑)。
「みんなYouTubeで1曲聴いただけで“このバンドを知ってる”って、分かるわけないだろって。やっぱりアルバム聴かなきゃ絶対に分からないですし、ライブも観なきゃ分からない。だからとにかく聴いて、何がどうなのか分からないけど聴いて、何かピンときたら好きな音楽になっていく。それが一番正しいかどうかは分からないですけど、俺はそれが楽しいと思ってやってきたんで。そこはTHE NAMPA BOYSの旨みとして、俺がカッコいいと思うことをやるということに繋がっているのかなって」
何だか分からないけど面白いっていうのが一番燃える
――今作のリリースに伴い、『MAKEINU SONG』のMVの制作費をCAMPFIRE(=クラウドファンディング)で募って。映画の『SAVE THE CLUB NOON』をはじめ、結構そういう成功例しか見てこなかったけど。
「まさかの(笑)」
――アハハハハ!(笑) チャレンジしたものの(笑)。
「目標の10分の1くらいで(笑)」
――でも行ってきたわけですよね、MVを撮りに上海へ。
「面白かったですね。監督が俺の望んでいるクリエイター気質をすごく持っていた人だったんで。やっぱ面白くないから、ライブハウスで演奏して負け犬ソングだっていうのは」
――浮かぶね、イメージ(笑)。ライブハウスで汗だくで演奏しているっていう。
「じゃあどうします?っていうところで、監督が“上海行こうや”って(笑)。最初は何言ってんだこの人は?って思ったんですけど、何だか分からないけど面白いっていうのが一番燃えると思ったんですよね。コンセプトとかは後付けも出来るんで、まずはやってみようと。それが=国を出るって、いきなり規模がデカ過ぎるんですけど(笑)。最終的に面白いものが出来たので」
――バンドの転機となる作品が出来たよね。
「カッコいいことやってるんだっていう確固たるものが1枚出来たことによって、すごく自信になりました。暗黒期はずっと自分を疑ってたんですけど、誰も俺の才能を否定しているわけではないし、どこに問題があるかと言ったらメソッドの部分だけなんで。そこをしっかりやってれば、いいコンテンツは絶対に出来ていくし、前に転がっていくはずだから大丈夫って思えたのは、すごくデカかったと思います」
――12月13日(金)にはFandangoでワンマン、そして大晦日はカウントダウンライブ『Ready Set Go!!』で大阪城ホールと、闘いは続くと。この先のTHE NAMPA BOYSを楽しみにしていますよ!
「はい! ありがとうございました!」
Text by 奥“ボウイ”昌史
(2013年12月10日更新)