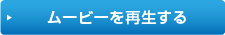ニコ生、さよならミッドナイト、お金、地方、音楽で食べていくこと
類まれなソングライティングとギター1本でサヴァイブする
“旅するシンガーソングライター”大柴広己の12年
音楽を信じ、音楽で夢を見る、『BANK』インタビュー&動画コメント
“テーブルの上に 缶ビールとコンドーム となりで眠ってるぼくの恋人”というセンセーショナルなはじまりを告げる名曲『さよならミッドナイト』が、ニコニコ動画でカバーされたのを皮切りに一躍話題となったシンガーソングライター、大柴広己。ところがどっこい、彼のキャリアは今年で12年。19歳で音楽活動を開始した彼は、天然パーマにハットにあごひげのファニーな佇まいに、ヒットポテンシャルを備えた類まれなるソングライティングのセンスと、切なさ成分を潤沢に含んだハスキーボイスを携えて、長年活動してきたアーティストだ。だが、この12年の間に音楽シーンの状況は激変、デビューを射程距離に入れながら、幾つものプロジェクトが日の目を見ずに終わった彼は、いつしか“旅するシンガーソングライター”として、地方のカフェやライブバーへと、アコースティックギター片手に全国行脚を開始する。昨年、ニコ動の追い風の中、4年ぶりとなる3rdアルバム『さよならミッドナイト』、4thアルバム『ソングトラベル』を同時リリースし積年の想いに決着をつけ、空っぽから始まった2013年。僅か1年で届いた5thアルバム『BANK』には、ロックミュージックやポップソングにおける仮想敵とも言える“お金”をテーマとしたタイトル曲『BANK』、臓器提供をモチーフとした前代未聞の『ドナーソング』をはじめ、大柴広己というシンガーソングライターの変化と未来が詰まったエポックメイキングな1枚となっている。音楽を信じ、音楽で生活し、音楽で夢を見る、この12年間のストーリーを語り尽くすインタビュー。彼の名前をまだ知らなくても、遅くはない。シーンの狭間に迷い込んでいた男が、表通りでしっかりと前を向き歩いていく姿を、ぜひこれから一緒に見届けて欲しい。
火照っているのか?(笑) 大柴広己からの動画コメント!
――大柴との付き合いはそれなりに長いけど、今までこういう風に話を聞くことはなくて。こういうインタビューとかってやってるの?
「いや、全然やってこんかった。まあ言うても去年のリリースも4年ぶりとかやったし、ライブに来てくれた人たちに“リスタートしましたよ”って直接伝えたかったんで、どっちかって言うと手売りしたかったというか。今回は初めてちゃんとお店で販売するのもあるし、今まではだいたいライブで先行発売してたから、今回はようやくCDがリリースされてから、そのレコ発ライブをするっていう」
――ようやく真っ当なミュージシャンとしての段取りを。そう考えたら、結構長いこと音楽をやってきたわけやん。それで今改めて、こういう新鮮な楽しみというか初体験があるのはいいね。
「普通のやり方を敢えて今までやってこなかったから。今回初めてやってみたらね、ちゃんとお店ってCD置いてくれるねんなぁって(笑)。ただ、デビュー盤とかやったらお店も扱いやすいけど、もう5枚目やから(笑)。まぁイニシャル付いてるから入れとこかみたいな、半信半疑なバイヤーさんも結構おったと思うし、売りにくいCDやと思うけど、ちゃんと聴いてくれる熱意のあるお店の人は確かにいて。TSUTAYAの本店でインストアしたときとかも、ありえへんぐらい展開してくれてて、終わった後に何でこんなにしてくれてるんですか?って聞いたら、“だって音源がホントに素晴らしかったんで”って。アレは嬉しかったなぁ」
――音楽業界も今はもうドンドン人が辞めていくというか切られていく中で、踏ん張って残ってる現場にそういう人がいてくれるのは嬉しいね。そういうこともやってみないと分からんもんね。
「そやねん。今まではCDを作る側の人間としか仕事してこんかったけど、売る側の人間といろいろ喋ると、全然見えてなかったところが見えてきて。あ~これもっと早くやれば良かったなぁって思うことが、結構いろいろあった。今までは演者側の感覚というか、自分で売ることにそこまでアイデンティティを持ってなかったのが、変わってきたのはやっぱりあるし。何か…ちゃんと売って、聴いて欲しいなって。30になってようやく売れたいと思うというか、ちゃんと売りたいなって思う。そういう気持ちなったら必然的に周りに人が集まってきて」
――そういう変化には何か大きなきっかけがあるのかな?
「やっぱり去年リリースしたのは結構デカかったかなぁ。結局、ミュージシャンってアルバムを出さないと先に進めへんねん。ウダウダ4年間やってきて、曲はあるけどそれって半分生きてて半分死んでるような状態で。でもそのときは、メジャーが決まったらシングルにするかもしれんから置いとこうみたいに、ヘンにヤラしいところがあったのよ。でも、そういうのをガッとなくして全部形にしてしまうと、そこにすがることはもう出来ひん。それってミュージシャンにとって次のステップに行くためにはやらなアカンことで。それをやったから、今回は1年という短いスパンで『BANK』を出せたし」
――なるほど。4年もリリースが空いたのは、いつかくるであろうデビューのために曲を使い切らないように、自分の持ち球を置いてたんやな。でも、置いててもその効果を発揮しないもんね、曲たちって。
「そやねん。去年の春にアルバムを出せて、夏が終わったぐらいに今回の『BANK』の収録曲を書き始めたんやけど、『さよならミッドナイト』がニコ動でスゴい取り上げられたから、そのイメージもずっと引き摺ってたし、やっぱそれは大きかったよ。今までは全部自分の中にあるモノで作ってたのね。自分は何を伝えたいのかとか、そういうパーソナルなアルバム。ホントに1stから全部そう。けど今回は、全部自分の周りにあることばっかり歌ってる。“俺のことを聴いてくれ”っていうぐらいたいした人間でもないし、自分のことばっかりは歌えへんと気付いたときに、自分の周りにドキッとする要素がイッパイあることに気付いて。例えば、2曲目の『ドナーソング』は、俺が去年の9月に免許の更新に行ったら、最近は免許証の裏がドナーカードになってて。そこに“私は脳死後および心臓が停止した死後のいずれでも”って書いてあって、それでもうメロディが降ってきた。今までにドナーカードの曲とか、臓器提供の曲なんかないやん? で、去年の『MINAMI WHEEL 2012』の深夜帯のときに、出来たばかりのその曲を『臓器の歌』っていうタイトルで歌ってみたら、全員ドン引き(笑)」
――南堀江ZEROの明け方ね。俺もその場で聴いたけど、やっぱ覚えてたもん。めちゃくちゃインパクトあったよ。今回のアルバムの中でも、『ドナーソング』は1つのハイライトというか。
「あの曲が書けたから、こんなことすら歌になるんだって、結構勇気付けられたところはある。『誰かのために働けば』(M-3)も全然自分のことじゃなくて働く女性の立場の歌やねんけど、そういうのも書いたことなかったし。自分のことしか歌ってこなかった自分が、自分の外側にあるモノを歌うことに絞っていけたのは、結構『ドナーソング』がきっかけやったな」
――歌詞にも脳死、臓器、肝臓、腎臓、すい臓etcとかいう言葉が飛び交うけど、これって大柴的にも新しいけど、下手したら日本のポップス史上でも初とも言える言葉たちというか。こういうのが出てきたのもやっぱり、昨年の2枚同時リリースで完全に出し切ってたからやなと。今までの代表曲と言われる曲もほぼ入ってるし、自問自答してたり…取材用のメモにも、この2作は“より自分”と“4年に決着”って書いてる(笑)。
「4年に決着、まさにそれ。3rdの『さよならミッドナイト』なんかは、ホントに自分が出過ぎて自分でも聴けないんよね。出し過ぎた。でもそれがあったからスゴくフラットに自分がなれたというか。あそこで中途半端に出してたら、またその同一線上で曲を作っていたのかもしれんけど、気持ちがいいぐらいに出し切ってしまったから。もうホントにね、何にもなくなった。今回の『BANK』はキレイに空っぽになったから出来たアルバムやね。でも、衝撃的って言われるね、もういろんな人に(笑)」
誰も聴いたことがないような歌を書かないと、自分がドキドキせーへんのよ
――衝撃的と言えば、弾き語りシンガーソングライターのイメージを完全打破する、サイバーな高速ダンスナンバー『あれと、それ』が1曲目っていうのがやっぱり(笑)。
「ね(笑)。今までだったらありえないわけじゃない。でも、何かそれすらも許せてしまう心境になったというか。自分のアレンジを人に投げることもなかったし。あれは元々はよくライブを観に来てくれてたお客さんやった、ボカロのクリエイター“れるりり”くんのアレンジで。彼が『さよならミッドナイト』のカバーをボーカロイドにしてアップしてくれてスポットが当たったのもあって、それとはまたちょっと違う感じで一緒にやりたいねって話してた上での今回だったりするから。“どんな感じになったんかなぁ~”って最初に聴いたとき自分でも衝撃やったから(笑)、聴いてくれる人もみんなブッ飛ぶわって」
――最初にCD再生したとき、“あれ? 大柴こっち行ったん?”みたいな(笑)。
「そしたら2曲目が『ドナーソング』でしれっと(笑)」
――その辺の意図が見えて何かズルいなぁと思いながらね(笑)。より作家的な表現というか、ソングライティングでもいい意味で遊べるようになったよね。
「それはディレクターをやり始めたのも大きいかもね。谷口(貴洋)のレコーディングとかもやってるから、より自分を外側に置けるようになったから。例えばライブとかでも、グワァ~ッ!!と盛り上がってやってんねんけど、心の中では実はスゴい穏やかとか。熱くなり過ぎると人には伝わり切らへん。120%で歌って120%伝わりゃそれでいいけど、80%しか伝わらなかったら全然意味がない。でも30%で歌って120%伝わったら、それはそれで最高の伝え方やし。何かそういうことをいろいろと考えられるようになってきたというか。脱力の極意というかね」
――以前の大柴って我が強いというか、抑えてるフリしてめっちゃ自分出すみたいなところがあったけど(笑)、やっぱり年齢もあると思うし、自分のレーベルを立ち上げてディレクションをすることで、さっき言ったように客観的な目線を持てたことが、自分のアーティスト活動にも返ってきてるわけやね。そもそも自分のレーベル、ZOOLOGICALを立ち上げたのは?
「立ち上げるきっかけになったのも谷口で。谷口に会ったとき、“あ、この才能をちゃんと伝えないとアカン”って思った。谷口って動員をガーッ!と増やしてどうこうとか、爆発的にストリートライブをやってワンマン来てください!っていうタイプでもない。でも、この手の人間って絶対必要やねん。ただ現状、レコード会社はスゴく動きが遅い。今しか出来ないタイミングっていうものがあって、アーティストとしてもいい感じにクリエイティブになってるこの状態でアルバムを作ったら、とんでもないモノが出来る確信があったわけよ。でも、周りのレーベルに相談しても、“これを今からブラッシュアップして…”っていやいや、今やらんとコレいつやるん!? 今でしょ! みたいな感じになったんやけど(笑)。メジャーでやるとリリースが1年後とかになるやん。1年後のことを考えて今曲書いてるヤツおる!?っていう。インディーズやったら3ヵ月で出せるかもしれないし、今の考えをいい速度でそのまま形に出来る。これからの音楽ビジネスとか音楽業界って、そういう速度感がスゴく大事やと思った。で、それは多分メジャーでは出来ないと。だったら自分たちでやろうよって始まったプロジェクトが、ZOOLOGICAL」
――なるほど。じゃあ谷口くんがスゴく大きなきっかけやね。
「そやね。自分とは全然違うベクトルで、全然違う考え方で、全然違う才能を持ってる。そういう人間がまだ24歳とかで。コレはズバ抜けてるなぁって思ったのがきっかけやね」
――それでも自分も同業者なわけであり、言わばライバルでもある。自分の状況をよくしていかなければいけない中で、プロデュースってやっぱり人のための動きで。
「それはね、今の年齢になったから分かったことやけど、結局自分1人が盛り上がったって話にならへん。シーンとして盛り上がらんとオモシロくないというかね。90年代にはオフィス・オーガスタがああやってシンガーソングライターを盛り上げたシーンがあって。だけど今それはないし、ビジョンを持ってちゃんと歌を歌ってる、しっかりしたボトムを持ってる人間が、こういうレーベルから出してるんだっていう風に見られないとね、どうもよくない。バンドはバンドでシーンがちゃんとあるじゃないですか。だけどシンガーソングライターはあるようでない。フェスとかに出ても、シンガーソングライターっていうだけで、デカいステージじゃなくてアコースティック・ステージだったり。アレ何なん!?って。今回のワンマンライブも敢えて弾き語りでデカいライブハウスでやったりするのも、バンドシーンに対してのアンチテーゼみたいなモノもあるわけです」
――大柴って、シンガーソングライター歴何年?
「19からで、今年で31になるから12年」
――そう考えたらそこそこ長いよね。それこそ当時柔道をやってて骨折して、そのリハビリのためにギターを弾き始めて…続いたね。
「続いたし、俺アホやから覚えるのが遅いのよ。先読みはしてんねんけど、頭の回転と行動が全然伴ってない。でも、その遅いのが功を奏してるかなって。10年経ったからこそ出来ることがあるわけで=それは10年前にやっても仕方がないことで。だって10年前の歌詞とか、ホンットにヒドいからね(笑)。自分的にはこの12年間、学校に入って日本語とか音楽のことを勉強していった感じ。社会の仕組みがどういうことになってるのかも勉強していって、今もいろんなことを知りたい欲求が尽きないわけよ。だから続けられる。歌もそうやし、誰も聴いたことがないような歌を書かないと、自分がドキドキせーへんのよ。人間って一番最初に何かに触れるとき、触れたことのないものに触れるときってドキドキする。そういう感覚で音楽を聴いて欲しいのよね。『ドナーソング』に衝撃を受けたなら、多分それは聴いたことがないからやと思うねん。『あれと、それ』もクソ速い16ビートのカッティングでテンポが155とか、ありえへんのよ。けど、それ聴いたことないでしょ? カッコいいでしょ? って思わせたいよね、音楽で。じゃないと自分がドキドキしないし。そういう歌を今後も作っていくための決意表明みたいなところはある」
――いい表現にたどり着いたよね。時間はかかったけど。
「かかったけどよかったなって思うのは、今回のアルバムに対するレスポンスが、もう分かりやすいぐらいに返ってきてる。結果としてもちゃんと返ってきてるし。そういうことを自分がちゃんと実感出来たのが嬉しいよね。今までは全然実感出来ひんかったからさ」
俺の音楽が好きじゃなくても別にええわって
音楽をずっと好きでいてくれやって感じ
――今回のアルバム資料にも、“かかった経費:数千万、レコード会社:今回で6社目”とあって(笑)。それこそ出会ったときからメーカーが付いてはくれてるけどなかなか決まらへんとかその辺の話はチラホラ聞いてたけど、そもそも19歳でシンガーソングライターを始めてさ、どういうことが起きてたん?
「ジェイムス・テイラーとかも好きやったし、70年代のあのいい感じの雰囲気のアルバムが作りたいなっていうのがあって、1stアルバム『ミニスカート』(‘06)を出したのが23歳で。そのアルバムが、ものスゴく業界のおじさんたちにウケたのよ。それでメジャーのレーベルからたくさん話がきて、決まったのね。決まったんだけど結局、曲が出来なくなった。その理由は分かってて、一番ダメだったのは、自分の責任を他のヤツに投げたこと。自分のことなのに、人がやってくれるんじゃないかとか、何かそういう妙な期待感を人に投げちゃって…最初にボタンを掛け違ったんよね。そうなると、それ以降全部掛け違うやん? “あのときウンって言ったやん”“内心ホントはそんなことやりたくないんです”みたいな。もう掛け違ってるからどないもならへんし、自分でもよく分かんなくなって…。ボタンの掛け違いを直すためには、一度全部ほどくしかない。だから思い切ってバッとほどいてみたら、“アレ? 俺なんでこんな服着てるんやろ?”みたいな(笑)。しまいには、“そもそもこの服自体要る? 何でこんなことにプライドを持ってたんやろ?”ぐらいな感じにまでなってきて、じゃあもうバーン!っと脱いでしまえと(笑)。そうするとね、ちゃんと人と会話が出来るようになってきたり、曲も書けるようになってきて。まぁ今となっては自分がやらなきゃ誰もやってくれんしね(笑)」
――その復活の兆しはいつぐらい?
「26の終わりぐらいちゃう? 事務所も27で辞めて…27ってさ、ロックスターが死ぬ歳やん。でも俺、死ぬどころか売れてもないし、尚かつレコード会社クビになったで! どないすんの!?って(笑)。そのときに作った曲が『27歳』で(※3rdアルバム『さよならミッドナイト』収録)。今まではずっと求められてきたのもあんねんけど、君のために、誰かのために、あなたのために曲を書こうとしてた。でもその時点でズレてんのよ。だって自分のために書いてたし、自分のことを聴いてもらいたくてやってたから。なのに歌ってる歌詞が君のためだから嘘くさいわけ」
――さっきの思ってることと、やってることがっていう。
「でもそれにちゃんと気付いて、そのときに初めて何のために音楽をやってんのか考えて、それで『27歳』の“負けるもんか ぼくのために”っていう、君のためじゃない歌詞が初めて出来て、もうボロ泣きしてもうて。で、そのとき『27歳』をYouTubeにアップしたの。そしたら前の事務所がそれを見てたんやろね。“あの歌何や? 全然アカンやろ”みたいなダメ出しを間接的に言われて。アカンねや…俺めっちゃいいと思ってんねんけどこの曲って。でもそこでね、俺の自我の方が強かったの。いや、コレは絶対にいい。申し訳ないけど、あなたたちがやろうとしてたことと俺は根本的に合わないって、そのときに初めて自分の意見が出来たわけ。俺、コレやわと。それがデカかった」
――それで今の大柴に続く道が形成されていくわけやね。
「僕のためにって歌えたことが、それ以降の作風につながっていって。3rdの『さよならミッドナイト』、4thの『ソングトラベル』を作るきっかけになったと」
――そう考えたら今回はさ、その先に行ったもんね。
「そうやねん。だから今考えてることは、僕のためでも誰かのためでもなく、音楽のためみたいなところに行ってるのよ。俺、最近ライブの終わりに“音楽を好きでいてくれてありがとう”って言ったりすんねんけど、もう俺の音楽が好きじゃなくても別にええわっていうぐらいやねん。音楽をずっと好きでいてくれやって感じ。何かそういう心境になったから、人のレコーディングでディレクションも出来るようになったし」
――なるほどな。自分を愛しているんじゃなくて、音楽を愛していれば出来るもんね。
「そうそう。だから余計にいろんな歌を書けるようになったのはあるかな」
――でも、自分にとってめちゃくちゃデカい2枚のアルバムを去年出して、空っぽになった自覚があったのに曲は出てきたんやね。
「やっぱり出し切ることってむっちゃ怖いし、ホントにあのときは全部出したから。30曲ぐらいある候補の中から2枚で計14曲。この14曲には勝てないなと思ったから捨てた16曲やったし。逆に言うと、それぐらいの決意で収録した曲たちやったから。あの2枚を越えないといけないプレッシャーもあったし、怖かったけど、出てきた曲が今までとは全然違うからよかったんよね」
今までライブハウスでは出会わなかった音楽の一面を知った
――『さよならミッドナイト』以降、ニコ動での動きとかも含めて、大柴はインディペンデントな弾き語りシンガーソングライターにとっての活動のヒント的なポジションでもあったと思うけど、その辺は何がどうなって?
「でもそれはね、ホントにいいって言ってくれるリスナーがニコ動の中の人たちにスゴく多いから。今まではボカロの曲しか聴いたことがなかったとか、言うたら弾き語りのライブなんか観たことない人がほとんどだったわけよ。そこで、ライブハウスのスタッフをやってて俺のことをたまたま観たキクチリョウタが、ニコ生で俺の歌をカバーして歌い始めて。曲がまず完全に先に行ってもうて」
――で、自分もその世界に行った、みたいな。
「みんなが俺の曲をそうやって歌ってくれてるんやったら、直接ありがとうを言いに行こうって思ったわけ。実際にそうやって生放送をやったら、みんながスゴい感動してくれて。ニコ生にとっての30分って、雑談したり何かよく分かんない感じで終わったりとかなんやけど、こっちはよくライブハウスでやる尺やから慣れてるし、5曲プラスMCみたいな感覚で、ホントに残り10秒とかで“ありがとうございましたー!”ってキレイに終わったら、“何ですかこれ!? すげー!”みたいな(笑)。普通に歌もMCもありで完全に30分のライブを生放送でやって、それにリスナーがウワァ~!とかオーイェー!とか反応してくれるのを観てると、何か今までになかった感動があって」
――そう考えたら、今までの観念にはないところに、めっちゃくちゃデカいマーケットがあったってことやんね。
「尚かつニコ動のリスナーはほとんどが10代なの。高校生がたまにTwitterに書き込んでくれるけど、時には小学生も大柴さんの曲が云々って言ってるんだよ(笑)。ライブハウスに小学生は来ない。でもこの先を作っていくのは10代やから、そういう子たちが“大柴広己っていう人いいよね”って言ってくれてるのは、今までライブハウスでは出会わなかった音楽の一面を知ったというか。スゴく可能性を感じたし、自分が感動したのがやっぱり大きかったね」
――それは、ここまで続けてきたこと、年齢を重ねてきたこと、あと時代が変わってきたこと、全部が絡んでるね。
「ニコ動とかってネットの荒れた部分のイメージしかなかったわけ。実際、創成期はそんな感じやったらしいけど、俺がやり始めた頃は、みんなスゲェあたたかくて。実際、ニコ生がきっかけでライブに来てくれた人たちが、“いつも放送聴いてます”みたいに、ホントに目をキラキラさせて来るわけよ。しかも、実際そうやってライブに来るのが初めての人も結構多いわけ。そのときに、こういう人たちにちゃんと音楽を聴いてもらいたい、ちゃんと音楽を好きになってもらいたいなって思った」
――あと、今回のアルバムって『あれと、それ』みたいなサウンド的な冒険とか、『ドナーソング』みたいに視野そのものが新しい曲とかいろいろあるけど、同時に今まで大柴がやってきた道のりもちゃんと入ってて。その中でも歳相応のお題というか、今までにウェディング・ソングとか歌ったことあったっけ?って。
「サビも“僕と結婚しておくれ”って、スゴい一般ピープルやもんね(笑)。その『きせき』(M-5)は、実はニコ生の30分番組の中で曲を作って、次の回の30分で発表するっていう企画で、ホントに1時間で出来た曲で。それも、Twitterのフォロワーが4000人を越えたときに、記念放送でみんなからネタをもらって曲を書いてたら、ウェディング・ソングになっちゃったんだよ(笑)。まぁ自分の本質というか年齢的なモノもあるし、そういう状況と自分を照らし合わせたときに、どう思うかみたいな歌で」
――それに続く別れの曲『掌』(M-6)なんかもスゴく意味深というか。『きせき』と並んでるっていうのもまたね。
「これは実はね、今までの自分にサヨナラっていう歌なのよ。今回は自分以外のことを歌うのがテーマやったから、そういう意味では3rdアルバム、4thアルバムにお別れを告げる。もうそういう自分に、小ちゃいことにゴチャゴチャすがるのをやめようっていう。実は結構前に書いた曲なんでちょっとリライトして、今の心境を詰め込んで修正して。でも今回のアルバムのブルースの部分にはピッタリやなぁと。収録曲的には一番最後にこれを入れることが決まったんやけど、一緒に制作してるエンジニアさんも、“あぁ大柴、こういう曲が欲しかったんだよ”って。俺もパズルの最後のピースはこれだと思った」
人は点で、音楽で線になって、最終的に円になったらええなと
――そして、それこそアルバムのタイトル曲でもある『BANK』やけど、例えばロックミュージックとか、ポピュラーソングにおけるお金って、基本的には悪の象徴というかアンチの対象になるモノやけど、それを肯定するっていうね。“やりたいことがないのなら お金を貯めればいい”って。
「コレは昔、スガシカオさんがインタビューで言ってたことで(笑)。でも、その言葉がこの10年ずっと頭の中に残ってた。歌よりも残ってるもん、そのインタビュー。10年ずっと自分の中に居続けてくれたから、コレは是非歌にしたいなと思って作り始めたのよ。でも、『BANK』っていうアルバムタイトル自体は、最初から決まってて」
――この曲が出来る前に?
「そう。何かね、人生って余白というか、余計な部分がいっぱいあった方がええんちゃうかなって。美しい人生に、素敵な人生にするために、何かを貯めないといけない。お金を貯めればいいっていうのはあくまできっかけで、“お金”というよりは“貯める”っていう部分をもしかしたら伝えたかったんじゃないかなって。何かええなぁ、楽しいなぁって思う瞬間って、結構どうでもええこととかアホみたいな話をしてるときとかで、そういうくだらないことの中にちゃんとした本質が実はあって。そういうことをドンドン貯め込んでいった『BANK』は、テーマが全然違う7曲が1つの貯金箱に収まってるイメージなのよ。だからアルバムのジャケットも貯金箱になってる。それをガンッ!って割って曲を出す。自分の殻を破る意味もあるし、スゴくいろんな想いを『BANK』が書けたときにもらったのよ。だからアルバムのタイトルも『BANK』がいいなって、最初から思ってた」
――俺もよく人と話すけど、人生でコレっていうモノが見付からない自分はダメだってよく言うけど、見付からないまま終わる人って実は結構いると思うし、こういう風にちゃんと歌でそう言ってくれると、心強いよね。
「新潟にいいライブハウスがあって、“『BANK』のリリースパーティをやりましょう!”って誘ってくれたから行ってきたのね。そのオープニングアクトに19歳の大学生の女の娘がいて、やりたいことが全然分かんなくて、そのことで周りに責められるって。俺はやりたいことがたくさんあって今までやってきたけど、今の若い子たちは、例えばミュージシャンを目指しても音楽業界は傾いてる、CDの売り上げが下がってるとかで、夢を抱いてよし行こう!っていう感じにはもうなかなかならないわけよ。ミュージシャンだってバイトしてるのもみんな知ってるし。でも、そういう人たちに夢を持ってもらうためには、音楽で夢を見せるしかないやんか。きっかけを持ってもらうしかないと思ってるねん。この曲が響く人ってスゴく多いと思うのよ。成功者のラブソングは世の中に腐るほどあるけど、失敗してどうしようもないヤツらのラブソングなんてあんまりないから(笑)。ドラマだってハッピーエンドになるやん。でも人生がハッピーエンドになることなんかほとんどなくて。俺は世の中の80%の人は失敗してると思ってる。でもその80%の人に対しての歌がなかなかない。みんな悩んでるし、ミュージシャンだって悩んでる。そういうことを言っちゃいけない風潮が今までもスゴいあったけど、それを打破したいなぁって思ったところはスゴくあった」
――それこそさっきね、音楽業界もしんどくてっていう話になったけど、大柴って地方のライブバーとかを廻って音楽で食うという、1つのフォーマットというか成功例を実践して見せたのも、他のシンガーソングライターに意識されてるところもあると思ってて。
「俺には座右の銘があって、それは“Music For Eat”やねん。ずっとそう。それだけは12年間変わってなくて。一番不安だったのは何かと言うと、レコード会社に所属してときに毎月振り込まれる給料。この金何? 俺働いてもないし、曲も作ってないし、ライブもしてないのに、月末になったら10万とか15万振り込まれるわけで。“これがなくなったら俺、食えんくなるんかな?”っていうのが、一番怖かった。結局、それが全部なくなったとき、自分が働いた分だけが対価としてあるからお金に対してもスゴくシビアになれたし、俺がちゃんと頑張ったからもらえたんやって感じられたのもあるし。そういうことを感じてないと、リアルに音楽なんて出来ひんと思ってて。それって今までのやり方やフォーマットとはまたちょっと違うじゃない。俗に言う“どさ回り”って、レコード会社をクビになった人がやるカッコ悪いやり方や、みたいに見られてしまいがちやん。でも、俺がリクオさんにくっついて地方を廻ったとき、全然そんなんじゃないわって思った。地方にはこの街を何とかしたいって思ってる人たちがめっちゃおったの。この場所が好きやから、この場所を何とか盛り上げていきたい。向こうはライブを打ってそこを盛り上げる、こっちは呼んでもらった分また新しいミュージシャンを連れていく。そうやってつないでいく。俺は人は点で、音楽で線になって、最終的に円になったらええなと思ってそれをやってきた。そういうことが出来ていれば、一生やっていける実感があったんよ。あと、そうやってるとさ、俺っていうミュージシャンがどういう人なのかが、いろんな人に伝わりやすくなってきて。昔は、“お前はどうやって売っていいか分からん。お前はどんなミュージシャンやねん?”って言われて、説明出来へんかった。“大阪出身で、東京で活動してるミュージシャンです”って、そんなミュージシャンどんだけおんねんって。そんなことよりも、“旅するシンガーソングライターです”って言った方がスゴく分かりやすい。そういう自分のフォーマットが出来たのも、やっぱ曲を書く発射台になったスゴい大きなきっかけで。旅をすると非日常に行くわけじゃない。で、日常に戻ってくるでしょ。そうするとギャップが生まれるよね。非日常と日常をスイングして曲が生まれる。東京はこんな感じやけど地方に行くと違うなぁとか、地方ではこうやったけど東京に戻ったら違うんや、みたいな。そういう当たり前をググッて抱えて旅に行って、出来るモノがスゴく大きくて」
――最後にさ、こういう意味のある作品を作れて、この先の大柴の目標というか、やりたいことってあったりする?
「もっとね、自分を柔らかくしたいなと思ってて。固定概念みたいなものが強かったんやけど、ニコ生をやってみたりいろんなクリエイターと喋ってたりすると、自分の知らない世界がスゴくあって。どんどんドアを開けて行きたいなぁ。俺、考え方をコロコロ変えるのよ。でも、変えることすら心地いい。だって本当にそう思ってるから。“ごめんなさい、今はこっちがめっちゃカッコいいと思ったから、やってみます!”って、それでも全然いいと思ってて。今回のアルバムを出せたことで、より頭が柔らかくなったから、もっと自由度の高いモノを作っていきたいなぁと思う。言葉は鋭く、サウンドは柔らかく。そういうイメージを持ってやっていきたいなって、思ってます」
Text by 奥“ボウイ”昌史
(2013年8月22日更新)