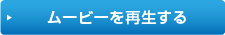7月に3年ぶりとなるオリジナルアルバム『ビオトープ』をリリースしたピアニストの西村由紀江が、9月6日(金)にサンケイホールブリーゼで「西村由紀江コンサートツアー2013 ビオトープ」と題したコンサートを行う。作曲家、ピアニストとして20年以上にわたって第一線で活躍を続ける彼女の音楽は、現在もテレビをはじめとする様々なメディアを通して私たちに届けられている。だが、コンサートに先駆けて、ぴあを訪れた西村がまず口にしたのが「最近、とても楽になりました」という言葉。この意外なひと言から、インタビューは始まった。

「楽になりましたね。この頃、とても楽にピアノを弾けるようになった気がします」
楽になった?
「そう、楽になった。私がデビューした頃ってバブルの時代だったんです。ピアノ音楽って退屈とか、物足りないとか、言われていた時期。テンポ感が悪いとか―。サウンドで言うとちょうどシンセの全盛時代だったので、テクノポップのあの時代にアコースティックでしんみりというのは時代に合わないって言われてた頃だったんですね。だから私はどういう音楽を作っていけばいいかっていう試行錯誤をずいぶんして来ました。アルバムによってジャズっぽい編成にしたりドラムとかベースとかをしっかりと入れたポップスっぽい編成にしたり、いろんなことを試行錯誤しながらやって来たんですが、それぞれの世界を経てきてやっと今、ピアノで自由に自分らしく表現できるようになったというところなんです。それでとても楽になったし、こうじゃないといけないんじゃないかっていうような縛りとか、欲とかそうしたものがなくなってきた感じですね」
それは今、現在がそう、という感じですか?それともだんだんとそうなって来たっていう感じ?
「そうですね、ここ何年か…。デビューして20年くらいたってからだから、徐々にということではあるんですけど、今回の『ビオトープ』では特にそう感じました。私、今、活動の一つとして、東北にピアノを贈る活動をしているんですね。先週も福島に届けてきたところなんですが、一軒一軒、家の中に入ってピアノを納めてその家の人とお話をして、被災した時のこととか、今どうやって家を建ててるとか、子供たちの話とか毎回うかがっているんです。そうすると、これは報道でも言われてることなんですけど、やっぱりみなさんが大変な思いをしながらも、一日一日をたくましく生きておられるのが伝わるんです。私がピアノを届けに行くとみんな近所の子供たちが集まって来て、手をつなぎながら、写真撮ろうって言ってくれて。朝、起きるたびに、今日も生きている感謝を思うんですよっていう話を被災した人から間近にうかがうと、人間のあり方ってこういうところにあるんだなっていう風に思うんです。だから私もこうやって毎日があることをありのままに、受け入れていこうと思うし、そこに音楽に余計な、これはインパクトつけなきゃとかそういう風に感じる必要はないんだ、そのままでいいんだっていう風に思うようになったんです。そういう気持ちになれたのは、ここ2,3年の東北での活動を通じてですね。それで今回は人間と自然との絆の深さを改めて感じて、『ビオトープ』っていうタイトルにしたんです」
3.11を経て西村さんが体験したことが、現在の気持ちに反映されている、ということでしょうか。そしてそれが素直に表現できたのが、『ビオトープ』という作品だった、と。
「はい。『ビオトープ』っていうのは「生息域」っていうか、生物が棲む環境を持った場所のことなんですね。最近では学校の校庭とかにも作ってあるらしくて、そこでは魚を飼っていて、陽が当たっていて、水草が生えて、その中に生態系が循環しているっていう、自然の成り立ちを教えているみたいです。タイトルにつけた理由は、いろいろあるんですけど、私の中では「つながってる」っていうことがひとつ、キーワードにあって」
「私が今、自然とのつながりっていうものをとても感じるのは、被災した人たちと直接会ってお話した時。たとえば被災直後は海を見るのも辛くて、なんで自分は海のそばにいるんだろうとか海が憎いって思っていた人が、何年か経つとやっぱり海から離れられなくて海のそばに家を建てている。自分は海に育まれてるし、海と一緒に生きてきた。だからやっぱり離れられない、今は感謝してるんだっていうようなことをおっしゃっていて。そんな風なお話をうかがうと、私がまた海を見るときの気持ちとか、あと東北からの帰りの車の中から何気なく見る空とか雲とかが、違ってくるんですよ。やっぱり人間はこうやって自然に生かされているんだな、自然とつながって生きているんだなって思って。そこから『ビオトープ』ってタイトルを思いついたんです」
「ジャケットを見ていただいた通り、森がひとつのテーマになっているんです。森ってね、癒しのイメージがあるけれど、もちろんとてつもない脅威の森にもなるし、嵐の森にもなるし、その存在感の大きさみたいなものを『生きとし生けるもの』という曲の中では表してみたんですね。ジャケットも、これは通常版ではアップなんですけど、初回版では自分が森の中の一部になりたいなって思って…。そういう気持ちでカメラマンの方に撮ってもらったんです。アルバムはもう聴いていただけましたか?」
物語を読むような、展開を感じました。川の水に陽が輝いているような曲から始まって、そこからだんだんと森の奥に足を踏み入れていくような。タイトルが曲のイメージにぴったりと寄り添っていて、詩のようにも思えるし…こういうタイトルはどこから思い浮かぶんですか?
「タイトルはですね(笑)。曲が浮かんだ時のシチュエーションに合わせて書くんですね、で、曲は作ろうって思うよりも日々の中で心が動いた時、頭の中に自然に浮かんでくるんですよ。ある時、鳴るので。そして鳴ったものをいつも持ち歩いている小さな五線紙に書いていくんですね。その時のシチュエーションを大体書いておくんです。たとえば今日だったら「大阪、暑い」とか。もしここで浮かん

だらね(笑)。で、書いておいて、アルバムにする時には、もう少しタイトルらしく直すっていうのが私のやり方なんですよ。たとえば『生きとし生けるもの』だったら「生命の大きさを感じた」ってことを私が書いておいて、あとで「その生命を感じた」をもっとわかりやすく、一言で言えないかなって考えて『生きとし生けるもの』っていう実際のタイトルにするっていう、そういう感じですね。詩のようにタイトルが寄り添う感じですか?…そうなってるとうれしい、かな(笑)」
■フレデリック・バックさんとの出会い、そして自分らしく。
『ビオトープ』の中の曲は、演奏はもう始められてるんですか?
「今やってますね。大阪ではインストアイベントで弾いたりとか東京ではコンサートの中で弾いたりとか」
手応えはいかがですか?
「やっぱりすごく力が抜けて弾ける感じはあります。で、弾くごとにその時に見てた景色とか東北に行ったときに会った子供達とか思い出したりもするので、怖くないっていうのか…。うん、楽に弾けますね」
確かにその楽さ、みたいなものは聴いてもわかるんですよ。とても自然な音楽だという印象を持ちました。弾いている人の感情の揺らぎとか、たゆたいみたいなものが心地よく伝わってくるというか。

「それは嬉しいかも。私、カッコいい音楽を作りたいとか、こういうテクニックで練習したいってことは、今は全然なくて、いかに感じたことをそのまま表現できるかっていうようなことしか考えてないんですよね。で、ピアノを届ける活動なんかを通じていろんな人に会えたりとかいろんな人に話を聞けるっていうのはすごい貴重な経験だと思っていて、それは何かの形でまた表現しなければいけないと思っているんです。そこで得たものとか感じたものとかは、今東京に住んでいるので東北以外の人たちにもちゃんと伝えたいし、音としてちゃんと残したい。素晴らしい音楽にしたいとか言うんじゃなくてこういう経験をさせてもらってるんだから、それをちゃんと素直に残していきたいっていう…そんな風に考えています」
「もうひとつ言うと、去年、フレデリック・バックさんというカナダのアニメーション作家の方と一緒にコラボレーション作品を作らせて頂いたんです。この方は私が20年間憧れていた大好きな作家なんですけど、『木を植えた男』という作品を発表していて、その時からバックさんの人となりに、アーティストとしてファンだったんです。震災があった年にバックさんが86歳にして日本にいらっしゃったんですよ。日本を励ますために。で、その時に私もバックさんに会うことができて。実は20年間ずっとファンだったんですって話をさせていただいて、そこから一緒にコラボレーションのアルバム作りましょうっていう話がまとまって。私がバックさんの絵にインスピレーションを受けて曲を作り、私が作った曲からインスピレーションを受けて、バックさんが絵を描いてくださりっていうコラボレーションが実現したんです」
「バックさんは『木を植えた男』っていう作品を手がけられている通り、植樹活動をずっとご自身でもされている方で、お会いした時には実際に自分がどういう絵を描くかということではなくて、自分の絵を通して大切なものを次の世代の子供たちに伝えていきたいとか自然の美しさと脅威っていうものをちゃんと人間に伝えられるような活動をしていきたいってことをおっしゃっていました。それは被災地にピアノを届ける活動とぴったりつながるところがあって、それもあって、ああ、これは今回はぜひ『ビオトープ』っていうテーマで作ろうって、めぐり合わせみたいに思ったんですね」
西村さんはピアニストとしても作曲家としても活動が長くて、その都度、素敵な音楽を作って来られたでしょう?。さきほど怖くない、という表現がありましたけど。今、ようやく、その重荷みたいなものから解放されたっていうのは、うかがっていて少し意外な気もしました。
「うーん、やっぱり全然違いますね。若い頃とは(笑)。もともとの話をすると、私は大阪の出身なんで、大阪のピアノスクールでピアノを弾き始めたんですけど、その時は手が小さすぎて友達より劣等生だったんですね。「由紀江ちゃんピアニストはちょっと無理なん違う?」って先生に言われてました。そのくらい誰もが弾ける曲が何時間かかっても弾けない子だったので、初めから弾けてたわけではないんですね。それに、とにかく言葉で自己表現することが苦手だったんですよ。デビュー後に『日曜日はピアノ気分』に出させていただいていた時にも、こんなに極端に話すことが苦手な私が、司会なんかさせてもらっていいんだろうかって思っていたくらい、とにかく苦手意識が強かったんです。若い頃は、そんなコンプレックスのかたまりのような状態だったんですよ。だからそれが20年経って楽になってきて、それはもう徐々に徐々に薄皮をはがすように楽になってきて自分らしくなってきている感じですね」
「歌詞を付けたり、詩を送ってくれるファンの方は多いですし、『ビオトープ』の一番最後の『希望』という曲は、去年私がコンサートでロシアに行ったときに歌手の林明日香さんが歌ってくれたんです。だから歌に近い、と感じてもらうことはとても嬉しいです。また子供の頃の話にさかのぼるんですけど、とにかく楽譜通りに弾こうと思っても手が小さいからうまく弾けない、で、幼稚園に行っても私は友達になかなか自分の表現ができないから、黙ったまま帰ってくるんです。そうやって黙って帰って来て、母親にもうまく言えないんです。自分のもどかしい思いを。で、結局向かったのがピアノ。それでピアノに向かってずーっと弾いてると心が落ち着いてきて、で、ピアノが「何とかなるよ」とか「大丈夫」とか言ってくれてる感じがして。そこからもうピアノで感情をぶつけて、ピアノに励ましてもらうっていうそういう対話をしていたんですね。だから、私にとってはクラシックをきちん弾くっていうのとは少し違って、感情表現がピアノであったということ。言葉の表現がピアノであったということなんです。そうした感情が、いろんな体験を経て、素直に出せるようになった、ということかも知れませんね」
ありがとうございます。では今回のコンサートについて教えてください。

「はい。今回は大阪サンケイホールブリーゼで弾くんですけど、演出的にも色々なことができるホールですから、できればこのCDジャケットの世界をそのままステージに持っていきたいなと思っています。で、まだ暑いですから皆さんが森林浴をしているような気分になれるようなステージを作ろうと。私、最近、コンサートツアーでは、オリジナルハーブの香りをそのアルバムの為に作っているんですよ。今回も『ビオトープ』というタイトルの香りを作って、つい2日前くらいにこの香りで行こうって決めたところなので、その香りを楽しみながら音楽を聴いていただこうって思っています。大阪は私の地元ですから、音楽は『ビオトープ』からのものと、私を昔から支えて下さっている皆さんが懐かしいと感じていただけるような曲を…ドラマの曲とかもやりますし、今回はパーカッションとベースが入りますのでアンサンブルでお届けします。『ビオトープ』の世界とこれまでの私の世界。そのふたつをお届けしようと考えています」