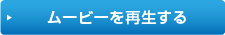ホーム > インタビュー&レポート > 実力派シンガー、平賀マリカが華やかに歌う。 最新アルバム『Sings With The Duke Ellington Orchestra』と アロージャズオーケストラを迎えたビルボード大阪でのライヴ!
実力派シンガー、平賀マリカが華やかに歌う。
最新アルバム『Sings With The Duke Ellington Orchestra』と
アロージャズオーケストラを迎えたビルボード大阪でのライヴ!
ジャズシンガー、平賀マリカがニューアルバム『シングス・ウィズ・ザ・デューク・エリントン・オーケストラ』をリリースした。2006年のアルバム『Faith』あたりから一作ごとに、バート・バカラック、カーペンターズらの作品を含む様々な世界にアプローチし、キャリアを積み上げてきた平賀マリカだが、今回彼女が飛び込んだのはジャズ史上最大の作曲家にして、バンドリーダー、デューク・エリントンの世界。『A列車で行こう』や『スイングしなけりゃ意味ないね』など、数々の名曲を、今なお彼の伝統を受け継ぐ最高のビッグバンド“デューク・エリントン・オーケストラ”をバックに華やかに歌い上げている。日本の歌手でここまでストレートにエリントン作品に取り組んだ作品は過去になく、まさに平賀マリカの集大成といったアルバムに仕上がった。
その平賀マリカが7月4日(水)、ビルボードライブ大阪でライブを行う。競演は関西を拠点に活躍するビッグバンドの雄、アロージャズオーケストラ。当日はニューアルバムからのナンバーを中心に、ホットな夜が楽しめるに違いない。
ライブに先駆けてぴあ関西支社を訪れてくれた彼女は、とても魅力的なおとなの女性。火曜日の午後、インタビューはジャズと映画の話題に満ちた、とても素敵なひとときとなった。
■エリントンを歌うとミュージシャンが“のる”!?
■デューク・エリントンの作品をそのオーケストラをバックに歌うっていうのは、ジャズ・シンガーとしても緊張するものですか?
平賀:それは、もう。ものすごく緊張して日本を発つ前にいろんな友達にメールして。今回は大きなプロジェクトになって失敗はできないし、超えなきゃいけない壁もたくさんあって、ちょっと助けの声が欲しいみたいな連絡をしました(笑)。それでみんなが頑張っておいでって言ってくれて。レコーディングではそういう声がとっても励みになりましたね。
■実際に歌ってみていかがでした?
平賀:そうですね。例えば分かりやすい比較で言うと前回ナット・キング・コールを歌って、あのときの歌と今回の歌とは違う、ということを感じる一瞬が自分の中ではありましたね。ナット・キング・コールの歌というのは非常に大衆性があってポピュラーで。誰もが口ずさめるみたいな歌です。でも今度のデューク・エリントンの曲っていうのは若干ジャズのスキルがないと歌えない部分がありました。もともとインストゥルメンタルで作られた曲なんだな、っていうのを感じる瞬間ですね。
■『A列車で行こう』とか『キャラバン』とか、エリントン・ナンバーはいろんな人に歌われていますが、平賀さんとデューク・エリントンの出会い、というのは?
平賀:まず歌でした。もちろん、作曲家としてのエリントンを知ってはいたんです。ただね、エリントンの曲をコンボの編成で歌うと、すごくミュージシャンが“のる”っていう、不思議な現象がありまして(笑)。スイングするっていうのか、ただの歌の伴奏にとどまらない演奏をしてくれるっていうのか、そんな経験が何度もあったんですね。だからこれは何だろうっていう手応えを昔から、感じていました。
エリントンを歌うとミュージシャンの良さが出るっていうのか、楽器が勢いづくとか、あとドラマーなんかがカッコよく見えるとか、このスイング感で叩くと華が出てくるとか。やっぱり楽器に対して、そこにスポットを当てるために出来上がった曲だなっていう感じもしました。かと言って、じゃあ歌で成立してないかっていうとそうでもなくて、スインギーな楽しい曲で、歌詞がとっても楽しかったりとか、またバラードには繊細さとか美しさっていうのが際立ってあるので、そんなところから少しずつデューク・エリントンの魅力に惹かれていって、それで1920年代後半から1930年代にかけてハーレムのコットンクラブっていうホールで演奏してたんだっていうことなんかを調べていったんです。
■モダンジャズ以前、スイングの黄金時代ですね。
平賀:ある意味アメリカの一番黄金時代っていうか、ジャズの一番華やかなりし時代、禁酒法の時代ですよね。ギャングが横行していてちょっと危ない猥雑な世界。音楽にも危険な雰囲気があったりして。私、映画とか好きなので、ちょっとビジュアルから入ったみたいなところもあったんですけど、その時代の雰囲気を作ってみたい、みたいな感じでした。でもそんな時代の音楽にもかかわらず、エリントンの教養にはすごく高いものがあって、クラシカルな理論もきっちり備わっているし、非常にクオリティの高い音楽をやってたっていうことがある意味ものすごいカルチャーショックで…。
■エリントンはクラシックの勉強もちゃんとした人ですよね。
平賀:そう、だから本当に私もちゃんと勉強しないとこれはダメだなと。舐めてかかっては絶対できない音楽ですね。いろんなことがプレッシャーではありましたけど、実際に海外でレコーディングで歌ってみて、とっても感慨深いものがありました。ジャズの歴史にきちんと触れることができたんだ、と思って、大変私の中での感動がありました。
■古い映像を観ていると、エリントンが演奏中にソリストを立ち上がらせて吹かせたりするじゃないですか。ビッグバンドならではの華やかで楽しい場面ですよね。
平賀:エリントンは基本的にメンバーにいかに華を持たせて際立たせるかっていうのを考えながら作曲やアレンジしたっていうのをある文献で読んだことがあります。非常に人間的にも自分ばっかりがボス'じゃなくて、バンド全体にもメンバー一人ひとりにも光を当てるってことをしていたので、とっても心があるっていうか人間としても素晴らしかったアーティストなんだなっていうのを感じる瞬間はありましたね。
■最高ですね。人間としても素晴らしい。
平賀:だからミュージシャンはみんなエリントンが好きなんですよ。それで私がエリントンの曲を歌うと急に楽しそうに吹き始めたりするんです。「えー、今までただの伴奏だったじゃない」って感じだったのが、急に掛け合いやらないとか、フォーパースやらないかとか、スキャットで半分くらいやってよとか、色々リクエストして来るんですよ。エンディングもっと引っ張ってとか、けしかけて来るんですよね。これは一体何なんだって不思議に思ってました。エリントンの曲に限ってすごくスイング感が表面に出て、ドラマーがうるさいぐらい張り切っちゃうとか…。
 ■ジョン・コルトレーンがデューク・エリントンと共演したアルバムがあって、録音の時、コルトレーンが何度もテイクを重ねようとしたのをエリントンが「同じ演奏は2度できないよ」って言って全部ワンテイクで決めたっていう…。
■ジョン・コルトレーンがデューク・エリントンと共演したアルバムがあって、録音の時、コルトレーンが何度もテイクを重ねようとしたのをエリントンが「同じ演奏は2度できないよ」って言って全部ワンテイクで決めたっていう…。
平賀:ああ、その話聞いたことあります。何度も吹きたいってコルトレーンが言うんですよね。でもそれを1回で終わらせるっていう。バンドでも全部ワンテイクかツーテイクで決める人だったみたいですよ、エリントンって。そういうミュージシャンシップっていうか、粋っていうか…。それも尊敬される理由のひとつなんでしょうね。
■今回は“ジャズ”に踏み込んでます。私が先陣を切って。
■これまでアルバムごとにいろんなスタイルにチャレンジなさって来てますけど、今回のアルバムはやはり、ひとつの達成、っていう感じでしょうか?
平賀:達成というよりは、やっぱりチャレンジですね。私のアルバムでいうと、今回は、2006年にリリースした『フェイス』に近いところがあると思います。
私はあの『フェイス』ってアルバムを作った時に、人に何でエリックのバンドなの、って言われたんですね。だって伴奏するバンドじゃないでしょって批判されたりもしたんですけどね。でも私にとっては、ああいう人たちとがっぷりと組んで他にないものを作り上げたいっていうのがひとつのコンセプトだったんです。インストの曲にもちょっと頑張ってアレンジしたいっていう、みたいな。
私、ふたご座なので女性的な私の部分とすごくチャレンジャーで体育会系の男性の部分と二つの顔を持ってると思うんですよ(笑)。非常に柔らかい部分と男気のある部分とが混在しているアーティストだと思っているので、アルバムごとに今回はちょっと女っぽい作品だね、これは男っぽい作品だねっていうのを裏コンセプトみたいにして作ってます(笑)。
■今回はどちら?
平賀:今回は男っぽいですよ。だって大きなチャレンジをしないとできなかったもの。でも前回の『MONA LISA』は割と女性的な。あれがとてもお好きという方もいらして。私のこの両極端の部分にそれぞれファンの方が別にいるみたいで。『フェイス』を出した時には結構インストゥルメンタルが好きな人たちが聴いていらしたみたいですね。
■エリック・アレクサンダーが吹きまくっていて。
平賀:もう手加減しないよ、みたいに(笑)。あれは日本のアレンジャーがアレンジをしてくれたんですけど『イン・ウォーク・バド』っていうセロニアス・モンクのフレーズにちょっとトライしないかって言われたり。『オーバー・ザ・レインボウ』ってあんなに皆さんがバラードで歌ってる曲を、3拍子と4拍子が交互に出てくるようにアレンジしてみたり。かなりチャレンジさせていただきました。
■録音順でいくと、『フェイス』の次が『クロース・トゥ・バカラック』ですね。
平賀:『クロース・トゥ・バカラック』も私にとってはちょっと男っぽい部類に入るんですね。アレンジが結構難しくって、バカラックの作品自体は女性的な曲が多いのにアレンジが男っぽいっていう(笑)。で、それから「モア・ロマンス」ではラブソングで女性的なところを出して。『バトゥカーダ』っていうのは、両方が混在してる感じかなぁ。それから『シング ワンス モア』はカーペンターズで、また女性的なところを出し…。
■次がナット・キング・コール『モナリザ』…。
平賀:割と女性的、みたいに言いましたけど、“歌”ですよね。本当に“歌”ってことを純粋に考えてナット・キング・コールを選んだんです。昔、ジャズの勉強を始めた頃、ジャズを歌うってどういうことって、判らなくなった時期がありましてね。海外のいろんなシンガーの歌も聴くんですけど、フェイクがすごいんですね。原曲がわからないほどやるんです。それでもうまったくジャズがわからなくなって。一時はジャズ・ヴォーカル辞めちゃおうか、って思ったりしました。私はね、そこでナット・キング・コールを聴いたんですよ。そしたらすごく楽しかった。歌うこと、歌そのものの純粋な魅力でしょうね。だから私にとってはジャズ・ヴォーカルを通過するにおいて、ナット・キング・コールが欠かせなかったんです。 アルバムはリラックスっていうコンセプトでやりました。まあフォーマットがドラムレスのギタートリオでしたから私一人があまり激しくアプローチしても(笑)。
アルバムはリラックスっていうコンセプトでやりました。まあフォーマットがドラムレスのギタートリオでしたから私一人があまり激しくアプローチしても(笑)。
■そして今回の『シングス・ウィズ・ザ・デューク・エリントン・オーケストラ』に至る、と。
平賀:今回はもう少し“ジャズ”に踏み込んでます。演奏がひとつ大きいですから。今回はリラックスするわけにはいかなくて、私がしっかりしてないと後ろがついて来ない。後ろを安心させるために私が先陣を切って、茨の道を行く感じでしたね。ただ、男性的っていうことで言えば、エリントンの楽曲自体が男性的な、顔を持ってるのかも知れないって感じました。バラード一つとっても、ものすごくクロマチックが多く使われていて『イン・ア・センチメンタルムード』とか、『プレリュード・トゥ・キッス』とか、ものすごくクロマチックで半音ずつ上っていったり、降りてきたり。それがとっても表情豊かで効果的にしっかりクラシカルなアレンジが施されていて素晴らしいんですよ。構成感というか、楽曲自体の持つ重厚さというか、ね。
■まだまだアイディアはいっぱいありますよ。
■これまで何人かの歌手のかたにお話をうかがう機会があったんですが、歌うことの楽しみや喜びについてうかがうと、クラシックのかた、ジャズのかた、ポピュラーのかた、皆さん、そこに人生があるからっておっしゃったんですね。でもじゃあ、ジャズの歌い手の方ならそれをほかのジャンルと分けるものは何、と(笑)。きっと、あるはずですよね、ジャズならではの醍醐味が。
平賀:ああ、みなさんがそうおっしゃるっていうの、歌い手としてはよく分かります。でも確かにちょっと漠然としてるかも知れないわね。私の場合は子供の頃、少年少女合唱団にいたんです。でもそれよりもっと前、幼稚園の時、遠足のバスの中で『小鹿のバンビ』を歌ったら、人から拍手をもらったっていうのが喜びで。そんなに勉強も好きじゃなかったのに拍手をもらうっていうのを初めて知ったのが幼稚園の時。で、今度は小学校に入って混声合唱団に入って、そしたらそこでまた拍手を頂いて(笑)。子供心に何か満足感っていうか優越感を感じましてね。人前で歌って拍手を頂いて喜びを感じるっていうのが、歌い手としては基本の‘き’なんです。
じゃあ何で私がジャズに行き着いたかっていうとね、あの後ろのミュージシャンと瞬間にしてその時にしか出せない1回だけのサウンドをクリエイトできるっていう音楽だったから。それはその時にしか出せない、本当に一瞬にして消えてしまう物の美学っていうかね。ね、二度とできないでしょう。で、このミュージシャンとベーシストABCDっていて、4人いたら4人とも違うっていうこととか、ピアニストが5人いたら5人とも違うって言うこととか、同じ楽曲が組み合わせによってサウンドが全然違う色を放ってくる。スタンダードも数多くあって、それは究極のカバーなんだけども、それがひとつのファクターとしてシンガーやミュージシャンを通過するときに時に、精神であるとか、性格であるとか、カラーであるとか、音色であるとかが現れて来る。その一瞬一瞬の閃きの中に加わって、アドリブも入れて歌えるっていうのは歌手にとってすごい快感なんですね。きっとそのアドレナリンが出る&拍手がもらえるっていう、そのことがひとつの生きる糧になってるっていうかね。そこで喜びを感じられるから次の日も生きていける、みたいな力に繋がってるんだと思います。生きてる瞬間っていうかその音楽のドラマに自分が関与してるっていうことがね、歌手である私にとっては一つのエクスタシーって言えるのかも知れませんね。
■今、音楽のドラマって言葉で思い出したんですが、映画がお好きだっておっしゃってましたよね。『真夏の夜のジャズ』って映画、きっとご覧になっていると思ったんですが。
平賀:ああ、ニューポートよね。アニタ・オディが出て来て。私もあの映画観た時、本当にジャズ歌いたいって思いましたもの。アニタ・オディの、あの帽子、あの手袋、真珠のネックレスして歌うもんねって。まったくファッションからですけど、本当にそう思いましたよ。アニタ・オディは、すごい存在感でしたね。昔の映画ではありますけど…。
私が一番懸念しているのは、ジャズ人口自体が減って行って、若い人に聴かれなくなっているってことなんですね。それでジャズ自体の灯火が消えかかっているってこと。ジャズってね、難しい音楽じゃないから初心者の方っていうか、知らない方にも聴いて欲しいって思います。スタンダード・ジャズっていうのは当時の流行り歌ですからね。難しく考える必要はまったくないんですよ…。昨日、名古屋で、私の仲良しのジャズバーの店主がね、昔レコード会社に勤めてた人なんだけど「誰それの“フェイク”は許せる。誰それまでは許せるけど、誰それの“フェイクは許せん!」って(笑)。結局エラ・フィッツジェラルドまでだね、っていうことで意見が一致したんですけど。つまり分かんなくなっちゃうんですよ。あんまりフェイクし過ぎると。せっかく作曲してくれた人が美しいメロディを書いてくれているのに。だから私たちはそれに敬意を表して歌い継いで行かなきゃいけないっていう使命感を感じたりもしていてね。それをなるべく再現してあげるつもりで、あんまり崩さない姿勢で歌っていきたいんですよ。で、フェイクは…そうですね、ライブで20%くらい、多くて30%。なるべく作曲家に敬意を表して。
■次のステップはどうなります? エリントンまで行ってしまうと。
平賀:うーん、それが課題。アメリカにいるとどうしてもアジアっていうことを意識せざるを得ませんから。日本の歌っていうと由紀さおりさんにやられちゃいましたけど(笑)。ただ、あれはジャジーなアレンジってわけではありませんから、ジャジーな何かをっていうことではまだ何かできないかなって構想はあります。本当のインターナショナルっていうのは、日本人であるっていうアイデンティティをきっちり持って、プライドを持って世界に立ち向かって行くこと、日本の言語や文化を大事にしながら世界とコラボして行くことだと思い始めていて。日本の曲を何か1曲歌ってよ、っていうことを言われることも向こうでは多々あるので、そこは…。まぁ、まだまだアイディアはいっぱいありますよ。ジャズのフィールドでやり残したことはいっぱいありますから(笑)。
(2012年4月25日更新)
Tweet
Profile

■平賀マリカ
日本のジャズシーンを代表するヴォーカリスト。香港で開催された『アジア音楽祭』で金賞を受賞後、プロデビュー。2006年にエリック・アレキサンダー、ハロルド・メイバーンらと共演した『フェイス』が『スイングジャーナル選定ゴールドディスク』を獲得しブレイク。その後もデビッド・マシューズ率いるマンハッタン・ジャズ・クインテットと共演した『クロース・トゥ・バカラック』、鬼才アレンジャー、ギル・ゴールドスタインを筆頭にマイケル・フランクス、マルコス・ヴァーリ、フィル・ウッズらを迎えた『バトゥカーダ~ジャズン・ボッサ~』などの意欲作、話題作を発表。しなやかにスイングするリズム感とロマンチックな表現力で、多くのファンを魅了している。
New Release

Album
『Sings With The Duke Ellington Orchestra』
発売中 3000円
BounDEE by SSNW
DDCB-13020
【収録曲】
1.アイム・ビギニング・トゥ・シー・ザ・ライト
2.ドロップ・ミー・オフ・イン・ハーレム
3.スウィングしなけりゃ意味ないね
4.ソリチュード
5.キャラバン
6.イン・ア・メロウ・トーン
7.アイ・ディドント・ノウ・アバウト・ユー
8.アイム・ゴナ・ゴー・フィッシン
9.イン・ナ・センティメンタル・ムード
10.ジャスト・ア・シッティン・アンド・ア・ロッキン
11.A列車で行こう
12.ダンス・イン・ハーレム
Live
『平賀マリカ featuring
アロー・ジャズ・オーケストラ』
一般発売5月8日(火)
Pコード170-378
▼7月4日(水)18:30/21:30
ビルボードライブ大阪
自由席6900円
ビルボードライブ大阪■06(6342)7722
※カジュアル エリアは取り扱いなし。未就学児童は入場不可。ビルボードライブ大阪の整理番号をお持ちでないお客様は開場時間の30分後のご案内となります。ビルボードライブ大阪の整理番号をご希望の場合はお問い合わせ先まで。