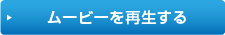1/28(土)心斎橋JANUS、2年ぶりの大阪ワンマン迫る!
スチャダラパーBoseやTHE BACK HORN山田将司も参加した
再結成後2枚目のアルバム『LIFE WORKS JOURNEY』の世界
FLYING KIDS浜崎貴司(vo)が現在地と覚悟を語ったインタビュー
90年代初頭の空前の“イカ天”ブームで名を馳せ、ファンクをボトムに据えたポップソングの数々をヒットさせシーンに名を刻んだFLYING KIDSが、『RISING SUN ROCK FESTIVAL 2007 in EZO』のステージで衝撃の再結成を果たしてからはや4年半。若くして結成されたバンドも、今やメンバー全員が40代に。昨年9月にリリースされた再結成後2枚目となるアルバム『LIFE WORKS JOURNEY』では、アーティストとしてキャリアと人としての人生経験、そして2011年という時代の空気が交差し、この年にしか生まれ得なかったFLYING KIDSたるゆえんが脈打つ人肌のアルバムに仕上がった。また、今作ではデビュー時を同じくする戦友・スチャダラパーのBose、一見異色の組み合わせにも見える激情型ロックバンドTHE BACK HORNの山田将司(vo)がフィーチャリングで参加し、作品に絶妙なスパイスを与えている。そこで、1月28日(土)心斎橋JANUSでの2年ぶりの大阪ワンマンを前に、バンドのフロントマンにしてソロアーティストとしても確固たる存在感を放ち続ける浜崎貴司(vo)に、今だから言える解散の内幕から再結成のドラマ、フィーチャリングのいきさつ、そして3.11…前作『エヴォリューション』より2年を費やしたどり着いた人生の旅路を記した、まさに“LIFE WORKS JOURNEY”なロングインタビューに答えてもらった。
浜崎貴司(vo)がアルバムとライブの見どころを解説!
――まずは、’98年に解散したFLYING KIDSが’07年に再結成に至った経緯を、なぜ解散して、逆になぜ再結成しようと思ったのかを改めて聞かせて頂きたいなと。
「解散した理由っていうのは、単純に音楽的にやることがなくなっちゃった感じがすごくあったんですよね。まぁ結果としては、別れていろいろ旅をして、蓄えたものとか勉強したもの、経験したものがあるからこそ今回の再結成につながりましたけど、解散するあの時点ではカラッカラというか。10年間走り続けて、作り続けて、ライブやってのホンットに繰り返しだったんで。そこがひとつの引き金になったような気がしますね」
――80~90年代のあの頃は音楽業界もまだ元気で、リリースしてプロモーションしてライブしての繰り返しで、バンドが続く限りはその流れも延々と続くみたいなところもありましたからね。
「プライベートな時間もホントに少なかったですし、どうしてここまでして無理やり曲を作らなければならないのかっていう疑問符みたいなものを感じながら、曲を書き続けてた時期もありましたね。それに対して1回ブレーキを踏みたかったんですけど、バンドという形態を維持していく中では、やっぱり走り続けないと経済的にも成り立たないみたいなところもありましたから。1回止まるんだったら解散に近い形っていうのは、リアルな現実的状況として受け入れざるを得なかったことだと思いますね」
――そもそも自分たちの音楽をやりたい、世に広めたい、知ってもらいたい、有名になるぞっていうモチベーションからエネルギーが発せられて始まったのに、逆に何かリリースしないといけないからアルバムを作る、そのために10曲書かなきゃいけないとかいう枠組が先に来て、そのための行動をするみたいな感じにはなっていきますもんね。
「まぁいい歳になってくればそれで尻を叩かれる的な感じで、ひとつの目標になってかえって元気にやれるんですけど、あの当時はちょっとキツかった。精神的に疲れてた部分もあったと思いますけど」
――その後、浜崎さんはソロ活動を開始させて。ソロとしても決して短い時間ではなく、むしろ積み重ねて確立されたものがあったにも関わらず、そこからまたバンドを、FLYING KIDSをやろうと思った動機は何だったんですか?
「10年ぐらいソロとしてやってきましたからね。ソロになってから、いろんなセッションミュージシャンとも一緒にやったし。例えばレミオロメンの前田啓介とかは、その最初のベーシストだったりして」
――そうなんですね! まだ彼がレミオロメンに入る前の、セッションミュージシャン時代の。
「そうですね。もうホントに毎日一緒にメシ食ったり酒飲んだりして。アイツの実家のお母さんとも付き合いがあるぐらいの感じだったんですけど(笑)」
――マジですか(笑)。
「そういう中でも、やっぱり僕はもうある程度のキャリアがあったし、いわゆる“バンド”にはならないんですよね。結局ソロという形になっちゃう。でも、僕の中にはいちバンドマンみたいな気持ちがまだすごくあって、中途半端にソロ曲をアレンジするとバンドを求めてる自分がいるというか。『NAKED』(‘10)というアルバムなんかは弾き語りなんで、かえってソロというものをシンプルに見つめ直すことが出来ましたけど、それが出来るまでは、やっぱりアレンジして、サウンドを作っていくイメージに“FLYING KIDS”というのはどこかであったと思うんです。それとの戦いみたいなところもあったし。そこで気付いたのは、自分は“バンドが好きなんだ”っていうことで、でも、FLYING KIDSのメンバーみたいな関係にはならないのも分かったんですよね。ソロワークスとして、どうしても僕が(サポートメンバーに)ギャラを払うみたいな立ち位置になっちゃうわけじゃないですか。要するにフラットじゃない。これは僕の持論なんですけど、バンドってガキんときにもう右も左も分からずみんなで肩寄せ合ってこの社会に出ていくぞ、一旗あげようぜっていうあの感じ、その通過儀式がないとバンドにならないんだなって。そのガキんときに出会ったっていう経験を、FLYING KIDSで僕は持てたということですよね。しかもデビューして、たくさんの人に音楽を聴いてもらえるチャンスをもらえた。それって多分一生に一度のめぐり合わせだと思うし。だからその“一生に一度”をもっと味わってもいいんじゃないかっていうのは、FLYING KIDSを再結成するときに自分の中で確かめたことだった気がしますね」
――社会に出てしまってからも友人関係は築けますけど、学生時代特有のあの空気ってありますもんね。損得勘定も何もない中で生まれる絆が。約10年間、きっちりソロとして確立することによって、逆にバンドの良さだったりFLYING KIDSとしてやってきた重みを改めて感じることも多かったと。
「やっぱり10年ぐらいやってくると素の自分の人生がずーっと一直線に見えてきて、ソロワークスもFLYING KIDSも、自分の一本の線なんだっていう風に思えてきた。それなら、それを分けるのではなくて、これからもその線を伸ばしていく、そういう人生を歩んでいけばいいんじゃないかって。そう思ったとき、FLYING KIDSはその線が一度途切れただけで、消えてしまったんじゃないという解釈が出来るようになったような気がしますね。この後どうなるかは分からないけど、ソロがあったりバンドがあったりすることを、またつなげていけばいいんじゃないかって素直に思えた感じですね」
――やっぱり時間が気持ちを整理させてくれるところはありますよね。
「まぁホントにビジネスライクに考えたら、もっと大人になって、会社勤めのようにFLYING KIDSという構図の中で、きちんとエンタテインメント出来てたら解散せずにずっとやり続けられてたと思うんですけど、もう残念なことにホントにそういう魂がないんですよね(苦笑)。だからホントに気まぐれなんですけれど、そこに付き合って頂いてるファンの方には申し訳ないなとは思ってます。だから今はね、逆にたくさんサービスしたいというか、喜んでもらいたい気持ちがすごく強くなりましたね」
――実際に再結成に向けて動き出したのは、浜崎さんのソロ曲でリーダーの伏島(b)さんにベースを依頼したのがきっかけとして始まったんですよね?
「それまで伏島は、ずっとスタッフというか…まぁ自分のマネージメントをやってて」
――そうなんですね! 現役のミュージシャンではなく、伏島さんに依頼したのはいったい?
「コーラスなんかを“ちょっと重ねてよ”なんて頼むと、ミョ~にハモっちゃって。あぁやっぱりバンドを通過してる声ってスゲェなって。やっぱりそういうサウンドがあるんですよね、メンバーには。だからベーシストとして現役からすごく離れてたんですけど、そのセッションでまたベースに火が付いたところもあって。いろんな音楽の話を2人で飲んでするようになっていった中で、時間と共にそれこそ沸々と」
――なるほど。いざFLYING KIDSをもう一度動かそうとなったときに、それこそずっと現役のプレイヤーもいれば裏方もいるし、一般の仕事をされてた方もいたんじゃないですか?
「いましたね~」
――みんなバラバラの10年間の生活が、家族があってという中、すんなりバンドは動き出したもんだったんですか?
「やっぱりそんなにスムーズではなかったですね。ドラマーなんて解散してからホントに10年間ドラム叩いたことなかったって言ってましたから。だから最初のリハーサルとかはひどかったですよ(笑)」
――そりゃそうですよね。10年もやってなかったら。
「そこから彼は練習して、今やすんごいいいグルーヴになってますけど。あと精神的な部分で、素直に“やろう!”って言う人と、やっぱりわだかまりを感じて悩む人もいたし。最終的には『RISING SUN( ROCK FESTIVAL 2007 in EZO)』に引っ張り出してもらって、みんなの前で演奏する、そしたらたくさん人がいてくれた、やるしかないっていう、そういう単純な思いで大きくまとまっていったという感じですね」
――その後、再結成後初のアルバム『エヴォリューション』(‘09)を出して、今回の『LIFE WORKS JOURNEY』は2枚目となるわけなんですけど、やっぱり前作とは趣が異なるというか。と言うのも、1枚は出せると思うんですよね。でも、FLYING KIDSは、このバンドは続いていくんだという意志をある種明確にするのが2枚目となる今作になると思うんですけど、前作をリリースしてからの2年間は、バンドにとってどういった時間だったのかなと。
「FLYING KIDSはちょっとイベントに出るとか、ミーティングとかはありましたけど、案外ソロが忙しくて(笑)。その頃、今までいた事務所からも独立するのもあって結構バタバタしてて、そんな中でちょうどさっき話したソロアルバム『NAKED』を出して、ツアーも始まったりもして。FLYING KIDSの曲も作ってたんですけど、“なんか集まるチャンスがないな~”なんて言いながら、グズグズしてました(笑)」
――せっかく動き出したのに(笑)。
「そうですよ! ソロもやんなきゃなんないし、みたいな感じで」
――“バンドが動いてる感”出さなきゃ、みたいな話にはならなかったんですね。
「そうそう。やたらと周りから言われたんですよね。“動いてる感出さなきゃ”っていう、そのフレーズが飛び交ったんですけど、その“欲張ってる感じ”をメンバーが嫌がるんですよ。イヤらしい感じが出ちゃうのが。なんかそういうことをやり始めようとすると、すごく空気がよどむんで(笑)」
――アハハハハ!(笑) 1年に1枚はアルバム出してツアーをやらなきゃとかじゃなくて…。
「とにかく純粋にやるという。あと単純に普段はサラリーマンもいるので…」
――なるほど。そんなにしょっちゅう動けないみたいな。
「全然動けない。練習だって土日ですから(笑)」
――そういう物理的な理由もありつつ、基本は純粋にFLYING KIDSとしての作品をまた作りたくなったらやろうぜっていう感じですかね。
「そうですね。まぁリーダーの伏島が今はFLYING KIDSのマネージメントもやってるんで、そういう意味では尻を叩いてくれる感じなんですけど」
――いざ再始動後2枚目のアルバムを作るとなったとき、何かしらの方向性はあったんですか?
「前作の『エヴォリューション』は結構気合い入れ過ぎちゃって肩の力も入ってる内容だったんですけど、だからこそ自分の中でなかなか整理が付かなくて、今回の2枚目をすぐには作れなかった。そんな中、昨年の頭に集まったときに“次のアルバムを出そう”ってリーダーから言われて…。この作品が、継続していくFLYING KIDSを物語っていく大事な一歩になる。でも、当時はそれがまだ正直ちょっとよく分からなかった段階で。自分が何曲か持っていって、ギターの丸山が作った『SQUALL』(M-2)もいい曲だから録音したいねっていう風に、何となく持ち曲を少しずつ出していって。でもそんな矢先、あの震災が起きて…。そこからはやっぱり、人々が音楽を聴いてくれたときに気持ちよくなって欲しい、幸福とまでは言わないけど、それに近いものを感じられるような、そういうアルバムにしたい想いが強くなりましたよね」
――やっぱり昨年は震災があって、ミュージシャンとしての音楽との付き合い方を考えさせられる年だったというのは、いろんな取材で話を聞いていてもすごく思いますよね。
「個人的には歌ってる方が気が紛れるのもあったし、いろんなチャリティイベントにもいっぱい出て。ただ、自分もダメージを受けた部分が正直言ってあるんですよね。震災以降、なぜかピアノを弾けなくなっちゃって…弾けなくなったというより、弾きたくない気持ちになっちゃったというか。不思議だなぁと。なんか落ち着かないんですよね」
――そうなんですね…。あと、今回は結構以前に作られた曲も多いそうで。割とじっくり曲を寝かせて作るのが珍しいなと思ったんですけど。
「今回は特にそれが多かったですね。ただ、全部が全部寝かしてるつもりはなかった…忘れてた(笑)」
――高野寛さんがハードディスクの整理をしていたら、昔作った浜崎さんの曲が出てきたというエピソードもあったみたいですもんね(笑)。
「そうなんですよね(笑)」
――でも、歌詞がずっと乗せられなかった曲も、今回のタイミングではなぜか書けたとか、そういうエピソードも多かったみたいですね。何なんでしょうね、その感覚は。
「やっぱりさっき言ったスケジュールに合わせて作っていく感じは、ピュアさを見失わせるんですよね。なるべく拾ったとか落ちてたとか、よく言う“降りてきた”状況の方の音楽でありたいなと思っていて。だから、好きな曲なんだけど歌詞が付いてない状態で取っておいたりする曲があるわけです。『カクレンボ』(M-4)とかがそうだったんですけど、そういう曲はホントにずーっと引っ掛かってて忘れなかったですね。毎回チャレンジするんですけど、出来なかったら置いとくわけですよ。無理やり作らない。でも、今回のアルバムではなぜか出来たんですよね。良かった~って思いましたけど」
――アルバムに収録するために期日までに歌詞を書くんじゃなくて、フィットする言葉が自分の中で生まれてきて初めて、作品に入れようみたいな。
「まさにそうですね」
――今作ではフィーチャリングで2組参加されてて、それぞれのエピソードを聞かせて頂きたいんですけど、まず『SQUALL』に参加したスチャダラパーのBoseさんとはデビューも近い仲ということで、出会ったきっかけと第一印象、今回誘った理由は何だったんですか?
「最初に観たのは恵比寿ファクトリーっていう、ガーデンプレイスが出来る前の倉庫を利用したイベントホールみたいのところで、そこでスカパラとスチャダラの対バンを観に行ったんですよ。その頃のスカパラもすっごいカッコよかったんだけど、そのときスチャダラがゴダイゴの『MONKEY MAGIC』をサンプリングしてて、衝撃だったんですよね。今でこそ、そういう風にいろんな元ネタ使うのはアリだけど、その当時に日本の音楽を再利用して、しかもゴダイゴかよみたいな。そのセンスにホントにビックリして。それにラップも気負いがなくて…もういろんな価値観を裏で解釈していくみたいな、そういうスタイルがすごく好きだった。最初はイベントで“どもども”みたいに挨拶するぐらいだったんですけど、’06年に『友情のエール』っていうチャリティソングを僕がプロデュースして作ったとき、いろんなミュージシャンに声をかけて。まぁその出演交渉って結構政治的な絡みがあって難航したんですよね。そんな中Boseくんに電話したら“了解”って、すぐに来てくれて。あのときのフットワークの軽さにものすごく心打たれたのはありますね。そこから竹中直人さんと一緒に飲むときにBoseくんもいたりして会うチャンスが増えて、ここ数年で距離を縮めていった感じですね」
――なるほど。
「ラッパーで言うとMCUとか僕に近しい人いっぱいいるんですけども、今回はリーダーが“この曲はキュートに仕上げたい。そんなラッパーいないかな?”って言うから、“それならBoseくんでしょう!”って俺が言ったら、“最高! その人選”って即決。で、すぐに電話したら“了解”って(笑)、もう相変わらず。で、お願いしたはいいけど何の打ち合わせもしてなかったんですけど(笑)、去年、一緒にCMに出たときも、Boseくんが撮影の合間に“浜ちゃんさ~、今回のこの曲なんだけどこういう歌詞だから、ドラマの中のナレーターみたいなラップ、どうかな~って思ってんだけど?”って言うから、“すげぇ、天才!”って。それで仕上げてくれたのが、今回の『SQUALL』のラップだったんですね。それはそれは素晴らしい切り口で、ホントに感動しました」
――そう考えたら出会ってから長年やってきて、ここにきてお互いのキャリアを活かしたひとつの楽曲が出来上がっていく様は美しいというか、嬉しいもんですよね。お互い音楽を続けてるからこそ生まれたものでもあるし。
「ホントに長年過ごしてきた時間の中で、お互いが育んできた音楽がそれぞれにあって。それがちょっとしたきっかけで交差することが出来る感動みたいなものを、作ってる側としてはやっぱり感じましたね。あとはまぁ同級生みたいな感覚も正直ちょっとありますし」
――あとはTHE BACK HORNの山田将司(vo)さんの参加曲『愛しさの中で』(M-3)も、出来たのはすごく昔の曲ということですけど、今だからこそ出す意味がある世界観というか。今回はそういう曲が多いですよね。
「そうなんですよね。これが去年高野(寛)くんが救済してくれて、俺に送ってくれた曲なんですけど(笑)。最初は、“おぉ~こんな曲あった! 何かの形でリリース出来たらいいけどなぁ…”ぐらいな感じだったんですよ。でも、震災後に急に歌いたいと思い始めて、慌てて探し出して。急にスイッチが入りましたね」
――歌詞を読んだら、ホントに今の時代にこの曲が鳴っていたら勇気づけられるというか、今まさに欲しい曲だなってすごく思いましたね。
「逆に何もない平穏無事な時代だと、なんかトゥーマッチな重さがあった曲なのかもしれない。僕は『GACHI』っていうライブシリーズを弾き語りでやってるんですけど、そのときに2人で歌ったのが事の発端で。男同士のデュエットで、しかも何て言うか、2人ともちょっと“気合い系”みたいな」
――アハハハハ(笑)! 言霊系というかね。
「そこにレコード会社の安パイなことしか言わないような人間がいたら、“いやいやちょっと濃過ぎじゃないですか?”とか言われてたと思うんですけど(笑)、今回はそういう人間が良くも悪くも全然いなかったんで。ホントに純粋に突き進むことが出来て良かったなって」
――Boseさんは何となくお話を聞く前から関係性が見えるんですけど、THE BACK HORNとFLYING KIDSって、世代も違うし音楽性も違うというところで、コレという接点が見えなくて不思議な組み合わせだなと思ってたんです。
「まぁ元々事務所が一緒だったのもあるんで、よく飲みに行ってなんだかんだ話してたんですよね。ドラムの松田が(猪苗代湖ズで)紅白歌手になる、そんな時代が来るとは思いませんでしたけど(笑)。その松田とはよく飲んでて、将司とは忘年会で会って飲むぐらいだったんですけど、ここ数年、僕の弾き語りライブに通ってくれるようになって、僕の歌がすごく好きだと言ってくれて。そんな中で、2人で会ったりするようになりましたね」
――山田さんの第一印象だったりボーカリストとしての魅力、一緒にやってみた手応えはどうでしたか?
「山田将司はやっぱり、美しい男ですよね、単純に。性格とかも含めていろんな意味でね。まだ二十歳そこそこぐらいの頃に最初に会って、THE BACK HORNの『風船』(‘00)っていうインディーズシングルのプロデュース的なことをやらせてもらったりしたんですけど。第一印象は何て言うか寡黙な、でも何かをジッと見てる、そういう男でしたね。その感じは今でもすごくあって、今回の曲でもそうなんですけど本当に彼が持ってる“清らかさ”と言うんでしょうか。そういうものが立ち昇ってくる感じがありますね。その中には激しさもあって…要するに“濁ってない”感じというか。その割には獣みたいなところもあって…だから動物っぽいですね、ホントに」
――今作はFLYING KIDSとしての新作ではあるんですけど、いろんな世代の仲間も参加して、今改めてバンドとしても成長出来る、刺激にもなるような作品ですよね。
「リーダーの伏島なんかも言ってましたけど、’90年に出した1stアルバム『続いてゆくのかな』を作ってる感じ…そのスタジオで生み出されていく感じにすごく似てるって。そういうバンドマジックみたいなものが久しぶりに訪れた、いいアルバムが出来たと思います」
――それこそタイトルが『LIFE WORKS JOURNEY』というのは、まさに生き方を想像させるというか、音楽と共に生きていく決意が感じられるタイトルですけど、そこに込めた想いはありますか?
「特に昨年みたいな1年は、ホントに山あり谷ありの谷みたいなもんで、突き落とされた感じがある。でもここで、さらにもう1回山に登ろうよ、でもまた谷もあるよ、昔もあったし、みたいな。2011年は、僕らが受け入れなきゃならない光でもあり影でもあるっていうことを、言いたかったような気がします。要するに生きるということ…ただ生きるということを、なんとか歌の中で見つけ出したい、生きていることは悪くないんだって肯定出来るような、そういう意味合いにしたいと思った気がしますね」
――覚悟が感じられるタイトルだなっていうのは、すごく思いましたね。
「さっき言われた、“音楽と共に生きていく”っていうことは、確かに思ったことですね。最近は『LIFE WORKS LIVE ~Since2011 / 終わりなきひとり旅』っていうタイトルで、本当に1人でツアーにも行ってるんで」
――スタッフも誰も付いて行かず、1人でと。
「これを始めたことは大きかったですね。そこには自分なりに歌うことの原点があると思ったんですよ。自分が憧れていた旅芸人みたいなものにだんだんと近付けていることが、今回の決意につながってる部分はあるかもしれない」
――20代でFLYING KIDS、30代ソロをやり、また40代でFLYING KIDSを始めるというそれぞれ異なる10年を過ごしてきて。今って音楽で飯を食っていくということがすごく難しい反面、誰でも音楽を発信出来るようになって。音楽活動に対する価値観もメジャーデビューしてどうのだけじゃない生き方がある時代だと思うんですけど、そういう風に移り変わっていく時代と共に音楽をやってきた今、改めて思うことはあります?
「う~ん…やっぱりどこか病気じゃないと、音楽が好きとか、歌いたいとか、表現したいっていう、そういう病に侵されてないと続かないですよね。ホントに好きじゃないと、どこかイカれてないと進んでいけないですよ(笑)。音楽って目には見えないけど、人の心を揺さぶるし、いろんな景色が思い浮かんだり、記憶が蘇ったり、涙が出たり、興奮したり、エロい気持ちになったり(笑)…音楽ってスゴいものだと思うんですよ。だけど俺はその反面、ちょっと残酷でもあると思うんですよね。やっぱり周りもどんどん…音楽を辞めていくんですよね。要するに音楽を扱うっていうことはある種の奇跡みたいなもので、いい面だけじゃなくて深い闇も持ってる。音楽を続けたいけど辞めていく人もいっぱいいるし、そもそもミュージシャンになれない人もいる。だからこそ、音楽っていうものはそんなに簡単じゃなくて、素晴らしいんだと僕は思うんですよね。“ミュージシャンになりたいんです”ってたまに言われると、“勧めないけどね”と基本は言うけど、それでもやりたいんだったら是非やるべきだし、ホントに何て言うか…“やる人はやる”んですよ。やれない人はやれない」
――うんうん。今回のアルバムが出来上がったときはどう思われました?
「好きだなぁと思ったんですよね、このアルバム。ホントに好きだなぁと思った、うん。こういうのを作りたいなと思ってたんですよね。それが出来た感じはありました」
――それはめちゃ、いい言葉ですね。
「キレイだなぁと思ったし」
――それがまた、FLYING KIDSの作品として出来たのも趣深いというか。ホントにいろんな人生が交錯して、ここに至った感じがありますね。
「そうなんですよね。そういう意味では集大成的なところもあるんです。そして、新しい始まりでもある気はするし。ジャケットもね、非常によく出来ましたし」
――いいですね、コレ。
「いいアルバムが出来るといいジャケットが出来るものなんですけど、ホントによく出来ましたっていう感じで」
――今回のアルバムに伴うツアーもあって。1月28日(土)には心斎橋JANUSにてワンマンライブがありますが、大阪でのライブはどれぐらいぶりになります?
「FLYING KIDSとしては2年ぶりですね。あと、当日はスチャダラパーのBoseくんも参戦します!」
――おぉ~! 素晴らしいですね。
「当日はスゴいですよ、18分ぐらいあるファンク組曲をやるぞと」
――スゲェ!
「『HESOの下☆WORLD』(M-7)っていう曲が今回のファンク組曲の生まれたきっかけになってるんですけど、『HESOの下☆WORLD』から始まって、ヘソの下の辺りを歌にした曲を集めて」
――アハハハハ!(笑)
「てんこ盛りにするという(笑)」
――濃いっすね~(笑)。
「エロバカ日誌みたいな(笑)」
――それはライブならではのスペシャルメニューですね。
「しかも、組曲ですから。いろんなテンポやキーが入り乱れながら、また『HESOの下☆WORLD』に戻る」
――スゴい。
「今回のツアーは『一期一会』というタイトルなんですけど、単純にメンバーとね、まず一緒のステージに立てるという喜び。それをまずは本人たちで思いっ切り楽しんじゃおうっていうことと、あとはやっぱり支えてくれている、来てくれるお客さんと会える一期一会。お客さん同士の一期一会もあると思うんですよね。長い時間ファンでいると、“久しぶり”みたいな人もいるかもしれないし、初めてFLYING KIDSのライブに行く人との新しい出会いだったり、そういうものを大事にしたいというか、きちんとスポットを当ててライブをしたいなって思ってます」
――FLYING KIDS、そして浜崎貴司の2012年はどうなっていくんですかね。
「とりあえず、ソロではひとり旅ツアーもガッツンガッツン決まってまして。2月に九州…長崎、博多、宮崎なんかに行って、大阪には3月24日(土)に心斎橋JANUSにまた来ます。あと、東京ではさっき言った『GACHI』のスペシャルで春の大感謝祭っていうのやるんですよ。10人ぐらい弾き語りで集まってもらって、片っ端から共演していくという。そんなのもやりながら、FLYING KIDSとしては夏フェス的なものにまた参戦していこうかなっていうところですね。とにかく、歌いまくります、2012年は」
――今後の動きも楽しみです。まずは1月28日(土)心斎橋JANUSのワンマンですね。ありがとうございました!
Text by 奥“ボウイ”昌史
(2012年1月24日更新)