
ホーム > インタビュー&レポート > 「いわば“バック・トゥ・明治”」 電気の消滅により廃墟寸前となった 東京から脱出を試みる一家の決死のサバイバルを描く 『サバイバルファミリー』矢口史靖監督&深津絵里インタビュー
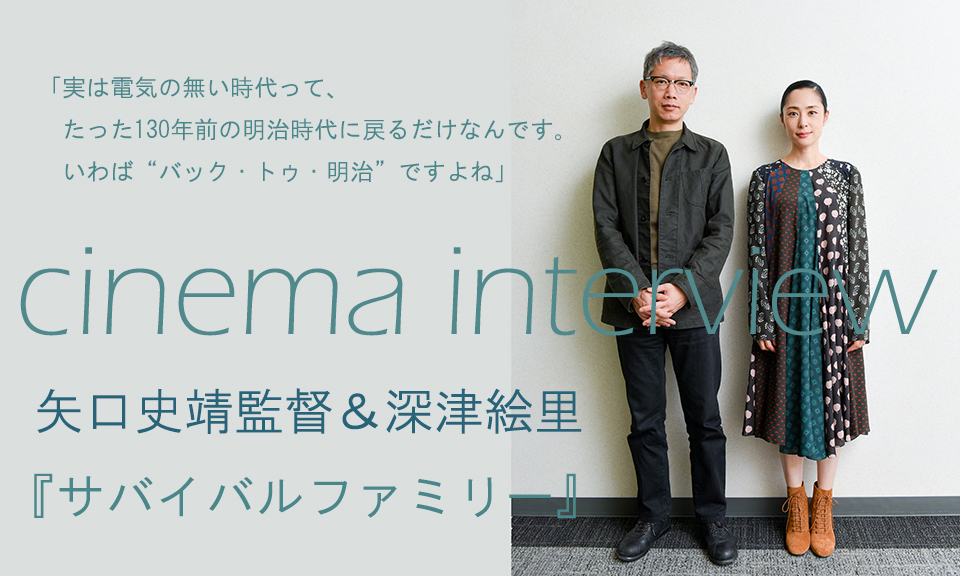
「いわば“バック・トゥ・明治”」
電気の消滅により廃墟寸前となった
東京から脱出を試みる一家の決死のサバイバルを描く
『サバイバルファミリー』矢口史靖監督&深津絵里インタビュー
ある日突然、電気がなくなったら……。『ウォーターボーイズ』(01年)、『スウィングガールズ』(04年)などの作品で知られる奇才、矢口史靖監督の新作『サバイバルファミリー』は、現代社会から電気がなくなったらどうなるのかを、ある家族の姿を通して描いた問題作(!?)。矢口作品独特のユーモアと感性が冴える。矢口史靖監督と深津絵里に話を訊いた。
――もともとの構想はずいぶん前からお持ちだったのですか?
矢口史靖監督(以下、矢口):『ウォーターボーイズ』を撮ったあとに次の作品として考えていたので、2001年ぐらいですね。その後、覚えている方も多いと思いますが、03年にアメリカの8つの州とカナダのオンタリオ州という広大な範囲で大停電が起こったんです。そのときニューヨークのビル群から明かりが消え、暗闇のなかを人々がぞろぞろとビルから出てきて、普段は車しか走っていない橋を人が歩いて渡っていたニュース映像を観て、なんてフォトジェニックなんだと思いました。これは映画になるなと確信しました。
――ただ、映画化までにはそこから13年もの時間を要した…。
矢口:そうです。03年当時、会社にプロットを提出したのですがスルーされてしまいました。作品規模が大きすぎるんじゃないかということで。でも、それから13年の間にコンピューター技術とか進歩して、いまならできると判断してくれたのかどうかはわかりませんが、プロデューサーから、今度はあの電気のやつやろうかと言ってもらえたんです。
――そもそもこの世界から電気がなくなる、電化製品が使えなくなるという発想はどこからきたのですか?
矢口:それは一言で言えば、ぼくの逆恨みです(笑)。20世紀末からパソコンやインターネットが発達してきて、01年ぐらいにはパソコンは一家に一台みたいな感じになっていたのですが、ぼくは機械が苦手で、パソコンやモバイルがうまく使えなくて、周りにどんどん追い抜かれるというか、置き去りにされていってた感じだったんです。それで、もういっそあんな機械なんて使えなくなればいいのにって思ったんですね。では、どうすればそうなるか、そうか電気がなくなればいいんだっていう発想です。
――まあ、気持ちはわからないでもないですが…(笑)。その監督の逆恨みから生まれた作品に深津さんは起用されたわけですが。
深津絵里(以下、深津):私は矢口監督から声をかけていただくのをずっと待っていたのでうれしかったですね。監督とは一度、01年にドラマのお仕事でご一緒させていただいて。私、『裸足のピクニック』(93年)が大好きだったのでご一緒できてすごくうれしかったんです。その仕事の終りに監督から「次は映画でご一緒しましょう」と言ってもらって、その言葉を私はずっと信じていたんです。なのに、なかなか声をかけてもらえなくて(笑)。
――今回、ようやくオファーがきた…。
深津:そうなんです。今までに何度も「次は映画で…」と言ってくださった監督を疑いそうになったこともあったんですが、矢口監督はそんな人じゃないって信じていてよかったです(笑)。高速道路のシーンや川をいかだで渡るシーン、それに畑で豚を掴まえるシーンも全部ロケ(ーション)で撮影すると聞いて、ぜひやりたいと思いました。
――高速道路のシーンもロケですか?
矢口:そうです。今回、全編ロケで撮影することにこだわりました。
――そうすると、企画からこれまでの年月でコンピュータ―技術が進歩したっていうのも、あまり関係なかったんじゃないですか(笑)。
矢口:そうですね。会社の人には訊かれなかったので話さなかったのですが、ロケについては初めから決めていました。でも、あるときスタッフに「この高速道路のシーンはセットとCGですよね」て言われて、「いえ、ロケでやります」と言ったら青くなっていましたね。実際に撮影場所をみつけるのには苦労しました。
――そうまでしてロケにこだわった理由はなんだったのですか?
矢口:一つは、ここで描いた家族の顛末を、観てくれた人がまるで自分の身に起こったことのように同時体験して欲しかったということ。ほんとにこうなったらどうしようという切迫感を感じて欲しかったんです。そのためにはやっぱり街も自然も本物でドキュメンタリーのように撮らないといけない。もう一つは開放感ですね。普段、高速道路を車で走っていて思ったことないですか? ここを自転車で走ったら気持ちいいだろうなって。ぼくにはずっとそんな思いがあって。それはこういう映画じゃないとできないですから。本物の高速道路を自転車で走る、その開放感も一緒に体験して欲しかった。
――矢口作品から感じる独特の開放感というのはある気がします。資料には『サバイバルファミリー』は矢口監督の新境地と書かれていますが、例えば『裸足のピクニック』や『ひみつの花園』(97年)でも、主人公はけっこうサバイバルしていますよね。
矢口:サバイバルというより、どこへ向かっているのか分からない旅はしていますね。そういう人やストーリーが好きですから。ただ、家族を題材にしたのは初めてです。
――そうか、新境地というのは家族の方ですね。今回、家族を題材にしたのはなぜですか?
矢口:スマホの存在が大きかったですね。現代はスマホのために家族の会話がなくなっていると思います。少し前までは、子供たちは何か知りたいことがあれば親に訊いた。ところが現代はみんなスマホで調べてしまう。その方が早いし正確だったりするわけですから。でも、それで親子の会話が消えた。ぼくはそれがさびしくて歪つなものに思えたんです。だから、初めは家族を描く予定ではなかったのですが、どうせ電気をなくすんなら、こういう壊れかけの家族が本来の姿に戻っていく話がいいかなと思ったわけです。
――その壊れかけの家族の要となっているのが、深津さん演じる主婦なわけですが、撮影はいろいろ大変だったのではないですか?
深津:大変でしたが、私はとても楽しかったです。監督は撮りたいものが明確なので、私たちはなんとかそこに近づきたいという思いだけでした。なにしろ監督が現場ですごく楽しそうにしてらっしゃるので、こちらも自然と楽しくなると言うか(笑)。しんどい現場で、監督もしんどそうにされていたらほんとに苦しくなるんですけど、矢口組でそれはない。畑で大きな豚を一家総出で捕まえるシーンも、初めは豚が怖かったんですけど、テイクを重ねていくうちになんとなく豚ともコミュニケーションがとれるようになって、だんだん面白くなりました。
矢口:大変だったって文句言うのは小日向さん(深津さんの夫を演じた)だけなんですよ(笑)。あの方、なんでも大袈裟に言うから。
深津:でも実際一番大変なことを監督がさせたわけだし(笑)。

――現場での小日向さんは深津さんからご覧になってどうでした?
深津:映画の中では全然だめなお父さんですけど、現場ではとても明るくて、私たちをグイグイ引っ張っていってくださる方でした。ご自分では違うっておっしゃるんですけど、すごくおしゃべり(笑)。それにいいものを創ろうという貪欲な方でした。
矢口:小日向さんがぁ!? (笑)、おしゃべりなのはほんとですけど。でも、実は小日向さんに出演オファーをしたのは撮影に入る1年前くらいなんです。だめなお父さん役をぜひやってもらいたくて。ご本人はすごく子煩悩ないいお父さんで、日本中が知っている小日向さんのキャラクターですよね。しかしです。誰もが知っているのに絶対ヒーローにならない、この人について行っちゃだめでしょっていう普通のお父さんができる人。そこを見込んだわけで、その理想のダメ父を演じてくれました。
――劇中では部分カツラを使用しているお父さんで、小日向さんだとその設定にも無理がないですものね(笑)。
矢口:いやいや、多くの人からそう言われるのですが、小日向さんを起用させてもらった理由にそれはないです。カツラの使用は、脚本の稿を重ねていくうちに、お父さんが普段身に付けている物が重要な意味を持つシーンが出てきて、眼鏡にしようかハンカチにしようかって考えているうちに、そうだカツラにしようということなった、後からの設定なんですから。
――そういうことにしておきましょう(笑)。二人の子供を演じられた泉澤祐希さんと葵わかなさんはどうでした?
矢口:経験則で芝居をしないところがいいですよね。
深津:二人とも監督がオーディションで選ばれていたので大丈夫だろうとは思っていました。私、母親役は二度目で(一度目は『博士の愛した数式』(06年))、今回のような大きな子供のいる役は初めてだったので、不安もあったんですが、会ってみたらとにかく二人とも性格がよくて、頼もしくて、この2人でほんとによかったと思いました。たくさん助けられました。
――深津さんご自身は、今回の役はいかがでした?
深津:このキャラクターを演じるのは豚を追いかけるよりずっと難しかったです(笑)。監督の作品のトーンというのがあると思うのですが、この作品では〝演じる〟ということが邪魔になる気がしたんです。オールロケで周りが全部リアルな描かれ方をしているなかで一人だけ〝お芝居してる人〟がいたらすごく変なので、どれだけなにもしない芝居をするかというのが難しかったですね。
――監督から見て、深津さんのお母さん役はいかがでした?
矢口:思った通り、変なボケのかまし方が絶妙でしたね。スーパーで隣のおばちゃんと「ウチ、今日の食べ物これしかないわー、あははは」って笑ったり、家中の現金をかき集めているときに「ハイ、これヘソクリ」ってぽんと大金を出したりする感じ。この人だったらこういう感じだろうなっていうリアリティ、それは深津さん自身が持っている、ちょっと不思議な雰囲気からのものなんです。そうそう、驚いたのが猫用の缶詰、ネコ缶を食べちゃったことですね。
――映画のなかにありますね、家族でネコ缶を食べるシーン…。
矢口:そうなんですが、あそこで食べているのは、あらかじめ中身をツナに入れ替えたものなんです。さすがに本物を食べるのは抵抗あるかなと思って。でも、息子役の泉澤君は二個目を食べる設定で、ここは蓋を開けるところから映るので中身を入れ替えられず、彼には二個目で本物を食べてもらったんです。それで彼が何口か食べて「ハイ、OK」ってなったんですが、そしたら急に深津さんが「それ、ちょうだい」って言って、泉澤君から受け取って食べ始めちゃったんです。
深津:えー、おかしいですか? なんだか急に食べたくなっちゃったんですよね。
矢口:ほら、こういうところなんですよ(笑)。
――最後にあらためて作品への思いを聴かせてください。

矢口:ぼくはスマホは使っていませんが、電動アシスト自転車に乗っているので(笑)、電気がなくなるとやっぱり困ります。でも、実は電気の無い時代って、たった130年前の明治時代に戻るだけなんです。いわば「バック・トゥ・明治」ですよね。そんなことを少し考えてもらえればと思うし、決して世界を壊したいという映画ではないんです。電気がないことで困ると同時に味わえるある種の開放感と、そうなって果たされる家族の再生を描いた映画です。
深津:私、映画に出演して今年でちょうど30年なんですって(デビュー作『1999年の夏休み』、公開は88年の3月)。矢口監督に15年ぶりに声をかけてもらって、30年の節目の年にこの映画に出会えたことはとても意味がありよかったと思っています。矢口監督のこれまでとは一味違う世界を映画を楽しんでもらえたらいいなと思います。
取材・文/春岡勇二
撮影/河上 良(bit Direction lab.)
(2017年2月12日更新)
Tweet Check
Movie Data

©2017フジテレビジョン 東宝 電通 アルタミラピクチャーズ
『サバイバルファミリー』
▼TOHOシネマズ梅田ほかにて上映中
監督・脚本:矢口史靖
出演:小日向文世/深津絵里/泉澤祐希/葵わかな/ほか
【公式サイト】
http://survivalfamily.jp/
【ぴあ映画生活サイト】
http://cinema.pia.co.jp/title/170905/
























