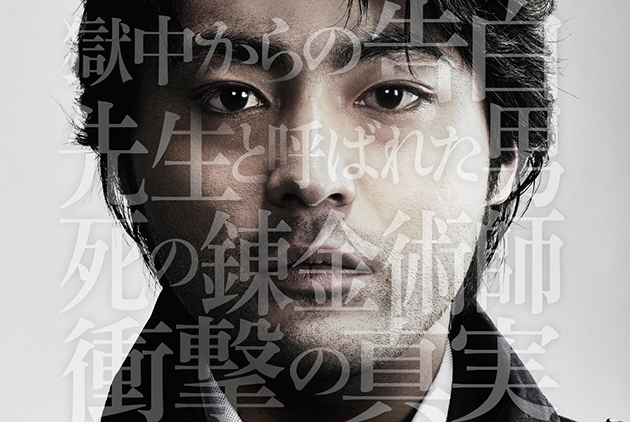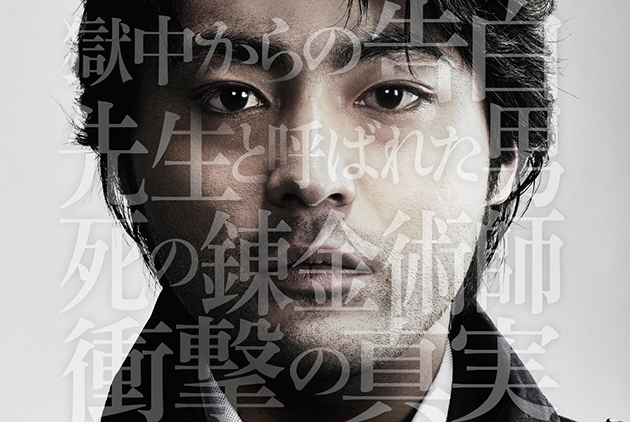
「社会や人間の在り方を弱者、底辺にいる人間から描いていきたい」
大ヒット上映中の社会派サスペンス『凶悪』
白石和彌監督インタビュー
ひとりの記者が埋もれた事件を掘り起こすルポルタージュを映画化した社会派サスペンス『凶悪』が、大阪ステーションシティシネマほかにて大ヒット上映中。
山田孝之演じるスクープ雑誌の記者が拘置所で面会した死刑囚(ピエール瀧)から、自分には3件の余罪があると告白を受ける。それらの殺人事件には「先生」と呼ばれる首謀者(リリー・フランキー)がおり、野放しのままでいる彼を記事の力で追い詰めてくれという“告発”でもあった…。個性的なキャスティングと衝撃的な内容で注目される本作の中で、事件の異常性に直面するうち、それが感染したかのように生じる記者の内面の変化を描くのは映画独自の展開である。
監督を務めたのは、若松孝二監督作品などへの参加を経て、2010年に『ロストパラダイス・イン・トーキョー』で長編デビューをした白石和彌だ。そこで先日来阪した白石監督に、地方都市を舞台にした犯罪ドキュメントを映画化して、抱いた思いなどを訊いた。
──映画化された『凶悪』は、まず時制、タイムラインの作り方に特徴があります。要にされた点は?
「構成の大きな流れは、脚本を書く前から決めてはいました。ただ、事件全体で殺される人の数が多いですよね。それをお客さんにストレスなく説明しなければいけないので、どう見せていけばベストかということを一番考えました」
──現在と過去の転換がシンプルに処理されていますね。原作がノンフィクションなので、「どこまでリアリティを尊重するか? 」、その匙加減も重要だったかと思います。キャストとのディスカッションなどは?
「リリー・フランキーさん演じる「先生」と、ピエール瀧さん演じる死刑囚とが事件に関わる過去の映像、それは取材する記者・藤井の頭の中で描かれているものなので、若干強調はしていますね。「普段よりも少しだけ強い演技をお願いしよう」と決めていて、他の部分は本当にその場所、その土地、その家に居てもおかしくない、あたかもドキュメンタリーを見ているかのような存在感を持って映画の中に居てほしいという話は皆さんにしました」
──ドキュメント性でいうと、中盤のクリスマスパーティのシーンはワンカットで撮られていました。あの場面もそういう“生っぽさ”を求めての撮影だったんでしょうか?
「生っぽさというより、あそこは本当は数カット撮ったんです。でもワンカットで撮っているということが面白かったんですね、芝居も含めて。それで、ここはワンカットで見せ切っちゃおうと判断しました」
──そうでしたか。カメラワークでは、拘置所の面会室で人物を正面から撮って切り返していきますよね。本作のカメラマンは今井孝博さん(近作に青山真治監督作『共喰い』など)。この撮り方は監督と今井さん、どちらからの提案でしたか?
「相談して決めていきました。面会室でふたりが会うシーンは、基本的にただ座って話すだけですよね。でもそのシーン数は多くて、実はこの作品では、どこかへ行けば必ず面会室へ戻ってくるのもポイントになっています。実際は座って喋っているだけですが、登場人物たちの心の中で大きな葛藤や動きが起こるシーンでもあるんです。物語が徐々に進んでいく中でダイナミズム、躍動感を出したかったので、あえて最初はなるべく静かに、しかも観ているお客さんが、自分が対面している錯覚を覚えるような方法論で構築していきました」
──途中でカメラの位置が変わるタイミングも、登場人物の心境の変化にシンクロしているんでしょうか?
「そうですね。途中で記者と死刑囚のふたりが気持ちをひとつにする、そしてそれがまた離れていくシーンがあります。区切られた面会室の中で、ふたりの在り方の流れを表現しないといけなくなったときに、(カメラが)横へ入っていきましたね。最初はひとりが情報をぶつけているだけだったのが、段々と心が近づいて再び離れてゆく。それを表すのに、正面からのカットだけでは見せきれなくなったというのが正直なところでしょうか」
──映像面では、ロケーションが持つ「匿名性」も大きいです。固有の土地と感じさせない、ありふれた風景が多いですね?
「撮影前に事件が起こった場所を調べて、行ける限り足を運んだんですね。ほとんどが茨城県でしたが、そのときに事件に特異性はあるものの「茨城のこの場所だから事件が起こった」という印象を受けなかったんです。どうしてかを考えると、今後3人に1人は老人になってゆく、その老人たちへ対する福祉の環境が地方で行き届いているとは言い難い。そういう現在の日本の“切り離された地方”だからこそ起きた事件だと感じました。見て回った場所や土地にも独特の匂いや空気感はありましたが、一見するとどこにでもありそうで、僕の出身地の北海道でも見たような気がする。街から車でほんの20分ほど走れば見えてくるような風景なんですね。そこで「あ、こういうことなんだな」と思って」
──その場所に立たれて逆に、地方でならどこででも起こり得る事件だと感じた?
「はい。「これは日本のどこで起きても不思議ではない事件なんだ」と強く思いました。たとえば細田守監督が『おおかみこどもの雨と雪』で描いた美しい日本ですとか、宮崎駿監督が描く田舎の風景などではない、樹から陰が落ちた荒れた土地、誰しもが行った経験を持つような場所を中心にして撮れば、この事件の特徴がより見えてくるかな? と考えてロケ地を選んでいきました」
──『凶悪』の制作が、白石監督の社会や現代への見方に与えた影響はありましたか?
「映画で描いた事件に限らず、以前はニュースなどで報道される事件を見ていても、どこか他人事だったんですね。だけど映画に取りかかって実際に現場へ出向いたり、いろんな経験をしていく中で、やっぱり同じ時代、社会に生きていれば地続きでつながっていて、一歩間違えて小石につまずくと僕や家族、愛する人が事件に巻き込まれる可能性もあると思うようになった。何事もなければ平和に暮らしているけれど、いかに僕たちの住んでいる社会や状況が危ういものであるかということを感じたんですよね。それは観てくれる方にも少し感じてほしいと思います」
──監督が持たれている、そのような現代への認識が本作のひとつの背景といえますね。
「原作もそうですが、この映画は「家族の話だな」と思ったんですね。殺される老人たちは社会や家庭から切り離されて、特に電気屋の老人は家族から捨てられる訳じゃないですか? 一方で、凶悪な死刑囚と「先生」は、セリフでも「僕たちはひとつの家族だよ」と言い、自分たちの子供や情婦、舎弟も含めて強固な家族的関係を守って頑なに愛そうとしている。その構図は今の日本をどこか浮き彫りに表現しているし、記者の家族は母親を施設に入れるかどうかで迷っている。それらのはざまに主人公の記者を置けば凶悪性を描くだけでなく、家族の物語としてもすっと一本、筋が通るんじゃないかと思い作っていました」
──本作は「擬似」であれ、家族というユニットが、山田さん演じる記者の周りで変形しながら重なり展開する物語と見ることができますね。そこで池脇千鶴さんが演じる記者の妻は、観る女性が作品に入り込みやすくなる「間口」の役割を果たしているようにも思えます。
「うん。女性は自分の気持ちを確かめることができるし、男性もそうかもしれません。記者も含めての事件だったので、それを客観的に直視して批判する人物が必要だなと思ったのと、出てくるのが皆“おかしい人”ばかりの映画だと、観ていて訳が分からなくなってしまう(笑)。だから、ひとりは“普通の人”も入れておきたいという考えが根本にありました。でも脚本を書いてゆく上で、結果的には彼女も片足を突っ込んでしまう形になっちゃったんですけどね」
──彼女だけが完全に悪から距離を置いているともいえないんですよね(笑)。
「凶悪を抱えているっていうね(笑)」
──そうした人間の持つ両義性が伝わる映画です。さて白石監督は、若松孝二監督の下で映画を作ってこられました。視線を向ける先に違いはあっても、若松さんが持っておられた時代や社会へのまなざしは、白石監督の中にもあると感じるのですが?
「僕が若松さんから受け継いでいるのは、やはり“弱者からの視点”ですよね。若松さんの場合はそのまま権力へ向かっていくんですが、僕は権力というよりは、この社会や人間の在り方を弱者、底辺にいる人間から描いていきたいという思いが根底にありますね。それは師匠の教えでもあり、すごく共感して僕の中に残っているものです」
──前作『ロストパラダイス・イン・トーキョー』(10)にもその要素はありましたね。
「そうでしたね。その意味では『凶悪』でも、死刑囚と「先生」は暴力においてのヒエラルキーは高いかもしれませんが、社会から完全にはじき出されて、そこで生きていけない人間たち。対して記者の藤井は、おそらく一流大学を出て高い給料をもらって、むしろ弱者ではないんだけれども、彼を主人公に据えて、死刑囚や「先生」と同じ目線に落としてみたかった。その思いは強くありましたね」
──「悪を追求する記者」にとどまらない脹らみを持たせています。
「記者の務めを考えれば、追い詰めた「先生」が逮捕された時点で本質的な仕事は終わっているはずですよね。実際に取材して原作のノンフィクションを書かれた宮本太一さんも、「先生」が捕まってそれを本にした段階で一件落着というか、一区切りされているんですが、映画ではそれだけじゃない。そこから記者を離れて、何を赦して何を赦さないか、罰を負わせるにはどうするんだと、ひとりの人間として動いてゆく藤井の物語にしていきました。それは僕自身も思ったことだし、主人公の“藤井に見せてもらいたかった”ことでもありますね」
──事件解決までの道筋だけでなく、主人公の変容も作品の芯で、その過程で藤井が“いなくなる”時間が少なからずありますよね? 物語上で主要な人物の不在の時間は、その間に何か変化が起こっているという捉え方ができます。『凶悪』の場合は、取材を通じた事件への没入でしょうか?
「その通りで、本当はしてはいけないことなんですよね。主人公が間にあれだけいなくなるというのは。それは脚本を書いているときから重々承知していました、ただ、たとえば過去の話を死刑囚に面会の度に「ひとりめはこう殺しました」と説明させて、その殺害場面があり、それを記者が調べてまた面会室へ戻ってゆくという細かな回想を入れることもできたんでしょうけど、それだと過去の映像が単なる再現ドラマにしかならないんですね。映画である以上、それは避けないといけないし、面白いと僕にはとても思えないところでもあったんです。だから途中の不在は分かっていながら、そうせざるを得なかった部分もあります。そこで山田さんが藤井役を引き受けてくれることになったときに、「山田孝之なら自分が消えてしまう部分も埋められる。その間に何があったということを説明しなくても体現してくれるんじゃないかな」という期待と、演出家としての僕の核心が鍵になりました」
──不在の時間の想像が、作品を観るときに厚みを与える。「そこにいない山田孝之」を見ようとするのも『凶悪』の楽しみ方かもしれません。
「そうですね。あと、この映画は観た後に爽快感などは無いかもしれませんが、圧倒的に面白い映画を作りたいという思いを持っていたし、山田さん、瀧さん、リリーさんたちも見たことのない顔をしています。その顔が映画の中でまたどんどん変化していって、それぞれのポジションもまったく違うところへ向かいますよね。感情というのか、そのあたりも最後まで観ていてどうなるかわからない面白さがあると思うんです。“気分のアガらないエンタテインメント”がどれほど面白いかを見せたくて、思い切って作った作品です」
(取材・文 ラジオ関西『シネマキネマ』)
(2013年9月27日更新)
Check

白石和彌 監督 プロフィール(公式より)
しらいし・かずや●1974年12月17日生まれ。北海道出身。1995年、中村幻児監督主催の映像塾に参加。以後、故・若松孝ニ監督に師事し、フリーの演出部として活動。若松孝ニ監督『明日なき街角』(97)、『完全なる飼育 赤い殺意』(04)、『17歳の風景 少年は何を見たのか』(05)などの作品へ助監督として参加する一方、行定勲、犬童一心監督などの作品にも参加。監督・脚本を務めた初の長編作品『ロストパラダイス・イン・トーキョー』(10)をへて、本作の監督を手がける
Movie Data

(C)2013「凶悪」製作委員会
『凶悪』
●大阪ステーションシティシネマ、
なんばパークスシネマ
ほかにて大ヒット上映中
監督:白石和彌
脚本:高橋泉/白石和彌
出演:
山田孝之/ピエール瀧/リリー・フランキー
池脇千鶴/白川和子/吉村実子
小林且弥/斉藤悠/米村亮太朗
松岡依都美/ジジ・ぶぅ/村岡希美 ほか
【公式サイト】
http://www.kyouaku.com/
【ぴあ映画生活サイト】
http://cinema.pia.co.jp/title/161371/
新潮45編集部編
『凶悪─ある死刑囚の告発』(新潮文庫)
http://www.shinchosha.co.jp/book/123918/