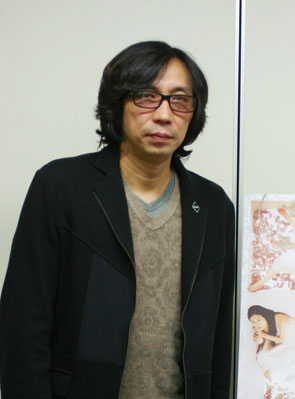「他人事のように笑ってくれればいいんです。
他人事だったら恋愛のごちゃごちゃの顛末を笑ってもいいと思う。
ま、たまに他人事じゃなくて身につまされてる人もいますが(笑)。」
『つやのよる ある愛に関わった、女たちの物語』
行定勲監督インタビュー
直木賞作家・井上荒野の同名小説を、『パレード』、『今度は愛妻家』の行定勲監督が映画化した『つやのよる ある愛に関わった、女たちの物語』が1月26日(土)より、梅田ブルク7ほかにて公開。恋愛に対して奔放な“艶(つや)”という名前の女性の存在によって見えてくる、彼女を取り巻く男女の愛や生き様を深く濃厚に描き出す。阿部寛が艶の夫役で主演を務め、小泉今日子、真木よう子、野波麻帆、風吹ジュン、大竹しのぶら豪華女優陣が共演する恋愛アンサンブルだ。モラルや正論を軽やかに飛び越えてみせる、美しい刺激に彩られたセンセーショナルな愛の物語を手がけた行定勲監督が来阪。話を訊いた。
――原作のどんなところに惹かれたんですか?
「井上荒野さんの小説は、ある状況を見出していたり、何が表現したいのかも明らかにあるけれど、それを説明しないで最低限のことしか書いていないんです。つらつらとまるで自分の日記のように書いてある恋愛小説とかよくありますが、荒野さんの小説は文学としてかなり崇高で、状況しか書いてないんですよね。感情は書いてないでしょ?」
――確かにそうですね。
「そのままを映画にしたいと思ったんです。読んでると様々な箇所で思いを馳せて、いろんな場面が浮かんでくるんですよね。小泉今日子さんが演じた女性というのは原作ではバトルしないんですが、行間から映画的な場面がポーンと飛び出してきたんです。それを見出せる力がこの原作にはあり、その見出した部分が映画なんです。」
――なるほど。
「長編小説の映画化などで、物語を一生懸命追いかけて4時間くらいになって、それを色々カットして2時間くらいにしたらダイジェスト版みたいになって、結局、映画より小説の方が面白いって言われるのは当たり前の話。短編を長編に伸ばす方が充実するに決まってるんですよ。今回はその感覚に近いんです。これは群像劇だから、その群像の間を埋める軋轢というか、ぶつかる衝突を作るための場面がいろいろ浮かんで。それを映画化したいと思ったのが最初です。」
――そこからどう組み立てていくんですか?
「で、どうまとめていくかとなった時に、実は松生がすべて仕掛けていた話だという流れを通したら松生の愛と女性たちの愛の比較が見えてきて。いろんな形はあるが、向いてるベクトルが“愛を貫く”という、同じ方向に向いていった。これは結果ですけどね。」
――監督は男性ですし、女性の愛の生き様を撮るのは難しかったんではないですか?
「難しかったですよ。愛の部分だけでなく、この映画は全員が自分の生き方を持ってて、全員が主役。映画が始まって1時間後から登場する人たちも登場する前からそこに生きていた空気を持ってないといけない、ということに気を配りました。そのためには、この人はどういう生活を送ってきたのかをかなり作り込まなければいけなくて、それぞれにどんな生活をしていてどんな歴史があったのかを全員に手紙を書いて渡しました。」
――女優さんそれぞれにですか?
「そう。その手紙の内容を理解して、その状況から生まれた愛の感情は女優から出てきたもの。信用できる女優でないと出来ないことですからキャスティングが大変でしたね。みなさん一様に「わたしはこういう女ではありませんが理解は出来ます」と言っていましたが、それが大事なんですよね。ただでさえ説明を排除している映画なので、分からないままではダメで。この映画は、愛の形を立体化させるというか、女優の表情や肉体でこの人はこういう人なんだと見えてくると思います。そういう意味でも女優にはこの映画の重要な部分を担っていただきましたね。」
――では、阿部寛さん演じる松生についてはどんな演出をされたんですか?
「阿部さんは撮影中、松生そのものでした。阿部さんが元々ああいう人だというわけではないんですが、まったく作ってもないんです。まず11キロ痩せるというところから始まって、そういう肉体に魂が宿っていったという感じで。阿部寛ってすごい俳優ですよ。出会えて良かったと思っています。」
――確かにこの作品の阿部さんはちょっといつもと違いますね。
「たとえ阿部さんが台詞を間違ったとしても、松生が言ってるから気付かないくらい、松生になっちゃってました。撮影中、阿部寛である一面をまったく見せないし、こちらも現実に戻したくなかったという感じ。せつないけど滑稽な変わった役だったと思いますが、阿部さんには分かりやすかったんですかね。完成した後に、最後の松生はどんな気持ちだったんですかね? と聞いたら「なんかね、松生は艶(つや)のことが自慢だったんですよ」と言っていました。それがクレイジーケンバンドの歌に絶妙に繋がるんですよ。」
――松生は艶(つや)を亡くし、残されるわけですが、行定さんの作品というは大切な人を亡くし残された人を描くことが多いですね。そのテーマにこだわる理由を伺ってもいいでしょうか?
「人は死にますからね。僕は、人の死を感じると自分の生き方を思い直すところが普段からあるんです。生きてるって漠然としてるから、生きてなくていいんじゃないかと思ったことが何度もあります。だからって自殺しようと思ったことはないんですが。ただ、人の死に直面すると明らかに生きてる自分が見えて、そこに意味があるような気がするんです。」
――はい。
「そこで、死んでいく人間の苦しみを描こうとは思わなくて、それより人の死に関わると、そこに“生きる”という課題が残る。この映画も、艶(つや)という女は、とんでもない女ではありましたが、松生は最愛の女を亡くすわけですから悲しいはず。だけど、僕はクレイジーケンバンドの歌も含め、何故か爽快な感じを受けたんです。」
――確かにそうですね。
「昔は少し残酷だったところもあって『ひまわり』って映画は、死の後に「あー携帯濡れた」とか言ってるんですが、その瞬間に死んだ人のことを忘れて、明日のことを考えてる。人って忘れないと前に進めないですからね。ただ今は、忘れられない死にまつわる話。死を目の前にして周りのみんなは何に直面するのかに興味があります。この映画で言えば、そこで女たちの“生”が輝くというか燃える。そんな感じがしています。この映画は特に生命力のある女性たちの映画ですね。」
「ひとつ、こちらから質問なんだけど、ラストの艶(つや)の胸が映るシーン見てどう思いました? 普通の胸でしたよね? むしろ小ぶりな。」
――はい。そうでした(笑)。
「(大竹)しのぶさんがあのシーンの撮影の時に「艶(つや)ってあんな胸なんですか」と僕に言ったんですよ。愛に奔放な女ですから、男を魅了する肉感的な胸を想像してたらしいんですがそうじゃなかったから。それで、「その胸を見て、どう感じました?」と聞いたら「綺麗だけど、大きくないんだね」って。それで「それがねらいです」と言ったら「なるほど。深いね。」とおっしゃてました。大竹さんが演じた女性が艶(つや)の肉体に触れるシーンがありますが、そこで絶妙な感情のにじみ具合で涙がポロッと出るんですよね。」
――その、ねらいを具体的に言ってもらってもいいですか?
「役柄的に45歳くらいの女性のいろんな胸を見ました。艶(つや)を演じてもらったのは、大島葉子さんという女優さんで、ものすごい綺麗な少女のような胸をしてらしたんです。45歳にして、そんな綺麗な胸で、そこに松生は歯形をつけていつも愛撫している。死にそうなのに。淫乱なイメージで語られてる女がこんな綺麗な胸をしている。それが、巨乳だったり肉感的なエロチックな胸だったら松生のことをバカだなぁと思うし、しのぶさんが演じた女性もこの胸にわたしは負けたのねと、もしかしたらホッと安堵するかもしれない。だけど、そうじゃないから嫉妬だけじゃなく複雑な気持ちになってくるんです。あれが余計に腹が立つという人もいれば、あれに泣けたという人もいますが、若い人たちは意外でした! って意見が多い。あの胸の話にしても恋愛の意外性をついてると思います。」
――そのシーンにしても、観客にどう思うか考えさせてるんですね。
「日本映画界自体がプロデューサー含め、分かりやすいものばかりを求めてる。日本だけでなく世界的に見ても何も考えなくなりましたよね? 60年代~ぎりぎり80年代とかもあったかな。僕が最も影響を受けた監督たちの映画はとても大人の話で感覚的なものが多くて、不可解なものがいっぱいありました。なんでそうするんだろう。なんでそうなるんだろう。それで結果的にこんな終わり方するんだ、と最初と最後で主人公の顔が違ったり。ものすごい大きな何かを達成した男の話とかではなく、日常的な話でもそうでしたね。人生がそれだけ豊かだったっていうことなんではないですかね。」
――確かに昔の映画と今の映画の圧倒的な違いかもしれないですね。
「インターネットの普及もあって自分の気に入ってる人、好きな人としか会話しない。自分の分かってるものにしか興味がなくて、その辺から影響を受ける。自分の好きな人が言ってることしか選択しない。映画もみんなが列を作って並ぶようなものって、面白いかどうかは関係なく並ぶ。でも、昔はもっと多様性がありました。この映画は多様性の映画です。」
――確かに、いろんな見方が出来る作品ですね。
「分からないことを決して悪いことだとは思ってなくて、恋愛映画にも分からないものはたくさんありました。昔は、僕が子供だから分からないのかなと思ったりもしたけど何か引っかかる。この映画にも引っかかるところがいっぱいあると思うんですよ。なんで松生は最初、艶(つや)を殺そうとしていたのか、彼は何を思って、何を始めるのか。でもそこから自然と色々見えてきて、最後に松生がどんな顔をしたかって話です。松生は何考えてるんだろうという疑問を抱くように作っています。でも、それはそんな難しいことではなくて、他人事のように笑ってくれればいいんです。基本的な構造として、これは他人の不幸を笑う映画ですよ。他人事だったら恋愛のごちゃごちゃの顛末を笑ってもいいと思う。ま、たまに他人事じゃなくて身につまされてる人もいますが(笑)。」
(2013年1月22日更新)
Check