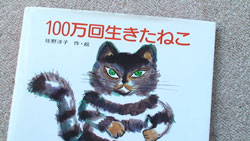「生き辛さを撮られる側も撮る側も肯定しようというコンセプト」
『ドキュメンタリー映画 100万回生きたねこ』
小谷忠典監督インタビュー
世代や時代を超えて愛され続けている人気絵本『100万回生きたねこ』の作者と読者を繋ぐドキュメンタリー『ドキュメンタリー映画 100万回生きたねこ』が1月5日(土)より、梅田ガーデンシネマにて公開。小谷忠典監督は、ガンを患い余命を告げられた作者・佐野洋子の最期の日々と絵本を読む読者の姿を通して、35年もの間、愛され続けてきた『100万回生きたねこ』の不思議な魅力と佐野洋子の世界を映し出す。そして、読者たちは絵本を朗読してそれぞれの“生と死”を語りだす。そこで、小谷忠典監督に話を訊いた。
――有名な絵本ではありますが、この絵本と監督の出会いは?
「特別に好きというわけではなく何冊もある絵本の中の1冊という感じでした。だけど他の絵本とは毛色が違って“死”について書かれていて人生には死ぬということがあるのかと5歳くらいの時に知りました。
――では、このドキュメンタリーを撮ることになったきっかけは?
「だんだん大人になるにつれて、例えば友人や祖父が亡くなったり、身近で“死”を体験することが増えていく中で『100万回生きたねこ』の存在が大きくなってきました。その度ごとに本棚から出して開いてみたりしながら成長してきたようなところがあります。絵本との関係はそういった感じなんですが、20歳頃に佐野さんのエッセイを読み始めてファンになっていたのがきっかけですかね」
――佐野さんのエッセイのどういったところがお好きだったんですか?
「20代なんて誰でも悩んでるのかもしれないですけど、僕も20代のころ人生について悩んでいて(笑)。自分は他の人とは違うんじゃないか、みんなとうまくやっていけないんではないかと勝手に思い込んだりしていたんです。でも、佐野さんの文章は、それでもOK!×だと思っていたものに○をつけてくれるような存在で。それで読んでました。」
――撮影を始める前から佐野さんが病気だということは知っていたんですか?
「そうですね。2008年の『シズコさん』というエッセイの中で“余命、後2年…”ということが書かれていて、僕がお会いしたのはそれから1年後だったので、余命が後1年ということは理解していました。だけど、この人が死ぬからドキュメンタリーを撮るということではなく、この人が好きだから撮りたいというところから始めました。」
――実際の佐野さんはどういう方でしたか?
「めちゃくちゃ怖い方でした。いつも怒られてましたし、2回くらい泣かされました。「あんたといても面白くない」と言われたり、結構厳しかったです。佐野さんにいろんなことを質問して引き出そうとするんですが全然答えてもられなくて。そういう関係を望んでいなかったらしく、僕もどうして接したらいいか分からなくなったりもしたんですが、僕の家族の話や面白かったことなんかをこちらから話すようにしたら少しづつ佐野さんも話してくれるようになりました。今思えばそこから関係性が変わってきたと思います。最初は「まだいるの?」と言われてましたが、仲良くなってきたら「もう帰るの?」と言ってくれたり(笑)。」
――では、実のお兄さんの話を聞けたのは、かなり貴重ですね。
「基本的に会話のほとんどが無駄話で、人の愚痴やしょうもない話が好きだったんですけどね。たまに重要な話をしてくださったので、それを映画で使ったような感じです。」
――とは言え、佐野さんは「自分の姿を写さなければ撮ってもいい」とおっしゃって、この映画には佐野さんは出てきません。撮影は大変ではなかったですか?
「致命的ですよね。最初はどう接したらいいんだと思い悩みました。でもそこがドキュメンタリーの面白さでフィクションではなくてある現実を撮るにあたって条件が出てくる。今回は姿が撮れないという条件だったわけですが、それをプラスに考えて、ではどういった撮り方があるんだろうかと試行錯誤して出てきたアイデアが映画の中にあります。」
――それで読者の方を探していったんですか?
「佐野さんの周りの著名人に語っていただくという形で撮ることも出来たんですが、今までにないものに挑戦したいなというのはありました。それで、佐野さんの存在を感じられるような人たちに出てもらいたいと思いました。ひとつの出来事に対してあらゆる年代の記憶で話すという佐野さんの話し方からヒントを得て、いろんな年代の人を撮らせていただきました。」
――出てくる読者の方々はどうやってみつけたんですか?
「道で偶然出会った人もいれば…」
――え? 突然声を掛けたんですか? その人に声を掛けたのは何故ですか?
「自分の中でどこか佐野さんを重ねたイメージが元々ありましたし、単純に年代別のイメージで声を掛けました。同世代の方に出会う機会はいくらでもありますけど60代、70代になるとなかなか出会えないので。」
――読者の方々の暗く思い雰囲気が映画のチラシやポスターのイメージと違って正直驚きました。
「ある種、生き辛さを抱えてる人たちが出てきて、その人たちの生き辛さを撮られる側も撮る側も肯定しようというコンセプトで描いています。例えばマッチを使うシーンでは、暗闇の中で誰にも見せずに隠していたものをマッチの炎で光をあてて浮かび上がらせて隠さずに見せるということで肯定するという意図がありました。」
――ドキュメンタリーではありますが他のドキュメンタリーと少し違う印象を受けました。
「僕自身が結構イメージ的な映像が好きということや、元々フィクションをずっと作っていたので、いわゆるカメラを持って追いかけるというようなことをやっていなくて。そういうのも影響してるのかもしれないですね。」
――そして、撮影中に佐野さんが亡くなってしまうわけですが、その後はどんな心境でしたか?
「佐野さんが実際亡くなってもその事実を実感できなくて…。40回くらい引越をされていたらしいんですが、佐野さんの死を受け入れて自分の中で消化する為に、そういった佐野さんがいた場所を回り始めました。それで、最終的に行った北京の胡同(フートン)の街が破壊されていくのを目の当たりにして、その時初めて佐野さんの死を実感したという感じです。」
――お葬式の場面を撮っていますがご家族からはどのように言われたんですか?
「息子さんでイラストレーターの広瀬弦さんにご挨拶をさせてもらった時に「お葬式撮りたい?」と聞かれて、その時は何も答えられなかったんですけど、その5日後に実際亡くなったことを知らされて撮りに行きました。」
――この映画を観た広瀬弦さんの反応はどうでしたか?
「佐野さんが亡くなった後、講談社との間に入ってくださったり、北軽井沢での撮影の段取りをしてくださったり、本当に協力的で作品に対しても肯定的に観てくれました。そういえば先日、今まで感想を聞いたことがなかったので聞いてみたら第一声は「暗い」でしたが(笑)、「他人が自分にそんなに興味を持ってくれることはないから佐野洋子はこういう映画を作ってもらって幸せ者だ」と言ってくださいました。」
――では、渡辺真起子さんやコーネリアス起用の経緯は?
「小山田さんは佐野さんのお葬式に行った時に見かけて「なんで小山田圭吾がここにいるんだろう?」と思ったら、広瀬弦さんと小山田さんが幼馴染とかで昔から交流があったと後から聞いて。渡辺さんも同じで小山田さん、広瀬さんが同じ学校に行ってたらしいんです。」
――すごい繋がりですね。最後にこの映画でこだわったポイントがあれば教えてください。
「絵本は雑草が揺れてるような感じのページで終わるんですが、そこに僕は“風”を感じて、映画の最後も佐野さんが亡くなって“死”で終わるんではなく“生”のイメージを描きたいと思い、そこにはちょっとこだわりました。そういう意味で最後のページの“風”は、北京の風を探しに行くというのにつながりました。」
コーネリアスが音楽を担当していることでも注目を集めている本作を観れば、想像以上の重さに驚くだろう。しかし、この感覚は絵本『100万回生きたねこ』を読んだ時の感覚にも似ている。絵本も決して明るく可愛い物語ではないが何かが深く心に刻まれるのだ。監督自身が佐野さんのエッセイから感じた“×だと思っていたものに○をつけてくれる”というところや、生き辛さを肯定するコンセプトを感じながら観てみてはいかがだろうか。
(2013年1月 3日更新)
Check