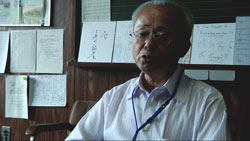「リスクを遠くに離して見えないことにしたいということを
原発に関して日本はやっている。
それに気づいてしまったからには見せまくるしかない」
『フタバから遠く離れて』舩橋淳監督インタビュー
『谷中暮色』や『ビッグ・リバー』の舩橋淳監督が福島県双葉町町民の避難生活に迫ったドキュメンタリー作品『フタバから遠く離れて』がシアターセブンにて上映中。3.11、東日本大震災発生。翌日に1号機の水素爆発の音を聞き死の灰を被った、福島県双葉町。原発により潤い、そしてその原発の事故によってすべてが奪われてしまった。住民はその後、立入禁止となった町から埼玉の高校に強制的に避難することとなった。カメラは、一向に先の見えない避難生活を続ける彼らの様子を捉えていく。3.11の後、町が全面立入禁止となり、避難生活を余儀なくされた彼らの生活と複雑な思いを映し出す。日本の原子力政策の現状に一石を投じる意欲作だ。そこで舩橋淳監督に話を訊いた。
――避難所の方々との接し方で気をつけたことはありますか?
「明らかに大変な状況の方々に、興味本位でズケズケと無神経に聞けないですよね。メディアはみんな聞きづらいから防御策として同情モードで行くんですけど、それを見ていてこれって誘導尋問じゃないかと思えてきたんです。要はその方々に寄り添って“被災者”の枠に当てはめてるように感じたんです。だから僕は誘導尋問はしない。ひとりの人間同士として普通に接して仲良くなっていくことを心がけました。自分が聞きたいことではなく、話してくれることを聞こうと。」
――震災後、現場に入られたのはいつですか? またどういうお気持ちで撮り始めたんでしょうか?
「現場に入ったのは3.11の直後ではなく4月だったんですけど、被害にあわれた方々を“被災者”とひとくくりにすることに当初から違和感を感じていました。本質的に違う災害がふたつあるんではないかと。映画の役割はジャーナリズムでは描けない、言語では表現できない人間の感情やジレンマ、矛盾などを見つめていくことだと思い、時間と共に定点観測していくべきではないかと撮り始めたんです。」
――津波と放射能の違いですね。
「避難している時間が長引くことによって矛盾が表面化してくるんじゃないかと思ったんです。2012年の4月に菅直人が「10年、20年帰れないんだから」と発言し「何言ってんだ!」と叩かれていましたが、それが過剰反応に見えて、僕はそれを少し奇異に感じました。」
――真実だったとしても、言ってはいけないことを言ってしまったということですね…。
「恐れているのはそういうことなんじゃないか、漠然とした恐怖に向けてキャメラを向けていくということがドキュメンタリーに出来ることなんではないかと。それは言語表現できないことかもしれないけれど、みんなが感じてた恐怖ですから。」
――デモを捉えたシーンが印象的でした。
「個人の“帰りたい、でも帰れない”という感情と、政治家が握手して笑顔で「どこから来たの?」と話してるのを通して国が見えてきますよね。必死で伝えてることがまったく国に伝わってない。民主主義が破綻してるそのものなんですよね。個人の物語が国とぶつかりあい、矛盾がカメラの中に映ってしまった瞬間だなと思いました。一時帰宅もそうです。自分の母親が亡くなったらすぐにでもその場所へ行くことが出来るのが当たり前なのに、ずっと行けなかったわけですから。これも原発避難の矛盾です。線香をあげるのに3ヶ月も待たされて、行っても時間制限があったり。いろんな矛盾がカメラの中に入ってしまいました。」
――そこには演出はなくともドラマが生まれてるんですね。
「ドキュメンタリーもフィクションも、時間の経過と共に感情の物語を作っていくと思うんです。演出せず現実をそのまま映すとしても、個人の感情としてある物語が、外の世界とぶつかりあって火花を散らした瞬間、社会の矛盾が見えてきたんです。」
――それで撮り続けたということですね。
「まぁ、そういったものが見えてこないかなぁと漠然と思ってたんですが、それがいつ見えるのかは分からない。だから今も続編に向けて撮影を続けてるんです。撮影をしてる時は、いつどこで区切りをつければいいか分からず、原発問題が続く限り、双葉町の人たちが双葉町に戻るまで撮ろうかなという話をプロデューサーともしています。」
――では今回この作品に区切りをつけたのはどういうタイミングで?
「2011年12月に野田総理が原発収束宣言を出して、その時に自分が毎日見ている避難所の現実を見ておかしいだろ、これのどこが収束したんだと思い、この撮った映像を国内だけでなく世界に突きつけたいと思ったんです。それで急ピッチで編集して2月のベルリン映画祭で上映しました。それまでにある程度まとめてたからいけたというのもありますけど本当に急ピッチでした。300時間をガッと縮めたつもりが11時間で(笑)。」
――では、観る人に何を感じてもらいたいですか?
「避難所の生活を一緒に生きて欲しい。朝起きて布団をたたんで隣の人を起こさないようにそっと出てパンを貰って食べて、午前中はぼーっとして昼のお弁当食べて、それから散歩してテレビ見てまた夜の弁当が来てという日々、時間を。避難所を描くというのはエピソードエピソードでつまみ食いをするのではなく本当にそこに生きてるかのように感じてもらえないかなぁと思ってたんで、お風呂へいくところなど細かいシーンもずっと撮ってて11時間になってしまってたんですよね。」
――双葉町の町長の発言を撮っているのがすごいですね。
「僕は彼のことを原発事故以前、以後に変わっていった日本人の意識の象徴だと思うんですよ。原子力を描くということは人間を超越したものを描くということなんです。1960年代頃に作られた“原子力未来のエネルギー”みたいなドキュメンタリーとか、経産省などがお金を出して撮ったようなドキュメンタリーもありますが、そういうのを観るとこの時代は原子力を信じきってたんだなと。鉄腕アトムもドラえもんも原子力ですからね。原子力というのはその時代の風潮や思想に影響された距離のとり方をしているんですよね。今は原発について批判的に思っているけど、もしかしたら20年後30年後にはスタンスが変わってるんじゃないか。原発万歳になってるとは思いがたいけども、それほど180度変わってしまったことを思うとまた変わるかもしれないと思ったので、あくまで受身に徹しようと思ったんです。」
――残念ながら現状、関西では他人事なところがあるのも事実です。
「だから観てほしいんですよね。我々は電気を使っていますから。東京の人間は本当に当事者なんですが、関西も当事者だと思います。もし何かあった時に割を食うのは地方の人なんですよね。原発はハイリスクハイリターンなんですよ。都会では湯水のように電力がじゃんじゃん使える。都会ではどこから電気がきているか分からない。今、携帯電話を充電した電気は火力なのか水力なのか原子力なのか意識せずに使えて経済も繁栄する、地方では交付金によって潤うし、雇用もある。ただ、リスクは不平等に拡散されてた。安全神話というのはそのハイリスクを隠していたんですよね。」
――監督がこの作品で伝えたいこととは?
「原子力について考えなければいけない。それが1歩なんですけど。原発反対! と行く前に原発というものが、とてつもなくリスクが高いものだと分かった。自分が使ってる電気で自分が避難しなくてはいけないんだったらまだ分かる。しかし、自分が使った電気でこんな遠くの方々が避難しなくてはいけないってどういうことだと。福島の原子力発電所の電気はほぼ100%関東で使われてました。双葉の方々は東北電力の電気を使っていました。なんだかとっても不公平な匂いがしたんですよね。こんなに大変な方々がいるのに僕は家に帰れば普通に電気が使えるのはなぜだろうというのが引っかかって。これは答えが出るまで撮り続けなくてはいけないなと思いました。不平等な犠牲のシステムが悪いということが分かったけど解決法が見つからない。僕が出来ることは「これ不平等です!」と言って訴状に乗せることです。我々が電気を使うということはイコール彼らにリスクを背負わせているんですよということをみなさんに知ってもらうということが。」
――それがタイトルに繋がってるんですね。
「遠く離れてというところにいろんな意味を含めてるんですけど“臭いものに蓋をする”ではないですが、リスクを遠くに離して見えないことにしたいということを原発に関して日本はやってるんですよね。それに気づいてしまったからには見せまくるしかないんです(笑)。」
(2012年12月11日更新)
Check