
ホーム > インタビュー&レポート > 山下敦弘監督と脚本家の向井康介が大阪芸大に凱旋! 『マイ・バック・ページ』ティーチ・インレポート

山下敦弘監督と脚本家の向井康介が大阪芸大に凱旋!
『マイ・バック・ページ』ティーチ・インレポート
『リンダ リンダ リンダ』や『天然コケッコー』の山下敦弘監督が映画化に3年半もの歳月を費やした渾身作『マイ・バック・ページ』が大阪ステーションシティシネマほかで公開中だ。60年代後半から70年代にかけての日本を舞台に、松山ケンイチ演じる、変化を起こそうと闘う活動家・梅山と、妻夫木聡扮する、新聞社で週刊誌編集記者として働く若きジャーナリスト・沢田、交錯する彼らの運命を描き出す。公開に先立ち、山下監督の母校である大阪芸術大学内の映画館で学生限定上映の後、山下敦弘監督と脚本家の向井康介が大森一樹映像学科長、脚本家で映像学科教授の西岡琢也とともにティーチ・インを行った。
山下と向井のふたりは、現在の大阪芸術大学映像学科、学科長である大森と教授の西岡とは、学生時代の面識はないが、大森と西岡もやはり大阪芸大を代表する映画監督であり脚本家である彼らに対しては様々な思いがあるよう。中には厳しい質問が飛び出し、山下と向井が苦笑する場面も。山下と向井は久しぶりの母校とはいえ、現在の学科長と教授に恐縮しきりの様子だった。
大森:僕は、どうなるかと思ってハラハラして観てたんですが、ちゃんとやってましたね(笑)。個人的には面白かったです。すごく丁寧に撮ってたし、自分たちが生まれる前の話なのに、人物像をうまく作り上げたところに感心しましたね。僕らの時代の話だし、(原作者の)川本三郎さんとはキネ旬をとおして親しくさせてもらってますし。さっき西岡先生とも話してたんですよ。なんでこの映画の話がふたりに行って僕たちに来なかったのかと(笑)。
西岡:今日は誉めろと言われてるので、誉め殺しの会ということで(笑)。作品の話に入るけど、(主人公の妻夫木演じる)沢田は、2回泣いてるんだよね? ラストシーンと表紙モデルの女の子(忽那汐里演じる倉田眞子)の前と。

向井:女の子の前では、泣いてるように見えたかもしれませんが、泣いてないんです。
大森:でも、あそこで泣かすんじゃないの? 映画の中であの女の子が「人前できちんと泣ける男の人が好き」って言ってたじゃない。
西岡:妻夫木くんのアップというか芝居を撮りたいから、ああいうラストシーンになったの?
向井:泣くっていうことがどういうことなんだろうと思って、最初の頃の脚本では、新聞社であの女の子の前で泣ける男の話にしようと思ってたんです。でも、沢田っていうキャラクターを考えた時に、あの女の子の前で泣くのは“やらしい”と思ったんですよね。
西岡:俺だったら、最後沢田が映画館で映画を観ているところに彼女が来るようにするな、と思いながら観てた。映画の前半のシーンで一緒に映画を観た時は、沢田がひとつ席を空けて座って彼女が近づいていったけど、今度は男の方から近づいていくようにして、それで泣くようにするな。
一同:なるほど。
山下:色々出てきますね。授業っぽいですね(笑)。ラストは何回も書き直したんです。
向井:でも、僕たちとしては納得してるんです。ちょっと妻夫木くんに託した部分は大きかったと思いますが。
西岡:松山くんのキャラクターはすごくわかる。偽者の過激派みたいな感じはすごく面白いと思った。松山くんは、やな奴っていう雰囲気と、あの時代の中での彼なりの存在感がすごく出てるよね。今までの彼の作品の中で一番良かった。妻夫木くんの方は、朝日新聞にいながらああいう事件を巻き起こしたということに対する葛藤、あの時代の言葉で言う自己批判みたいなものがないから、結局泣くことが自己愛にしか見えない。安田講堂を平和なところから見ていた彼自身がどう感じていたのか、ということに触れてほしかった。それが物足りなかったかな。
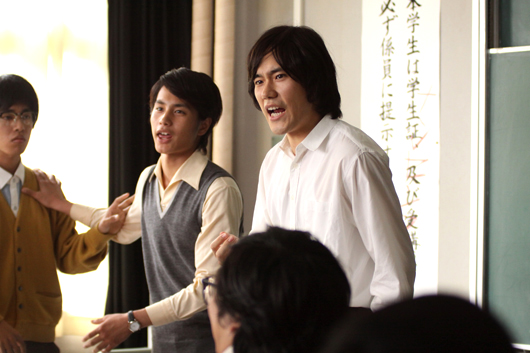
大森:最初にこの映画の話が来た時はどう思ったの? 生まれる前の話じゃない?
山下:まずは原作を渡されたんですが、読んだ時には学生運動の知識が全くなかったんです。でも原作の視点が川本さんの視点だったので、当時の空気やニュアンスがわかったような気になって。川本さんがあの時代の映画や音楽を散りばめて書かれていたので、一気に読んだし面白いと思いました。でも、この原作だけじゃ映画にならないと気付いて、この事件にまつわる本を2冊読んだんです。それを読んだ時に、松ケンが演じた梅山のキャラクターがすごく面白くて。それで、ふたりの話にしようと書き出したのがスタートです。
大森:たしかに松山くんの人物像の方がうまくできてるし、よく生まれる前の時代の人を作り上げたよね。
西岡:結局、時代に翻弄されるふたりの若者の話だよね。だけど、彼らのそれまでというか、学生運動のそれまでを全く描くことなく本編に入るのは狙ってたの?
向井:そうですね。それまであったあの時代を描いた映画って、『光の雨』(※1)とか『実録・連合赤軍 あさま山荘への道程〈みち〉』(※2)とかって、全部最初にあの時代の映像が入るんですよね。そこに「あの頃僕らはこうだった」みたいな語りが入って、そこから遡っていくのがパターンで。最初はそういう感じの脚本だったんですが、(山下くんと)色々話して、ああいうのに抵抗したい思いが芽生えてきたんです。
西岡:僕らの世代は記憶があるし、補強して観るからそれでもいいと思うけど、今の学生たちってあの時代を知らないわけだから、この映画をどう観たのかはすごく気になる。
向井:そこは冒険したんですよね(笑)。学生運動や全教徒って資料で読むとわかるんですけど、彼らがどういう気持ちで運動をしていたのかって、僕らにはわからないんですよね。理解はできても共感はできないんです。そこで、何か普遍的なものを見つけようと思って。この映画は大きく言うと青春映画なんです。青春の終わりや挫折みたいなものをこのふたりで描けば、今の若い人たちに見せられるものになるかと思ったんです。
大森:学生運動を描いた作品といえば、大阪芸大伝説の熊切くんの『鬼畜大宴会』(※3)だよね。あれも過激派の内部抗争を描いたものだけど、それにふたりは関わってるんだよね? あれに影響された部分はあるの?
山下:現場でヘルメットなんかを見てると思い出しましたけど、作る時には意識してなかったです。
大森:監督の山下くん、脚本の向井くん、撮影の近藤くん(※4)も、俳優で山本浩司(※5)も出てたし、大阪芸大OBだけで作った映画みたい。そういう意味では、映画の中の過激派の生活に、山下くんたちの学生時代の体験がオーバーラップして見えるんだけど、そういう部分はないの?
山下:正直沢田に関してはなかなか入り込めなかったんですが、今回松山くんが演じてくれた梅山については「こういう奴いるよな」っていう話を向井としていて。学生時代に映画を作る奴の中にも、言うだけ言って周りを巻き込んで、後輩たちがどんどんボロボロになって、撮影終わる頃にはスタッフ誰もいない、みたいな人がいたんですよね。梅山は、たしかにそういう気持ちで作っていました。ふたりの話にしようとして、ジャーナリストと(梅山が率いる)赤邦軍と両方の話を書いてたんですが、途中で、僕も向井も赤邦軍の方に気持ちが寄っていったので、そっちの厚みが増してしまって、最後に沢田に戻らない脚本とかも最初の頃は書いてました(笑)。

大森:やっぱりこの映画を作ったベースには、学生時代の君たちの思いが入ってるということ?
山下:この映画って、ふたりとも“本物”になりたくて、特に梅山は革命家という肩書きがほしいんですよね。映画の中に「これが新聞記事になれば僕ら“本物”になれるんです」という台詞があるんですが、今思えば僕らが最初に映画作った時もそんな感じだったんですよね。周りがバンドを始めたり、色々活動する中で、向井とふたりで「俺たち何もやってないから、8mmカメラあるし映画撮ろう」というところから始めたんですよね。だから「“本物”になりたい」というキーワードは、19、20歳ぐらいの気持ちとリンクしてるというか、その気持ちはわかりますね。僕も、何かやらなきゃ、これじゃまずいなという気持ちで映画を撮り始めたんです。
4人のトークは、いつまでも続きそうなほど盛り上がりを見せていたが、ここで学生からの質問に。
学生:山下監督といえば長回しが多くて独特な雰囲気を感じますが、今回は長回しをしていても違う雰囲気があったような気がしました。何か気をつけられたことはありますか?
山下:今までは長回しを使って、登場人物を眺めてるような視点だったと思うんですが、今回は登場人物に寄っていかないと、すごく白けた映画になると思っていたので、今まで以上にキャラクターに寄って撮っていました。ただ、梅山が沢田の部屋でギターを弾くふたりのシーンだけは今までどおりの撮り方でした。あの瞬間だけがふたりが近づいてるんですが、今回の映画ってみんな一方通行で、交わらずに言いたいことを言って進んでいくんですよね。
学生:主演の妻夫木さんと松山さんにどんな演技指導をされたんでしょうか?
山下:細かくは特に何も言ってないんですが、とにかく松山くんには「言ってることはめちゃくちゃなキャラクターだけど、常に真剣に言ってくれ」と、本人は人を騙そうとして言ってるんじゃない、という気分で常に芝居してほしいと言ってました。妻夫木くんには演技指導というより、クランクイン前から話をしていく中で、「ジャーナリストって」とか漠然とした話をしてたぐらいです。妻夫木くんに関しては、一緒に考えていったという感覚です。
山下監督への質問が続く中、大森はやはり、「生まれる前の時代のことを映画化した」ことでふたりを高く評価しており、「プロになった」と絶賛していた。
大森:自分が生まれる前の時代を映画にするのって、脚本書くのにめちゃくちゃ調べたんじゃないの?
向井:僕は、高校時代から山下くんと自分たちの世界でしかやってこなかったんです。地続きというか、半径5m以内のことばかりで、それはそれでいいんですが、そういう日本映画ってすごく多くて、そうじゃないことに挑戦したいというのは前々からありました。それで『ニセ札』(※6)や『マイ・バック・ページ』に挑戦したんです。でも、いち作家としてそういうことに自覚的になっていかなきゃいけないと思ってきたのは、ここ4、5年ぐらいです(笑)。知らなかった世界を描くっていうのは面白いし、挑戦し続けたいと思ってます。
最後は、大森と西岡がそろって『マイ・バック・ページ』の2時間21分という上映時間の長さへの不満を主張し、山下も向井も「これでも短くしたんですが(笑)、そこは課題です」と気を引き締めていた。学科長で映画監督の大森と教授で脚本家である西岡ならではのリードで盛り上がりを見せたティーチ・インだった。
(2011年6月 3日更新)
Tweet Check
Profile

山下敦弘(映画監督)/
やましたのぶひろ●’76年愛知県出身。高校時代から自主映画制作を始め、’95年大阪芸術大学映像学科に入学。初の長編『どんてん生活』(99)でゆうばり国際ファンタスティック映画祭オフシアター部門グランプリを受賞。その後も『ばかのハコ船』(02)、『リアリズムの宿』(03)などで評価され、女子高生バンドの青春を描いた『リンダ リンダ リンダ』(05)がスマッシュヒットを記録。『松ヶ根乱射事件』(06)に続き手がけた『天然コケッコー』(07)は数多くの賞に輝いた。『マイ・バック・ペー ジ』は4年ぶりの新作となる。常に新作に期待が集まる数少ない若手監督。
向井康介(脚本家)/
むかいこうすけ●’77年徳島県出身。大阪芸術大学映像学科在学中に熊切和嘉監督と出会い、『鬼畜大宴会』(97)で照明・編集助手を経験し、山下監督の『どんてん生活』で脚本・照明・編集を担当。その後も『ばかのハコ船』『リアリズムの宿』『リンダリンダ リンダ』『松ヶ根乱射事件』と山下作品には欠かせない脚本家に。山下作品以外では『神童』(07)『俺たちに明日はないッス』(08)『色即ぜねれいしょん』(08)『ニセ札』(09)などで注目を集める若手脚本家。

大森一樹(映画監督)/
おおもりかずき●’52年大阪府出身。大学時代に自主制作した『暗くなるまで待てない』(75)が高く評価され、『オレンジロード急行』(78)で商業映画デビュー、映画監督に。斉藤由貴主演の3部作や平成ゴジラシリーズ、『大失恋。』(95)など、幅広いジャンルで定評がある、日本を代表する映画監督。近作に『世界のどこにでもある、場所』(11)、『津軽百年食堂』(11)。’05年4月より大阪芸術大学映像学科、学科長を務める。
西岡琢也(脚本家)/
にしおかたくや●’56年京都府出身。’79年に『暴行魔真珠責め』でシナリオライターとしてデビュー。『ガキ帝国』(81)『TATOO〈刺青〉あり』(82)などでその名を知られる脚本家となる。近作に『秋深き』(08)『沈まぬ太陽』(09)『太平洋の奇跡-フォックスと呼ばれた男-』(11)。映画だけでなく、TVドラマでも活躍。日本シナリオ作家協会理事長で大阪芸術大学映像学科教授。
Movie Data

『マイ・バック・ページ』
●大阪ステーションシティシネマほかにて上映中
【公式サイト】
http://mbp-movie.com/
【映画生活サイト】
http://cinema.pia.co.jp/title/154372/
【注釈】
『光の雨』※1
立松和平の同名小説を劇中劇のスタイルで重厚に描き、連合赤軍幹部役の山本太郎、裕木奈江を筆頭とした若手キャストが迫真の演技を見せた、リアルで見応えのある群像ドラマ。高橋伴明監督作。
『実録・連合赤軍 あさま山荘への道程
〈みち〉』※2
'72年2月に日本中を揺るがした“あさま山荘事件”を題材に、革命に挫折した“連合赤軍”の若者たちが追い詰められていく過程を、鬼才・若松孝二監督が渾身の描写で浮き彫りにした、必見の超大作。
『鬼畜大宴会』※3
PFFアワード'97で準グランプリに輝いたパワフルな怪作。学生運動全盛期の70年代を背景に、左翼グループの内部分裂をエネルギッシュに描く。次第にエゴをむきだしにしていく登場人物たちの描写が、政治色以上に見る者に衝撃を与える。熊切和嘉監督作。
撮影の近藤くん ※4
近藤龍人(こんどうりゅうと)●‘76年愛知県出身。大阪芸術大学卒業。脚本家の向井康介とともに山下作品には不可欠の映画カメラマン。主な作品に『どんてん生活』から『リアリズムの宿』までの山下作品や『天然コケッコー』『ウルトラミラクルラブストーリー』『ソラニン』『海炭市叙景』など。『マイ・バック・ページ』の撮影を担当。
俳優の山本浩司 ※5
やまもとひろし●’74福井県出身。大阪芸術大学卒業。俳優、映画監督。山下作品の『どんてん生活』や『ばかのハコ船』『リアリズムの宿』で主役を務めるなど、山下作品には不可欠の俳優。その独特の佇まいで、若くして日本映画の名脇役の名をほしいままに。近作に『色即ぜねれいしょん』(08)『雷桜』(10)など。『マイ・バック・ページ』では、松山ケンイチ演じる梅山が率いる赤邦軍と共闘する運動家役で出演。
『ニセ札』※6
お笑い芸人として知られる木村祐一の初監督作品。戦後の混乱が続く昭和20年代の山村を舞台に、小学校の女教頭を筆頭とした村人たちの“ニセ札作り計画”の顛末を描く。主演に倍賞美津子、脚本に『松ヶ根乱射事件』の向井康介を迎えるなど、磐石の布陣をひいて挑んだデビュー作。
























